blog
ブログ
知らず知らずのうちに高血糖を放置すると、血管が損傷し、動脈硬化をはじめとする合併症のリスクを高めることをご存知ですか?現代社会において、血糖値のコントロールは健康維持の重要な鍵です。厚生労働省の報告では、糖尿病患者数と予備軍を合わせると約2,000万人と推定されており、国民の5人に1人が糖尿病または予備軍という状況です。
この記事では、血糖値の正常値や年代別の基準値、高血糖のリスクと合併症、そして具体的な血糖値コントロール対策を詳しく解説します。あなたの健康を守るためにも、ぜひこの記事で血糖値コントロールの重要性について理解を深めましょう。
以下の記事では、血糖値を下げるために効果が期待できる7つの具体的な方法について解説しています。食事・運動・睡眠など日常生活で取り入れやすいポイントを紹介しているので、すぐに実践したい方におすすめです。
>>血糖値を下げる7つの効果が期待できる方法!生活習慣改善のポイント
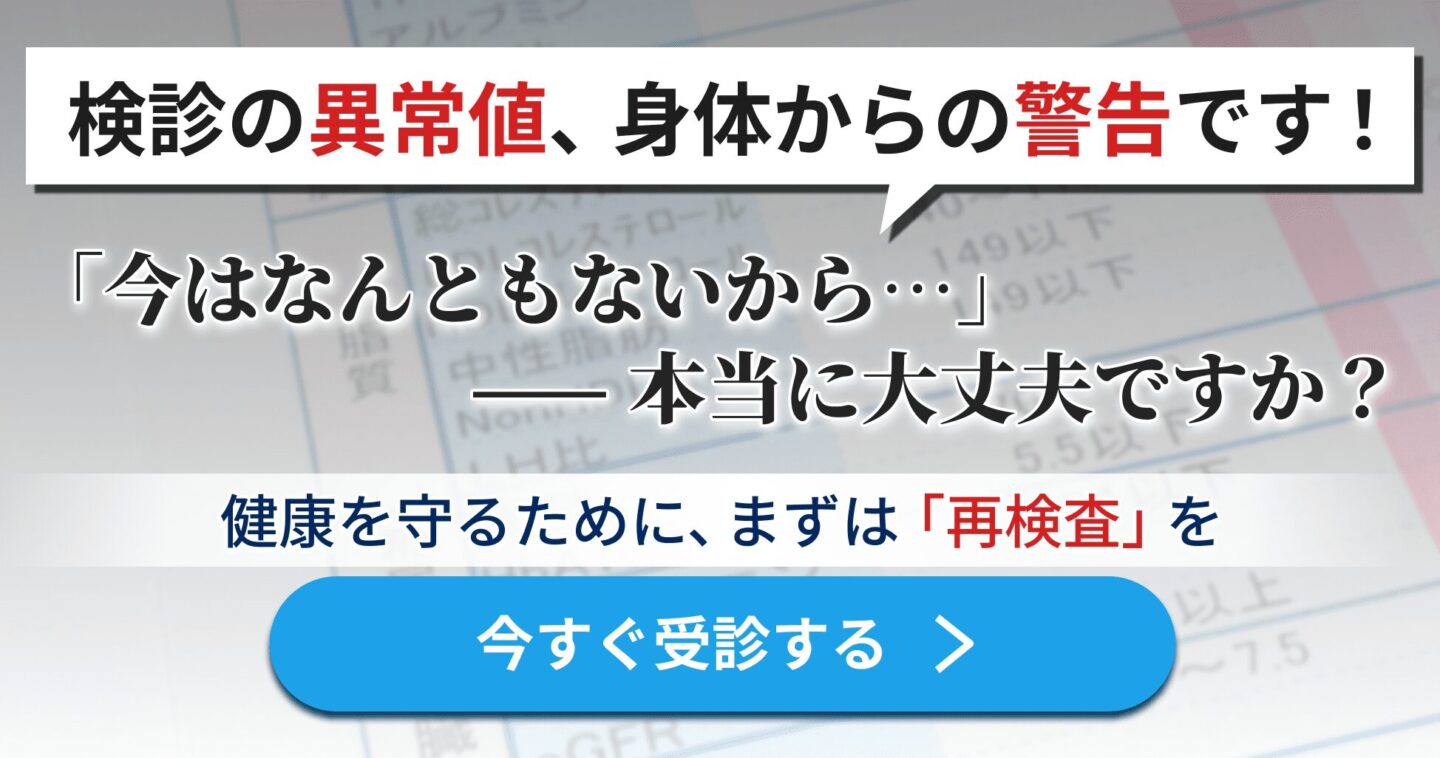
血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖の濃度
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。単位はmg/dL(ミリグラム・パー・デシリットル)で表します。血液1デシリットル(100ミリリットル)の中に、何ミリグラムのブドウ糖が含まれているかを示す数値です。
ブドウ糖は、体にとって重要なエネルギー源です。ご飯やパン、果物などの炭水化物を摂取すると、体内でブドウ糖に変換され、血液によって全身の細胞に運ばれます。インスリンというホルモンの働きによって細胞内に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。
インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、血糖値を適切な範囲に保つために重要な役割を担っています。空腹時70〜99mg/dL、食後2時間で140mg/dL未満が正常範囲とされています。血糖値は食事や運動、ストレスで変動し、高血糖だと動脈硬化や網膜症・腎症などの合併症リスクもあります。
低すぎるとめまいや意識障害を招く可能性があります。血糖値の適切な管理は、健康を維持するために重要です。
血糖値の年代別の基準値
血糖値の正常範囲(空腹時70〜99mg/dL、食後2時間値<140mg/dL)は基本的に年齢やライフステージによって大きく変わることはありません。しかし、高齢者など一部のケースでは例外的な基準が設けられることがあります。
0~9歳(幼児~小児)は、成長ホルモンの影響を受けやすいため、血糖値が日によって変動しやすいのが特徴です。10~19歳(思春期)は、ホルモンバランスの変化の影響で、血糖値が一時的に高くなることがあります。
20~39歳(成人前半)は、健康な代謝が保たれやすい年代です。妊娠中は妊娠糖尿病のリスクがあるため、特に女性は血糖値管理が重要です。40~64歳(中高年)になると、年齢とともに内臓脂肪が増えやすくなり、インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ため、生活習慣病の予防が大切です。
65歳以上(高齢者)は、インスリン分泌の低下や腎機能の変化により、高血糖だけでなく低血糖のリスクも高まりやすくなります。そのため、血糖コントロールの目標値は、医師と相談のうえで個別に設定することが望まれます。定期検査と生活習慣の見直しを行い、自身のライフステージに合った目標設定で適切に管理しましょう。
高血糖のリスク
高血糖のリスクとして、以下が挙げられます。
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
高血糖を放置すると、血管にダメージが蓄積しやすくなり、全身にさまざまな悪影響を及ぼします。今のうちから血糖値を適切に管理する意識を持つことが大切です。
網膜症
網膜症は、高血糖によって網膜の血管が傷つけられることで起こる病気です。初期には自覚症状がない場合も多いですが、放置すると視力が低下し、最悪の場合は失明に至ることもあります。網膜の血管がもろくなって出血することで、視野がかすみ、物が歪んで見えたり、視野の一部が欠けたりといった症状が現れます。
さらに進行すると、網膜剥離を引き起こし、視界全体がかすんだり、黒い点が飛んで見えたりするようになり、最終的には失明に至る可能性があります。血糖値が高い状態が続けば続くほど、網膜症のリスクは高まります。定期的な眼科検診と適切な血糖値コントロールによって、網膜症の発症や進行を抑えることが期待できます。
腎症
腎症とは、腎臓の働きが徐々に低下していく病気です。特に糖尿病などで高血糖状態が続くことによって引き起こされることが多くあります。腎臓は血液を濾過し、老廃物や余分な水分を尿として排出する、体内の浄化装置です。
高血糖が長期間続くと、腎臓内の糸球体と呼ばれる毛細血管の塊が傷つき、濾過機能が少しずつ低下していきます。初期にはほとんど自覚症状がありませんが、進行すると老廃物が体内に蓄積します。むくみ・だるさ・息切れといった症状が現れるようになります。
さらに悪化すると、腎臓の機能が失われ、最終的には人工透析が必要な場合もあります。腎症の進行を防ぐためには、血糖値の適切な管理に加えて、血圧のコントロールや塩分を控えた食事、生活習慣の見直しが欠かせません。
以下の記事では、糖尿病の疑いがある場合に何科を受診すればよいのか、受診のタイミングや診察の流れを詳しく解説しています。早期発見・早期対応の参考にしてください。
>>糖尿病の相談は何科が適切?受診のタイミングと診療の流れを解説
神経障害
神経障害は、以下の2つに分類されます。
- 末梢神経障害:手足のしびれや痛み、感覚の鈍化といった症状が現れる
- 自律神経障害:便秘や下痢、立ちくらみなどを引き起こす
末梢神経障害は、手袋や靴下を履いているような感覚がしたり、逆に素足で歩いても地面の感触がわかりにくくなったりします。少しずつ腕や脚の上のほうへ広がっていくことがあります。
自律神経障害は、胃腸の働きや血圧、排尿などを調整する神経に影響するため、便秘・下痢、立ちくらみ、頻尿や残尿感など、さまざまな症状が現れます。症状がバラバラで気づきにくいのが特徴です。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を届ける「冠動脈」が血のかたまり(血栓)などで突然詰まることで起こります。血流が止まると、心筋が壊死し、激しい胸の痛み、息苦しさ、吐き気などの症状が現れます。放っておくと心臓が止まってしまうこともある、危険な病気です。
心臓は、全身に血液を送るポンプの役割をしており、生命維持に欠かせない臓器です。高血糖の状態が続くと、心臓の血管(冠動脈)に動脈硬化が進みやすくなり、心筋梗塞のリスクが高まります。
以下のページでは、血管の硬さや動脈硬化の進行度を調べる血圧脈波検査について紹介しています。
脳梗塞
脳梗塞は、脳の血管が詰まって脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、麻痺やしびれ、意識障害などの症状が現れる病気です。高血糖は、脳梗塞の主な危険因子である動脈硬化を促進するため、血糖値が高い状態が続くと脳梗塞のリスクが上昇します。
脳梗塞は、発症すると後遺症が残る可能性が高く、迅速な診断と適切な治療が重要です。高血糖のリスクと合併症の深刻さを理解し、日常生活の中で血糖値をコントロールする努力が、健康な生活を送るうえで大切です。
以下の記事では、高血圧がなぜ脳梗塞の引き金になるのか、その仕組みや予防・対処法について詳しく解説しています。血圧が気になる方はぜひ参考にしてください。
>>高血圧が脳梗塞を引き起こす可能性も!理由や対処法など詳しく解説
血糖値をコントロールする対策
血糖値をコントロールするための対策は以下のとおりです。
- 低GI食品を摂取する
- 食物繊維を摂取する
- 適度に運動する
- 十分な睡眠を確保する
- ストレスを管理する
- 定期的に受診する
毎日の生活の中で、できることから少しずつ始めてみましょう。
低GI食品を摂取する
GI値が低い食品は、血糖値の上昇が緩やかになり、膵臓から分泌されるインスリンの負担軽減が期待できます。逆にGI値が高い食品は、血糖値が急激に上昇し、インスリンが過剰に分泌される原因です。
GI値とは、Glycemic Index(グリセミック・インデックス)の略で、食品が食後に血糖値を上昇させる速さを表す数値です。ブドウ糖を摂取した時の血糖値上昇率を100とした場合、その食品が血糖値をどの程度上昇させるかを示しています。
インスリンの乱高下は、将来的に糖尿病のリスクを高めるだけでなく、血管を傷つけ、動脈硬化を進行させる可能性があります。白米よりも玄米や雑穀米、食パンよりも全粒粉パンなど、普段の食事を少し工夫するだけで、低GI食品を摂り入れることができます。
GI値は食品の調理法によっても変化します。パスタは茹で時間が短いアルデンテの状態よりも、よく茹でたほうがGI値が低くなります。加熱調理によってデンプンの構造が変化し、消化吸収が遅くなるためです。
食物繊維を摂取する
食物繊維は、血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。野菜や海藻、きのこ類、豆類などに多く含まれています。食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、それぞれ異なる働きで血糖値コントロールをサポートします。
水溶性食物繊維は、胃の中で水分を吸収してゲル状になり、糖質の吸収を遅らせ、血糖値の急上昇を抑えます。善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える効果も期待できます。
不溶性食物繊維は、水分を吸収して便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進することで、排便を促します。血糖値への直接的な影響は少ないですが、食後の血糖値上昇を緩やかにする効果が期待できます。どちらの食物繊維もバランス良く摂ることが大切です。
目標摂取量は1日あたり成人男性で21g以上、成人女性で18g以上です。意識的に食物繊維を摂取することで、血糖値の改善だけでなく、便秘の解消や腸内環境の改善など、さまざまな健康効果が期待できます。
適度に運動する
適度な運動は、血糖値コントロールに効果が期待できます。おすすめの運動には、以下の2種類があります。
- 有酸素運動:ウォーキングやジョギング、水泳など
- レジスタンス運動:筋力トレーニングなど
有酸素運動は、酸素を効率的に使ってエネルギーを生み出すため、脂肪燃焼効果が高く、体重管理にも役立ちます。継続的な運動はインスリン感受性を高め、血糖値を下げる効果が期待できます。
レジスタンス運動は、筋肉量を増やすことで基礎代謝を高め、エネルギー消費量を増やし、血糖値の安定につながります。筋肉はブドウ糖の貯蔵庫としての役割も果たしているため、筋肉量を増やすことは血糖値コントロールの観点からも重要です。
いずれの運動も、インスリン抵抗性を改善する効果がありますが、週に2~3回程度、無理のない範囲で続けることが重要です。研究によると、高強度運動と低強度運動を交互に繰り返すインターバルトレーニングも血糖値の改善に効果があることが示唆されています。
短時間で運動効果を高めることはできますが、体に負担がかかるため、体力に合わせて行いましょう。
十分な睡眠を確保する
質の良い睡眠を十分に確保することは、血糖値のコントロールだけでなく、心身の健康維持にも不可欠です。毎日、同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂らない、寝室を暗く静かに保つなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。成人の場合、7時間程度の睡眠時間を目安にしてください。
睡眠不足は、血糖値を上昇させる原因の一つです。睡眠不足になると、食欲を抑制するホルモンであるレプチンが減少し、食欲を増進させるホルモンであるグレリンが増加します。結果、過食につながりやすく、血糖値が上昇しやすくなります。
ストレスを管理する
ストレスは、血糖値を上昇させるホルモンであるコルチゾールを分泌させます。コルチゾールは、肝臓に蓄えられているグリコーゲンをブドウ糖に変換し、血糖値を上昇させる働きがあります。ストレスを感じると、一時的にインスリンの分泌が低下する可能性があります。
ストレスを慢性的に抱えていると、常に血糖値が高い状態が続き、糖尿病のリスクを高めるだけでなく、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。ストレスを溜め込まないように、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
リラックスできる時間を作ったり、趣味に没頭したり、適度に体を動かすなど、自分に合った方法でストレスを管理しましょう。
定期的に受診する
血糖値をコントロールするためには、定期的に医療機関を受診し、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)などの検査を受けることが大切です。HbA1cは、過去1~2か月の平均的な血糖値を反映する検査で、診断や治療効果の目安として医師が活用する指標です。
医師の指示に従って、適切な治療や生活習慣の改善に取り組むことで、血糖値をコントロールし、合併症を予防できます。血糖値やHbA1cの数値だけでなく、ご自身の体調で気になることがあれば、すぐに医師に相談しましょう。早期発見、早期治療は、健康な生活を送るうえで重要です。
まとめ
血糖値の正常値は空腹時70~99mg/dL、食後2時間値は140mg/dL未満が目安です。しかし、年齢やライフステージ、個々の体質によって異なり、妊娠中や高齢期には特に注意が必要です。高血糖を放置すると、動脈硬化が進行し、以下の深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
血糖値コントロールには、低GI食品や食物繊維を積極的に摂り、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理を心がけましょう。定期的な健康診断と医療機関への受診も大切です。毎日の生活習慣を少し見直すことで、将来の健康を守ることができます。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Miquel Bennasar‑Veny, Narges Malih, Aina M Galmes‑Panades, Ivonne C Hernandez‑Bermudez, Natalia Garcia‑Coll, Ignacio Ricci‑Cabello, Aina M Yañez. Effect of physical activity and different exercise modalities on glycemic control in people with prediabetes: a systematic review and meta‑analysis of randomized controlled trials. Front Endocrinol (Lausanne), 2023, 14, 1233312
- 厚生労働省:糖尿病診療の現状
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







