blog
ブログ
健康診断で「血圧が高い」と言われたことはありませんか?日本人の約4300万人が高血圧といわれており、年齢に関係なく誰にでも起こりうる身近な病気です。自覚症状がないまま放置すると、脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる病気を引き起こす可能性もあります。
この記事では、血圧の正常値の確認方法や高血圧の原因、放置した場合のリスク、血圧を下げる具体的な対策について解説します。ご自身の血圧の状態を正しく理解し、毎日の健康管理に役立てましょう。
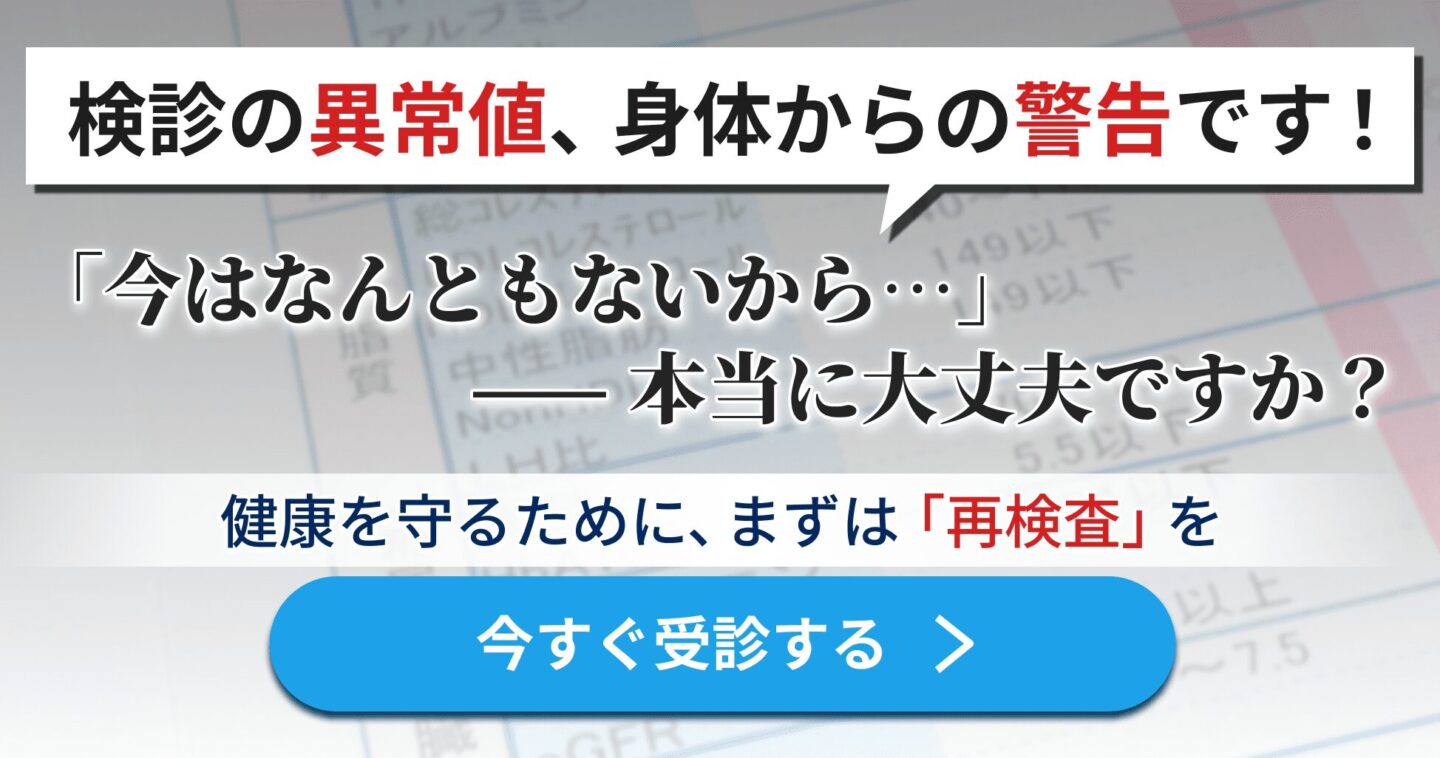
血圧の正常値
血圧の正常値は、診察室で測定する診察室血圧と、家庭で測定する家庭血圧で基準が異なります。診察室血圧と家庭血圧の基準値は以下のとおりです。
- 診察室血圧:収縮期血圧(上の血圧)120mmHg未満、拡張期血圧(下の血圧)80mmHg未満
- 家庭血圧:収縮期血圧115mmHg未満、拡張期血圧75mmHg未満
血圧は起床時は高く、リラックスしているときは低い傾向です。1回の測定だけで判断せず、複数回測定して平均値を見ましょう。家庭で血圧を測る際は、朝や排尿後、服薬・食事前などに安静の状態で測定し、毎日同じ時間帯に測定することが大切です。
健康診断の結果が、診察室血圧で120~139/80~89mmHg、家庭血圧で115~134/75~84mmHgの場合、正常高値血圧や高値血圧と呼ばれます。正常高値血圧や高値血圧は、将来的に高血圧になるリスクが高い状態です。生活習慣の改善に取り組み、血圧を正常範囲に維持することが重要です。
健康診断で血圧が高いと指摘された場合は、医療機関を受診し、医師の指示に従って再度血圧を測定しましょう。必要に応じて、24時間血圧測定などの精密検査を行い、適切な診断と治療を受けることが重要です。
以下のページでは、血管の硬さや動脈硬化の進行度を評価する血圧脈波検査について詳しく解説しています。
高血圧の原因
高血圧の原因は以下のとおりです。
- 肥満
- 塩分過多
- 睡眠不足
- 加齢
- 基礎疾患
高血圧の原因は単一ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合があります。薬剤や急性疾患による一時的な血圧上昇の可能性もあります。
肥満
肥満は、高血圧の大きな原因の一つです。体重が増加して体が大きくなると、体内の血管の総延長も長くなり、心臓はより多くの血液を送り出す必要があります。血液量が多くなると血管にかかる圧力が高まり、血圧が上昇します。脂肪細胞からは、血圧を上げる物質が分泌され、肥満はさまざまな面から血圧に影響を与える可能性があります。
BMI(ボディマス指数)が25以上で肥満と判定されます。BMIは体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算できます。ご自身のBMIを計算し、適正体重の範囲内かどうかを確認しましょう。適正体重を維持することは、高血圧の予防に重要です。
塩分過多
塩分の摂りすぎも、高血圧の主要な原因です。塩分の主成分であるナトリウムは、体内の水分を保持する働きがあります。ナトリウムを摂りすぎると、血液中の水分量が増え、血管内の圧力が高まり、血圧が上昇しやすくなります。厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取量は6g未満ですが、超過しているのが現状です。
外食や加工食品には、塩分が多く含まれている傾向です。ラーメン1杯には約6g、コンビニのおにぎり1個には約1gの塩分が含まれています。普段の食事で減塩を意識し、カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂取することで、ナトリウムの排泄を促す効果が期待できます。
睡眠不足
睡眠不足も、高血圧のリスクを高める要因です。睡眠中は、血圧や心拍数が低下し、体が休息する時間です。睡眠時間が短いと、休息時間が十分に確保できず、交感神経(活動時に働く自立神経)が優位な状態が続きます。交感神経が活発になると、血管が収縮し、血圧が上昇しやすくなるため、適切な対処が必要です。
睡眠不足はホルモンバランスを崩し、食欲を増進させるホルモンの分泌を促進するため、肥満につながる可能性も高まります。質の高い睡眠を十分にとることは、血圧管理だけでなく、健康維持のためにも不可欠です。7時間睡眠を目安に、睡眠時間と質の両方を意識するようにしましょう。
加齢
加齢も、高血圧を引き起こす要因です。年齢を重ねると、血管の壁が硬くなり、弾力性が失われていきます。加齢によって弾力性を失った血管は、血液がスムーズに流れにくくなり、血管にかかる圧力が高まります。血管の老化を早める生活習慣(喫煙、過度の飲酒など)を避けることで、血圧上昇を抑制することが重要です。
禁煙や節酒を心がけ、バランスの良い食生活を維持することで、血管の健康を保ちましょう。
基礎疾患
高血圧は、他の病気によって引き起こされる場合もあります。他の病気による高血圧を「二次性高血圧」と言い、腎臓病やホルモン異常などが原因です。腎臓の機能が低下すると、体内の水分や塩分バランスの調整機能がうまく働かず、血圧が上昇することがあります。
副腎や甲状腺などのホルモン異常も、高血圧を引き起こす可能性があります。健康診断で血圧が高いと指摘された場合は、生活習慣の見直しだけでなく、基礎疾患の有無も医師に相談することが大切です。
高血圧は心臓に負担をかけ、心不全の進行にも関わる重要な要因の一つです。血圧について詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
>>大石内科循環器科医院|高血圧の基礎知識・症状・治療について
高血圧を放置するリスク
高血圧を放置することで起こる可能性のあるリスクは以下のとおりです。
- 脳卒中
- 心筋梗塞
- 腎臓病
- 認知症
脳卒中
高血圧は脳卒中のリスクを高める可能性があります。脳卒中は3種類に分けられます。脳卒中の種類は以下のとおりです。
- 脳梗塞:脳の血管が詰まる
- 脳出血:脳の血管が破れる
- くも膜下出血:脳のくも膜にある血管が破れる
高血圧によって動脈硬化が進行すると、脳の血管が脆くなり、詰まりやすくなったり、破れやすくなったりします。脳卒中は、後遺症が残る可能性が高く、重度の場合は寝たきりになるケースもあります。一過性脳虚血発作は、脳の血管が一時的に詰まることで、手足のしびれや麻痺、ろれつが回らないなどの症状が現れることが特徴です。
多くの場合、数分〜数十分で自然に回復しますが、脳梗塞の前触れである可能性が高く、本格的な脳梗塞を発症するリスクが高まります。手足のしびれや麻痺などの症状が現れたら、早急に医療機関を受診することが重要です。
心筋梗塞
心筋梗塞とは、心臓の筋肉に血液が供給されなくなる状態です。高血圧によって動脈硬化が進行すると、心臓にある冠動脈が狭窄、閉塞し、心臓の筋肉に血液が供給されなくなります。心筋梗塞は、激しい胸の痛みや呼吸困難などの症状を引き起こし、突然死につながる可能性もある危険な病気です。
狭心症も高血圧と関連の深い病気です。狭心症は、冠動脈が狭窄することで、心臓への血流が不足し、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れます。狭心症は、以下の2つに分けられます。
- 安定狭心症:安静にしていると症状が治まる
- 不安定狭心症:安静にしていても症状が治まらず、心筋梗塞に移行する可能性がある
以下のページでは、不整脈や心臓への負担を確認するために行われる心電図検査について紹介しています。
腎臓病
高血圧が続くと、腎臓の血管(腎動脈)にも負担がかかり、腎臓の機能が徐々に低下します。腎臓は、血液を濾過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出する重要な臓器です。腎臓病が進行すると、人工透析が必要になる場合もあり、生活の質に大きな影響を与える可能性があります。
腎臓病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに病気が進行しているケースもあります。定期的な健康診断で尿検査や血液検査を受け、早期発見・早期治療につなげることが重要です。
認知症
高血圧は、血管性認知症のリスクを高める可能性があります。血管性認知症は、脳血管障害によって脳の神経細胞がダメージを受け、認知機能が低下する病気です。高血圧は、脳血管障害の大きなリスク要因となるため、認知症予防の観点からも、血圧管理は重要です。
認知症は、物忘れなどの記憶障害だけでなく、判断力の低下や人格の変化など、さまざまな症状が現れます。早期発見・早期治療が重要であり、少しでも気になる症状があれば、医療機関を受診しましょう。
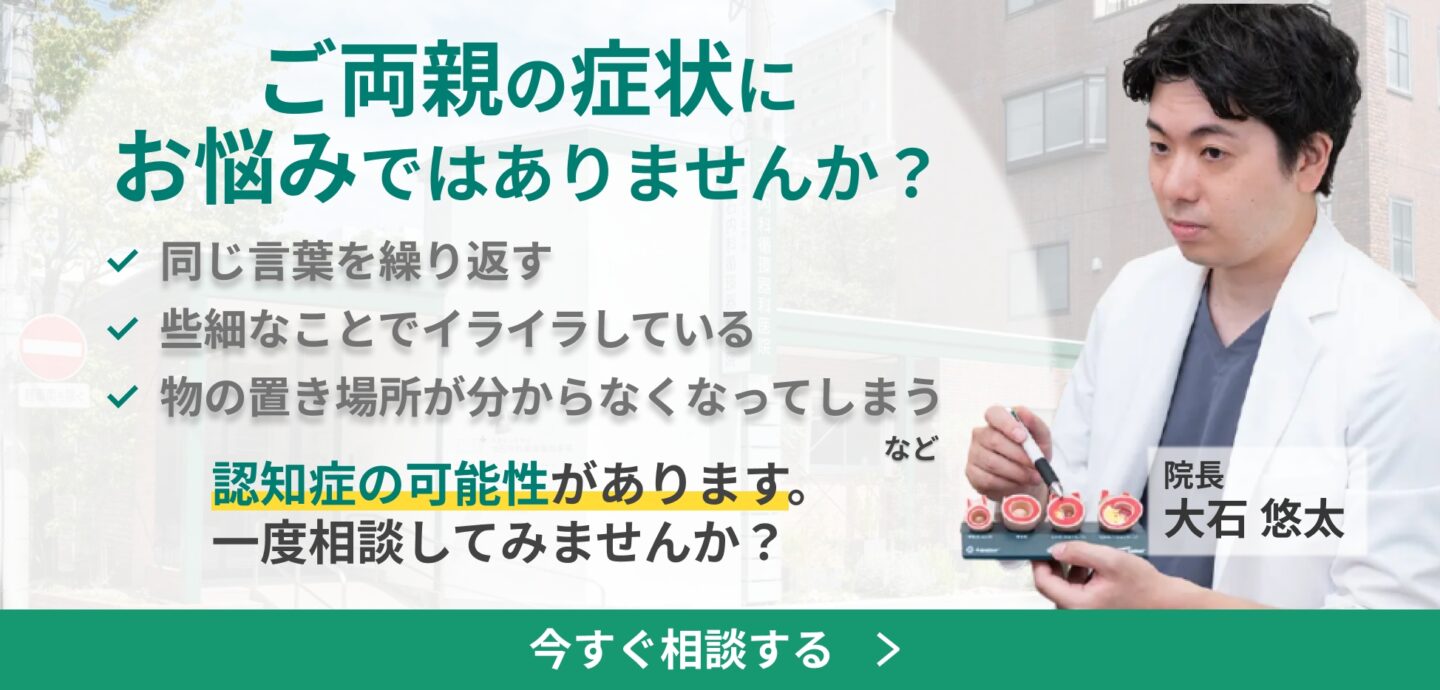
血圧を下げる正しい対策
血圧を下げるための対策は以下のとおりです。
- 食生活を見直す
- 適度に運動する
- 禁酒・禁煙する
- 十分な睡眠を確保する
- ストレスを管理する
- 定期的に受診する
食生活を見直す
食生活の見直しは、血圧コントロールの基盤です。まずは減塩に取り組みましょう。過剰な塩分摂取は体内の水分量を増加させ、血圧が上昇する要因になります。す。1日の塩分摂取量の目標は、6g未満を目指しましょう。外食や加工食品は、気づかないうちに多量の塩分を摂取してしまう可能性があります。
可能であれば自炊を増やし、薄味調理を心がけましょう。だしや香辛料、酢、レモン汁などを活用すれば、減塩しても風味豊かに食事を楽しめます。カリウムには体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、かリウムを多く含む野菜や果物、海藻を積極的に摂ることが大切です。
適度に運動する
適度な運動は、血圧を下げる効果だけでなく、ストレス軽減や体重管理にもつながります。ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなど、自分が楽しめる運動を見つけ、習慣化することが大切です。1回30分程度、週に3~5回を目安に、無理なく続けられるペースで取り組みましょう。
日常生活の中でも、体を動かす機会を意識的に増やすことが重要です。エレベーターやエスカレーターではなく階段を使ったり、一駅分歩いたりなど、小さな積み重ねが大きな効果を生み出すことがあります。日常生活の工夫を継続することで、運動習慣を自然と身につけましょう。
運動療法については以下の記事で詳細に解説していますので、あわせて読んでみてください。
>>高血圧の運動療法のおすすめの方法や効果を高血圧治療ガイドラインをもとに解説!
禁酒・禁煙する
喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるだけでなく、動脈硬化を促進する作用もあります。禁煙は高血圧対策だけでなく、さまざまな病気のリスクを減らすためにも重要です。飲酒も血管を収縮させ血圧を上昇させる可能性があります。過度な飲酒は避け、適量を守りましょう。
厚生労働省では、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で10〜19g、女性で9gまでで最も死亡率が低いとされています。節度ある適度な飲酒量は、1日平均純アルコール摂取量を20g程度が推奨されます。
十分な睡眠を確保する
睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、血圧上昇の一因となります。睡眠時間は7時間程度を目安に、睡眠時間と質の両方を意識することが大切です。質の良い睡眠のための工夫は以下のとおりです。
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 寝る前にカフェインを摂らない
- リラックスできる睡眠環境を作る
ストレスを管理する
ストレスは血圧上昇の要因となるため、積極的なストレスマネジメントが重要です。ストレス解消法の例は以下のとおりです。
- 趣味やリラックスできる時間をもつ
- 軽い運動をする
- 自然の中で過ごす
- 瞑想やマインドフルネスを実践する
- カウンセリングなどの専門家のサポートを受ける
定期的に受診する
診察室血圧で140/90mmHg以上、あるいは家庭血圧で135/85mmHg以上の場合、医療機関への受診が推奨されます。内科や循環器内科を受診し、医師の指示に従って検査や治療を受けましょう。治療は生活習慣の改善や、必要に応じて降圧剤などの薬物療法が検討されます。服薬中であっても、生活習慣の改善を継続することは重要です。
日本における高血圧と心血管疾患・腎疾患との関連性について、大規模なリアルワールドデータを用いた研究が進んでいます。高血圧管理と治療は継続的な取り組みが必要です。定期的な受診と医師との連携を通じて、適切な治療を継続し、健康管理に努めましょう。
まとめ
血圧が高いと診断されたら、生活習慣を見直しましょう。減塩や適度な運動、十分な睡眠など、小さな努力の積み重ねが、血圧を正常値に近づける大きな一歩です。高血圧は自覚症状が現れにくいため、放置せずに、定期的な血圧測定と健康診断を心がけましょう。
高血圧と診断されたら、一人で悩まずに医療機関を受診し、専門家のアドバイスを受けながら、安心して治療を進めていきましょう。あなたの健康は、あなた自身の手で守ることができます。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Satoh M, Nakayama S, Toyama M, Hashimoto H, Murakami T, Metoki H. Usefulness and caveats of real-world data for research on hypertension and its association with cardiovascular or renal disease in Japan. Hypertension Research, 2024, 47巻, 11号, p.3099-3113
- 厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書266-272, 2019.
- 厚生労働省:アルコール
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







