blog
ブログ
健康診断の尿検査は、確認されていますか?尿糖や尿蛋白、ケトン体などの項目は、糖尿病の早期発見につながる手がかりです。糖尿病は初期症状に気づきにくく、知らないうちに進行しやすい病気です。
厚生労働省の統計によると、1997年に糖尿病が強く疑われる人数は約690万人でした。しかし、2016年には約1000万人まで増加しており、年々増加傾向にあります。この記事では、糖尿病の尿検査について解説します。糖尿病の初期サインや具体的な対処法も紹介するので、ご自身の健康管理に役立てましょう。
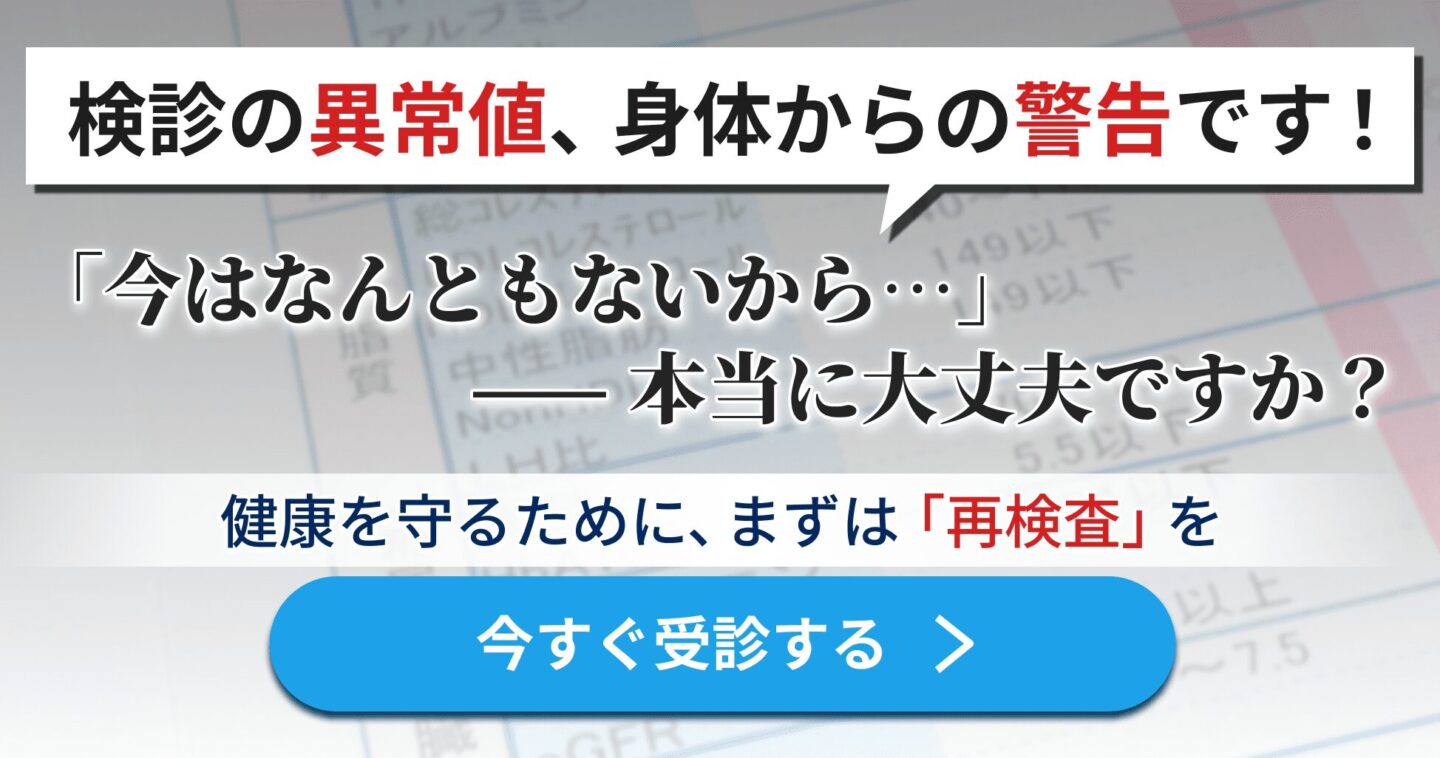
糖尿病の尿検査でわかる3つのこと
健康診断の尿検査に尿糖や尿蛋白、ケトン体などの項目があります。それぞれの項目と内容を説明します。
- 尿糖:血糖コントロールの状態
- 尿蛋白:腎臓の状態
- ケトン体:危険な状態のサイン
尿糖:血糖コントロールの状態
血糖値が160~180mg/dLを超えると、尿中に糖が検出されます。腎臓の再吸収能力を超えている状態であるため、過去数時間の血糖値が高かった可能性があります。食後に尿糖が出た場合は、食事の内容や量、食べるスピードなどを見直しましょう。水分を多く飲んだ後に検査をすると、尿が薄まり、尿糖が陰性になる場合があります。
尿糖が繰り返し検出される場合は、医療機関での検査をご検討ください。のどの渇きや頻尿症状を伴う場合は、糖尿病の可能性が高いため、早期に医療機関を受診しましょう。
尿蛋白:腎臓の状態
尿蛋白の検査は、尿中の蛋白の量を測定します。尿中に蛋白が確認されると、糖尿病性腎症を合併している可能性があります。腎臓に負担がかかっている状態や糖尿病が進行すると、腎臓の濾過機能が低下するため、血液中の蛋白が尿に排出されるためです。初期の糖尿病性腎症は自覚症状が乏しく、病気に気付かず進行する可能性があります。
慢性腎臓病の主な原因は、糖尿病であることが報告されています。尿蛋白の値が30mg/gCrを超えている場合は、早期の腎症が疑われるため、医師に相談することが大切です。
ケトン体:危険な状態のサイン
ケトン体とは、体内の脂肪が分解されたときに作られる物質です。尿にケトン体が出ている場合は、糖尿病性ケトアシドーシスの可能性があります。糖尿病性ケトアシドーシスは、1型糖尿病の方に現れやすい症状です。意識障害や脱水症状を引き起こし、命に関わる可能性があります。以下の症状が現れたらすぐに病院受診してください。
- 高血糖
- 脱水
- 倦怠感
- 吐き気
- 腹痛
- 浅い呼吸
尿検査でケトン体を確認したら、医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
糖尿病の初期のサイン
糖尿病の初期症状は、以下があります。
- 喉の渇き
- 頻尿
- 体重減少
- 疲労感
喉の渇き
高血糖値が継続すると、血液中の糖濃度を下げるために、尿を多く生成します。体内の水分が過剰に排出され、脱水症状を引き起こし、喉の渇きを感じるのです。糖尿病の場合、喉の渇きが慢性的に続く傾向があります。夜間に何度も喉の渇きで目が覚める人もいます。
原因が分からない喉の渇きが続く場合は、糖尿病の可能性も考慮し、医療機関を受診しましょう。大量の水分を摂取しても喉の渇きが改善しない場合は、要注意です。
以下の記事では、健康診断では糖尿病が見逃されることがある理由や、見逃しを防ぐために取るべき対策について詳しく解説しています。異常がないと言われたのに不調が続く方は参考にしてください。
>>糖尿病は健康診断ではわからない?見逃されやすい理由と対策
頻尿
糖尿病になると、血糖値を下げるために尿を多く生成するため、頻尿の症状が現れます。夜間頻尿も、糖尿病の初期症状の一つです。頻尿は、膀胱炎や前立腺肥大症などの泌尿器系の疾患でも起こる可能性があります。糖尿病による頻尿は、排尿時の痛みや残尿感を伴わないことが多く、一度に排出される尿量が多いのも特徴です。
糖尿病の初期段階では、頻尿は自覚しにくい場合もありますが、排尿回数や尿量の変化に注意することで、早期発見につながります。日常生活の中で、トイレに行く回数が増え、夜中に何度もトイレに起きる、と感じたら医療機関への受診をおすすめします。
体重減少
体重減少は、糖尿病や1型糖尿病の初期症状で現れる人がいます。インスリンが不足すると、体はエネルギーを補うために脂肪や筋肉を分解し、体重が減少しやすいです。糖尿病は体重減少の他に、喉の渇きや頻尿も同時に現れる場合があります。症状が複数見られる場合は、糖尿病の可能性を考慮し、医療機関を受診することが重要です。
急激な体重減少は、疾患が隠れている可能性があるため、放置せずに医療機関を受診しましょう。糖尿病による体重減少は、適切な治療によって改善することが期待できます。
疲労感
高血糖値が続くと、エネルギー源である糖をうまく利用できず、エネルギー不足になり慢性的な疲労感や倦怠感を感じる傾向があります。糖尿病の疲労感は、睡眠不足や過労、貧血など他の原因と区別がつきにくいです。糖尿病の場合は、疲労感に加えて、喉の渇きや頻尿、体重減少なども同時に現れる人が多いです。
症状が複数見られる場合は、糖尿病の可能性を考慮し、医療機関を受診しましょう。
糖尿病の対処法
糖尿病でも生活習慣を正しく対処すれば、血糖値の管理や合併症の予防につながります。糖尿病の対処法は以下です。
- 低GIな食生活を意識する
- 食物繊維を摂取する
- 適度に運動する
- 禁酒・禁煙する
- 十分な睡眠を確保する
- 定期的に受診する
低GIな食生活を意識する
GI値(グリセミック・インデックス)は、食品が食後の血糖値をどの程度上昇させるかを示す数値です。GI値が高い食品は、血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌量を急増させます。GI値が低い食品は、血糖値の上昇が緩やかで、インスリンの負担を軽減します。
白米や食パンはGI値が高く、玄米や全粒粉パンはGI値が低い食品です。毎日の食事で、低GI食品を意識的に選び、取り入れることが大切です。主食だけでなく、おかずや間食にも気を配りましょう。野菜を茹でるよりも蒸したほうが、GI値が下がります。少しの手間で血糖値への影響をコントロールできるため、毎日のメニューにも変化が生まれます。
食物繊維を摂取する
食物繊維は、糖質の吸収を穏やかにするとされており、血糖値の変動を抑制する可能性があります。食物繊維は、コレステロール値や便通に対しても良い影響が期待されますが、効果には個人差があります。以下の食物繊維を多く含む食品を毎日の食事に取り入れましょう。
- ごぼう
- わかめ
- きくらげ
- 大豆
- 納豆
普段の食事に食材をプラスするだけで、食物繊維が摂取できます。食物繊維を意識して摂り、腸内環境を整えましょう。
適度に運動する
適度な運動は、糖尿病の血糖値をコントロールするうえで重要です。運動はインスリン感受性を高め、インスリンの働きを改善する効果があります。同じ量のインスリンでも、運動をしているほうが血糖値が下がりやすいです。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理なく続けられる運動を見つけ、習慣化することが大切です。
1回30分程度の軽い運動を週に数回行うだけでも、血糖値の管理に良い影響を与えたり、心血管疾患のリスク軽減につながったりします。運動は全身の健康維持に役立つためおすすめです。腎機能が低下している糖尿病患者さんは、激しい運動で症状が悪化する可能性があります。運動の種類や強度を主治医と相談したうえで行いましょう。
禁酒・禁煙する
糖尿病と診断された方は、医師と相談のうえ、禁酒・禁煙を検討しましょう。過度の飲酒は、血糖値のコントロールを乱し肝臓に負担をかけます。喫煙は動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中などのリスクを高めます。糖尿病の方は、合併症の発症リスクが健常者に比べて高いため、禁酒・禁煙は合併症予防のために重要です。
飲酒は、飲酒量や頻度に注意する必要があります。空腹時の飲酒は、低血糖を引き起こす可能性があるため、食事と一緒に摂取します。喫煙に関しても、禁煙は容易ではありませんが、医師や禁煙外来のサポートを受けながら、禁煙に取り組みましょう。
十分な睡眠を確保する
睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、血糖値のコントロールを困難にする可能性があります。睡眠不足は、食欲増進ホルモンの分泌を増加させるため、過食につながる可能性もあります。糖尿病の管理には、規則正しい生活リズムを維持し、質の高い睡眠の確保が重要です。
毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間を一定に保つ行動を意識しましょう。寝る前にカフェインを摂取したり、スマートフォンやパソコンを長時間使用したりすると、睡眠の質を低下させるため避けてください。不眠症状が継続する場合は、医師と睡眠導入剤を検討したり、睡眠専門医に相談したりするのも一つの方法です。
定期的に受診する
糖尿病は自覚症状が現れにくい病気です。定期的な検査を受けなかったり、症状を放置したりすると、病気が進行し合併症を引き起こすリスクがあります。糖尿病性腎症による腎不全や、糖尿病網膜症による失明など、糖尿病の合併症は生活の質を低下させる可能性があります。
定期的に医療機関を受診し、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)などの検査を受けることで、病状の早期発見・早期治療につながります。HbA1cで血糖コントロールの状態を評価し、医師と相談のうえで治療計画を継続的に見直し、ご自身の状態に合った治療を続けることが大切です。
以下の記事では、糖尿病によって心臓や血管にどのような影響が及ぶのか、具体的な合併症のリスクとその対策方法について解説しています。心血管系への影響が気になる方は、ぜひご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
まとめ
糖尿病の尿検査では、尿糖や尿蛋白、ケトン体などをチェックします。定期的な検査は、血糖コントロールや腎臓の状態把握に欠かせません。検査結果を理解することは、糖尿病の早期発見・早期治療に役立ちます。糖尿病の初期症状である喉の渇きや頻尿、体重減少に注意が必要です。糖尿病と診断された後は、以下の対処法が重要です。
- 低GI食
- 食物繊維の摂取
- 適度な運動
- 禁酒・禁煙
- 十分な睡眠
- 定期的な受診
日頃の生活習慣を見直しながら、糖尿病と上手に付き合いましょう。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic Kidney Disease. Lancet, 2017, 389, 10075, p.1238-1252
- 厚生労働省:糖尿病(平成9年)
- 厚生労働省:糖尿病診療の現状(令和4年)
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







