blog
ブログ
ご家族に認知症の方がいると「将来、自分も発症するのでは?」と不安になる方は少なくありません。しかし、遺伝だけが原因となるケースはまれであり、多くは生活習慣などさまざまな要因が関わっていると考えられています。研究では、認知症のリスク要因のうち45%は、生活習慣の見直しなどによって予防できる可能性があると報告されています。
この記事では、認知症と遺伝の関わりについて正しい理解を深め、具体的な予防法まで詳しく解説します。認知症について、正しい知識を身につけ、不安を和らげましょう。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
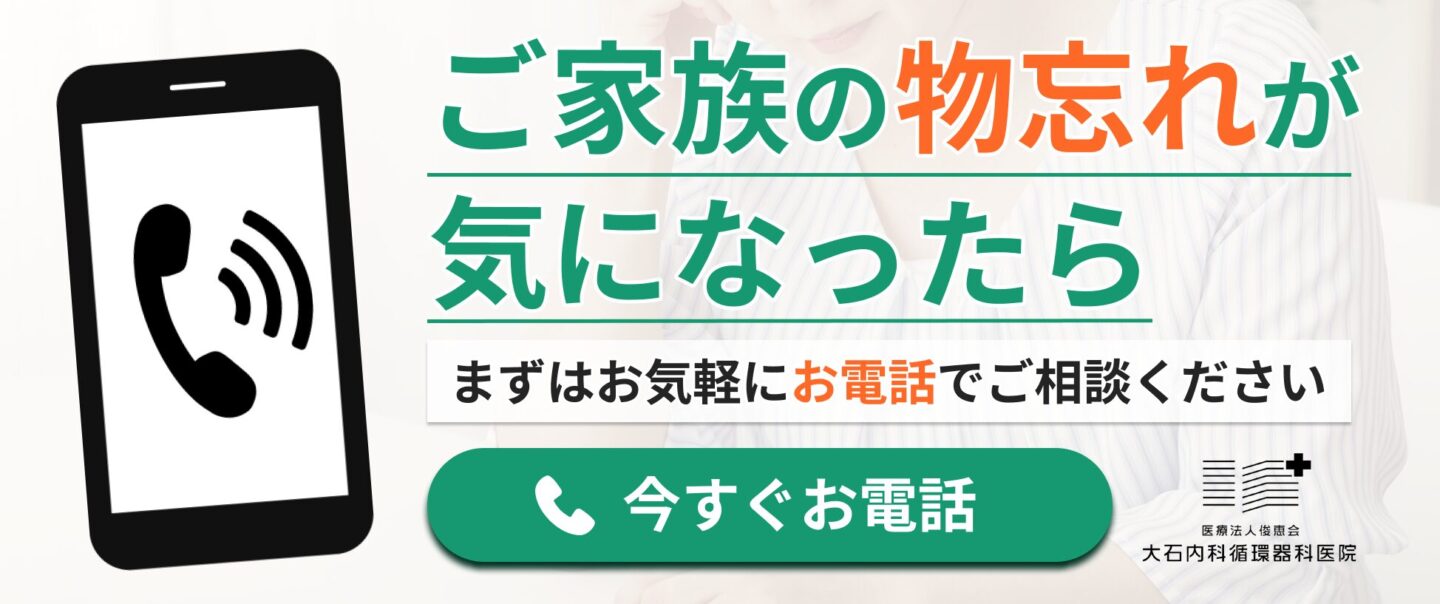
遺伝が関係する認知症のタイプ
遺伝が関係する認知症のタイプは、以下のとおりです。
- 家族性アルツハイマー病
- 前頭側頭型やレビー小体型認知症
家族性アルツハイマー病
家族性アルツハイマー病は、アルツハイマー病の全体の1%未満とまれな病気です。遺伝する力が強く、特定の遺伝子の変化が原因で起こります。家族性アルツハイマー病の特徴は、以下のとおりです。
- 若い年齢で発症しやすい
- 進行が速い傾向がある
- 遺伝の確立がはっきりしている
通常のアルツハイマー病は65歳以降に多いですが、家族性アルツハイマー病は、30〜50代で発症する方もいます。症状が速く進行することも特徴であり、原因となる遺伝子を受け継ぐと、高い確率で発症する可能性があります。家族性アルツハイマー病の原因の遺伝子は以下のとおりです。
- APP遺伝子
- PSEN1遺伝子
- PSEN2遺伝子
APP遺伝子はアミロイドを作るタンパク質の遺伝子です。50代前半で発症する可能性が高くなります。PSEN1遺伝子は、家族性アルツハイマー病の原因として最も多い遺伝子です。40代半ばに発症する可能性が高くなります。PSEN2遺伝子は日本ではまれな遺伝子です。中年期に発症する可能性が高くなります。
近年の研究では、アルツハイマー病に対する新たな治療アプローチとして、間葉系幹細胞を活用した再生医療などの治療法が開発されています。しかし、実用化には至っておらず、さらなる検証が必要です。
前頭側頭型やレビー小体型認知症
アルツハイマー病以外にも、遺伝との関連が指摘される認知症に前頭側頭型やレビー小体型認知症があります。前頭側頭型の認知症は遺伝的な要因が強く、人の気持ちがわからなくなったり、言葉が出にくくなったりするのが特徴です。レビー小体型認知症は、実際にはないものが見える、体がこわばるのが特徴です。
認知症の原因が、すべて遺伝と関係するわけではありません。遺伝は数ある要因の一つであり、生活習慣を見直すことで認知症リスクを減らせる可能性があります。
もし不安を感じたときは、早めの検査で現状を確認することが安心につながります。以下の記事では、認知症の検査内容や受ける目安、検査の種類・流れについて詳しく紹介しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
認知症の発症リスクを高める要因
認知症の発症リスクを高める要因は、以下のとおりです。
- APOE遺伝子
- 生活習慣病(高血圧・糖尿病・肥満など)
- 喫煙・過度の飲酒
- 社会的な孤立
- 過去の頭部外傷
- 難聴やうつ病
APOE遺伝子
APOE(アポイー)遺伝子は、アルツハイマー型認知症の「なりやすさ」に関わる遺伝子です。病気の原因ではなく、リスクを高める要因の一つです。APOE遺伝子は、両親から1つずつ受け継ぎ、2つの組み合わせでタイプが構成されており、以下のタイプがあります。
- ε2(イプシロン2)タイプ
- ε3(イプシロン3)タイプ
- ε4(イプシロン4)タイプ
ε2タイプは、認知症の発症を抑える「守り」の働きがあります。ε3タイプは日本人に最も多いタイプです。ε4タイプは、組み合わせ次第では注意が必要です。研究では、ε4を1つ持つ人は数倍、2つ持つ人は十数倍から数十倍リスクが高まると報告されています。ただし、必ず発症するわけではなく、生活習慣や環境要因も大きく関わります。
ε4を持つことは珍しくなく、ε4を持っているからといって、必ず認知症になるわけではありません。持っていなくても発症する人はいます。大切なのは、ε4を持っていても、生活習慣の改善によって発症を遅らせる可能性があるということです。
なお、アルツハイマー型認知症の初期にはどのような症状が現れるのかを知っておくことは、早期発見・早期対処の大きな手助けになります。以下の記事では、アルツハイマー型認知症の初期症状や原因、治療法について詳しく解説しています。
>>アルツハイマー型認知症の初期症状は?発症する原因や治療法、早めの対処が大切な理由
生活習慣病(高血圧・糖尿病・肥満など)
高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣病は、認知症のリスク要因です。高血圧が続くと、血管に負担がかかり、血流が低下しやすくなります。脳細胞に酸素や栄養の供給が不十分になることが常態化し、認知症リスクにつながります。糖尿病はインスリンの働きが悪くなり、アルツハイマー病の原因物質が蓄積しやすくなります。
肥満は直接、認知症リスクを高めるわけではありませんが、高血圧や糖尿病の原因となるため、間接的に認知症リスクを高めます。適切な治療と生活習慣の見直しで管理できます。
喫煙・過度の飲酒
毎日の習慣である喫煙や飲酒も、ご自身の意思でコントロールできるリスク要因です。タバコの煙は、脳の血流が悪くなるだけでなく、脳細胞に悪影響を与える「酸化ストレス」を引き起こす可能性もあります。禁煙は、何歳から始めても決して遅くありません。
長期間にわたる過度の飲酒は、脳を縮ませ、認知機能を低下させます。アルコールの分解で大量に消費されるビタミンB1が不足し、記憶障害を引き起こすこともあります。大切なのは飲みすぎないことです。飲む量を決め、週に2日以上の「休肝日」を設けるなど、節度ある飲酒を心がけましょう。
社会的な孤立
人と話したり、一緒に活動したりすることは、認知機能を刺激し、脳の活性化に役立ちます。定年退職後や身近な人との別れをきっかけに、人との交流が減る「社会的な孤立」は、うつ病だけでなく認知症のリスクも高めることが知られています。社会的な孤立を避けるために、人との会話は大切です。
会話は脳に複雑な刺激を与えます。相手の話を聞いて理解し、自分の考えを話すプロセスは、脳のさまざまな部位を同時に使うため、高度なトレーニングになります。「一人でいるのが楽」と感じるときでも、意識して社会とのつながりを持ちましょう。
過去の頭部外傷
過去の事故で頭を強く打つ「頭部外傷」も、認知症リスクを高めます。特に、意識を失うほどの強い衝撃を受けた場合は、注意が必要です。頭に強い衝撃が加わると、脳の神経細胞が傷ついたり、脳内で炎症が起きたりします。過去の頭部外傷が、認知症の原因物質が蓄積する引き金になる可能性があります。
過去のけがは変えられませんが、未来の外傷は予防できます。階段に手すりをつけるなど、頭部外傷につながる転倒を防ぎましょう。
難聴やうつ病
難聴やうつ病も、適切な対処で改善できる認知症のリスク要因です。難聴になると、脳への刺激が減り、脳の活動が低下しやすくなります。「何度も聞き返すのが申し訳ない」と感じ、会話を避けるようになると、社会的な孤立にもつながります。「年のせい」と諦めずに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
うつ病になると、物事への興味や関心が薄れ、活動量が減少します。脳への刺激が少なくなり、認知機能が低下しやすくなります。うつ病による意欲の低下や思考力の低下は、認知症の初期症状に似ています。気分が落ち込む、何もする気になれない状態が続く場合は、一人で抱え込まず、専門医に相談してください。
認知症予防の4つの生活習慣
認知症予防の4つの生活習慣は、以下のとおりです。
- 食事療法:地中海式食事法
- 運動療法:コグニサイズ
- 人との交流を続けて脳を元気に保つ
- 生活習慣病から脳を守る健康管理
食事療法:地中海式食事法
体や脳は、毎日の食事から作られています。脳の健康を保つ食事法として、特に注目されているのが「地中海式食事法」です。地中海式食事法は、脳の「酸化」や「炎症」を抑える働きが期待できます。認知機能の低下を緩やかにする可能性が示唆されています。
近年の研究から、地中海式食事法や高血圧の予防のための食の「MIND食」という食事法も、認知症予防の観点から推奨されています。MIND食は、脳に良いとされる食品を積極的に摂り、脳に悪影響を与える食品を減らす食事法です。以下の食品を意識して食事に取り入れることが大切です。
- 魚(特に青魚)
- 色の濃い野菜や果物
- 良質な油(オリーブオイルなど)
- ナッツ類や豆類、全粒穀物
肉やバターなどの動物性脂肪、甘いお菓子やジュースの摂りすぎは、脳の炎症を促す可能性があるため、控えることを意識しましょう。
運動療法:コグニサイズ
運動には「脳由来神経栄養因子」を増やし、神経細胞を育てたり、細胞同士のつながりを強めたりする効果が期待されています。近年、運動と頭の体操を同時に行う「コグニサイズ」が推奨されています。コグニサイズのやり方のポイントは、体を動かしながら、脳が少し混乱するくらいの課題に挑戦することです。
以下にコグニサイズの一つとして、しりとりウォーキングの手順を示します。
- ウォーキングや足踏みを始める
- 一定のリズムで歩きながら、しりとりをする
- 慣れてきたら「動物の名前だけ」など、ルールを追加して難易度を上げる
「次は何だっけ?」と考えながら体を動かすことが、脳を刺激します。少し息が弾むくらいの有酸素運動を、週に合計150分程度行うことを目標に、楽しみながら続けましょう。
人との交流を続けて脳を元気に保つ
人との交流や社会的な役割を持つことは、脳の機能を維持するうえで重要です。人との交流がない場合、うつ病だけでなく認知症のリスクも高め、脳への刺激が減少します。意識的に社会との接点を持つことが大切です。社会とのつながりを保つ具体例は、以下のとおりです。
- 地域の趣味のサークルやボランティアに参加する
- 友人や家族と、週に一度は電話や対面で話す
- 地域のイベントや図書館、公民館へ出かける
- シルバー人材センターに登録してみる
- オンラインのコミュニティに参加してみる
役割を持って社会と関わり続けることは、心と脳の健康に不可欠です。
生活習慣病から脳を守る健康管理
食事や運動、社会参加は、すべて体の健康につながります。体の健康管理は、認知症予防の重要な土台です。特に、生活習慣病は自覚症状がないまま進行することが少なくありません。年に一度は必ず健康診断を受け、ご自身の体の数値をきちんと把握しましょう。
自分の体の状態を知り、早期に対策を始めることが、10年後、20年後のあなたの脳を守るための基本です。
まとめ
認知症への不安は、ご家族の経験を通じて強まることもあります。しかし、認知症は遺伝だけで決まるものではありません。日々の生活習慣を見直すことで、予防や進行の遅れにつながる可能性があります。大切なのは、バランスの良い食事や適度な運動、人との交流を楽しむこと、年に一度は健康診断でご自身の体と向き合うことです。
今日から始められる小さな一歩を、ぜひ意識して取り入れてみてください。心配なことがあれば、一人で抱え込まず、かかりつけ医などに気軽に相談してみましょう。
以下の記事では、認知症の進行を緩やかにするために医療機関で行われる治療や、日常生活で実践できる工夫について、医師監修のもと詳しく解説しています。
>>【医師監修】認知症の進行を止める方法はある?症状悪化を防ぐ治療や対策を解説
参考文献
- Gill Livingston, Jonathan Huntley, Kathy Y Liu, Sergi G Costafreda, Geir Selbæk, Suvarna Alladi, David Ames, Sube Banerjee, Alistair Burns, Carol Brayne, Nick C Fox, Cleusa P Ferri, Laura N Gitlin, Robert Howard, Helen C Kales, Mika Kivimäki, Eric B Larson, Noeline Nakasujja, Kenneth Rockwood, Quincy Samus, Kokoro Shirai, Archana Singh-Manoux, Lon S Schneider, Sebastian Walsh, Yao Yao, Andrew Sommerlad, Naaheed Mukadam. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet, 2024, 404, 10452, p.572-628
- Qianying Feng, Fengxia Chen, Rui Liu, Dan Li, Huigen Feng, Junzheng Yang. Mesenchymal stem cell application in Alzheimer’s disease. Regen Ther, 2025, 30, , p.439-445
- Yu Yamazaki, Na Zhao, Thomas R Caulfield, Chia-Chen Liu, Guojun Bu. Apolipoprotein E and Alzheimer disease: pathobiology and targeting strategies. Nat Rev Neurol, 2019, 15, 9, p.501-518
- Oliwia Stefaniak, Małgorzata Dobrzyńska, Sławomira Drzymała-Czyż, Juliusz Przysławski.Diet in the Prevention of Alzheimer’s Disease: Current Knowledge and Future Research Requirements.Nutrients,2022,14,21,p.4564
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







