blog
ブログ
ご家族が認知症と診断されたとき、以前とは異なる言動に戸惑い「どう接すればいいの?」と不安を抱くのは自然なことです。認知症は記憶障害や言語機能の低下、認知機能の変化などの症状を伴う疾患です。
現在、医学研究では間葉系幹細胞を活用した再生医療などの治療法が開発されていますが、実用化には時間を要するとされています。重要なのは、認知症の方との適切な接し方を学び、日常生活の質(QOL)を向上させることです。認知症によって最も大きな不安と混乱の中にいるのは、ご本人自身です。
この記事では、認知症の方の心に寄り添い、穏やかな時間を取り戻すコミュニケーションの「コツ」を解説します。認知症の方の尊厳を守る接し方を学び、心安らぐ毎日への第一歩を踏み出しましょう。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
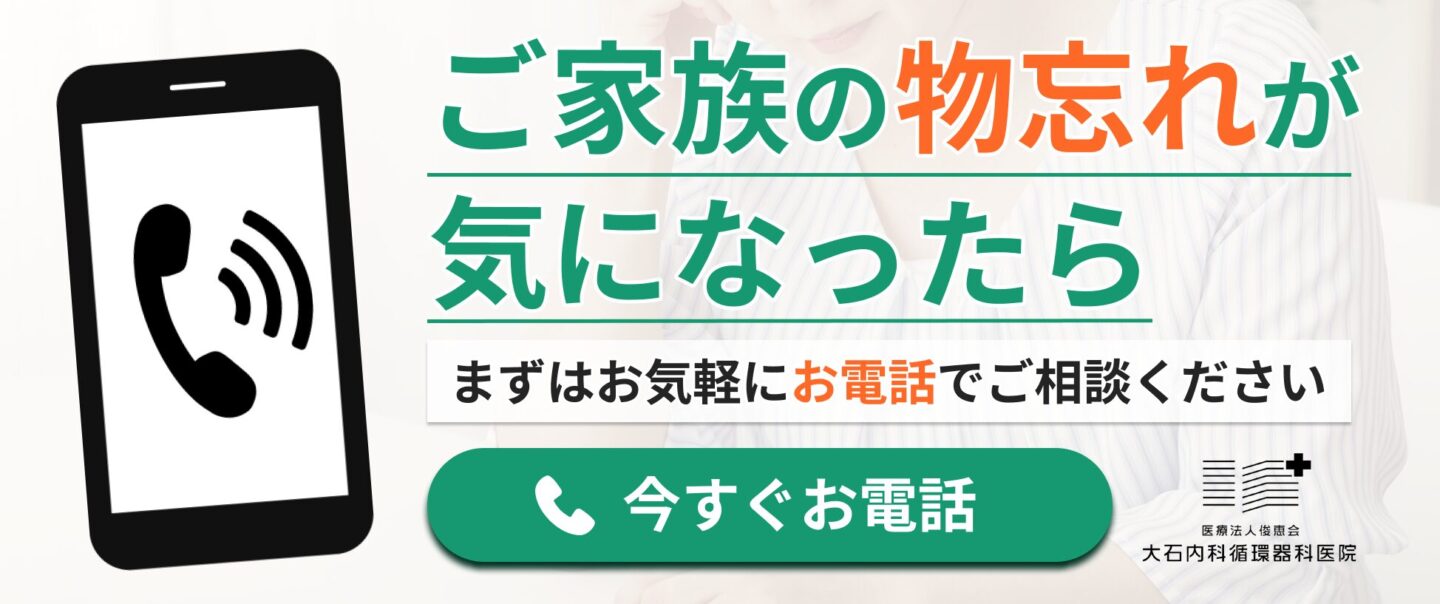
認知症の方への接し方で大切にしたい3つのポイント
認知症の方への接し方で大切にしたいポイントは、以下の3つです。
- 安心感を与える話し方を意識する
- 相手の目線に合わせて関わる
- 穏やかな声のトーンと表情を心がける
安心感を与える話し方を意識する
安心感を与える話し方のコツは、以下のとおりです。
- ゆっくり、はっきりと話す
- 短い言葉で、具体的に伝える
- 一度に伝える情報は一つだけにする
認知症の方は、脳が情報を受け取ってから理解するまでに、少し時間が必要です。早口で話されたり、難しい言葉を使われたりすると、内容が追いつかずに混乱してしまい、心を閉ざしてしまうことがあります。子ども扱いせず、相手の脳の情報処理のペースに合わせてあげる思いやりが大切です。
話し方を意識することで、認知症の方が「自分を理解してくれている」と感じ、落ち着いて会話ができる場合があります。
相手の目線に合わせて関わる
認知症の方と接する際には「目線を合わせる」行為が、私たちが思う以上に重要です。車椅子に座っている方やベッドで横になっている方を、立ったまま見下ろす体勢は、威圧感や不安感を与えてしまうことがあります。
相手と同じ高さまで目線を下げることで「あなたのことを大切に思っていますよ」という気持ちが、言葉以上に伝わります。相手を驚かせないためのチェックポイントは、以下のとおりです。
- 相手の視界に入る正面から、ゆっくり近づく
- 急に体に触れず、相手に認識してもらってから話しかける
- 車椅子や椅子に座っている方には、膝をかがめて目線の高さを合わせる
- 横になっている方には、ベッドの横に座るなどして、同じ高さから話しかける
認知症の方は視野が狭くなっている場合があり、視界の外からの動きに敏感に反応し、驚いてしまうことがあります。相手の視界に入り、声をかけましょう。小さな配慮は、信頼関係を築くうえでとても大切です。
穏やかな声のトーンと表情を心がける
穏やかな雰囲気を保つために心がけたいポイントは、以下のとおりです。
- 笑顔で接する
- 落ち着いた声で話す
- 話に耳を傾け、否定しない
認知症が進行すると、言葉の理解が難しくなることがあります。話している人の表情や声のトーンなど「雰囲気」から感情を敏感に感じ取る力は、認知症が進行しても保たれていることが多いです。言語を理解する脳の機能が低下しても、感情を司る部分は比較的保たれやすいことが一因と考えられています。
認知症の方は言葉の内容よりも、あなたの「感情」を感じ取っています。優しい言葉をかけていても、イライラした表情や低い声のトーンは、相手に不安を与えます。にこやかな表情と穏やかな声で接することで、認知症の方が安心感を抱くことができます。
こうした日々の接し方に加えて、進行を少しでも緩やかにするための治療や対策についても知っておくと安心です。以下の記事では、認知症の進行を緩やかにする方法や最新の治療法、日常生活でできる工夫について医師の監修のもと詳しく解説しています。
>>【医師監修】認知症の進行を止める方法はある?症状悪化を防ぐ治療や対策を解説
認知症ケアの基本対応として押さえたいこと
認知症ケアの基本対策として押さえたいことは以下のとおりです。
- 本人のペースに合わせて待つ姿勢を持つ
- 同じ話にも根気よく付き合う
本人のペースに合わせて待つ姿勢を持つ
認知症の方は、脳の情報処理に少し時間がかかるため、考えをまとめたり、次の行動に移ったりするのに時間が必要です。認知症の方の頭の中では、一生懸命に言葉を探し、手順を思い出しています。認知症の方を急かし、焦らせると、脳が混乱して不安になり、かえって時間がかかることがあります。
認知症の方のペースを尊重して「待つ」姿勢が、結果的にスムーズな進行につながります。すぐに手伝ってしまうと、認知症の方が持っている力を発揮する機会を奪うことにもなりかねません。認知症の方がご自身でできることは、なるべく見守ることを意識しましょう。
「待つ」ことが大切な場面は、以下のとおりです。
- 会話をしているとき:先回りして答えを言わずに、ゆっくり待つ
- 着替えや食事のとき:ご自身でできることは最後まで見守る
- 何かを決めるとき:すぐに答えが出なくても考える時間をつくってあげる
認知症の方のペースに合わせることは、ご本人の尊厳を守ることにつながります。すぐに行動を促すのではなく、一呼吸おいて見守る姿勢を心がけましょう。
同じ話にも根気よく付き合う
認知症の症状の一つに、新しい出来事を記憶しておくことが苦手になる「短期記憶障害」があります。脳の記憶を保存する機能がうまく働かないため、認知症の方に悪気があるわけではなく、本当に記憶していないのです。認知症の方にとっては、毎回が初めて口にする新鮮な話です。
漠然とした不安な気持ちから、安心したくて何度も同じ質問を繰り返す場合もあります。毎回初めて聞くような気持ちで、穏やかに耳を傾け、同じように答えてあげることが大切です。毎回同じように答える対応は、認知症の方の安心感につながる可能性があり、信頼関係を築くうえで重要と考えられます。
同じ話への対応のヒントは以下のとおりです。
- まずは受け止める:「そうなんですね」「なるほど」と、話に耳を傾け受け止める
- 話題を自然に切り替える:興味がありそうな別の話題を振る
- 言葉を行動につなげる
「お腹がすいた」と何度も言う場合は「では、おやつにしましょうか」と一緒にキッチンに立ってみましょう。認知症の方は言葉を具体的な行動に移すと、気持ちが切り替わることがあります。根気強く付き合うのは大変ですが、認知症の方の不安な気持ちに寄り添う視点を持つと、少し気持ちが楽になります。
認知症の方にしてはいけない3つの対応
認知症の方にしてはいけない対応は、以下の3つです。
- 否定・叱責・無視を避ける
- 焦らせることや命令口調にならないようにする
- 不安をあおるような言動を控える
否定・叱責・無視を避ける
認知症の方を頭ごなしに否定したり、間違いを指摘したりすることは避けましょう。やってしまいがちなNG対応は以下のとおりです。
- 「そんなことないでしょ」と間違いを正す
- 「何回同じことを言うの」とイライラして叱る
- 返事が面倒で、聞こえないふりをする(無視)
言動を否定されることは、認知症の方がご自身の存在を否定されたように感じてしまいます。否定されたときの悲しみや屈辱感は、記憶に深く刻まれるものです。「嫌な感情」が積み重なると、介護者に対して不信感を抱き、服薬や入浴を含むすべてのケアの拒否につながりかねません。
焦らせることや命令口調にならないようにする
認知症になると、脳が情報を処理したり、行動の計画を立てたりするのに時間がかかるようになります。時間がかかることを「遂行機能障害」と呼び、複数のことを一度にこなすのが難しくなるのです。認知症の方を焦らせることは大きなストレスとなり、かえって混乱や失敗を招いてしまいます。
「〇〇しなさい」という命令口調は、相手に威圧感や反発心を与え、頑なに行動を拒否する原因にもなりかねません。認知症の方の「やる気」を引き出す声かけの工夫は、以下のとおりです。
- 命令ではなく「提案・お願い」の形にする
- 選択肢を示して、自分で決めてもらう
認知症の方がご自身で選んで決める行為は、ご本人の満足感につながります。どうしても手伝いが必要な場合は「少しお手伝いしてもいいですか?」と一声かけてから、さりげなくサポートしましょう。
不安をあおるような言動を控える
認知症の方は、記憶が不確かになったり、今いる場所や時間がわからなくなったりします。介護する側の何気ない一言や態度が、認知症の方の不安を大きくしてしまうことがあるので注意が必要です。認知症の方の不安が強まると、落ち着きがなくなる、興奮することもあります。
認知症の方の言動の背景にある不安な気持ちに寄り添い、安心できる環境づくりを心がけましょう。以下の言動は認知症の方の不安を大きくさせます。
- 能力が落ちたことを指摘する:「どうしてそんなこともできないの?」「さっきも言ったじゃないですか」と指摘する
- ご本人の前で深刻な話をする:ご本人がいないかのように、病状や将来の介護について話し合う
認知症の方の不安な気持ちを理解し「大丈夫ですよ」「私がそばにいますからね」と、安心できる言葉をかけることが大切です。穏やかで落ち着いた環境を整えることが、認知症の方の心の安定に直接つながります。認知症の方は視野が狭く、視界の外からの動きに敏感にもなっているため、注意を払いましょう。
認知症の方と接する際に心がけたい4つのポイント
認知症の方と接する際に心がけたいポイントは、以下の4つです。
- 妄想や徘徊の背景にある不安を理解する
- 「帰りたい」の気持ちに寄り添う
- 暴言や拒否には冷静に対応する
- 食事・入浴拒否には無理強いせず工夫する
妄想や徘徊の背景にある不安を理解する
妄想や徘徊は認知症の代表的な症状で、単なる「困った行動」ではありません。妄想や徘徊は、認知症の方が感じている強い不安や、記憶の混乱からくる、心の叫び(SOS)です。物を置いた場所を忘れた不安から、脳が自分を守るために「誰かに盗られた」という物語を作り出すことがあります。
「そんなことはない」「あなたが失くしたんでしょ」と否定するのは認知症の方のプライドを傷つけます。「心配ですね」「よかったら一緒に探しましょうか」と、味方であることを示してあげてください。徘徊は、今いる場所がどこかわからなくなる「見当識障害」が原因で起こります。
仕事や夕飯の支度などの、過去の習慣や役割を思い出して行動している場合もあります。無理やり引き留めようとすると、目的を邪魔されたと感じてしまうことがあるため「どちらかへお出かけですか?」と優しく声をかけましょう。
「お茶を一杯飲んでからにしませんか?」など、関心を別のことにそらす工夫もおすすめです。
「帰りたい」の気持ちに寄り添う
認知症の方がご自身の家にいるにもかかわらず「家に帰りたい」と訴える「帰宅願望」も、よく見られる症状の一つです。「家に帰りたい」という言葉の裏には、以下の気持ちが隠されています。
- 不安感・疎外感:漠然とした居心地の悪さ
- 過去の記憶:実家や家族がいた場所など、心安らぐ場所の記憶の蘇り
- 役割の喪失:過去の役割を果たしたい気持ちの表れ
「家に帰りたい」という訴えがあったとき「ここがお家ですよ」と事実を伝えることは、認知症の方の混乱を大きくします。「お家に帰りたいのですね」と、まずは認知症の方の気持ちを丸ごと受け止めてあげてください。認知症の方が求めているのは、事実の訂正ではなく、不安な気持ちへの共感です。
言葉の背景にある寂しさや不安な気持ちを想像し「大丈夫ですよ」と寄り添うことが、何よりの安心につながります。
暴言や拒否には冷静に対応する
認知症の方の暴言や拒否は、脳の前頭葉という、感情をコントロールする部分の働きが低下するために起こる症状です。認知症の方は、不安や混乱、思い通りにいかないもどかしさを、うまく言葉で表現できません。暴言や拒否といった形で、認知症の方の感情が直接的に表に出てしまうのです。
暴言や拒否は認知症の方の性格が変わったわけではなく「病気の症状」だと理解することが重要です。冷静に対応するためのステップは、以下のとおりです。
- まずは距離を置く
- 原因を考える
- 気持ちを切り替える
感情的に言い返すと、状況は悪化するだけです。認知症の方の興奮が激しく、身の危険を感じる場合は、一旦その場を離れてお互いに気持ちを落ち着かせましょう。落ち着いてから、なぜ怒っているのか、拒否しているのかを考えてみます。
体調が悪い、何か嫌なことをされた、プライドが傷ついたなど、暴言や拒否には何らかの理由が隠されています。少し時間が経ってから、全く違う楽しい話題を振ってみるのも一つの方法です。
食事・入浴拒否には無理強いせず工夫する
認知症の方が食事や入浴を拒否することは珍しくありません。無理強いは認知症の方にとって苦痛なだけでなく、介護者との信頼関係を損なう原因にもなります。拒否の背景にある理由を探り、工夫をこらすことが大切です。考えられる食事の拒否理由は以下のとおりです。
- 食欲がない
- 口の中のトラブル(虫歯や合わない入れ歯)
- 食べ物だと認識できない
- うまく飲み込めない
食事拒否時の工夫は以下のとおりです。
- 本人の好きなメニューにする
- 食べやすいように細かく刻んだり、とろみをつけたりする
- 楽しい雰囲気で食事ができるように声をかける
研究により、バランスの良い食生活が認知機能の維持に有効である可能性が示唆されています。食事の拒否は、栄養状態が心配になりますが、無理強いはせず、少しでも栄養が摂れるようなアプローチを心がけましょう。完食を求めず、食べられる量やタイミングに柔軟に対応する姿勢も介護を続けるうえで重要な考え方です。
考えられる入浴の拒否理由は以下のとおりです。
- 裸になることへの恥ずかしさ
- 浴室が寒い
- 何をされるかわからない恐怖心
- お湯の温度が合わない
入浴拒否時の工夫は以下のとおりです。
- 浴室を事前に温めておく
- シャワーチェアを使う
- 手足だけ洗う「部分浴」や体を拭く「清拭」に切り替える
まとめ
認知症の方の一見不思議に思える言動は、大きな不安や混乱からくるSOSサインの場合があります。認知症の方の世界観を否定せず「そうなんですね」と気持ちに寄り添い、安心感を与えることが大切です。認知症の方への寄り添いは、認知症の方の尊厳を守り、穏やかな関係を築くための第一歩です。
介護をする中で、戸惑ったり、つい感情的になったりする日もあるかもしれません。完璧にできなくても、決してご自身を責めないでください。認知症の方とご家族にとって、少しでも心穏やかな時間が増えることを心から願っています。
なお、認知症の診断にはどのような検査が行われるのかを知っておくことも、ご家族が安心して対応するうえで役立ちます。以下の記事では、認知症の検査内容や受診のタイミング、検査の流れについて詳しく解説しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
参考文献
- Qianying Feng, Fengxia Chen, Rui Liu, Dan Li, Huigen Feng, Junzheng Yang.Mesenchymal stem cell application in Alzheimer’s disease.Regen Ther,2025,30,,p.439-445
- L N Blinkova, M A Yakushin, O V Karpova.NUTRITION MANAGEMENT FOR COGNITIVE DISORDERS AND DEMENTIA (OVERVIEW).Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhranenniiai Istor Med,2025,33,3,p.494-501
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







