blog
ブログ
「もしかして認知症の始まりでは?」と、ご自身や大切なご家族に起こる変化に、不安を抱えていませんか。現在の医療では、認知症の進行を完全に止めることは難しいものの、スピードを「穏やかにする」方法は数多く存在します。
「もの忘れが気になる」というご本人の自覚が、将来のリスクを示す重要なサインであり、早期の対策が鍵を握ります。この記事では、最新の治療薬から実践できる生活習慣まで、症状の悪化を防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。ご本人らしい穏やかな毎日を一日でも長く続けるために、確かな知識と希望を見つけましょう。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
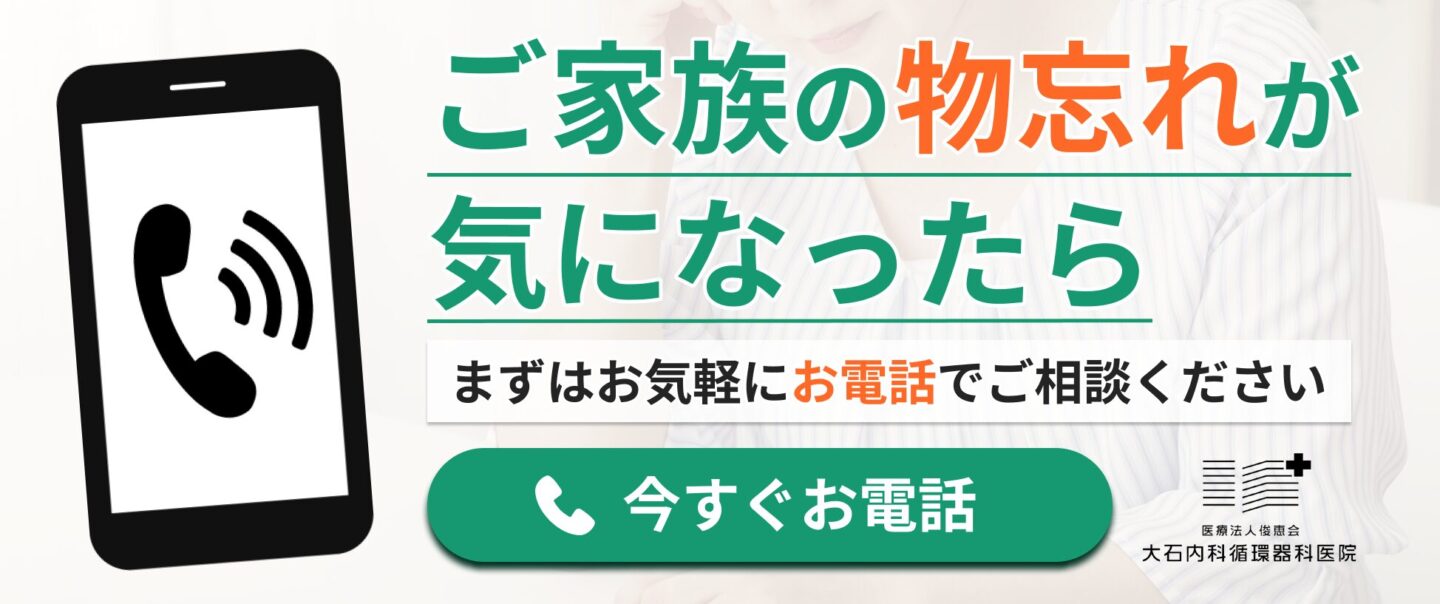
認知症の進行の完全な停止は困難
現在の医療では、認知症の進行を完全に止めることは困難です。認知症は、脳の神経細胞が少しずつ働きを失っていく病気です。一度働きを失った神経細胞を、完全に元通りにすることは簡単ではありません。進行のスピードを緩やかにするために、今からでもできることはたくさんあります。
大切なのは、病気のサインにできるだけ早く気づき、適切な対応を始めることです。「最近もの忘れが気になる」というご本人の自覚は「主観的認知機能低下(SCD)」と呼ばれます。客観的な検査では異常がなくても、ご本人が認知機能の低下を感じている状態です。
実際に、もの忘れなどの自覚症状が強いほど、将来的に軽度認知障害や認知症へ進むリスクが高まるという研究報告もあります。「年のせいかな?」と感じる症状の強さが、将来を予測する重要な手がかりです。ご本人やご家族が変化に気づいた時点で専門医に相談することが、進行を穏やかにする第一歩です。
早期から適切な対策を行うことで、ご本人らしい生活をより長く続けられる可能性が高まります。
認知症の進行を遅らせる2つの治療
認知症の進行を遅らせる治療は以下の2つです。
- 進行を穏やかにする薬物療法
- 脳を活性化させる非薬物療法
進行を穏やかにする薬物療法
薬物療法の目的は、記憶障害や判断力の低下といった症状の進行を緩やかにすることです。アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症など、特定の認知症に対して効果が認められた薬が使われます。脳の神経の働きを助け、情報伝達をスムーズにすることで、症状の進行を遅らせる効果が期待されます。薬の種類と効果は以下のとおりです。
- アセチルコリンエステラーゼ阻害薬:記憶障害や見当識障害(時間や場所がわからなくなる症状)の進行を緩やかにする
- メマンチン(NMDA受容体拮抗薬):イライラや興奮などの症状を和らげる効果が期待できる
飲み始めに吐き気や食欲不振などの消化器症状が出ることがありますが、多くは続けていくうちに体が慣れて軽くなります。副作用がつらい場合は、ご自身の判断で薬を中断せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。病気が進行し、ご本人の反応が乏しくなった状態では、薬を続けるメリットが少なくなるため、中止するという選択肢もあります。
以下の記事では、アルツハイマー型認知症の進行速度の特徴や、進行を緩やかにするための対処法を詳しく解説しています。
>>アルツハイマー型認知症の進行速度は早い?症状の変化と進行を緩やかにする対処法
脳を活性化させる非薬物療法
非薬物療法は、薬による治療と並行して、残っている機能をできるだけ維持・向上させる治療法です。 ご本人が楽しみながら取り組める活動は、心の安定にもつながり、生活の質を高めます。非薬物療法は以下の種類があります。
- 認知リハビリテーション:計算ドリルやパズル、塗り絵や書道、簡単な調理などで脳を刺激する
- 回想法:昔の写真や音楽を使って思い出を語り合い、自信や安心感を得る
- 音楽療法:懐かしい歌や楽器演奏を通して、リラックスすることで不安を和らげる
- 園芸療法:土に触れて植物を育てることで、五感を刺激し時間感覚を保つ
大切なのは「楽しいと感じられること」です。無理強いはせず、ご本人の興味に合わせて、できそうなことから試しましょう。ご家族や周りの方も一緒に楽しむことで、孤立を防ぎ、大切なコミュニケーションの機会にもなります。
最新の治療薬と治験の現状
近年、アルツハイマー病の進行の原因に働きかける、新しいタイプの薬が開発されています。代表的な薬が「レカネマブ(商品名:レケンビ®)」です。レカネマブは、アルツハイマー病の原因と考えられている「アミロイドβ」という異常なたんぱく質を、脳内から取り除く働きがあります。
レカネマブの使用によって、病気の進行を緩やかにする可能性があります。しかし、レカネマブは誰でも使えるわけではありません。レカネマブの治療のポイントは以下のとおりです。
- 対象となる方:ごく初期のアルツハイマー病と診断された方や特別な検査でアミロイドβの蓄積が確認された方
- 期待される効果:認知機能の低下スピードを平均で約27%遅らせることが報告されている
- 治療法:2週間に1回、病院で点滴によって投与する(所要時間:約1時間)
- 注意すべきこと:副作用として、脳のむくみや小さな出血が起こる可能性がある
世界中で、認知症への効果が期待される薬や治療法を見つけるための「治験(ちけん)」が数多く行われています。治験とは、新しい薬の候補が、本当に安全で効果があるのかを確かめるための研究です。薬だけに頼るのではなく、運動や食事といった日々の生活習慣を整えることが、脳の健康を守る土台として、重要です。
気になる症状があれば、専門の医療機関に相談し、ご自身やご家族に合った治療法を一緒に見つけましょう。以下の記事では、認知症の検査内容や受ける目安、検査の種類・流れについて詳しく紹介しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
認知症の進行を穏やかにする5つの生活習慣ポイント
薬による治療とあわせて、毎日の生活習慣を見直すことで、症状の進行スピードを穏やかにできる効果が期待できます。認知症の進行を緩やかにする5つの生活習慣について、以下のとおり解説します。
- 有酸素運動の習慣化
- バランスの良い食事と水分補給
- 人との交流を通じた活動
- 生活リズムの確立
- 心理的ケア
有酸素運動の習慣化
体を動かすことは、脳の健康にとって大切です。ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。有酸素運動は脳への血液の流れをスムーズにする効果が期待できます。脳に十分な酸素や栄養が届くことで、脳の神経細胞が活性化します。ハードな運動が難しくても、継続することが力になります。
運動を楽しく続けるポイントは以下のとおりです。
- 楽しむこと:景色を楽しんだり、音楽を聴いたりして運動に楽しさを取り入れる
- 無理のない範囲で:体調がすぐれない日は休み、自分のペースで続ける
- 誰かと一緒に:家族や友人と一緒に歩くと、会話もできて継続しやすくなる
バランスの良い食事と水分補給
脳が元気に働くためには、毎日の食事が重要な土台です。特定の食品だけを食べるのではなく、いろいろな食材をバランス良く食べることが、脳の健康を保つ秘訣です。特に、野菜や果物、魚、豆類などを食事に積極的に取り入れましょう。「主食・主菜・副菜」の摂取を意識すると、栄養のバランスが整いやすくなります。
主食・主菜・副菜の例は、以下のとおりです。
- 主食:ごはん、パン、麺類など
- 主菜:魚、肉、卵、大豆製品など
- 副菜:野菜、きのこ、海藻など
認知機能が低下している高齢者の方には、栄養不足が多く見られるという指摘もあります。食が細くなってきた場合は、栄養価の高いおやつを取り入れたり、栄養補助食品を活用したりするのも良い方法です。食事と同じくらい大切なのが水分補給です。体内の水分が不足すると、頭がぼんやりしたり、混乱したりする原因になります。
のどが渇いたと感じる前に、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。
人との交流を通じた活動
人と話したり、一緒に笑ったりすることは、脳にとって良い刺激です。人との交流が少ないと、認知症になる可能性が高まることがわかっています。家に閉じこもりがちになると、脳への刺激が減り、症状が進みやすくなるため注意が必要です。
家族や友人との会話、趣味のサークルへの参加、デイサービスの利用など、社会とのつながりを持ち続けることが、認知機能の維持に役立ちます。社会とのつながりを保つポイントは以下のとおりです。
- 会話の機会を持つ:週に1回以上、同居家族以外の人と話す機会をつくる
- 地域の集まりに参加する:地域のサロンや認知症カフェなど、気軽に立ち寄れる場所を探す
- 聞こえの問題に対処する:難聴は交流を避ける原因になるため、気になる場合は専門医に相談する
読書や囲碁、将棋、簡単な計算ドリルなど、頭を使う活動も脳を活性化させます。大切なのは、ご本人が「楽しい」と感じられることです。義務感でやるとストレスになるため、好きなことから始めてみましょう。
生活リズムの確立
睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、脳の健康を保つために不可欠です。眠っている間に、脳は一日の情報を整理し、不要になった老廃物を掃除しています。睡眠不足が続いたり、睡眠の質が悪かったりすると、脳の機能が低下し、認知症のリスクを高める可能性があります。
研究によると、睡眠時無呼吸症候群は、約1.3倍認知症になるリスクが高まります。睡眠時間が短すぎても長すぎても、脳の健康には悪影響を及ぼすため、適切な睡眠時間を取ることが大切です。レム睡眠行動障害では、レビー小体型認知症の前兆の可能性があります。
質の高い睡眠のためには、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることが基本です。日中に太陽の光を浴びて適度に体を動かすと、夜の自然な眠りにつながります。眠れない日が続く場合は、自己判断で睡眠薬を飲むのではなく、主治医に相談しましょう。
心理的ケア
認知症の進行には、心の問題も大きく影響します。ご本人が失敗を恐れたり、周りから責められたりなど強いストレスを感じると、症状が悪化することがあるため注意が必要です。ストレスを感じると、脳の中では「コルチゾール」というストレスホルモンが過剰になり、記憶を司る部分に悪影響を与えます。
大切なのは、ご本人の自尊心を守り、安心できる環境を整えることです。「どうして忘れるの?」と問い詰めるのではなく「大丈夫だよ」と寄り添うことが大切です。できなくなったことよりも、まだできることに目を向ける関わりが、ご本人の心の安定につながります。
介護をするご家族も、一人で悩みを抱え込まないでください。介護の疲れやストレスは、ご自身の心と体だけでなく、ご本人との関係にも影響します。心穏やかに過ごすためのポイントは以下のとおりです。
- ご本人の気持ちに寄り添う:間違いを正すよりも、話の背景にある感情に目を向ける
- 介護者が休憩をとる:介護サービスを活用し、自分の時間も大切にする
- 相談できる場所を見つける:地域包括支援センターや家族会などに相談する
注意すべき認知症の進行を早める3つの要因
認知症の進行を早める3つの要因は以下のとおりです。
- 入院や引っ越しなど急激な環境変化
- 考える機会の減少
- 乱れた生活習慣
入院や引っ越しなど急激な環境変化
慣れ親しんだ自宅から病院や施設へ移ることは、ご本人にとって想像以上に大きなストレスです。いつもと違う天井や知らない人の声、時間の流れなどの急激な変化は、脳がついていけず、混乱してしまいます。混乱状態を「せん妄」と呼び、時間や場所がわからなくなったり、落ち着きをなくしたりすることがあります。
ひどい場合には、現実にはないものが見える「幻視」といった症状が現れることも少なくありません。脳の混乱は、認知症の症状を一時的に悪化させるだけでなく、長期的な進行にも影響を及ぼします。環境の変化へのストレスを和らげる工夫は以下の3つです。
- 使い慣れたものを持ち込む
- 生活リズムを保つ
- 安心できる声かけを意識する
事前の心の準備として、入院や引っ越しの前に写真を見せたり、生活の話をしたりすることも大切です。
考える機会の減少
脳は、体と同じように使わなければ働きが鈍ってしまいます。毎日ただテレビを眺めているだけだったり、ご家族が身の回りのことをすべてやってしまったりすると「考える機会」が奪われます。脳への刺激が少ない生活は、認知症の進行を早める原因の一つです。
社会とのつながりが減ることは、気分の落ち込みや「うつ病」を招くこともあります。意欲がなくなると、活動量が減り、脳が刺激を受けないという悪循環に陥ります。生活の中に「考える機会」を作る工夫は以下のとおりです。
- ご本人に合った役割をお願いする:お茶碗を並べる、洗濯物をたたむなど、できる範囲の作業を依頼する
- 知的活動を習慣にする:新聞の音読や計算ドリル、日記を書くなどを取り入れる
- 外に出て五感を刺激する:散歩で季節の変化を感じたり、店先の品物について会話したりする
また、認知症に対して「遺伝するのでは?」と不安を抱く方も多くいらっしゃいます。実際には遺伝以外にもさまざまな要因が関与しており、予防できるケースもあります。以下の記事では、認知症の遺伝リスクや関係する要因、日常生活でできる予防策について詳しく解説しています。
>>認知症は遺伝する?考えられる要因や発症リスク、予防法を解説
乱れた生活習慣
食事や睡眠、運動といった基本的な生活習慣は、脳の健康を支える大切な土台です。生活習慣が崩れると、脳の働きに直接影響し、症状の悪化につながることがあります。食事のバランスが乱れると、脳に必要な栄養が届きません。塩分や動物性の脂肪が多い食事は、生活習慣病のリスクを高めます。
研究では「高コレステロール血症(血液中の油分が多い状態)」が、認知機能の低下を早める要因となる可能性が示されています。血液がドロドロになると、脳の血流が悪くなり、神経細胞がダメージを受けます。不規則な睡眠は、脳が情報を整理し、老廃物を掃除する大切な時間を奪います。
生活習慣の乱れは、認知機能だけでなく身体機能も悪化させ、日常生活全般に支障をきたす原因となります。以下を取り入れ、生活習慣の土台を立て直しましょう。
- バランスの良い食事:野菜・果物・魚・大豆製品を意識して取り入れる
- 質の良い睡眠環境:朝は日光を浴び、夜は暗く静かな環境で過ごす
- 日々の無理のない運動:散歩などの有酸素運動で脳の血流を促す
まとめ
現在の医療で認知症の進行を完全に止めることは困難です。薬による治療と、運動や食事、人との交流といった日々の生活習慣を組み合わせることで、進行のスピードを緩やかにできる可能性があります。大切なのは、できなくなったことではなく、まだできることに目を向け、ご本人の気持ちに寄り添うことです。
認知症の問題をご家族だけで決して抱え込まないでください。気になる変化に気づいたら、まずは専門の医療機関に相談し、ご本人とご家族に合ったサポートを一緒に見つけていきましょう。
参考文献
- David S Knopman.Lecanemab reduces brain amyloid-β and delays cognitive worsening.Cell Rep Med,2023,4,3,p.100982
- Yan-Peng Li, Yan-Yan Zhang, Xiao-Meng Du, Yong-Qing Ding, Jin Sun, Xiao-Yan Lang, Zhi-Yong Kang, Xiao-Dong Li.The relationship between sleep apnoea and the risk of dementia: An updated systematic review and meta-analysis.Folia Neuropathol,2024,62,4,p.406-415
- Frank Earl Robertson, Claudia Jacova.A Systematic Review of Subjective Cognitive Characteristics Predictive of Longitudinal Outcomes in Older Adults.The Gerontologist,2023,63,4,p.700-716
- Michelle Marshall, Joanne L Jordan, Ram Bajpai, Danielle Nimmons, Tilli M Smith, Paul Campbell, Kelvin P Jordan.Systematic review of prognostic factors for poor outcome in people living with dementia that can be determined from primary care medical records.BMC Geriatr,2024,24,1,p.801
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







