blog
ブログ
大切なご家族がアルツハイマー型認知症と診断され、先の見えない未来に不安を感じるのは当然のことです。「進行はどれくらい速いのか」「これからどう変化するのか」という疑問は、ご本人や支えるご家族にも切実な問題です。
この記事では、アルツハイマー型認知症の初期・中期・後期の各段階における具体的な症状の変化を詳しく解説しています。さらに、薬物療法から日常生活の工夫、期待される最新治療まで、進行を穏やかにするためのアプローチをわかりやすく紹介します。正しい知識で、これからの時間を穏やかに過ごすための準備を始めましょう。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
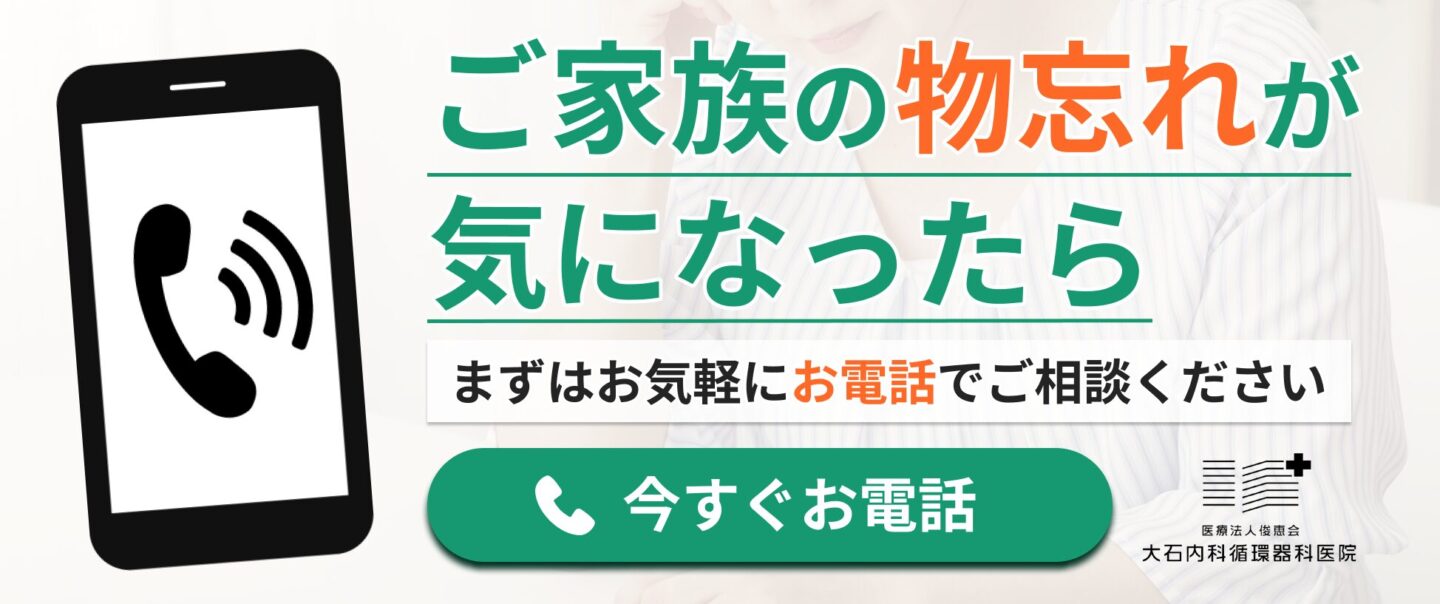
アルツハイマー型認知症の症状の変化
アルツハイマー型認知症の症状の変化について、3つ解説します。
- 初期(軽度)の症状
- 中期(中等度)の症状
- 後期(重度)の症状
初期(軽度)の症状
初期段階では、身の回りのことや日常生活の多くはご自身で行えます。しかし、ご本人や身近なご家族が「あれ、何かおかしいな」と感じ始める時期です。初期段階の平均的な期間は数年単位ですが、個人差が大きいのが特徴です。脳の機能が少しずつ低下することで、以下の症状が現れます。
- 記憶力の低下
- 判断力の低下
- 気分の変化
「ついさっきの出来事」を忘れてしまい「同じことを何度も質問する」「物の置き場所を忘れる」などが増えます。計画を立てて物事を実行することが苦手になり、料理の手順がわからなくなったり、お金の管理でミスが増えたりします。
ご自身でもの忘れを自覚しているため、不安になったり、落ち込んだり、いらだちやすくなることがあります。初期段階では、ご本人が一番つらさや戸惑いを感じています。軽度認知障害(MCI)という、認知症の一歩手前の状態から、1年で約5〜10%が認知症に移行するというデータもあります。
中期(中等度)の症状
中期に入ると脳の機能低下がさらに進み、日常生活を送るうえでご家族のサポートが欠かせなくなります。ご家族にとっては、今までとは違うご本人の言動に戸惑い、介護の負担を感じ始める時期です。
初期からの症状が悪化することに加え、以下の変化が現れます。
- 記憶障害の悪化
- 見当識障害
- 実行機能障害
- 行動・心理症状(BPSD)
最近の出来事だけでなく、古い記憶も曖昧になり、ご自身の年齢や経歴を忘れてしまうこともあります。時間や季節、場所などに関しては、慣れた場所で道に迷ったり、家族の顔がわからなくなったりします。服の着替えや入浴、トイレといった日常的な動作が一人では難しくなります。
理由もなく歩き回る(徘徊)、物を盗られたと思い込む(物盗られ妄想)、急に興奮したり大声を出したりします。行動・心理症状は、ご本人の不安や混乱、恐怖心から現れることが多く、決してわざと困らせようとしているわけではありません。症状を和らげるための治療薬の研究も進んでいます。
研究では、ナビキシモルス(nabiximols:日本未承認)が、興奮状態を安全に和らげる可能性があることが示されました。今後の治療の選択肢が増えることが期待されています。
後期(重度)の症状
後期になると、脳全体の機能が大きく低下し、常時介護が必要な状態となります。ご本人との言葉でのコミュニケーションは難しくなりますが、感情は最後まで残っていると言われています。穏やかに過ごせるよう、尊厳を守るケアが大切になります。後期段階で見られる主な症状は以下のとおりです。
- 高度な認知機能の低下
- 身体機能の低下(歩行障害・嚥下障害)
ご家族のこともわからなくなり、言葉での意思疎通がほとんどできなくなります。意味のある言葉を発することが少なくなる「失語」という状態です。筋肉がこわばり、歩くことが難しくなり、やがて寝たきりの状態になることがあります。飲食も難しくなり、むせやすくなります。
誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」から肺炎を起こすリスクも高まります。以下のような介護が必要になる可能性があります。
- 食事の介助(食べやすいように刻む・ペースト状にする)
- 排泄の介助(おむつの交換など)
- 体の清潔を保つケア(入浴介助や体を拭く清拭)
- 床ずれを防ぐための体位交換
ご家族だけですべての介護を担うのは心身ともに大変な負担となります。介護保険サービスなどを積極的に活用し、専門家のサポートを受けながらケアにあたることが重要です。
アルツハイマー型認知症の進行速度の違い
アルツハイマー型認知症の進行速度について、次の2点を解説します。
- 若年性アルツハイマー型認知症の進行が早いと言われる理由
- 他の認知症と比べた進行速度の違い
若年性アルツハイマー型認知症の進行が早いと言われる理由
65歳未満で発症するアルツハイマー型認知症は「若年性アルツハイマー型認知症」と呼ばれます。基本的な症状の経過は高齢で発症する方と同じですが、いくつか特徴的な点があります。進行速度については個人差が大きいものの、高齢で発症するケースと比較して進行が速い傾向があるという報告があります。
個人差が大きく、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。症状の現れ方にも人によって違いが見られることがあります。主な症状は以下のとおりです。
- 失語:初期症状と違い、一般的なもの忘れよりも、言葉が出にくい
- 失行:道具をうまく使えない
- 失認:物を見てもそれが何か認識できない
若年性アルツハイマー型認知症は、働き盛りや子育て世代で発症することが多いです。仕事の継続が困難になったり、経済的な問題に直面したりと、社会的・経済的な影響が出る可能性が高くなります。早期に診断を受け、利用できる公的支援や相談窓口につながり、生活設計を立て直していくことが重要です。
他の認知症と比べた進行速度の違い
認知症にはアルツハイマー型の他にもいくつかの種類があり、それぞれ進行の仕方が異なります。進行の仕方の違いを知っておくことは、適切な対応をするうえで役立ちます。アルツハイマー型認知症の進行の仕方の特徴は、以下のとおりです。
- 比較的ゆっくりと、着実に進行する
- 進行を完全に止めることは難しい
- 薬やリハビリテーションで進行を穏やかにできる可能性(個人差あり)
血管性認知症の進行には、以下の特徴があります。
- 脳梗塞や脳出血が起きるたびに、大きく悪化する
- 再発を防ぐ生活習慣の改善や治療が、進行を食い止める可能性がある
レビー小体型認知症は、症状が良いときと悪いときを繰り返す「波」があります。日によって、頭がはっきりしているときとぼんやりしているときの差が激しい特徴があります。
上記のように、認知症の種類によって進行パターンはさまざまです。もの忘れなどの症状が気になった場合は、自己判断せずに専門の医療機関を受診してください。正しい診断を受けることが、適切な治療やケアにつながる第一歩となります。
血管性認知症は、脳血管障害によって起こる認知症の一つで、早期の兆候や原因を知っておくことが予防や対処の鍵となります。以下の記事では、血管性認知症の初期症状や特徴、治療の選択肢について詳しく解説しています。
>>血管性認知症の初期症状は?原因や特徴、治療法を解説
アルツハイマー型認知症の進行を緩やかにする3つの方法
アルツハイマー型認知症の進行を穏やかにする3つの方法を、以下のとおり解説します。
- 脳の働きをサポートする薬物療法
- 脳機能の維持を目指すリハビリテーション
- 進行抑制が期待される最新治療薬
ご本人の状態に合わせて、できることから一つずつ始めていきましょう。
脳の働きをサポートする薬物療法
アルツハイマー型認知症の治療では、薬を使って症状の進行を抑え、残っている脳の機能をできるだけ長く維持することを目指します。現在、中心的に使われている薬は、脳の働きをサポートするものです。主な治療に用いられる薬は以下のとおりです。
- コリンエステラーゼ阻害薬
- NMDA受容体拮抗薬
コリンエステラーゼ阻害薬は、脳の中で情報を伝える「アセチルコリン」という物質が減るのを防ぎます。記憶力や判断力の低下といった中核症状の進行を緩やかにする可能性があります。効果には個人差があります。NMDA受容体拮抗薬は、神経細胞が過剰な刺激で傷つくのを防ぎ、脳を保護する働きがあります。
いらいらや興奮といった行動・心理症状(BPSD)を和らげる効果が期待される薬です。服薬により、吐き気や食欲不振、下痢などの副作用が出る可能性があります。気になる症状があれば、ご自身の判断で薬をやめず、必ず主治医や薬剤師に相談してください。
ご本人の興奮や攻撃性が強い場合には、気持ちを落ち着かせる漢方薬や抗精神病薬が使われることもあります。薬による治療と合わせて、日々の生活習慣を見直す「非薬物療法」は、進行を穏やかにするために重要です。ご本人が楽しみながら続けられることを見つけるのが、長続きのコツです。主な非薬物療法を以下にご紹介します。
- 食事の工夫
- 適度な運動
- 脳の活性化
- 人との交流
1日3食、栄養バランスの良い食事を心がけ、野菜や果物、魚、オリーブオイルなどをバランス良く摂りましょう。無理のない範囲で体を動かす習慣(散歩、ラジオ体操、軽い筋トレなど)をつくることをおすすめします。運動は脳の血流を良くし、気分転換にもつながると考えられています。
昔の趣味を再開したり、新しいことに挑戦したりしてみましょう。計算ドリルや音読、パズルなども脳への良い刺激になります。家族や友人と会話する時間も大切です。デイサービスや地域の集まりに参加するなど、社会とのつながりを保つことをおすすめします。
非薬物療法は、脳に適度な刺激を与え、心と体の健康を保つのに役立ちます。ご家族も一緒に楽しみながら、生活の中に取り入れてみてください。
脳機能の維持を目指すリハビリテーション
日常生活の工夫に加えて、理学療法士や作業療法士などの専門家のサポートを受けながら行うリハビリテーションも効果が期待できます。残された機能を十分に活かし、ご本人らしい生活を長く続けることを目指します。主なリハビリテーションの種類は以下のとおりです。
- 作業療法
- 理学療法
- 言語聴覚療法
作業療法では、食事や着替え、料理といった日常生活に必要な動作の練習を行います。手芸や園芸などの趣味活動を通して、手の細かい動きや集中力を維持し、生活に張りや楽しみを見出すことを目指します。理学療法では、歩行訓練や筋力トレーニングなどを行い、身体機能の維持・向上を図ります。転倒を防ぎ、安全に動ける体づくりをすることで、ご本人の活動範囲を広げることにもつながります。
言語聴覚療法では「話す」「聞く」「読む」といったコミュニケーション能力の訓練や、食べ物を安全に飲み込むための嚥下訓練を行います。ご家族との意思疎通を支え、食事の楽しみを保ちます。
リハビリテーションでは、ご本人の「まだできること」に焦点を当てることで、失われがちな自信や意欲を取り戻すきっかけにもなります。リハビリテーションは主に介護保険サービスなどを利用して受けることができます。
進行抑制が期待される最新治療薬
世界中で、アルツハイマー型認知症の原因物質に直接働きかけ、病気の進行を抑えることを目指した治療薬の開発が進められています。近年、特に注目されているのが、脳にたまる異常なたんぱく質「アミロイドβ」を取り除くタイプの薬です。日本でもこのタイプの薬が使えるようになり、治療の選択肢が一つ増えました。
神経細胞を守る新しい仕組みの薬の研究も進んでいます。「p75NTR」という神経細胞の働きに関わる部分に作用する飲み薬(LM11A-31:日本では未承認)の研究報告があります。軽度〜中等度の患者さんを対象に、薬の安全性が確認されました。
MRIなどの画像検査で評価したところ、病気による脳の変化を遅らせる可能性が示されました。研究の段階では、記憶力などのテストで明らかな改善は見られませんでした。今後は、より多くの患者さんを対象とした長期間の研究で、効果を詳しく調べていくことが期待されます。
新しい治療法は、対象となる方の病気の進行度などに条件がある場合がほとんどです。ご自身に適した治療法や最新の情報は、必ず主治医に相談するようにしてください。
症状の進行に備える公的支援サービス
症状の進行に備える公的支援サービスについて、以下の3つを解説します。
- 介護保険サービスの利用手続き
- 介護保険サービスの内容
- 介護者の心身ケア相談窓口
介護保険サービスの利用手続き
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。「介護や支援が必要な状態である」という認定(要介護認定)を受けるための、基本的な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相談・申請をする
- 認定調査を受ける
- 主治医の意見書
- 審査・判定
- 認定結果の通知
お住まいの地域にある「地域包括支援センター」か、市区町村の介護保険の窓口で相談し、申請します。地域包括支援センターは、高齢の方の暮らしに関する総合相談所です。市区町村の調査員がご自宅などを訪れ、心と体の状態について、ご本人やご家族からお話を聞きます。
普段の生活で困っていることや、手助けが必要なことを具体的に伝えることが大切です。市区町村からの依頼を受け、かかりつけの医師がご本人の病状に関する「主治医意見書」を作成します。普段からご本人の状態をよく理解している医師に依頼することが、適切な認定につながります。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が集まって審査します。介護がどのくらい必要か、度合い(要介護度)が決まります。申請してから原則30日以内に、要介護度が書かれた結果通知書と、新しい介護保険被保険者証が郵送で届きます。
介護保険サービスの内容
要介護認定を受けると、ご本人の状態やご希望に合わせ、さまざまなサービスを組み合わせて利用できます。サービスを上手に使うことは、ご本人の自立を支え、介護するご家族の負担軽減にも直結します。ご自宅で受けられる主なサービスは以下のとおりです。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所(ショートステイ)
訪問介護では、ヘルパーがご自宅を訪問します。食事や入浴、排せつの介助のほか、掃除や調理など生活のサポートをします。訪問看護では、看護師がご自宅を訪問します。血圧や体温などの健康チェックや、薬の管理、医療的なケアを行います。
訪問リハビリテーションでは、理学療法士などがご自宅を訪問します。身体の機能を保ち、転倒などを防ぐためのリハビリテーションを行います。通所介護(デイサービス)では、日帰りで施設に通い、食事や入浴の支援を受けます。他の利用者さんと交流したり、体操や趣味活動に参加したりします。
短期入所(ショートステイ)では、介護施設に短い期間宿泊するサービスです。ご家族が休息をとりたいとき(レスパイトケア)などにも利用されます。以上のサービスは、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家と一緒に計画を立てて利用します。ケアマネジャーは、ご本人とご家族にとって最適な介護を一緒に考えてくれるパートナーです。
介護者の心身ケア相談窓口
介護は長期にわたることが多く、ご家族の心と体には想像以上の負担がかかります。ご本人が理由なく興奮したり、強い不安を感じたりする行動・心理症状(BPSD)が現れると、ご家族はどう対応すれば良いかわからず、悩んでしまうことがあります。大切なのは、介護するご家族が一人で悩みを抱え込まないことです。
疲れたとき、困ったときには、ぜひ以下の相談窓口を頼ってください。
- 地域包括支援センター
- ケアマネジャー
- 認知症の人と家族の会
- 市区町村の高齢者福祉担当窓口
- シルバー110番
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える地域の総合相談窓口です。保健師や社会福祉士などの専門家が、介護の悩み全般に無料で応じてくれます。ケアマネジャーは、ケアプラン作成だけでなく、介護に関する最も身近な相談相手です。日々の小さな変化や悩みも、気軽に相談してみましょう。
認知症の人と家族の会は、同じ境遇にある人たちが集まり、情報交換をしたり、悩みを分かち合ったりできる場所です。他の人の経験を聞くだけで、気持ちが楽になったり、介護のヒントが得られたりすることがあります。市区町村の高齢者福祉担当窓口は、介護保険以外の公的なサービスや、地域の制度について相談することができます。
シルバー110番は、高齢者やそのご家族のための相談窓口です。各都道府県に設置されています。「#0808」とダイヤルするだけでつながり、日常生活の困りごとや介護・福祉、認知症に関する相談ができます。電話で気軽に相談したいときにおすすめです。
まとめ
ご自身やご家族の将来に、大きな不安を感じている方も多いです。病気の進行には個人差がありますが、薬や生活習慣の工夫、リハビリテーションなどを組み合わせることで、進行のスピードを緩やかにできる可能性があります。
大切なのは、ご本人もご家族も、決して一人で抱え込まないことです。介護保険サービスや地域の相談窓口など、皆さんを支える心強いサポーターがいます。不安なことやわからないことがあれば、まずは地域包括支援センターや主治医などの専門家に相談することから始めましょう。
以下の記事では、認知症の検査内容や受診のタイミング、検査の流れについて詳しく解説しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
参考文献
- Mitchell AJ, Shiri-Feshki M. Rate of progression of mild cognitive impairment to dementia–meta-analysis of 41 robust inception cohort studies. Acta Psychiatr Scand, 2009, 119, 4, p.252-265
- Grønning H, Rahmani A, Gyllenborg J, Dessau RB, Høgh P. Does Alzheimer’s disease with early onset progress faster than with late onset? A case-control study of clinical progression and cerebrospinal fluid biomarkers. Dement Geriatr Cogn Disord, 2012, 33, 2-3, p.111-117
- Christopher P Albertyn, Ta-Wei Guu, Petrina Chu, Byron Creese, Allan Young, Latha Velayudhan, Sagnik Bhattacharyya, Hassan Jafari, Simrat Kaur, Pooja Kandangwa, Ben Carter, Dag Aarsland.Sativex (nabiximols) for the treatment of Agitation & Aggression in Alzheimer’s dementia in UK nursing homes: a randomised, double-blind, placebo-controlled feasibility trial.Age Ageing,2025,54,6,afaf149
- Shanks HRC, Chen K, Reiman EM, Blennow K, Cummings JL, Massa SM, Longo FM, Börjesson-Hanson A, Windisch M, Schmitz TW.p75 neurotrophin receptor modulation in mild to moderate Alzheimer disease: a randomized, placebo-controlled phase 2a trial.Nat Med,2024,30,6,p.1761-1770
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







