blog
ブログ
女性の高血圧には、女性ならではの原因があるかもしれません。ホルモンバランスやライフスタイルの影響を受けやすいため、女性は高血圧になりやすいと言われています。
女性が高血圧になる原因は、更年期によるホルモン変化やストレス、遺伝などさまざまです。この記事では、女性が高血圧になる原因を解説し、具体的な対策方法を紹介します。健康的な生活を送るために、ぜひ参考にしてください。
大石内科循環器科医院では、高血圧の診療をしております。通院しやすい立地にあり、地域のかかりつけ医として診療を行っています。高血圧にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
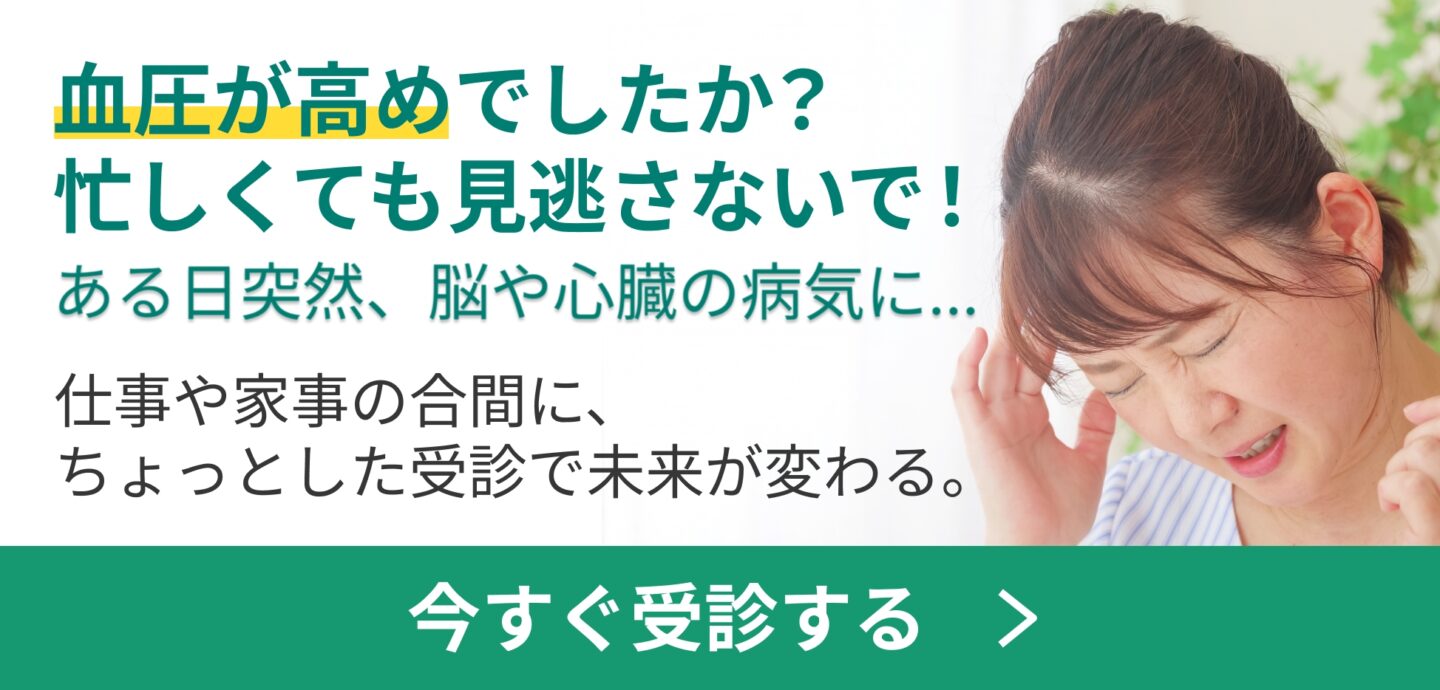
女性特有の高血圧の原因を解説
女性が高血圧になってしまうのは、男性と同じ原因だけではありません。女性ホルモンや、女性ならではのライフスタイルが関係していることもあります。女性特有の高血圧の原因を解説します。
更年期とエストロゲン減少がもたらす影響
40代後半から50代は「更年期」と呼ばれ、女性の身体は女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減っていきます。エストロゲンは血管をしなやかに保ったり、血圧を調整したりする働きがあります。エストロゲンが十分にあれば血管のしなやかさを保てますが、減少すると血管の弾力性が低下し、動脈硬化が進みやすくなるのです。
動脈硬化が進むと、血管の中は狭くなってしまい、血液が流れにくくなります。すると、心臓は血液を全身に送ろうと、より強い力で血液を送り出さなければならなくなります。上記の状態が続くと、血管にかかる圧力が高くなり、高血圧へとつながってしまうのです。
ストレスが高血圧に与えるメカニズム
ストレスは現代社会において多くの人が抱える問題の一つですが、実は高血圧との関連も指摘されています。私たちはストレスを感じると、体の中では交感神経が優位になります。交感神経の働きは、心拍数を上げたり、血管を収縮させたりすることで、血圧を上昇させる働きがあります。
緊張したり興奮したりすると、ドキドキと心臓が速く鼓動するのを感じるのは、交感神経が活発に働いているサインです。仕事でプレッシャーを感じているときや、人間関係で悩んでいるときなど、ストレスにさらされると交感神経が活発になり、血圧が上昇しやすくなるのです。
ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは身体をストレスから守るために分泌されるホルモンですが、血管を収縮させる作用があるため、長期間にわたって過剰に分泌されると高血圧のリスクを高める要因となります。ストレスをうまく解消し、心身ともにリラックスした状態を保つことが、高血圧予防には重要です。
ホルモンバランスの変化やストレスは、無自覚のうちに心臓や血管へ負担をかけます。以下のページでは、心臓の動きや機能を画像で調べる検査や、血管の硬さ・詰まりを客観的に評価する検査について解説しています。
遺伝的要因が女性の高血圧に関与する可能性
高血圧は、遺伝的な要因も影響する病気です。両親のどちらかが高血圧の場合、子どもが将来的に高血圧になる可能性が高くなると言われています。高血圧に関連する遺伝子が親から子に受け継がれるためです。
ただし。遺伝的に高血圧になりやすい体質を持って生まれたとしても、必ずしも高血圧になるとは限りません。高血圧は、遺伝的要因と生活習慣などの環境要因が複雑に関係して発症すると考えられており、環境要因の影響のほうが大きいという報告もあります。両親が高血圧でも、塩分控えめな食生活を心がけ、適度な運動を習慣にすれば、高血圧を発症しない可能性も十分にあります。
食生活が高血圧に与える影響
生活習慣病の代表格である高血圧は、毎日の食生活の積み重ねによって引き起こされます。高血圧の予防や改善をするために、どのような食生活を心がければ良いのか、具体的な方法を解説します。
塩分摂取と高血圧の関係
塩分の摂りすぎは、高血圧の最大の原因の一つです。塩分の主成分であるナトリウムは、体内の水分バランスを調整する役割を担っています。塩分を摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が高くなり、血液量が増加します。血液の量が増えると血管の内壁にかかる圧力が高まり、高血圧を引き起こしてしまうのです。
日本高血圧学会が推奨する1日の塩分の目標摂取量は6グラム未満です。外食や加工食品中心の食生活では、自分が思っている以上に多くの塩分を摂取している可能性があります。コンビニエンスストアの商品やファストフードなどは、塩分量が多い傾向です。
高血圧予防のためには、減塩を意識した食生活を心がけることが重要です。以下の方法を実践してみましょう。
- 醤油やソースなどの調味料を控えめにする
- だし汁や香辛料を活用して薄味にする
- インスタント食品や加工食品の摂取頻度を減らす
外食が多い方は、メニューを選ぶ際に、塩分量が少ないものを選ぶように心がけることも大切です。
食品添加物と高血圧のリスク
高血圧を予防、改善するためには、食品添加物を減らすことも重要です。
リン酸塩は加工食品の保水性や弾力性を高めるために、ハムやソーセージなどの加工肉製品、スナック菓子や清涼飲料水などに広く使用されています。リン酸塩を過剰に摂取すると、血管を収縮させる作用のあるカルシウムが体外に排出されやすくなります。結果、血管が収縮しやすくなり、血圧上昇につながってしまうのです。
リンはカルシウムの吸収を阻害する働きがあるため、過剰に摂取することで骨粗鬆症のリスクを高める可能性も懸念されています。
食品添加物は、品質を保持し風味や食感を向上させるために使用されますが、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼします。食品を選ぶ際には、原材料名表示を確認し、食品添加物が含まれている場合は、摂取量を控えましょう。
健康的な食事療法の選択肢
高血圧を予防・改善するための食事療法として、近年注目を集めているのが「DASH食」です。DASH食とは「Dietary Approaches to Stop Hypertension」の略称で、高血圧を予防、改善するために考案された食事療法です。DASH食では以下の食材を積極的に摂取します。
- 野菜
- 果物
- 低脂肪乳製品
- 全粒穀物
- 魚
- 豆類
- ナッツ類
DASH食は、飽和脂肪酸やコレステロール、塩分を制限することも特徴です。DASH食は高血圧だけでなく、脂質異常症や糖尿病、心臓病や一部のがんのリスクを低下させる効果も期待できます。
高血圧の予防、改善には、バランスの取れた食事が何よりも大切です。特定の食品に偏ることなく、主食、主菜、副菜をそろえて、多様な食品をバランス良く摂取しましょう。ゆっくりと時間をかけてよく噛んで食べることや、腹八分目を心がけることも重要です。食事は毎日の生活の楽しみの一つでもありますが、健康を維持するために、食生活を改善していきましょう。
生活習慣が高血圧に及ぼす影響
女性が高血圧になる原因には、生活習慣が大きく関わっていることをご存知ですか? 毎日のちょっとした心がけが、未来のあなたの健康を守ることにつながります。高血圧を防ぐための生活習慣について、具体的に見ていきましょう。
運動不足と高血圧の関連性
運動不足になると、血液の循環が悪くなり、心臓に負担がかかりやすくなります。すると、心臓は全身に血液を送り届けるために、より強い力で血液を押し出す必要があり、血管にかかる圧力が高くなってしまうのです。
運動不足が続くと、血管の柔軟性が失われて硬く狭くなり「動脈硬化」と呼ばれる状態になります。動脈硬化は高血圧を悪化させるだけでなく、脳卒中や心筋梗塞など、命に関わる病気を引き起こす要因の一つです。高血圧を予防し、健康な血管を維持するためには、日頃から適度な運動を心がけることが大切です。
激しい運動をする必要はありません。1日30分程度のウォーキングや軽いジョギングなどを行うだけでも、血圧を下げ、動脈硬化のリスクを減らせます。運動は、ストレス発散効果も期待できます。ストレスは交感神経を刺激し、血圧を上昇させる要因となります。運動によって心身のリフレッシュを図り、ストレスをうまくコントロールすることも、高血圧予防には効果的です。
運動療法については以下の記事で詳細に解説していますので、あわせて読んでみてください。
>>高血圧の運動療法のおすすめの方法や効果を高血圧治療ガイドラインをもとに解説!
アルコールと喫煙がもたらす危険性
お酒とタバコは、高血圧のリスクを高めるだけでなく、健康全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
アルコールを摂取すると、血管が一時的に拡張し、血圧が下がったように感じます。しかし、一時的な効果に過ぎず、時間が経つと血管が収縮し血圧が上昇してしまうので注意が必要です。大量のアルコールを一度に摂取すると交感神経が過剰に刺激され、血圧が急上昇する危険性もあります。
アルコールには利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうため、脱水症状を引き起こしやすいです。脱水症状になると血液の濃度が高くなり、血液がドロドロするので、血栓ができやすくなり脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まります。
タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させて血圧を上げる作用や、血管内皮細胞を傷つけて動脈硬化を促進する作用もあります。タバコを吸うと悪玉コレステロールが増え、動脈硬化の原因である脂質異常症のリスクが高くなり危険です。高血圧を予防し、健康な体を維持するために、禁酒や禁煙を心がけましょう。
睡眠不足と高血圧の関係
睡眠不足は、高血圧のリスクを高めるだけでなく、さまざまな体の不調を引き起こす可能性があります。睡眠中は血圧が低下し、心臓や血管を休ませられる時間帯です。しかし、睡眠不足が続くと休息時間が十分に確保できず、血圧を下げられません。
睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンの分泌にも影響を与え、食欲を増進させて代謝を低下させる可能性があります。結果、肥満のリスクを高め、高血圧をさらに悪化させてしまいます。
睡眠時間を確保するには、仕事の内容や時間帯を見直し、リラックスする環境を整えるなど、生活習慣全体の改善が必要です。良質な睡眠は、高血圧の予防だけでなく、心身の健康を維持するためにも欠かせません。
まとめ
女性は男性と比べて、ホルモンバランスやライフスタイルの違いから高血圧になりやすいです。特に更年期にはエストロゲンの減少によって血管の弾力性が低下し、高血圧のリスクが高まります。以下の要因も高血圧に影響を与えます。
- ストレス
- 遺伝的要因
- 食生活
- 運動不足
- アルコール
- 喫煙
- 睡眠不足
高血圧は放置すると、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な病気を引き起こす可能性があるため、日頃から健康的な生活習慣を心がけることが大切です。
高血圧について網羅的に知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
>>大石内科循環器科医院|高血圧の基礎知識・症状・治療について
参考文献
Erden M, Uyanik E, Demeestere I, Oktay KH. Perinatal outcomes of pregnancies following autologous cryopreserved ovarian tissue transplantation: a systematic review with pooled analysis. American journal of obstetrics and gynecology (2024).







