blog
ブログ
静脈血栓症は「足のむくみや痛み」など一見ありふれた症状から始まることが多く、初期段階では見逃されやすい病気です。しかし、血栓が進行すると血流を妨げ、最悪の場合は命に関わる肺血栓塞栓症を引き起こすこともあります。
長時間のデスクワークや旅行など、私たちの日常に潜む生活習慣がリスクを高めるため、他人事ではありません。この記事では、初期サインから重症化の兆候、日常生活で注意すべき点まで解説します。正しい知識を持つことで、早期発見や予防につなげ、ご自身や大切な人の健康を守る一歩となるはずです。
静岡市の大石内科循環器科医院では、静脈血栓症をはじめとする血管の病気に対して、丁寧な診察と超音波検査などを用いた的確な診断を行っています。 足の違和感や不安な症状がある方は、早めの受診で重症化を防ぐことが大切です。当院では安心して検査・治療を受けていただける体制を整え、ご自身やご家族の健康をしっかりサポートいたします。
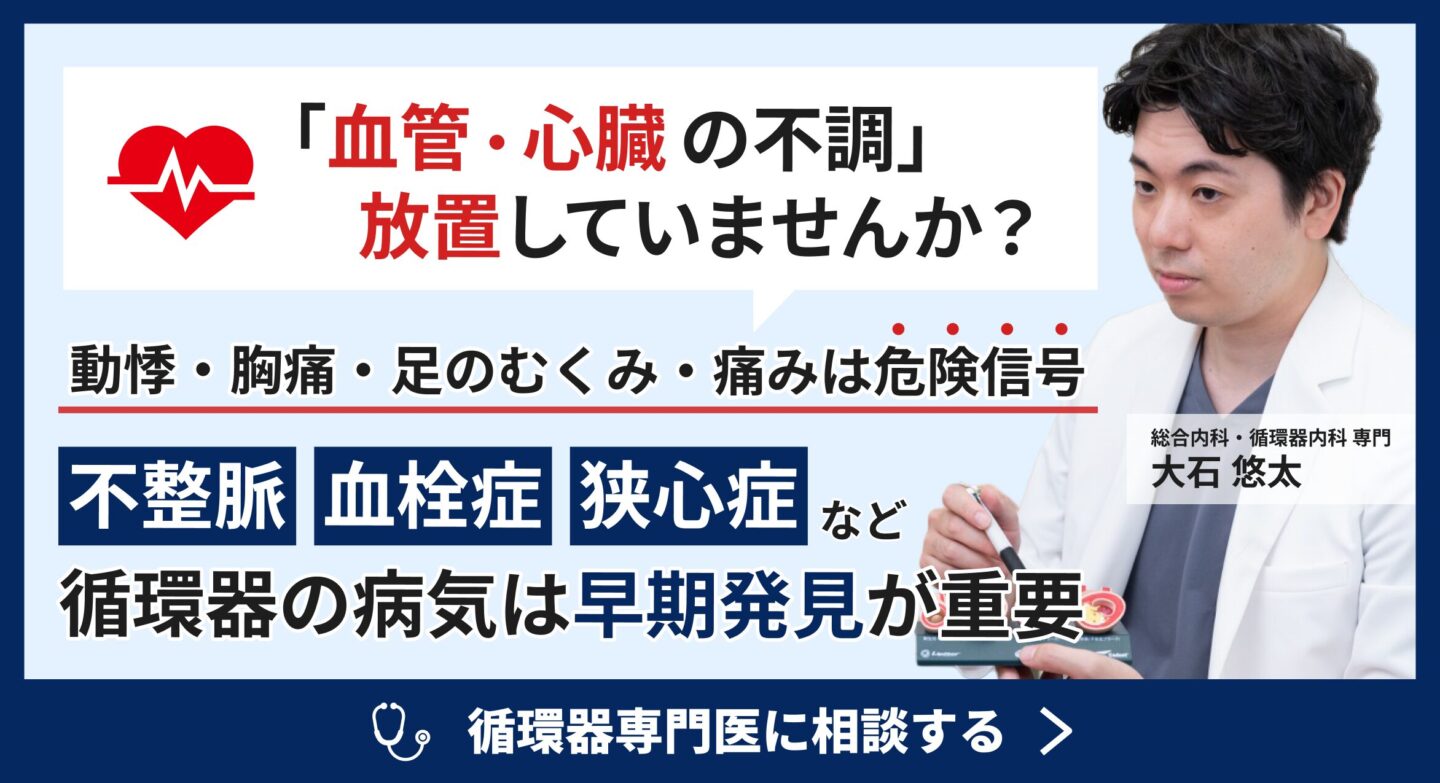
静脈血栓症の主な症状5つ
静脈血栓症は、静脈に血の塊(血栓)ができて血流を妨げる病気です。初期段階では自覚症状が乏しいこともありますが、進行すると重篤な合併症につながる恐れがあります。ここでは、代表的な5つの症状を取り上げ、それぞれの特徴や注意すべきポイントを解説します。
足の腫れや痛み:初期症状の見逃し注意
静脈血栓症の初期症状で最も多いのが、片足に現れる腫れや痛みです。 血栓によって血流がせき止められると静脈内の圧力が上がり、足に水分や血液が滞ることでむくみや違和感が生じます。普段の生活でありがちなサインだからこそ、見過ごしやすい点に注意が必要です。
代表的な症状には次のようなものがあります。
- 靴下の跡がいつまでも残る
- 夕方になると足がパンパンに張る
- 足に鈍い痛みや重だるさがある
- 歩いたり動かしたりすると痛みが強まる
これらは単なる疲労やむくみと勘違いされがちですが、静脈血栓症の可能性も否定できません。特に長時間のデスクワークやフライト後に症状が出る場合は要注意です。 こまめに立ち上がって足を動かす、軽いストレッチを行うなど、日常生活での小さな工夫が予防や早期発見につながります。
足における皮膚の変色:血流の変化を示すサイン
静脈血栓症が進行すると、脚の皮膚に赤みや紫色の変化が現れることがあります。 これは血流が滞ることで酸素が十分に行き渡らず、皮膚が異常な色調を示すためです。単なる皮膚トラブルに見えることもありますが、体からの重要なサインと受け止める必要があります。よく見られる変化には次のようなものがあります。
- ふくらはぎや足の甲が赤くなる
- 足全体が紫色に変色する
- 足の皮膚が熱をもって熱っぽく感じる
- 皮膚を触ると硬く感じる
赤みや熱感は炎症のサイン、紫色の変色は酸素不足を示す危険信号です。 こうした皮膚の異常は、血栓による血流障害がすでに進行している可能性を意味します。特に腫れや痛みと同時に現れた場合は重症化のリスクが高く、早めの医療機関受診が欠かせません。
日常の中で足の色や温度を意識することが、早期発見につながります。
胸の痛みや息切れ:重篤な症状の可能性
静脈血栓症の血栓が肺に移動すると、命に関わる「肺血栓塞栓症」を引き起こす危険があります。 その際に現れる代表的な症状が、突然の胸の痛みや強い息苦しさです。肺は酸素を取り込み全身へ供給する重要な臓器であり、その血管が塞がれると急激に酸素不足に陥ります。特徴的な症状として、以下が挙げられます。
- 胸に刺すような鋭い痛み
- 息を吸うと胸の痛みが強まる
- 呼吸が速くなり息苦しくなる
- 動悸が激しくなる
- 咳が出る
- 血が混じった痰が出る
これらの症状は心筋梗塞や肺炎など他の病気とも似ていますが、静脈血栓症を疑う状況では特に注意が必要です。 少しでも異常を感じたら自己判断せず、救急車を呼ぶなど一刻も早い対応が命を守る行動につながります。胸の痛みや呼吸の異変は軽視せず、重大なサインとして受け止めましょう。
不整脈のサインとしてよく現れる「動悸」については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
>>動悸の詳細はこちら
息切れ以外に現れる可能性のある症状
肺血栓塞栓症では、息切れだけでなく全身に酸素不足の影響が広がり、さまざまな症状が現れます。 血栓によって肺の血管が塞がれると、体は酸素を十分に取り込めなくなり、日常動作でも大きな支障を感じるようになります。代表的な症状には次のようなものがあります。
- 呼吸が速くなる
- 息を深く吸えない
- 唇や指先が青紫色に変色する
- 意識がもうろうとする
これらは体が深刻な酸素不足に陥っているサインであり、進行すると意識を失う危険もあります。 階段を上がる程度の動作で強い息苦しさが出たり、唇や指先の色が変化したりする場合は要注意です。静脈血栓症の既往やリスク要因がある人は特に警戒が必要であり、違和感を覚えたらすぐに医療機関を受診することが早期発見と救命につながります。
以下の記事では、「息切れ」の原因や注意すべきサインについて、より詳しく解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。
>>息切れに関する詳細を見る
日常生活への影響:静脈血栓症の管理方法
静脈血栓症は治療だけでなく、日常生活での工夫によって再発予防や症状の悪化防止が可能です。 医師の指示のもとで薬物療法を受けつつ、生活習慣の改善を取り入れることが重要です。特に意識しておきたい取り組みには次のようなものがあります。
- 弾性ストッキングを着用する
- 適度な運動を心がける
- 長時間同じ姿勢を避ける
- 水分をこまめに摂る
- 禁煙を徹底する
これらは血流を良くし、血栓ができにくい状態を保つために効果が期待できます。デスクワーク中でも1時間に一度は立ち上がる、飛行機に乗るときは足首を回すなど、日常に取り入れやすい工夫が大切です。
水分補給や禁煙もシンプルながら効果が期待されます。治療と合わせて生活習慣を見直すことで、再発リスクを減らし安心して日常生活を送ることにつながります。
静脈血栓症の原因
静脈血栓症の主な原因は以下のとおりです。
- 血流の低下
- 血液が固まりやすい状態
- 静脈壁の内壁の損傷
3つの要因はいずれも血栓をつくりやすい環境を生み出し、互いに重なり合うことで発症リスクを高めます。
血流の低下
血液の流れが滞ると、血管の中で血液が固まりやすくなり、静脈血栓症のリスクが高まります。通常、血液は筋肉の動きや呼吸によってスムーズに循環しています。しかし、長時間同じ姿勢を続けると流れが弱まり、血栓ができやすい環境が生まれます。以下のような場合に起こりやすいです。
- 長距離の飛行機やバス移動で座りっぱなしになる場合
- 入院や手術後で安静を強いられる場合
- 加齢や運動不足で下肢の筋肉ポンプが働きにくくなる場合
血流の低下は目に見えないため気づきにくいですが、足のむくみやだるさがサインとなることもあります。日常生活の中で定期的に体を動かし、下肢の循環を保つことが予防において重要です。
血液が固まりやすい状態
血液は本来、出血したときに固まって止血する大切な働きを持っています。しかし、体の中でその機能が過剰に働くと、必要のない場所で血栓ができやすくなり、静脈血栓症の原因となります。
脱水やホルモンの影響、病気の有無などによって、血液は通常より固まりやすい状態になることがあります。先天的に血液凝固因子に異常がある人は遺伝的にリスクが高まることも知られています。
こうした背景がある場合、知らないうちに血栓が形成されやすいため、体調の変化に注意し、必要に応じて医師と相談することが大切です。
静脈壁の内壁の損傷
静脈の内壁が傷つくと、その部分に血液が固まりやすくなり、血栓形成のきっかけとなります。損傷の原因にはいくつかの要因が考えられます。
- 外傷や手術による物理的なダメージ
- カテーテルの留置や注射など医療処置による刺激
- 動脈硬化や炎症などによる血管内壁の変化
このように静脈壁の損傷は、血液の流れを乱し、血小板や凝固因子が集まりやすい環境をつくります。一度損傷が起こると自然に修復されにくく、血栓の温床となるため注意が必要です。
特に動脈硬化は血管の柔軟性を損ない、血栓リスクを高める要因の一つです。以下の記事では、動脈硬化が体に与える影響や進行を抑える可能性のある方法を詳しく解説しています。
>>動脈硬化の詳細を見る
静脈血栓症の症状に関するよくある質問
静脈血栓症の症状について、よくある質問5つを解説します。
静脈血栓症の初期症状は何ですか?
静脈血栓症の初期症状は、片脚に現れるむくみや痛み、皮膚の赤みや熱感です。 特にふくらはぎや太ももに出やすく、日常的な疲れや筋肉痛と見分けにくいことが多いため注意が必要です。代表的なサインには次のようなものがあります。
- 足のむくみが片側にだけ出る
- ふくらはぎや太ももが重だるく感じる
- 皮膚に赤みや紫色の変化が出る
- 触ると熱っぽく感じる
- 鈍い痛みや違和感が続く
ただし、患者さんの約半数は無症状で経過するとも言われています。 そのため、「長時間座っていた後にむくみが取れない」「飛行機やバス移動後に足が張る」などの状況では、見逃さないよう注意することが大切です。軽い症状であっても、続く場合は早めに医療機関で相談しましょう。
静脈血栓症の症状が悪化するとどうなりますか?
静脈血栓症を放置すると、血栓が大きくなり命に関わる合併症を引き起こす危険があります。 足の症状だけでなく、全身に深刻な影響を及ぼすことがあるため、早期対応が欠かせません。主なリスクには次のようなものがあります。
- 足の腫れや痛みが悪化する
- 血栓が肺に移動し肺血栓塞栓症を起こす
- 突然の呼吸困難や胸の痛みが出る
- 脈が速くなり失神に至ることもある
- 先天的な心臓の穴がある場合は脳梗塞を発症する可能性
特に肺血栓塞栓症は発症が急激で、救命が難しいケースもあります。心臓に異常がある人では血栓が脳に達して脳梗塞につながる危険性もあるため注意が必要です。こうした重篤な合併症を防ぐには、症状が軽いうちに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
日常生活でできる予防法はありますか?
静脈血栓症予防には、長時間同じ姿勢を避けることが大切です。特にデスクワークや長距離移動時は、こまめに立ち上がってストレッチしたり、足首を動かす運動を行いましょう。適度な水分補給も血液をさらさらに保つため重要です。
肥満や喫煙、薬剤の使用歴がある場合は医師に相談し、リスク管理を心がけましょう。
静脈血栓症はどのように診断されますか?
診断は問診と身体所見のほか、Dダイマーという血液検査で血栓の存在を疑います。次に、足の静脈状態を超音波検査(エコー)でリアルタイムに確認し、血流の停滞や血栓を検出します。必要に応じてCT造影検査も行い、肺塞栓の有無を調べます。これらの検査を総合して診断が確定されます。
静脈血栓症の疑いがある場合、まず何科を受診すべきですか?
静脈血栓症が疑われる場合は、循環器内科や血管外科を受診するのが一般的です。 症状の程度によっては救急外来を利用する必要もあります。状況別の受診先は次のとおりです。
- 足の腫れや痛み → 循環器内科・血管外科
- 軽度のむくみや違和感 → かかりつけ医や内科でも相談可能
- 突然の胸痛や息苦しさ → 迷わず救急外来を受診
専門医が必要な場合は、医療機関から紹介を受けられることも多いです。静脈血栓症は軽い症状でも進行することがあり、放置すると重篤な合併症につながります。 そのため「少しおかしい」と感じた段階で早めに受診することが重要です。
まずは身近な内科でも構いませんが、必要に応じて専門科での詳しい検査や治療へとつなげてもらえます。
まとめ
静脈血栓症は、足の静脈に血の塊(血栓)ができる病気で、放置すると命に関わる肺血栓塞栓症へ進行する危険があります。静脈血栓症の症状として以下が挙げられます。
- 足のむくみや痛み
- 皮膚の変色
- 胸の痛み
- 息切れ
初期は軽いため見逃されやすいのが特徴です。そのため、早期発見と早期治療が何より重要です。予防のためには、長時間同じ姿勢を避け、こまめに休憩やストレッチを行うことで改善効果が期待できます。弾性ストッキングの着用や禁煙も血栓予防に役立ちます。
足のむくみや違和感、息切れなどの症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに早めに医療機関を受診してください。当院では循環器専門の診療を通じて、一人ひとりに合った検査と治療をご提案します。
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







