blog
ブログ
最近、ご家族や身の回りの高齢者が、些細なことで怒りっぽくなったと感じたことはありませんか?それはもしかしたら、年のせいではなく認知症の初期症状かもしれません。
日本では高齢化が進み、認知症患者数は増加の一途をたどっています。認知症は、もの忘れだけでなく、感情や行動にも変化が現れる病気です。これまで穏やかだった人が、些細なことで激昂したり、攻撃的な言動を見せるようになるなど、周囲を戸惑わせるケースも少なくありません。
この記事では認知症によって怒りっぽくなる原因や症状、具体的な例を交えながら解説していきます。高齢者の変化に戸惑っている方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
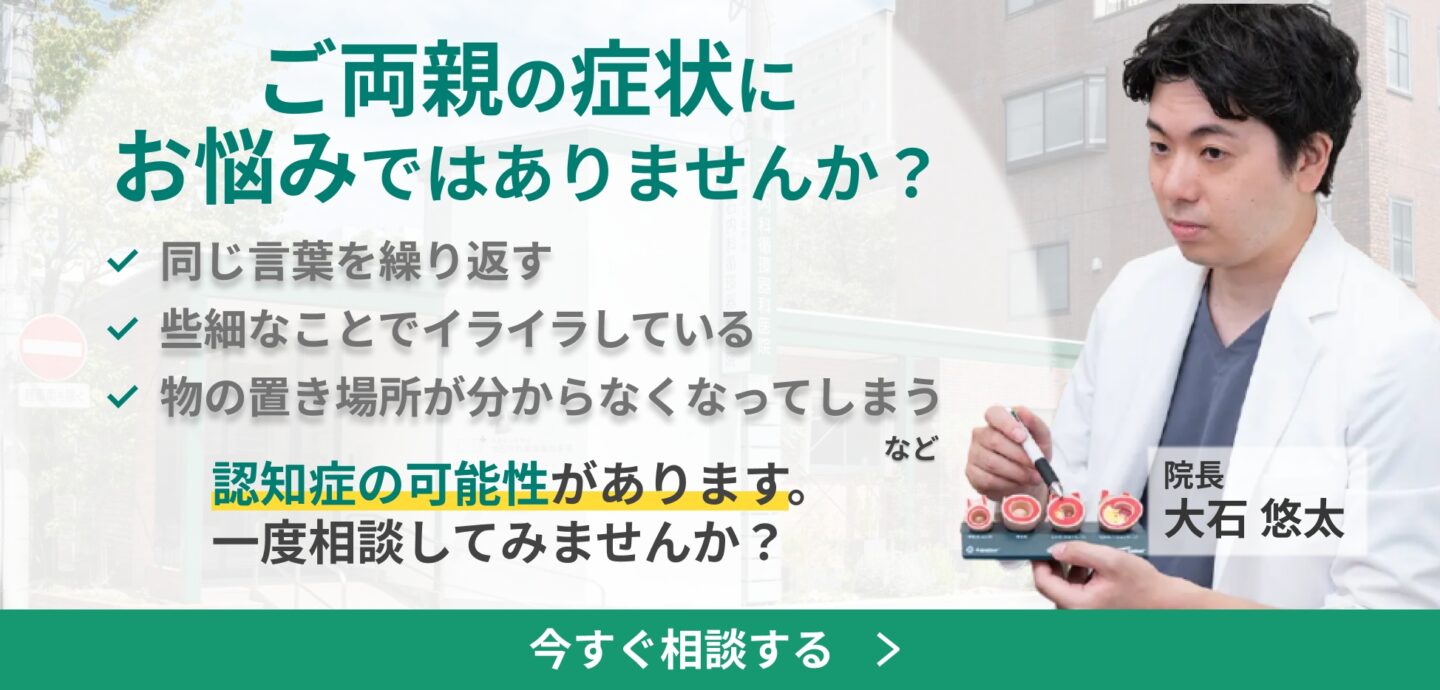
怒りっぽさは認知症のサイン?原因と症状、対処法を解説
最近、おじいちゃんやおばあちゃんが怒りっぽくなったと感じていませんか?もしかしたら、それは年のせいだけじゃなく、認知症の初期症状かもしれません。認知症は脳の働きがだんだん弱くなっていく病気で、もの忘れ以外にも感情の変化や行動の変化が現れることがあります。
これまで穏やかだった方が、些細なことで怒り出すようになったり、攻撃的な言動が増えたりするなど周囲が戸惑ってしまうケースは少なくありません。
例えば外来の待合室で順番を待っている際に待ち時間が長くなったことに腹を立てて受付のスタッフに大声で怒鳴ったり、他の患者さんに文句を言ったりする方がいらっしゃいます。
このような場合、周囲の方は驚き、戸惑いを感じられると思います。しかし認知症の初期症状として、感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなってしまうことが少なくないのです。
認知症による怒りっぽさの症状の特徴
認知症の人が怒りっぽくなるのは脳の機能が低下することで、感情をコントロールすることが難しくなるからです。
特に感情を司る脳の前頭葉と呼ばれる部分が萎縮してくると、怒りやイライラなどの感情を抑えにくくなり周囲に表現してしまうことがあります。
例えば、こんな風に感じたら認知症による怒りっぽさかもしれません。
- 些細なことで怒り出すことが増えた。
- 以前は怒らなかったようなことで、激しく怒るようになった。
- 怒っている理由が、わからないことが多い。
例えばテレビのリモコンが見つからないだけで、大声で怒鳴ったり物を投げたりすることがあります。
また「財布を盗まれた!」と家族を犯人扱いしたり「誰かが部屋に勝手に入ってくる!」と被害妄想を抱いたりすることもあります。
これらの症状は認知症の進行とともに悪化する傾向があり、日常生活に支障をきたす場合もあります。
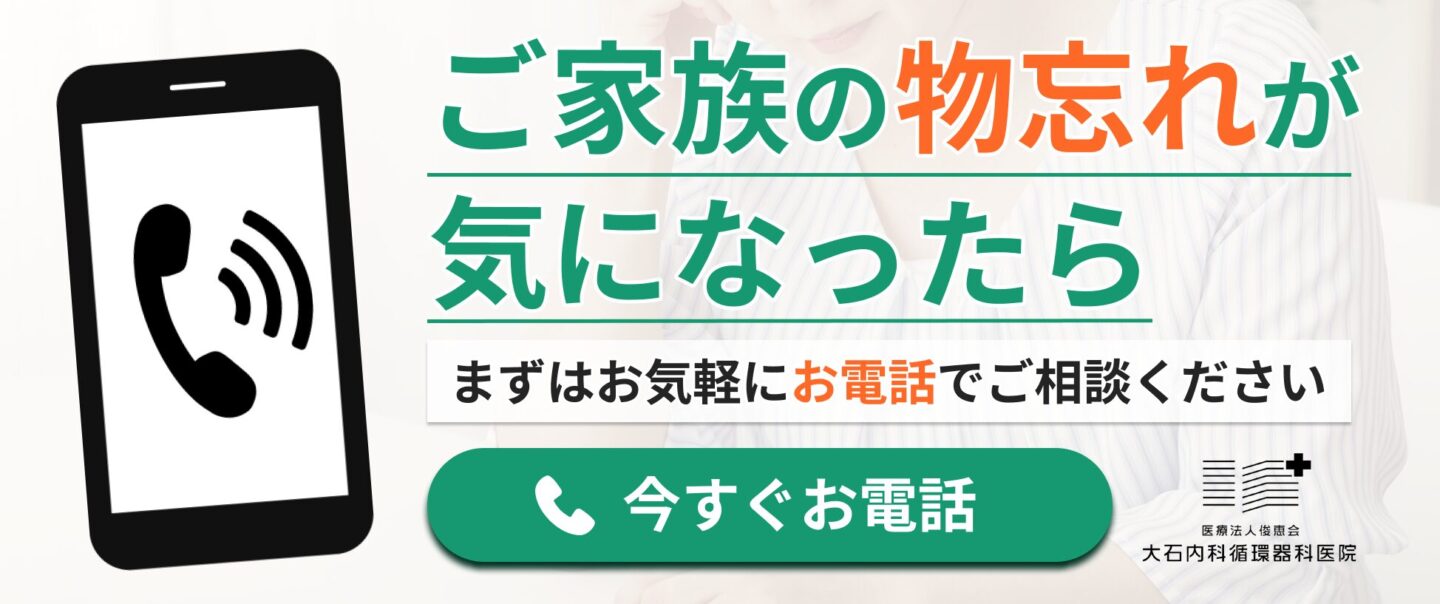
怒りっぽくなる認知症の種類と症状
認知症には、いくつかの種類があり怒りっぽさが目立つ種類もあります。
1. アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は認知症の中でも最も患者数が多いとされ、脳全体がゆっくりと萎縮していくのが特徴です。
- もの忘れがだんだんひどくなる
- 同じことを何度も聞いたり、言ったりする
- 時間や場所がわからなくなる
これらの症状に加えて感情の起伏が激しくなったり、些細なことで怒り出したりするようになることもあります。
進行すると、徘徊や妄想、睡眠障害などの行動・心理症状(BPSD)が出現することもあります。
2. レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで患者数が多い認知症です。脳内にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで、脳の神経細胞が壊れていく病気です。
- hallucinations(幻視)が見える:ありありとした人物や動物の幻視が見えることが多いです。
- 動作がゆっくりになったり、体が硬くなる(パーキンソン症状)
- 怒りっぽくなったり、不安が強くなったりする:特に、夕方から夜にかけて症状が強くなる傾向があります。
認知機能の低下とパーキンソン症状、幻視、行動・心理症状(BPSD)が特徴です。
3. 脳血管性認知症
脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって脳細胞がダメージを受け、認知機能が低下する病気です。
- 脳卒中の後遺症で、脳の機能が一部損なわれる
- 症状は脳卒中の部位や大きさによってさまざま
症状は階段状に悪化することが多く、比較的早期から抑うつ症状や感情失禁が出現しやすいのが特徴です。
認知症以外の原因で怒りっぽくなる病気
怒りっぽさは、認知症以外にも、様々な原因で起こることがあります。
- うつ病:気分が落ち込み、何事にも興味や喜びを感じなくなる。
- 脳腫瘍:脳に腫瘍ができることで、周囲の組織を圧迫し、様々な症状を引き起こす。
- 甲状腺機能亢進症:甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気。
また加齢に伴い脳の機能が低下することで、感情のコントロールが難しくなり怒りっぽくなることもあります。
もし身近な人が急に怒りっぽくなった場合は、自己判断せずに、早めに医療機関を受診しましょう。
まとめ
怒りっぽさは認知症のサインの可能性があり、特にこれまで穏やかだった人が些細なことで怒り出すようになった場合は注意が必要です。認知症は脳の機能低下により、感情コントロールが難しくなる病気です。アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症など、種類によって症状は異なります。認知症以外にも、うつ病や脳腫瘍などの病気でも怒りっぽくなることがあります。身近な人が急に怒りっぽくなった場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
当院は、認知症(物忘れ外来)を行っております。また、認知症の方でもご利用いただける認知対応型通所介護センター(デイサービス)も併設しております。気になる症状等がある方は、当院にご相談ください。
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







