blog
ブログ
心雑音とは、心臓の拍動に伴う異常な音のことです。健康な人でも聞こえることがあるため、必ずしも病気を意味するわけではありません。しかし、重大な心臓病のサインである場合もあります。
この記事では、健診で心雑音が見つかった際の重症度の見極め方と再検査方法について解説します。保護者の方に役立つ情報も提供します。ご自身の状況と照らし合わせながら、心臓の健康について考えるきっかけにしてください。
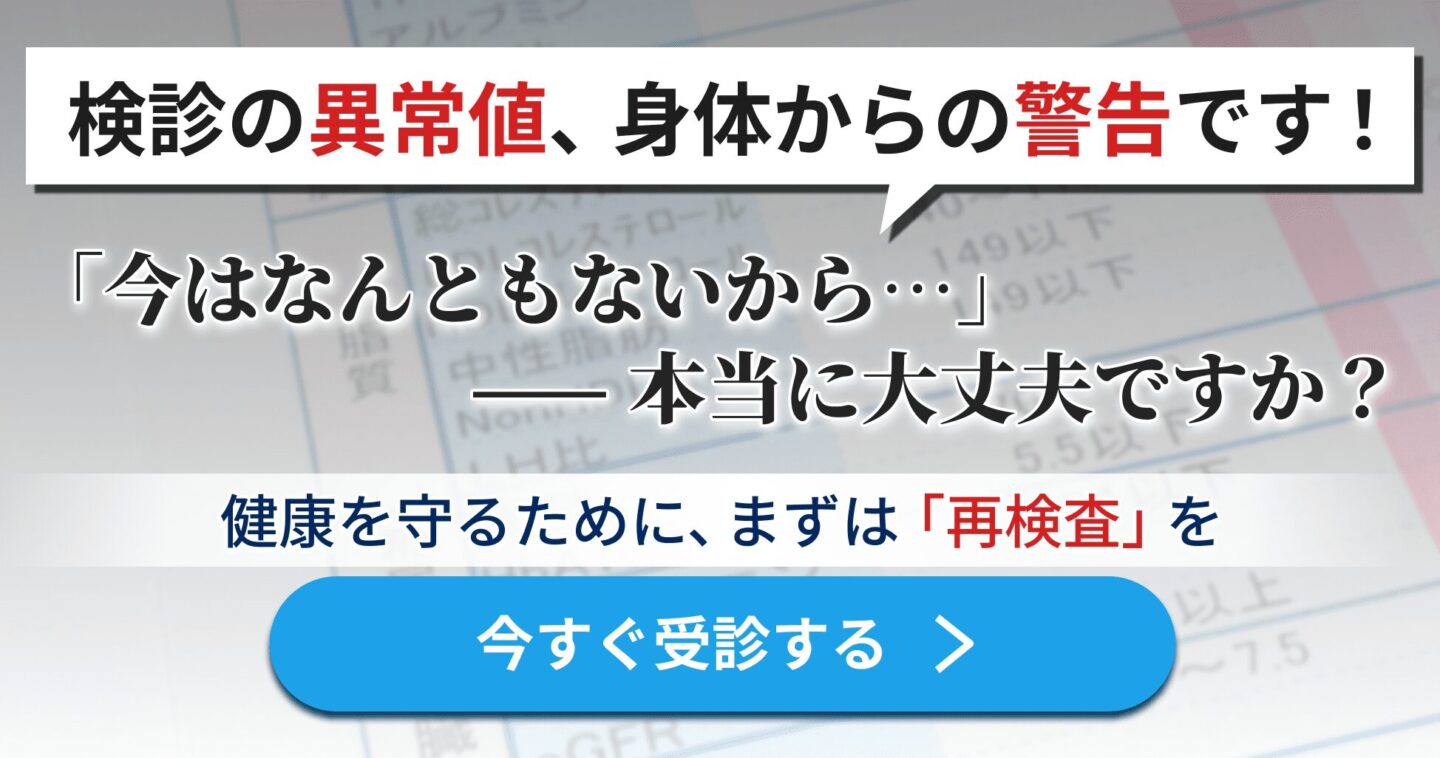
心雑音の種類4選
心臓から聞こえる「ドックン、ドックン」という音は、心臓が全身に血液を送るために働いている証拠です。心臓の音に混じる「ザー」や「シュー」といった雑音を「心雑音」と呼びます。心雑音の種類には、主に以下の4つがあります。
- 機能性心雑音:心配のない心雑音
- 器質性心雑音:治療を考慮する必要がある心雑音
- 小児の心雑音:成長とともに消失する場合も
- 妊娠中の心雑音:一時的なものが多い
機能性心雑音:心配のない心雑音
機能性心雑音は「生理的雑音」や「無害性心雑音」とも呼ばれています。心臓に異常がない場合や、心臓以外の原因で発生する心雑音です。健康診断で緊張しているときや運動後、貧血、発熱時など、一時的に心拍数が上昇したり血液の流れが変化したりする際に生じます。
聴診器で聞くと「シュー」という柔らかい音が聞こえることが多いです。血液が勢いよく流れる音で、心臓の弁や壁に異常があるわけではありません。機能性心雑音は、一般的に病気とはみなされず、多くの場合治療の必要はありません。他の心臓病との区別が重要なため、医師による診察と検査を受けることが推奨されます。
器質性心雑音:治療を考慮する必要がある心雑音
器質性心雑音は、心臓の構造的な問題により発生する異常音です。主な原因として、心臓弁膜症や心筋症、先天性心疾患などが挙げられます。器質性心雑音の特徴は、以下のとおりです。
- 心臓の弁や筋肉、血管の異常
- 心臓の機能に影響を与える可能性
- 症状の程度はさまざま
重症の場合、失神や突然死のリスクが高まる可能性があるため、医師の診断にもとづいた適切な治療が必要です。大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべんきょうさくしょう)では、弁が狭くなり心臓に負担がかかるため、状態に応じて薬物療法や手術が検討されます。
小児の心雑音:成長とともに消失する場合も
小児の心雑音は、子どもによく見られる症状です。子どもの胸壁(きょうへき)が薄いため、心臓に異常がなくても心雑音が聞こえることがあります。胸壁は、成長とともに心臓から離れるため、自然に聞こえなくなることが多いです。
小児の心雑音は、心室中隔欠損症(しんしつちゅうかくけっそんしょう)などの先天性心疾患が原因となる場合があります。心室中隔欠損症とは、心臓の壁に穴が開いている状態を指し、自然に穴が閉じる場合が多いです。
小児の心雑音を指摘された場合は、先天性心疾患などの可能性を考慮しましょう。医師の診察を受け、適切な検査を行うことが重要です。
妊娠中の心雑音:一時的なものが多い
妊娠中は、母親の心臓が胎児により多くの血液を送り出すために、拍動が強くなります。心臓の弁である大動脈弁や肺動脈弁の開きが悪くなり、弁膜症(べんまくしょう)と同じ心雑音が聞こえることがあります。多くの場合、心雑音は一時的なもので、出産後に自然に消失します。
妊娠前から存在していた心臓の病気が原因で、心雑音が聞こえる場合もあります。妊娠中に心雑音を指摘された場合は、医師に相談し、必要に応じて検査を受けることが重要です。
健康診断で異常を指摘された場合、どのように対応すべきか不安に感じることもあるかもしれません。再検査や治療の必要性について、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
心雑音の再検査方法
心雑音の再検査方法について、以下の内容を解説します。
- 聴診
- 心エコー検査
- 心電図検査
聴診
聴診は、聴診器を用いて心臓の音を直接聞く基本的な検査方法です。聴診では、心雑音の種類や大きさ、聞こえるタイミングなどを確認します。以下のポイントから、心雑音の原因や重症度をある程度推測することができます。
- 雑音が心臓の収縮期に聞こえるのか
- 拡張期に聞こえるのか
- 連続して聞こえるのか
聴診だけでは、心雑音の原因を特定することはできません。心臓に疾患が隠れている可能性がある場合は、さらなる精密検査が必要になる可能性があります。
心エコー検査
心エコー検査は、超音波を使って心臓の構造や動きをリアルタイムで観察する検査です。ゼリーを塗った探触子(プローブ)と呼ばれる装置を胸に当て、超音波を心臓に送受信することで、心臓の内部の様子を画像化します。
心エコー検査では、心臓の大きさや形、弁の開閉状態、心筋の厚さ、血液の流れなどを詳細に調べることができます。心雑音の原因となっている異常を特定するのに役立ち、心雑音の検査の中でも有用な検査方法です。
検査時間は20〜30分程度で、痛みはほとんどありません。費用は健康保険が適用されます。一般的に3割負担の方で数千円程度になる場合が多いです。
心電図検査
心電図検査は、心臓の電気的な活動を記録する検査です。手足と胸に電極を付け、心臓の収縮と弛緩のリズムや速さを調べます。心電図検査では、不整脈や心筋梗塞、狭心症など、心臓の電気的な活動に異常がないかを調べることが可能です。
心雑音自体は心電図には直接現れませんが、心雑音の原因となっている病気を発見できる場合があります。検査時間は5分程度で、痛みはありません。費用は、健康保険が適用されます。一般的に3割負担の方で数百円程度になる場合が多いです。
心電図検査以外にも、24時間心臓の動きを記録するホルター心電図検査や、運動負荷試験など、さまざまな種類の心電図検査があります。しかし、健診で心電図異常を指摘された場合は、異常の種類や原因によって適切な精密検査が必要となることがあります。
以下の記事では、健診で心電図異常を指摘された際の精密検査の流れや具体的な対処法について詳しく解説しています。検査を受けるべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
>>心電図異常を健診で指摘された方へ!精密検査の流れと対処法
心雑音が見つかった場合の対処法
心雑音が見つかった場合は、以下の対処法が挙げられます。
- 専門医への相談
- セカンドオピニオン
- 運動や食事の制限
- 精神的なケア
専門医への相談
心雑音が見つかったら、循環器内科などの心臓の専門医に相談することが重要です。専門医への相談では、問診や身体診察に加えて、心エコー検査や心電図検査、ホルター心電図検査、運動負荷心電図検査などが行われます。
専門医は、聴診器を用いて心音を注意深く聴診し、雑音の種類や大きさ、聞こえるタイミングなどを確認します。心雑音は大きく分けて「機能性心雑音」と「器質性心雑音」の2種類に分類されます。
機能性心雑音は、心臓に異常がない場合でも聞こえるので心配ありません。成長期のお子さんによくみられる機能性心雑音は、心臓の成長に伴い自然に消失することが多いです。貧血や発熱、妊娠中などでも一時的に心雑音が聞こえることがあります。
器質性心雑音は、心臓の病気によって引き起こされるため、精密検査が必要です。器質性心雑音の原因としては、弁膜症(心臓の弁の異常)や心筋症(心臓の筋肉の異常)、先天性心疾患(生まれつきの心臓の異常)などが挙げられます。
専門医は検査結果を総合的に判断し、心雑音の原因や重症度を評価し適切な治療方針を決定します。
運動や食事の制限
心雑音の種類や重症度によっては、日常生活で注意すべき点があります。健診で心雑音を指摘された場合は、専門医に相談することをおすすめします。ご自身の状態を正しく理解し、適切な生活習慣を心がけることが大切です。
重度の弁膜症などの場合は、激しい運動を制限する必要があります。心不全を合併している場合は、塩分や水分の摂取制限などの食事療法が必要になる場合があります。機能性心雑音の場合は、日常生活を過度に制限する必要はありません。
まとめ
心雑音は、健康な人にもみられる場合があります。多くの場合、治療の必要がないことが多いですが、精密検査が必要な場合もあります。
健康診断で、もし心雑音など指摘された場合には当院へご相談ください。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
E G Dimond, A Benchimol. Phonocardiography. Calif Med, 1961, 94(3), p.139-146.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







