blog
ブログ
健康診断の脂質検査で「要精密検査」に不安を感じたことはありませんか?血液中のコレステロールや中性脂肪の値が基準値を超えている状態を、脂質異常症といいます。脂質異常症は自覚症状がないまま進行し、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの病気を引き起こす可能性があります。
本記事では、脂質検査の見方や異常値が出た場合の対策、治療法をわかりやすく解説します。健康診断の結果は、現在の健康状態を客観的に知るための情報源です。脂質の検査結果を正しく理解し、生活習慣の改善や治療に役立てましょう。
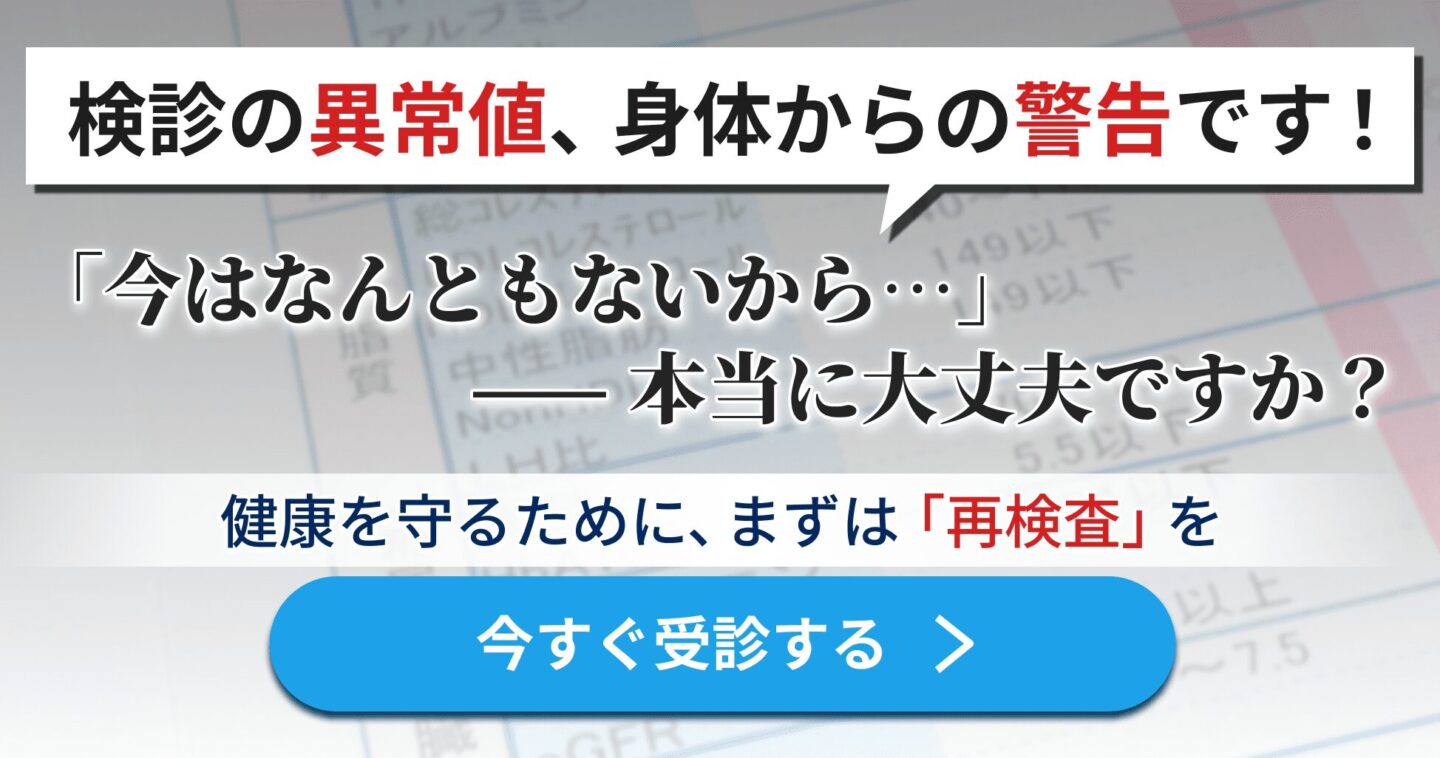
健康診断の脂質検査結果を正しく読み解くための基礎知識
脂質は、細胞膜の構成成分やホルモンの原料となるなど、体にとって欠かせない栄養素です。脂質検査結果の見方や異常値が出た場合の対処法について、以下の5つを解説します。
- 脂質検査の項目(LDL・HDL・中性脂肪)
- 脂質異常症の診断基準
- 再検査や医療機関の受診の目安
- LDL型・HDL型・中性脂肪型の違い
- 原因:食生活・運動不足・体質など
脂質検査の項目(LDL・HDL・中性脂肪)
脂質検査では、主に以下の3つの項目が測定されます。
- LDL(悪玉)コレステロール:基準値140mg/dL未満
- HDL(善玉)コレステロール:基準値40mg/dL以上
- 中性脂肪(トリグリセリド):基準値150mg/dL未満
LDLコレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを全身の細胞に運ぶ役割を担っています。LDLコレステロールが過剰に増えると、血管壁にコレステロールが蓄積し、血管が狭くなることで血流が悪化します。動脈硬化を引き起こす主な原因の一つです。
HDLコレステロールは、血管壁に溜まったコレステロールを回収し、肝臓に戻す役割を担っています。HDLコレステロールが高いほど、動脈硬化の予防に役立ちます。
中性脂肪は、エネルギー源として体に蓄えられる脂質です。中性脂肪の高い状態は、LDLコレステロールを増加させ、HDLコレステロールを減少させるため、動脈硬化のリスクを高めます。急性膵炎の原因につながる可能性もあります。
脂質異常症の診断基準
脂質異常症の診断における基準値は、下記のとおりです。
- LDLコレステロール140mg/dL以上:高LDLコレステロール血症
- LDLコレステロール120〜139mg/dL:境界域高LDLコレステロール血症
- HDLコレステロール40mg/dL未満:低HDLコレステロール血症
- 中性脂肪150mg/dL以上(空腹時採血):高トリグリセライド血症
- 中性脂肪175mg/dL以上(随時採血):高トリグリセライド血症
- Non-HDLコレステロール170mg/dL以上:高non-HDLコレステロール血症
- Non-HDLコレステロール150〜169mg/dL以上:境界域高non-HDLコレステロール血症
Non-HDLコレステロールは、総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値です。日本動脈硬化学会のガイドラインでは、中性脂肪について、随時採血の値でも診断されるようになりました。随時採血とは、食事の時間に関係なく、いつでも行える採血検査のことです。
再検査や医療機関の受診の目安
健康診断で脂質の値に異常があった場合、再検査は医師の診察のうえで異常値の程度や他の検査結果、個々の状況などで異なります。健診機関や職場の健康管理室、かかりつけ医師などに相談をしましょう。
研究では、標準化された健康相談が受診率を58.1%にまで向上させ、血圧やHbA1c、LDLコレステロールの低下などへの効果を報告しています。生活習慣病のリスクが高い人々の行動変容を促すうえで、健康相談が有効な手段であることを示唆しています。
健康診断の結果を放置せず、長期的な視点で健康管理に取り組むことが重要です。「要精密検査」と診断された場合は、医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。
LDL型・HDL型・中性脂肪型の違い
脂質異常症は、以下の3つのタイプにわかれます。
- LDL型:LDLコレステロールが多いタイプ
- HDL型:HDLコレステロールが少ないタイプ
- 中性脂肪型:中性脂肪が多いタイプ
LDLコレステロールが過剰に増えると、動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などにつながる可能性があります。動脈硬化が進行する原因に、HDLコレステロールの減少と、LDLコレステロールがたまりやすい傾向があるからです。
中性脂肪はエネルギー源として必要ですが、増えすぎると肥満や動脈硬化、急性膵炎などを引き起こしやすくなります。異常は一つではなく、複数組み合わさっている場合もあるため、健康診断で総合的な確認が大切です。
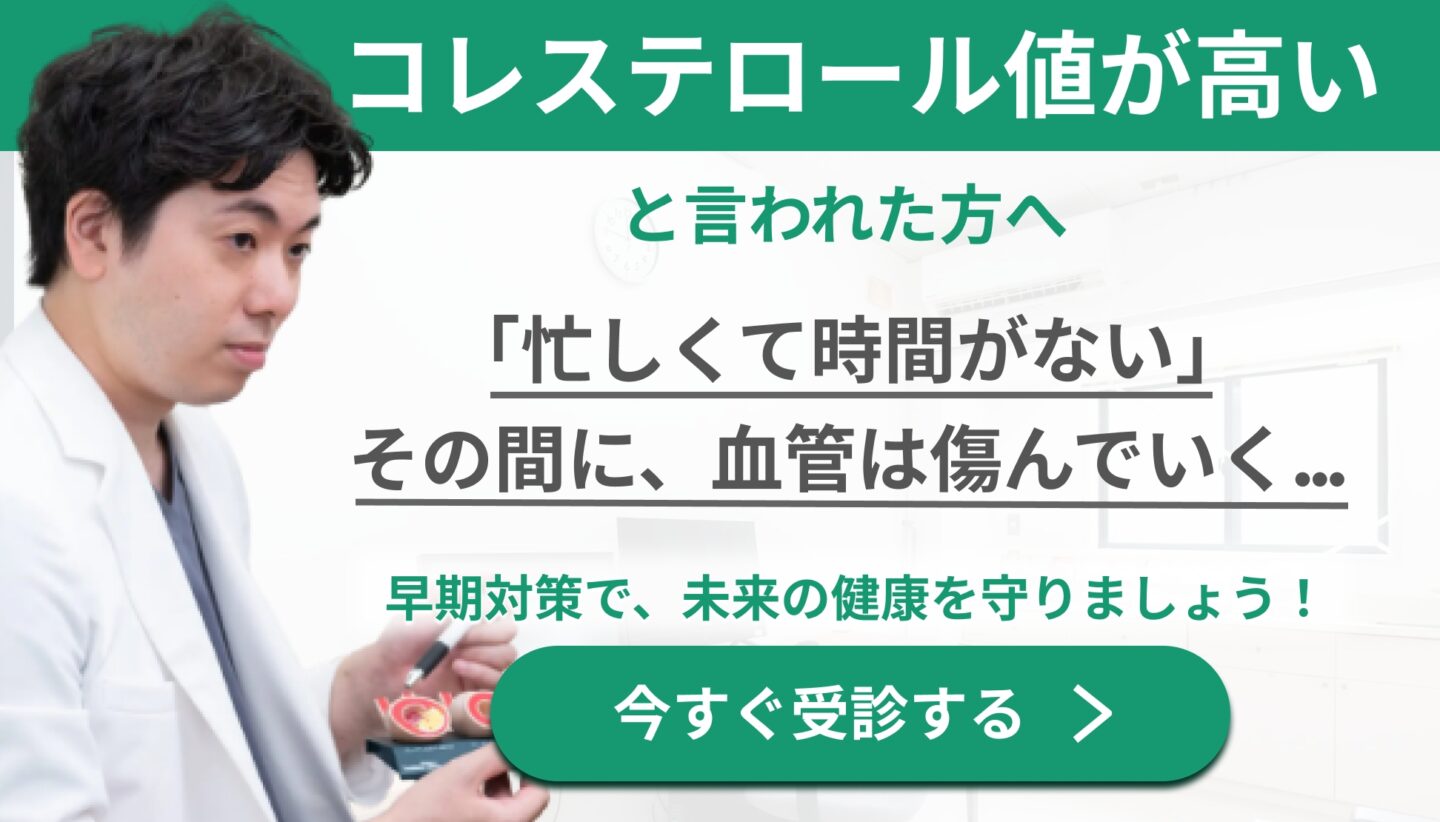
原因:食生活・運動不足・体質など
脂質異常症の原因は、遺伝的な要因と生活習慣に分けられます。遺伝的な要因は、生まれつきコレステロールや中性脂肪の代謝機能が弱く、両親の遺伝子が原因となる場合もあります。生活習慣の要因と影響は、以下のとおりです。
- 高カロリー・高脂肪食:LDLコレステロールや中性脂肪の増加
- 運動不足:HDLコレステロールの減少、中性脂肪の増加
- 喫煙:HDLコレステロールの減少
- 過度の飲酒:中性脂肪の増加
- ストレス:自律神経のバランスを崩し、脂質代謝に影響
健康に悪い生活習慣は、脂質代謝を乱しやすく、自覚症状に気付かず動脈硬化や他の病気を進行させている可能性があります。
脂質異常症を改善する方法
脂質異常症は、食事療法や運動といった生活習慣の改善によって、数値の改善が期待されます。具体的な方法は、以下の3つです。
- 食事療法の基本
- 具体的な食事メニュー例
- 運動療法の実践
食事療法の基本
食事療法では、脂質の摂取量を減らしながら質の良い脂質を摂取し、コレステロールの吸収を抑え体外へ排出を促すことが重要です。具体的には、以下の3つです。
- コレステロールを多く含む食品を控えめにする
- 油の種類に気をつける
- 食物繊維をたくさん摂る
卵の黄身や肉の脂身、レバーなどはコレステロールを多く含みます。卵は卵白を使用し、肉は赤身肉を選ぶなど、コレステロール摂取量を調整しましょう。肉やバターに含まれる飽和脂肪酸は、LDLコレステロールを増やしやすいです。
HDLコレステロールの改善に役立つ、魚やオリーブオイル、ナッツ類などの不飽和脂肪酸を取り入れましょう。食物繊維は、コレステロールの吸収を抑制し、体外への排出を促進する効果が期待されます。食物繊維は腸内環境を整える効果も期待できるため、野菜や海藻、きのこなどを意識して摂取しましょう。
以下の記事では、そもそも脂質異常症とはどのような病気なのか、原因や症状、そして相談すべき診療科についてわかりやすく解説しています。初めて脂質異常症と向き合う方にも役立つ内容です。
>>脂質異常症とは?何科に相談すれば良いのか原因や症状についても解説
具体的な食事メニュー例
バランスの良い食事を続けることが、脂質異常症の改善には重要です。具体的なメニュー例は、以下のとおりです。
- 朝食:ご飯、焼き鮭、野菜とキノコの卵白炒め、わかめと豆腐の味噌汁
- 昼食:全粒粉パンのサンドイッチ(野菜、ハム、チーズ)、ミネストローネ
- 夕食:鶏肉のソテー(皮なし)、ひじきの煮物、ほうれん草のおひたし、きのこの味噌汁
和食中心の朝食は、バランス良く栄養を摂取できるだけでなく、腹持ちも良く、間食を防ぐ効果も期待できます。全粒粉パンは、食物繊維が豊富であるため、コレステロールの吸収を抑える効果が期待できます。肉料理は、鶏肉の皮を取り除き、脂身の少ない部位を選ぶことで脂質の摂取量を調整できます。
食事は、主食や主菜、副菜などをそろえて、バランスの良い組み合わせを心がけましょう。間食には、果物やヨーグルト、ナッツなどがおすすめです。
以下の記事では、脂質異常症の方が避けるべき具体的な食品や、健康的に食事を整えるためのポイントについて詳しく解説しています。
>>脂質異常症の食事療法|食べてはいけないもの一覧と健康的な食事法を解説
運動療法の実践
運動は、脂質異常症の改善に効果が期待できます。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、HDLコレステロールの改善や中性脂肪が減少する可能性があります。1回30分程度、週に3回以上を目標に、できる範囲から始めることが大切です。
最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくと、無理なく続けることができます。エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、日常生活の中に体を動かす機会はあります。運動を始める前は、適切な運動の種類や強度について、医師よりアドバイスを受けましょう。
脂質異常症の合併症のリスク
脂質異常症の合併症のリスクについて、以下の2つを解説します。
- 動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞など
- 他の生活習慣病との関連性
動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞など
脂質異常症の合併症は、動脈硬化です。動脈硬化は全身の血管で起こり得ますが、心臓や脳の血管で生じると、重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。心臓の血管で動脈硬化が進行すると、狭心症や心筋梗塞を発症しやすく、脳の血管で動脈硬化が起こると、脳梗塞のリスクが高まります。
脳梗塞は、半身麻痺や言語障害、意識障害など、さまざまな症状が現れ、後遺症が残る可能性も少なくありません。狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などは、突然発症する病気であり、命に関わることもあります。脂質異常症の早期発見と適切な管理が重要です。気になる症状がある場合は、医師に相談しましょう。
以下のページでは、動脈硬化の進行度を評価するために行われる頸動脈エコー検査について詳しく解説しています。
他の生活習慣病との関連性
脂質異常症は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病と関連しています。脂質異常症で高血圧の方は、血管に負担がかかりやすく、動脈硬化を促進させやすいです。加えて糖尿病になると、高血糖値が続くことで、血管内皮が傷つけられ、動脈硬化が進行する可能性があります。
脂質異常症や高血圧、糖尿病などは単独でも健康に影響を及ぼしますが、重なることで、動脈硬化のリスクを高めます。生活習慣を改善することで、脂質異常症の予防や改善につなげましょう。バランスの良い食事や適度な運動、禁煙などを心がけることが大切です。
日頃より、定期的な健康診断を受け、脂質異常症の早期発見に努めましょう。以下のページでは、血管の硬さや詰まりやすさを調べる血圧脈波検査について詳しく紹介しています。
脂質異常症の治療法
脂質異常症の治療法について、以下の2つを解説します。
- 食事・運動療法と薬物療法の使い分け
- 脂質異常症の主な治療薬
食事・運動療法と薬物療法の使い分け
脂質異常症の治療は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つです。治療法は、患者さんの状態に合わせて単独、あるいは組み合わせて行われます。最初に取り組むのは、食事療法と運動療法です。食生活を見直し、適度な運動を続けることで、脂質の改善を目指します。薬物療法は、以下の場合に検討されます。
- 食事療法と運動療法を3~6か月ほど続けても脂質の値が改善しない場合
- 動脈硬化の危険因子(高血圧、糖尿病、喫煙など)が多い場合
- 心血管疾患の既往がある場合
生活習慣の改善は、薬物療法を行う場合でも、並行して継続することが推奨されます。
脂質異常症の主な治療薬
脂質異常症の治療に用いられる、主な薬剤は以下のとおりです。
- スタチン系薬剤
- フィブラート系薬剤
- コレステロール吸収阻害薬
- PCSK9阻害薬
それぞれ異なるメカニズムで、脂質の値を改善する作用があります。医師は、患者さんの状態(脂質異常症の種類や程度、年齢、他の病気の有無など)や生活習慣などを考慮して処方します。薬を服用する際は、効果と副作用について、医師から十分な説明を受けましょう。
まとめ
脂質異常症は自覚症状がないまま進行し、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞など命に関わる病気を引き起こすリスクがあります。食事や運動などの生活習慣の改善に取り組むことで、数値の改善が期待できます。改善が得られにくい場合は、患者さんの状態に合わせた薬物療法を併用する場合もあるため、医師に相談しましょう。
具体的な対策を実践し、生活習慣を見直すことで、リスク低減に役立つ可能性があります。定期的な健康診断を受け、脂質異常症の早期発見に努めます。要精密検査の場合は、医療機関を受診して医師と相談しながら治療を進めましょう。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- 一般社団法人日本動脈硬化学会:動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2022年)
- Hiroyasu Iso, Midori Noguchi, Tetsuji Yokoyama, Toshiko Yoshida, Isao Saito, Ayumi Shintani, Toshimi Sairenchi, Hitoshi Nishizawa, Hironori Imano, Akihiko Kitamura, Iichiro Shimomura.Effect of a Community-Based Program to Accelerate Referral to Physicians for Individuals at High-Risk of Lifestyle-Related Diseases: A Cluster Randomized Trial.J Atheroscler Thromb,2023,30,10,p.1389-1406
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







