blog
ブログ
20代で健康診断の血圧に引っかかり、不安を感じる方は少なくありません。高血圧は年齢に関係なく注意が必要な症状です。厚生労働省の2019年度国民健康・栄養調査によると、20代の血圧の平均値は男性115.9/68.1mmHg、女性105.7/63.8mmHgです。
血圧が平均よりも高い場合、将来的な脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まる可能性があります。この記事では、20代で血圧が高くなる5つの原因と、具体的な改善策を解説します。今から血圧管理を始め、10年後、20年後の健康を守りましょう。
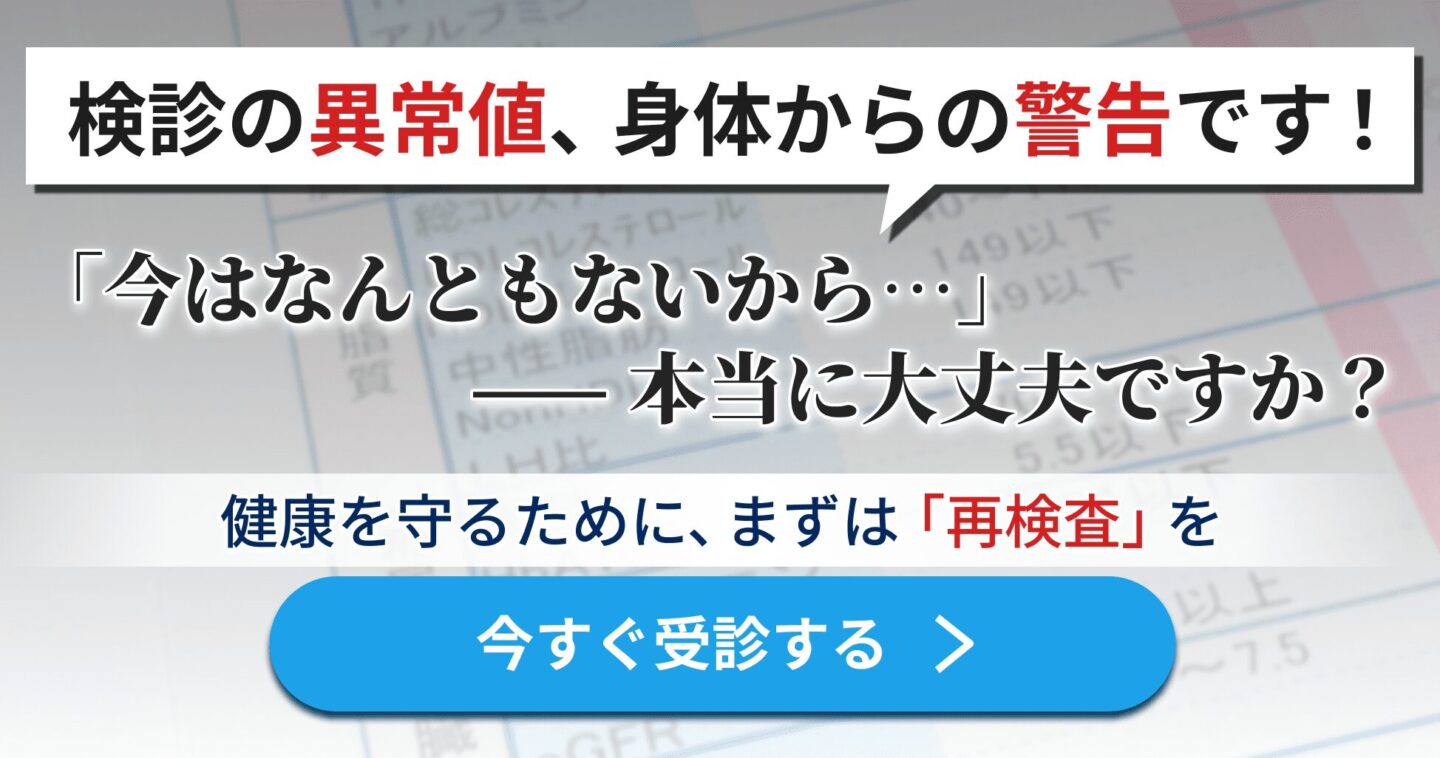
20代で血圧が高い原因5選
20代で血圧が高くなる主な原因は、以下の5つです。
- 食生活の乱れ
- 運動不足
- 睡眠不足
- ストレス
- 遺伝的要因
食生活の乱れ
食生活の乱れは、高血圧の大きな原因の一つです。現代の食生活では、塩分や脂質、糖質を過剰に摂取しやすくなっています。特に、塩分の摂りすぎは血圧を上昇させる直接的な原因となります。外食やコンビニ食、インスタント食品などは塩分量が多い傾向があるため、注意しましょう。
脂質の摂りすぎにも注意が必要です。脂質を過剰に摂取すると、血液中のコレステロールや中性脂肪が増加し、動脈硬化を促進する可能性があります。動脈硬化は高血圧をさらに悪化させる原因となります。研究によると、減塩食の実践が高血圧の在宅管理において重要な要素の一つであることが示されています。
無理のない範囲で継続できる方法を選ぶことが重要です。以下の記事では、健康診断で脂質の異常値が出た際に考えられる原因や、生活習慣の見直しを含めた改善策、医療機関で行われる治療法について詳しく解説しています。放置せず早めの対策を検討したい方は確認してみてください。
>>健康診断の脂質検査で異常値が出たら?改善のための対策や治療法を解説
運動不足
運動不足は、高血圧だけでなく、さまざまな生活習慣病のリスクを高めます。適度な運動は、血圧を下げるだけでなく、ストレス解消や睡眠の質の向上にもつながります。運動は継続が重要です。毎日少しずつでも体を動かす習慣を身につけましょう。
運動療法については以下の記事で詳細に解説していますので、あわせて読んでみてください。
>>高血圧の運動療法のおすすめの方法や効果を高血圧治療ガイドラインをもとに解説!
睡眠不足
睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、血圧を上昇させる原因となります。睡眠中は、心拍数や血圧が低下し、体が休息している状態です。睡眠不足になると、交感神経が優位な状態が続き、血圧が上昇しやすくなります。良質な睡眠を確保するためには規則正しい生活リズムを心がけましょう。
寝る前にカフェインを摂取したり、スマートフォンやパソコンなどの画面を見たりするのは推奨できません。寝る前に読書やストレッチをするなど、リラックスした状態で眠りにつくことが大切です。寝室の環境を整えることも一つの方法です。
ストレス
現代社会において、ストレスは避けて通れませんが、過剰なストレスは血圧を上昇させる原因となります。ストレスを感じると、交感神経が活発になり、血管が収縮し、血圧が上昇します。
ストレスをため込まないためには、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。趣味や運動、リラックスできる時間を持つなど、自分に合った方法でストレスを発散しましょう。
遺伝的要因
高血圧には、遺伝的な要因も関わっていると考えられています。両親が高血圧の場合、子供が高血圧になるリスクが高まる傾向があります。家族に高血圧の方がいる場合は、若い頃から血圧に気を配り、定期的に測定することが重要です。遺伝的な要因は、生活習慣の改善だけではコントロールが難しい場合もあります。
しかし、食生活や運動習慣、ストレス管理などに気を配ることで、血圧を管理し、将来的なリスクを軽減できます。健康診断で血圧が高いと指摘された場合は、医師に相談し、適切に対応しましょう。
20代で高血圧を発症するリスク
20代で高血圧を発症する主なリスクは、以下のとおりです。
- 動脈硬化
- 脳卒中
- 心筋梗塞
動脈硬化
動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失ってしまう状態です。血管は、体中に酸素や栄養を運ぶための重要な管です。高血圧の状態が続くと血管の内壁に負担がかかり、血管が傷つきやすくなります。血管の傷ついた部分を修復しようと、血管の内側にコレステロールなどが蓄積し、血管の壁が厚く硬くなっていきます。
20代では自覚症状がない場合が多いですが、血管の老化は静かに進行するため、正しい対処が必要です。高血圧になると、血管が少しずつ硬く、もろくなり、動脈硬化を引き起こします。動脈硬化が進むと、血管が狭くなり、血液の流れが悪くなります。血流が悪化すると、臓器に十分な酸素や栄養が届かず病気の原因となるため、注意が必要です。
血管が詰まると、命に関わる重大な病気を引き起こす可能性も高くなります。腎臓の血管が硬化すると腎機能が低下し、最終的には人工透析(じんこうとうせき)が必要になることもあります。
以下のページでは、血管の硬さや動脈硬化の進行度を調べる血圧脈波検査について詳しく解説しています。
脳卒中
脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりして、脳に障害が起こる病気です。高血圧は脳卒中の大きなリスク要因の一つです。若い頃から血圧が高い状態が続くと、血管がもろくなり、破れやすくなります。動脈硬化も脳卒中のリスクを高めます。脳卒中は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 脳梗塞:脳の血管が詰まることで起こる
- 脳出血:脳の血管が破れることで起こる
どちらも脳への血液供給が途絶えるため、脳細胞がダメージを受け、さまざまな神経症状が現れます。手足の麻痺やしびれ、言語障害、意識障害などが起こり、重症の場合は命を落とすこともある危険な病気です。脳卒中は後遺症が残る可能性も高く、生活の質が大きく低下します。
心筋梗塞
心臓は、全身に血液を送るポンプの役割をしています。心筋梗塞は、心臓の血管が詰まってしまい、心臓の筋肉に血液が送られなくなる病気です。高血圧は、心筋梗塞の大きなリスク要因の一つです。高血圧の状態が続くと、心臓に負担がかかり、動脈硬化も進行しやすくなります。
心臓の筋肉は、常に血液から酸素や栄養を受け取ることが必要です。心臓の血管が詰まると、心臓の筋肉に必要な酸素や栄養が届かなくなり、壊死(えし)します。心筋梗塞は、激しい胸の痛みや呼吸困難、吐き気などの症状が現れます。重症の場合は、心停止に至る可能性もあるため、早期の対策が重要です。
20代から血圧を適切に管理すれば、将来の心筋梗塞のリスクを軽減できます。
血圧を管理する5つの方法
血圧を管理する5つの方法は以下のとおりです。
- 食生活を改善する
- 適度の運動する
- ストレスを発散する
- 血圧を測定する
- 禁煙する
食生活を改善する
食生活は血圧に大きな影響を与えます。特に、塩分の過剰摂取は血圧上昇の直接的な原因となります。厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取量の目標値は、男性7.5g未満、女性6.5g未満です。高血圧の予防・治療のためには6g未満を目標にすることが望ましいです。
食品の栄養成分表示をよく確認し、減塩を意識した食生活を心がけましょう。カリウムを多く含む野菜や果物、海藻、大豆製品は、体内の余分なナトリウム(塩分の主成分)を排出する働きがあります。積極的に摂取しましょう。
脂質の過剰摂取も動脈硬化を促進し、血圧上昇につながる可能性があります。肉類の脂身の多い部位は控えめにし、アジ、サバなどの青魚に含まれるDHAやEPAを積極的に摂るようにしましょう。DHAやEPAはn-3系脂肪酸(オメガ3:体内で作れない必須脂肪酸)の一種で、血圧に良い影響を与えることが期待できます。
なお、近年では若年層でも生活習慣の乱れが原因で糖尿病を発症するケースが増えています。以下の記事では、20代で糖尿病になる背景やリスク要因、今からできる予防策について詳しく解説しています。健康管理に不安を感じている方は、ぜひご一読ください。
>>20代で糖尿病になる原因とは?若年性糖尿病の特徴と対策
適度に運動する
世界保健機関(WHO)は、成人に週150分〜300分の中強度の有酸素運動を行うことを推奨しています。ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなどは、中強度の有酸素運動に該当します。有酸素運動に加えて、週に2日以上は筋力トレーニングを行うことも推奨されています。筋力トレーニングは、スクワットや腕立て伏せなど、自宅でも手軽に行えます。
体を動かす習慣は、血圧管理だけでなく、健康維持にもつながります。特別な運動だけでなく、日常生活の中で体を動かすことを意識してみてください。エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う、一駅分歩くといった工夫を取り入れてみましょう。
ストレスを発散する
ストレスは、血圧を上昇させる原因の一つです。趣味や運動、リラックスできる時間を持つなど、自分に合った方法でストレスを発散しましょう。具体的なストレス解消法は、以下のとおりです。
- 十分な睡眠をとる
- 好きな音楽を聴く
- 散歩をする
- 旅行に行く
- 友人と話す
定期的にストレス発散しながらストレスとも上手に付き合っていくことが、血圧管理にもつながります。
血圧を測定する
家庭用血圧計を用いて、毎日血圧を測る習慣を身につけましょう。朝と晩、同じ時間に測定するのがおすすめです。毎日測定することで、血圧の変化に気づき、適切に対処ができます。血圧計は、上腕で測定するアーム式血圧計が推奨されます。測定前に1~2分程度安静にすることも忘れずに行いましょう。
なお、血圧とあわせて確認しておきたいのが血糖値です。血糖値の異常は自覚症状が乏しく、放置すると生活習慣病のリスクが高まります。以下の記事では、年代別の血糖値の正常値や注意すべき数値、異常時の対策について詳しく解説しています。健康管理の一環として、ぜひ参考にしてください。
>>血糖値の正常値とは?年代別の基準値と異常時の注意点を解説
禁煙する
喫煙は、血管を収縮させ、血圧を上昇させる原因となります。動脈硬化を促進し、さまざまな病気を引き起こすリスクを高めます。禁煙は、血圧を下げるだけでなく、健康全体を維持するために重要です。
病院を受診する目安
病院を受診する目安について、以下の内容を解説します。
- 健康診断で再検査が必要と言われたとき
- 140/90mmHgが続くとき
- 気になる症状があるとき
健康診断で再検査が必要と言われたとき
健康診断で血圧の再検査が必要と言われた場合は、必ず再検査を受けましょう。再検査が必要な基準は、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上です。健康診断では、環境や緊張などから血圧が高めに出る場合もあり、一度の測定で高血圧と診断されるわけではありません。
再検査が必要と言われた場合、高血圧の可能性があります。精密検査を受けることで、より正確な診断、適切な対応が可能です。再検査では、複数回の血圧測定や、必要に応じて追加の検査が行われます。
140/90mmHgが続くとき
家庭で血圧を測った際に、140/90mmHg以上の数値が続く場合は、医療機関への受診を検討しましょう。家庭血圧は、リラックスした状態で測定できるため、より正確な血圧の状態を把握できます。140/90mmHg以上の数値が続く場合は、高血圧の可能性が高いと考えられます。
高血圧は大きく分けて「本態性(ほんたいせい)高血圧」と「二次性高血圧」の2種類に分類されます。本態性高血圧は、原因が特定できない高血圧で、高血圧全体の9割以上を占めます。生活習慣の改善や薬物療法での血圧コントロールが重要です。
二次性高血圧は、腎臓の病気やホルモン異常など、特定の病気が原因で起こる高血圧です。原因となる病気の治療で、血圧の改善が期待できます。
以下のページでは、高血圧の評価や不整脈の有無を確認するために行われる心電図検査について紹介しています。
気になる症状があるとき
血圧が高い状態が続くと、めまいや頭痛などの症状を感じる場合もありますが、多くの場合は自覚症状がないため注意が必要です。高血圧の症状は多岐にわたるので、倦怠感(けんたいかん)や吐き気なども現れることがあります。少しでも気になる症状があれば医療機関を受診しましょう。
急な血圧上昇に加え、以下のような症状が現れた場合は高血圧緊急症の可能性があります。
- 激しい頭痛
- めまい
- 吐き気
- 意識障害
- けいれん
- ろれつ不良
高血圧緊急症は命に関わる危険な状態であるため、すぐに救急車を呼びましょう。
まとめ
高血圧は年齢に関係なく、動脈硬化や脳卒中、心筋梗塞などの病気につながるリスクを高める可能性があります。自覚症状がないまま進行する場合も多いので、健康診断で指摘されたら放置せず医師に相談することが大切です。
食生活の見直しや適度な運動、ストレス管理、血圧測定の習慣づけ、禁煙など、無理なく続けられることから始めましょう。日々の小さな積み重ねが将来の健康を守る第一歩になります。若いうちから血圧を意識して管理し、年齢を重ねても元気で過ごせる体を作りましょう。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Kennedy Diema Konlan, Jinhee Shin.Determinants of Self-Care and Home-Based Management of Hypertension: An Integrative Review.Global Heart,2023,18,1,p.16
- 厚生労働省:令和元年国民健康・栄養調査報告(2019年)
- 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書(2025年)
- 世界保健機構(WHO):WHO身体活動・座位行動ガイドライン日本語版(2021年)
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







