blog
ブログ
自分や家族の「もの忘れ」が増え、認知症の可能性を考えて不安になる方は少なくありません。加齢による自然なもの忘れと、認知症による記憶障害では、原因や特徴が異なります。病院での検査や費用が気になり、受診をためらう方もいます。
この記事では、認知症が疑われたときに行われる問診や神経心理学的検査、画像検査、診断までの流れ、費用の目安を解説します。検査の内容や手順を知ることで、不安の軽減につながります。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
認知症を疑ったときに確認すべきポイント4つ
認知症は特別な人にだけ発症する病気ではありません。認知症を疑ったときに確認すべきポイントについて、以下の4つを解説します。
- 加齢によるもの忘れとの違いを理解する
- 認知症の初期症状を把握する
- 自宅でできる認知症セルフチェックを試す
- 受診のタイミングを把握する
加齢によるもの忘れとの違いを理解する
年齢を重ねることによってもの忘れが増えても、脳の自然な老化現象であり心配しすぎる必要はありません。認知症による記憶障害は、加齢によるもの忘れと質が根本的に異なります。加齢によるもの忘れの特徴は、以下のとおりです。
- 昨日の夕食のメニューなど、体験の一部を忘れる
- 忘れた自覚がある
- きっかけがあれば思い出す可能性がある
- 日常生活に支障は出にくい
- 症状が進行する可能性は低い
認知症による記憶障害の特徴は、以下のとおりです。
- 夕食を食べたことなど、体験の全てを忘れる
- 忘れた自覚がない
- きっかけがあっても思い出せない
- 日常生活に支障が出ることがある
- 時間の経過とともに症状が進行する
加齢によるもの忘れは「思い出す力」が衰えた状態です。記憶そのものは残っているため、ヒントがあれば思い出す可能性があります。認知症による記憶障害は「記憶する力」が低下している状態です。体験が脳に記録されず、ヒントをもらっても思い出せないことがあります。
以下の記事では、認知症の方への基本的な接し方や避けるべき言動、寄り添うための心構えについて詳しく解説しています。
>>認知症の方への接し方は?基本の対応やしてはいけないこと、心がけたいポイント
認知症の初期症状を把握する
認知症のサインは、もの忘れだけではありません。認知症によって脳のさまざまな機能が低下するため、当たり前にできていたことが難しくなる可能性があります。注意が必要な症状は、以下のとおりです。
- 判断力・理解力の低下:料理や買い物の段取りを考えることが苦手になる
- 時間や場所がわからなくなる(見当識障害):日付や曜日がわからなくなる
- 人柄の変化:以前は穏やかだったのに、ささいなことで怒りっぽくなる
- 意欲の低下:長年続けていた趣味や、好きだったテレビ番組を見なくなる
症状が確認された場合、脳機能の低下が原因の病気である可能性があります。ご本人は変化に気づきにくいため、ご家族や周りの方が気づくことが重要です。
自宅でできる認知症セルフチェックを試す
病院へ行く前に、ご家庭で気になる症状を確認できるセルフチェックリストを活用しましょう。当てはまる項目が多いほど、専門機関への相談がおすすめです。セルフチェックリストの項目は、以下のとおりです。
- 何度も同じことを言ったり、聞いたりする
- 大切な物をどこに置いたか忘れて、探すことが増えた
- 今日が何月何日か、何曜日かわからないときがある
- 慣れている道で迷うことがある
- 預金通帳や印鑑の大切なものを失くしてしまう
- 蛇口やガス栓の閉め忘れ、火の消し忘れがある
- 以前はあった趣味や活動への関心がなくなった
- ささいなことで怒りっぽくなり、性格が変わった
- 服装がだらしなくなり、身だしなみに気を使わない
- 複雑な会話やテレビの内容が理解しづらくなった
チェックリストは診断用ではなく、専門家に相談する「目安」です。受診の際に、医師へ症状を具体的に伝えるためのメモとして活用しましょう。
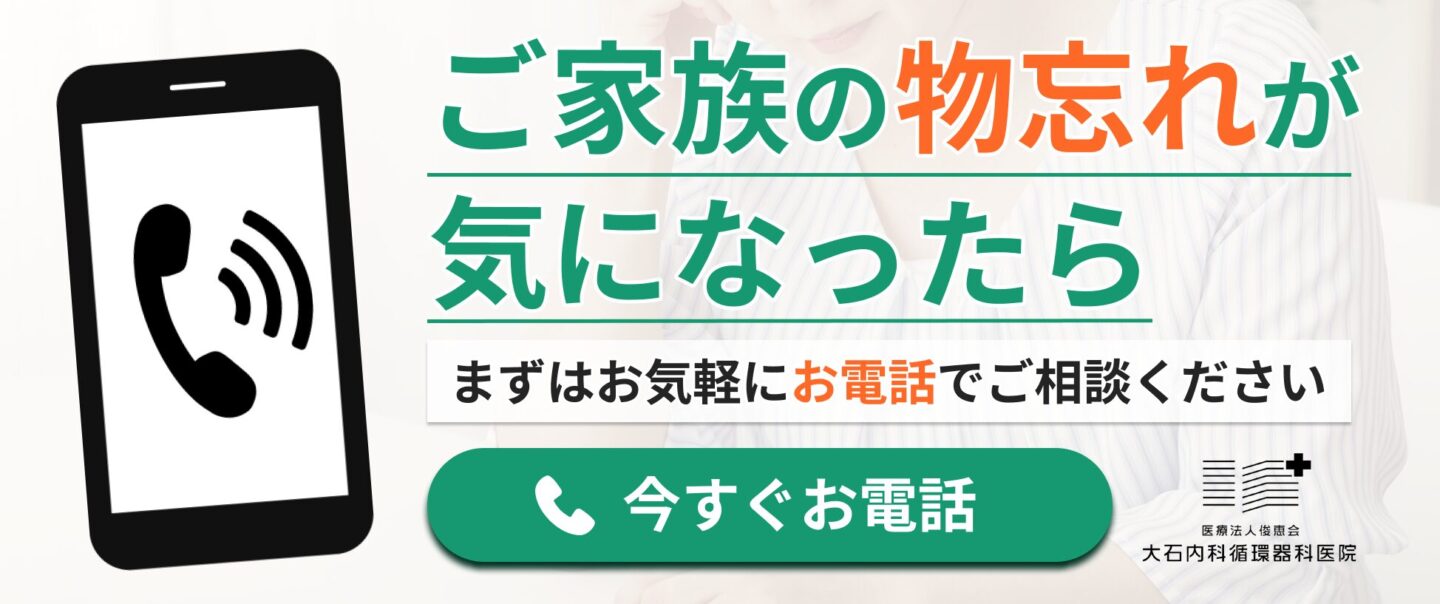
受診のタイミングを把握する
受診を考える目安は「もの忘れで日常生活に支障が出始めたとき」です。お金の管理が難しくなったり、一人での外出が不安になったりした場合は、早めに相談しましょう。
近年の研究では、生活習慣病(糖尿病や高血圧)、運動不足、社会的孤立が、認知機能低下のリスク要因であると示唆されています。早めに気づいて適切に対応することで、病気の進行を遅らせ症状を軽くできる可能性があります。
受診先は、かかりつけ医やもの忘れ外来、脳神経内科、精神科などです。相談先がわからない場合や、ご本人が受診を嫌がるときは、ご家族だけでも地域包括支援センターなど公的な窓口を利用しましょう。
認知症検査で行われる主な検査の種類
認知症の検査を受けることで現在の状態を把握し、医師と相談しながら今後の方針を検討できます。認知症の診断で行う主な検査について、以下の4つを解説します。
- 問診で確認されること
- 神経心理学的検査(長谷川式・MMSE)
- 画像検査(MRI・CT・SPECT)
- 他の病気の可能性を調べる検査(血液検査・脳脊髄液検査など)
問診で確認されること
問診は認知症診断の出発点で、重要なステップの一つです。医師がご本人やご家族から、生活の様子や気になる症状をお聞きします。ご本人が感じる症状だけでなく、ご家族から見た客観的な変化が、診断において重要です。主な問診の内容は、以下のとおりです。
- いつごろからどのような症状が気になり始めたか
- 日常生活で困っていることはあるか
- 高血圧や糖尿病などの持病があるか
- 現在飲んでいる薬はあるか
- 生活環境に変化はあったか
ご本人が受診を嫌がる場合は、ご家族だけでも相談しましょう。ご家庭での具体的なエピソードをメモにまとめておくと、医師に状況が伝わりやすくなります。
以下の記事では、認知症になりやすい人の特徴や傾向について、最新の知見をもとにわかりやすく解説しています。
>>認知症になりやすい人の特徴とは?
神経心理学的検査(長谷川式・MMSE)
神経心理学的検査は、簡単な質問や作業を通して脳の働きを調べる検査です。記憶力や判断力の「認知機能」の状態を、客観的な点数で評価します。代表的な検査は以下の2つです。
- 長谷川式認知症スケール(HDS-R)
- ミニメンタルステート検査(MMSE)
長谷川式認知症スケールは、認知機能の低下を調べる日本の標準的な検査です。所要時間は約10分、30点満点で、20点以下で認知症の疑いが高まります。主な質問内容は、年齢や今日の日付、今いる場所、野菜の名前、今の季節などです。
ミニメンタルステート検査は、国際的によく使われる認知機能検査です。所要時間は約10~15分、30点満点で、23点以下で認知症の疑いが高まります。主な質問内容は、100から7を順番に引く、文章を読んで指示に従ってもらう、図形を書き写すなどです。
検査は認知機能の状態を把握するための指標です。点数が低くても、すぐに認知症と診断されるわけではありません。慣れない場所で緊張したり、体調が悪かったりすると、普段の力が出せないこともあります。できるだけリラックスして受けることが大切です。
画像検査(MRI・CT・SPECT)
画像検査は、機械を使って頭の中を写し出す検査です。脳の形や血流に変化がないか、医師が直接目で見て確認します。認知症の原因や種類を特定し、他の病気の有無を調べることが期待できます。主な画像検査は以下の3つです。
- MRI(磁気共鳴画像)
- CT検査(コンピュータ断層撮影)
- SPECT検査(脳血流シンチグラフィ)
MRI検査は、強い磁石と電波を使い、脳の断面を撮影します。記憶を司る「海馬」の萎縮を確認し、アルツハイマー型認知症の診断に役立ちます。CT検査は、X線を使って、脳を輪切りにした画像を短時間で撮影します。脳出血や脳梗塞、脳腫瘍の緊急性の高い病気がないかを調べるのに有効です。
SPECT検査は、微量の放射線を出す薬を注射し、脳の血流を色で示します。脳の働きが落ちている部分を見つけ、アルツハイマー型やレビー小体型など、認知症の種類の特定を目指します。検査を組み合わせることで、より正確な診断が期待できます。
治療や生活支援の方針を立てる際の参考になる場合があるため、医師と相談しながら進めることが大切です。
他の病気の可能性を調べる検査
もの忘れの症状は認知症以外の病気が原因で起こることがあるため、原因を治療し症状が改善する可能性があります。病気の可能性を見逃さないために、以下の検査を行うことがあります。
- 血液検査
- 脳脊髄液検査
血液検査は簡単な採血で、全身の状態や栄養状態を調べます。認知症と似た症状を引き起こす病気の種類と特徴は、以下のとおりです。
- 甲状腺機能低下症:新陳代謝が低下し、疲れやすくぼんやりする
- ビタミン欠乏症:ビタミンB1・B12や葉酸が不足し、記憶力や集中力が落ちる
- 肝臓や腎臓の病気:体内の毒素が排出されにくく、脳の働きに影響が出る
- 神経梅毒:感染症の一種で、認知機能に影響を与える
脳脊髄液検査は、アルツハイマー型認知症の原因物質の蓄積の有無を調べる検査で、特殊な病気が疑われる場合に行われます。背中から細い針を刺し、脳の周りを流れる「脳脊髄液」を採取します。
検査によって他の病気ではないことを確認し、正確な診断を目指します。早期に原因を特定し、適切な治療や支援につなげることが大切です。
また、認知症に対して「遺伝するのでは?」と不安を抱く方も多くいらっしゃいます。実際には遺伝以外にもさまざまな要因が関与しており、予防できるケースもあります。以下の記事では、認知症の遺伝リスクや関係する要因、日常生活でできる予防策について詳しく解説しています。
>>認知症は遺伝する?考えられる要因や発症リスク、予防法を解説
認知症検査後に知っておきたい生活の備え
診断を受けた後は、ご家族や専門家と一緒に将来の生活に備えることが大切です。診断後に知っておきたい生活の備えについて、以下の4つのポイントを解説します。
- 薬物療法
- リハビリや脳トレなどの非薬物療法
- 認知機能を保つための生活習慣
- 介護保険や相談窓口などの公的な支援制度
薬物療法
認知症と診断された場合、薬を使った治療(薬物療法)を始めることがあります。早期から治療を始めることで、病気の進行を遅らせ症状を和らげる効果が期待できます。認知症の種類ごとに、使われる薬のタイプや役割は異なります。主な例は以下のとおりです。
- アルツハイマー型認知症:記憶障害の中核症状の進行を緩やかにする薬
- レビー小体型認知症:実際にはないものが見える「幻視」の症状を和らげる薬
薬によって、眠気や食欲不振の副作用が出ることがあります。気になる症状があれば自己判断で服用を中止せず、主治医や薬剤師に相談しましょう。
リハビリや脳トレなどの非薬物療法
薬を使わない「非薬物療法」も、認知症治療では大切です。残された能力を活かし、自信や意欲、心の安定、生活の質の向上につながり、症状改善も期待できます。認知リハビリテーションの主な内容は、以下のとおりです。
- 回想法:思い出を語り、心を落ち着かせ自己肯定感を高める
- 現実見当識訓練:日付や季節を確認し、時間や場所の感覚を保つ
- 学習療法:計算や音読で脳を活性化し、会話力を高める
- 運動療法:無理なく体を動かし、血流改善や気分転換を促す
- 音楽療法:歌や楽器で心を和ませる
- 園芸療法:植物を育て、心を穏やかにする
ご本人が楽しく感じられることを見つけることが大切です。ご家族や専門家と一緒に、その人に合った方法を探しましょう。
認知機能を保つための生活習慣
認知症の進行を緩やかにするには、毎日の生活習慣も大切です。認知機能を守るためにおすすめの生活習慣は、以下のとおりです。
- 食事:1日3食、さまざまな食材をバランス良く摂取する
- 運動:週2~3回、30分程度のウォーキングなど軽い運動をする
- 知的活動・社会参加:読書や囲碁、手芸などの趣味を楽しむ
- 睡眠:毎日、質の良い睡眠をとる
全てを完璧に行う必要はありません。できることから1つずつ、楽しみながら生活に取り入れることで、脳の健康を保つ効果が期待できます。
まとめ
認知症の可能性に不安を感じたときは、一人で抱え込まず、早めに専門機関へ相談しましょう。問診や神経心理学的検査、画像検査などを行い、医師が総合的に診断を行います。検査で現状を正しく理解し、今後の対応や治療方針を立てられます。多くの検査は健康保険が適用され、費用は数千~数万円程度が目安です。
日頃の変化をメモしておくと、診察時に役立ちます。診断後も、薬物療法や非薬物療法、生活習慣の見直しにより、進行を緩やかにできる可能性があります。介護保険や地域包括支援センターなど、公的な支援も積極的に活用しましょう。
公的機関や医療機関を上手に活用しながら、無理のない計画を立てることが大切です。利用できる支援を整理し、ご本人とご家族が安心して生活できる毎日を目指しましょう。
参考文献
Blinkova LN, Yakushin MA, Karpova OV.NUTRITION MANAGEMENT FOR COGNITIVE DISORDERS AND DEMENTIA (OVERVIEW).Problemy sotsial’noi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny,2025,33,3,p.494-501
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







