blog
ブログ
もの忘れは年のせいだと感じていませんか?アルツハイマー型認知症の発症予防は、病気を正しく理解し、早めの対策が大切です。アルツハイマー型認知症の原因となる脳の変化は、もの忘れといった症状の出現前から始まっていることが研究でわかっています。
生活習慣病だけでなく、中年期の不安やストレスといった心理状態も、将来の発症リスクを高めるという報告もあります。本記事では、アルツハイマー型認知症の初期症状や原因、進行を穏やかにする具体的な治療法、生活の工夫を解説します。
早期対応の重要性を知ることで、正しい知識をもとに自分や家族の健康を考えるヒントが得られます。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
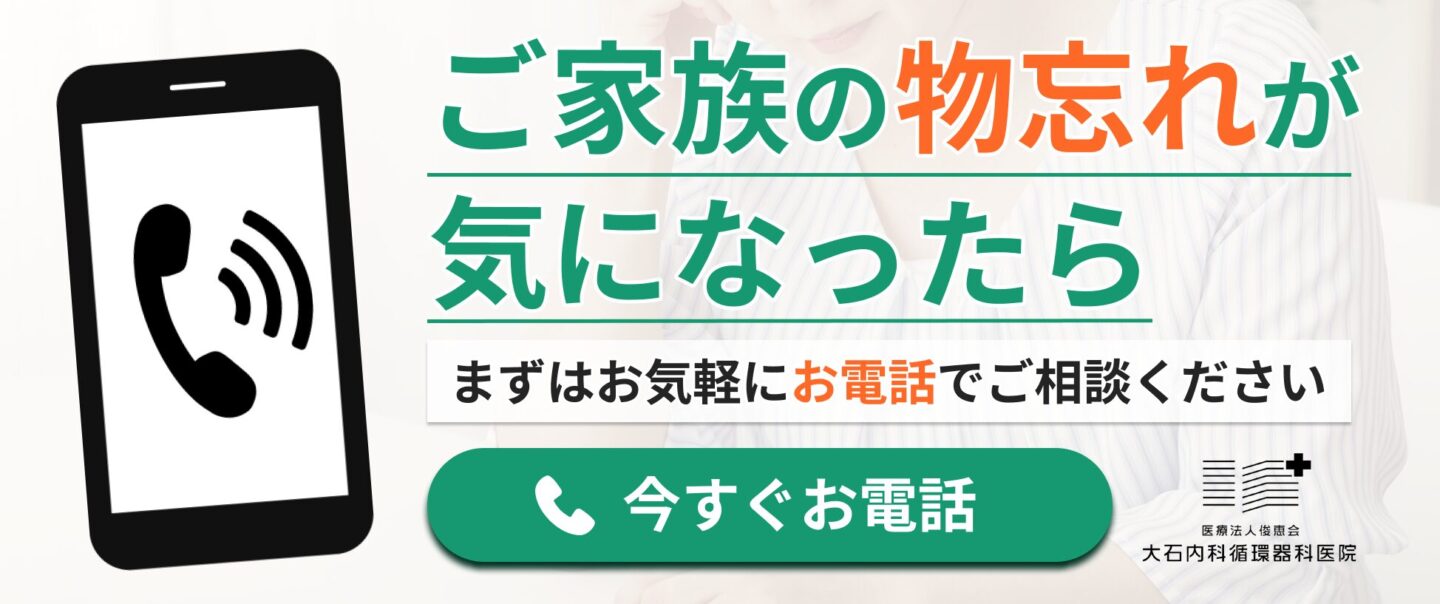
アルツハイマー型認知症の主な症状
アルツハイマー型認知症の主な症状について、以下の4つを解説します。
- 最近の出来事を忘れる記憶障害(初期症状)
- 判断力の低下や段取りが組めない実行機能障害(中期症状)
- 徘徊・妄想・怒りっぽくなるなどのBPSD(行動・心理症状)
- 会話や意思疎通が難しくなる末期症状
最近の出来事を忘れる記憶障害(初期症状)
アルツハイマー型認知症の初期は、新しいことが覚えられない記憶障害がみられます。脳の中で記憶を司る「海馬(かいば)」という部分が、最初にダメージを受けるためです。日常生活で以下のような症状が現れます。
- 何度も同じことを聞いたり、話したりする
- 約束や予定を忘れる
- 探し物が増える
- 時間や場所がわからなくなる
加齢によるもの忘れは、夕食のメニューを忘れるといった体験の一部を忘れます。認知症による記憶障害は、夕食を食べた体験そのものを忘れます。記憶障害に加え、意欲の低下も初期症状の一つです。趣味に無関心になり、身だしなみに気を使わなくなります。
失敗を指摘されると、取り繕ったり怒り出したりすることは、できなくなることが増えた不安の表れです。
判断力の低下や段取りが組めない実行機能障害(中期症状)
症状が進むと、記憶障害に加え物事を順序立てて考え、計画的に行動することが難しくなります。「実行機能障害」と呼び、当たり前にできていた家事や仕事で戸惑うことが増えていきます。具体的には、以下のような状況が生じます。
- 料理や買い物で混乱する
- 金銭管理が難しくなる
- 機械の操作ができない
- 状況に応じた判断ができない
複数の情報を一度に処理し、適切に判断し行動する作業が苦手になります。ご本人の「できなくなった」という自覚から自信を失い、ふさぎ込んでしまうことも少なくありません。
徘徊・妄想・怒りっぽくなるなどのBPSD(行動・心理症状)
アルツハイマー型認知症が進行すると、記憶障害などの中核症状に加え、行動や心理面に症状が現れます。BPSD(行動・心理症状)と呼びます。行動面では、以下のような症状が現れます。
- 徘徊:目的もなく歩き回り、夕方になるとそわそわし始める
- 介護への抵抗:入浴や着替えなどを嫌がる
- 暴言・暴力:些細なことで大声を出し、手をあげる
心理面の症状は、以下のとおりです。
- 物盗られ妄想:財布を盗られたなど、身近な人を疑う
- 幻覚・幻視:いない人が見える、動物がいるなどを訴える
- 抑うつ:気分が落ち込み、何事にもやる気が起きなくなる
- 不安・焦燥:理由もなく不安になったり、イライラしたりする
症状は脳の機能低下に加え、ご本人のプライドが傷つけられた思いも関係します。周囲が叱ったり否定したりすると、症状は悪化しやすいです。
会話や意思疎通が難しくなる末期症状
末期では、脳全体の萎縮が進み、言葉を理解し意思を伝えることが難しくなります。主な症状は、以下のとおりです。
- 失語(しつご):言葉の理解や表出の障害で会話が成立しなくなる状態
- 失行(しっこう):服の着方や箸の使い方など、日常動作ができなくなる状態
- 失認(しつにん):鏡に映った自分や家族の顔も認識できなくなる状態
- 身体機能の低下:歩行困難や寝たきりが起こりやすくなる状態
身体機能の低下は、食事を飲み込む嚥下(えんげ)機能の低下、食べ物が気管に入ってしまう誤嚥性(ごえんせい)肺炎も起こしやすくなります。言葉でのやり取りは難しくなりますが、快・不快などの感情は残っていると言われています。
アルツハイマー型認知症の原因
アルツハイマー型認知症の原因について、以下の内容を解説します。
- 脳に蓄積する異常タンパク質のメカニズム
- 遺伝や生活習慣病などの危険因子
脳に蓄積する異常タンパク質のメカニズム
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が徐々に失われ、脳萎縮をきたす病気です。脳内に蓄積する「アミロイドβ」と細胞内に蓄積する異常な「タウ」が関与すると考えられています。メカニズムは、以下のとおりです。
- アミロイドβが分解されず、脳に少しずつ蓄積する
- 蓄積したアミロイドβが神経細胞の周囲に付着する
- 炎症を引き起こして、ダメージを与える
- アミロイドβの影響で、神経細胞の中にあるタウも異常な形に変化する
- 神経細胞を内側から壊す
脳の神経細胞が減っていくと、記憶を司る海馬から脳全体が縮み、脳の働きが徐々に低下します。
遺伝や生活習慣病などの危険因子
アルツハイマー型認知症は、いくつかの危険因子が重なることで発症しやすくなると考えられています。主な危険因子は、以下のとおりです。
- 加齢
- 遺伝的な要因
- 生活習慣病(高血圧・糖尿病など)
- その他の生活習慣や環境(運動不足・栄養バランスの乱れた食事・喫煙・歯の健康状態・社会的な孤立)
加齢とともに発症する人の割合は高くなります。遺伝的な要因はご家族にアルツハイマー型認知症の方がいる場合、発症することがありますが、必ず発症するわけではありません。生活習慣病は、動脈硬化を招き、脳血流を低下させることで、神経細胞の機能障害や認知機能の低下に関与すると言われています。
高血圧や糖尿病がある人は、認知症のリスクが高いという報告もあります。以下の記事では、認知症の遺伝リスクや関係する要因、日常生活でできる予防策について詳しく解説しています。
>>認知症は遺伝する?考えられる要因や発症リスク、予防法を解説
進行を緩やかにする治療法
アルツハイマー型認知症の進行を緩やかにする主な治療法は、以下のとおりです。
- 薬物療法(ドネペジル・レカネマブなど)
- 非薬物療法(リハビリテーションなど)
薬物療法(ドネペジル・レカネマブなど)
薬物療法は、記憶障害などの症状を和らげるコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬が主流です。コリンエステラーゼ阻害薬としては、ドネペジルやリバスチグミン、ガランタミンがあります。アセチルコリンに作用し、神経伝達を改善することで、記憶や認知機能の維持が期待されます。
メマンチンといったNMDA受容体拮抗薬は、脳の神経伝達を調整し、記憶や学習、日常機能の維持を補助することが期待されます。副作用があるときは、自己中断せず、医師に相談しましょう。
レカネマブなどは、原因物質の「アミロイドβ」に直接働きかけ、病気の進行に対する効果が報告されています。治療効果には個人差があり、適応は早期の患者さんに限られ、医師により慎重に判断されます。
以下の記事では、認知症の進行を緩やかにするために医療機関で行われる治療や、日常生活で実践できる工夫について、医師監修のもと詳しく解説しています。
>>【医師監修】認知症の進行を止める方法はある?症状悪化を防ぐ治療や対策を解説
非薬物療法(リハビリテーションなど)
非薬物療法は、活動を通して脳と心に良い刺激を与えることが目的です。具体的な方法は、以下の3つです。
- 運動療法(散歩や軽い体操などの有酸素運動)
- 認知リハビリテーション(回想法・音楽療法・作業療法)
- 社会的な交流
運動療法は、脳血流が良くなるだけでなく、神経細胞を元気にする物質が増えることが報告されています。無理のない範囲で、日々の生活に取り入れることが大切です。認知リハビリテーションの主な種類は、以下のとおりです。
- 回想法:昔の写真や懐かしい音楽をきっかけに、思い出を語り合う
- 音楽療法:歌や簡単な楽器の演奏で心を落ち着かせ、感情を表現する
- 作業療法:料理や手芸、園芸といった得意な活動を通して、指先や頭を使いながら役割を持ち、自信をつける
社会的な交流は、デイサービスや地域の集まりに参加し、人と話す機会を持つことで脳を活性化させ、孤立による不安を防ぎます。
早期発見・早期治療が本人や家族の負担を軽くする理由
アルツハイマー型認知症は、早期に気づき、治療を始めることが大切です。ご本人に残された機能を活かし、穏やかな生活を送るための選択肢を多く残せるからです。具体的に、以下の4つの利点があります。
- 進行を穏やかにし、自分らしい時間を長く保てる
- ご本人が「これからの生き方」を自分で決められる
- ご家族が心の準備と正しい知識を持てる
- 経済的・社会的な支援をスムーズに受けられる
症状が軽いうちから治療を始めると、病気の進行を緩やかにできる可能性が高まります。判断力のあるうちに病気と向き合うことで、今後の医療や介護、財産管理などについて家族と話し合うことができ、ご本人の尊厳を守ることにもなります。
早期の診断により、介護保険サービスや医療費の助成制度などを必要なタイミングで利用できる可能性があります。経済的な不安を和らげることも、大切な準備の一つと言えます。
アルツハイマー型認知症の進行を穏やかにする4つの対策
アルツハイマー型認知症の進行を穏やかにする4つの対策について、以下の内容を解説します。
- 食事・運動・知的活動で実践する予防のポイント
- 生活習慣病の管理
- ストレスケア
- 本人の尊厳を守るコミュニケーション
食事・運動・知的活動で実践する予防のポイント
脳の健康を守るためには「食事」「運動」「人とのつながり」が大切です。積極的に摂取したい食品は、魚や野菜、果物、大豆製品、ナッツ類、オリーブオイルです。バランス良く摂取できるように心がけましょう。ご自身で献立を考え、料理することもリハビリになります。無理のない範囲で、楽しみましょう。
運動は、脳血流を良くする習慣になります。「1回30分程度を週に3回以上」を目標にしましょう。具体的には、ウォーキングやラジオ体操、水中ウォーキングです。ご家族や友人と一緒に散歩するのも良いです。
人とのつながりの中で、誰かと話し笑いあうことは、脳を活性化させ、心の安定につながります。研究では、社会的なつながりが多い人は、高齢期における認知機能低下が少ないことが報告されています。趣味のサークルや地域の集まり、ボランティアに参加し、友人や家族とも会話する機会を意識的に増やしましょう。
以下の記事では、アルツハイマー型認知症の予防に役立つ生活習慣や、リスクを下げるために意識したいポイントについて、医学的な視点から詳しく解説しています。
>>アルツハイマー型認知症を予防する方法|発症リスクを下げるために大切なポイント
生活習慣病の管理
アルツハイマー型認知症は、健康状態とも関わっています。生活習慣の管理のポイントは、以下の3つです。
- 定期的な健康診断を受ける
- かかりつけ医の指示を守る
- お口の健康を保つ(口腔ケア)
定期的な健康診断を受けることは、体の状態を知る機会となります。かかりつけ医がある場合は、血圧や血糖値などを管理しましょう。歯の本数が少ないと、認知症のリスクが高まることが研究で指摘されています。定期的な歯科受診、日常の口腔ケアも大切です。
ストレスケア
精神状態は、脳にも影響を与えます。報告では、中年期に不安や嫉妬といった感情を強く抱えていた人は、アルツハイマー型認知症発症のリスクとの関連が認められています。具体的なストレスケアは、以下のとおりです。
- 十分な睡眠をとる
- 音楽を聴く
- お風呂にゆっくり浸かる
- 悩みを一人で抱え込まず、誰かに話す
- 軽い運動で気分転換する
ご家族も、ご本人が安心して穏やかに過ごせるように、心と体のケアを一緒に考えていくことが大切です。
本人の尊厳を守るコミュニケーション
本人の気持ちに寄り添い、尊重して接することは、症状の進行を穏やかにするうえで大切です。接する際のポイントは、次のとおりです。
- 驚かせない:視界に入ってから優しく話しかける
- 急がせない:ご本人のペースに合わせる
- 自尊心を傷つけない:プライドを傷つけない
以下のようなコミュニケーションの工夫も、ご本人の安心につながります。
- 目線の高さを合わせて、笑顔で話す
- 優しく、穏やかな口調を心がける
- 一度に多くの情報を伝えず、短い言葉ではっきりと話す
- 「はい」「いいえ」で答えられる質問を工夫する
- 話の内容が事実と違っていても、否定せずに受け止める
ご本人が「できること」に目を向けることも大切です。温かいコミュニケーションは、ご本人の心を支え、穏やかな毎日を送るための大きな力となります。
以下の記事では、認知症の方への基本的な接し方や避けるべき言動、寄り添うための心構えについて詳しく解説しています。
>>認知症の方への接し方は?基本の対応やしてはいけないこと、心がけたいポイント
まとめ
アルツハイマー型認知症は、現時点では根本的な治療が難しい病気ですが、進行を穏やかにすることは可能です。早期発見と適切な対応が、今後の治療の選択肢を広げることにつながります。薬物治療をはじめ、バランスの良い食事や運動、人とのつながりは、ご本人らしい穏やかな時間を長く保つために役立つとされています。
ご家族も早期対応によって、ご本人の尊厳を守りつつ、心の準備や経済的・社会的支援をスムーズに受けやすい環境を整えられます。気になる症状があるときは、ご本人やご家族だけで悩みを抱え込まず、かかりつけ医や専門の医療機関へ相談しましょう。
もし不安を感じたときは、早めの検査で現状を確認することが安心につながります。以下の記事では、認知症の検査内容や受ける目安、検査の種類・流れについて詳しく紹介しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
参考文献
- Randall J Bateman, Chengjie Xiong, Tammie L S Benzinger, Anne M Fagan, Alison Goate, Nick C Fox, Daniel S Marcus, Nigel J Cairns, Xianyun Xie, Tyler M Blazey, David M Holtzman, Anna Santacruz, Virginia Buckles, Angela Oliver, Krista Moulder, Paul S Aisen, Bernardino Ghetti, William E Klunk, Eric McDade, Ralph N Martins, Colin L Masters, Richard Mayeux, John M Ringman, Martin N Rossor, Peter R Schofield, Reisa A Sperling, Stephen Salloway, John C Morris; Dominantly Inherited Alzheimer Network.Clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer’s disease.N Engl J Med,2012,367,9,p.795-804
- Lena Johansson, Xinxin Guo, Margda Waern, Svante Ostling, Deborah Gustafson, Calle Bengtsson, Ingmar Skoog.Midlife psychological stress and risk of dementia: a 35-year longitudinal population study.Brain,2010,133,Pt 8,p.2217-2224
- Michelle Canavan, Martin J O’Donnell. Hypertension and Cognitive Impairment: A Review of Mechanisms and Key Concepts. Front Neurol, 2022, 13, p.821135
- Christopher H van Dyck, Chad J Swanson, Paul Aisen, Randall J Bateman, Christopher Chen, Michelle Gee, Michio Kanekiyo, David Li, Larisa Reyderman, Sharon Cohen, Lutz Froelich, Sadao Katayama, Marwan Sabbagh, Bruno Vellas, David Watson, Shobha Dhadda, Michael Irizarry, Lynn D Kramer, Takeshi Iwatsubo.Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease.N Engl J Med,2023,388,1,p.9-21
- Kristin L Szuhany, Matteo Bugatti, Michael W Otto. A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. J Psychiatr Res, 2015, 60,p.56-64
- Bryan D James, Robert S Wilson, Lisa L Barnes, David A Bennett. Late-life social activity and cognitive decline in old age. J Int Neuropsychol Soc, 2011, 17, 6, p.998-1005
- Sakura Kiuchi, Yusuke Matsuyama, Kenji Takeuchi, Taro Kusama, Upul Cooray, Ken Osaka, Jun Aida.Number of Teeth and Dementia-free Life Expectancy: A 10-Year Follow-Up Study from the Japan Gerontological Evaluation Study.J Am Med Dir Assoc,2024,25,11,105258
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







