blog
ブログ
アルツハイマー型認知症は、誰でも発症する可能性がある身近な病気です。日々の生活習慣や高血圧、糖尿病などが間接的に発症リスクを高めやすくします。食事や運動だけでなく「腸と脳の関係」や「過去にかかった感染症」などの要因も脳の健康に関わっているのです。
本記事では、今日から実践できる具体的な予防法から、注意すべきリスクまでを解説します。ご自身と家族のためにできることから始め、認知症への進行を緩やかにする方法を知りましょう。
静岡市にお住いの方やご家族様で違和感を感じたら、当院の「もの忘れ外来」をご予約ください。日常生活から改善できることを始めると、進行を遅らせることができる場合もあります。ご家族の方が負担にならないよう医療面のサポートを受けながら向き合っていきましょう。
今日から始められる!アルツハイマー型認知症の予防法4つ
アルツハイマー型認知症の予防法について、以下を解説します。
- 食事療法
- 運動療法
- 知的活動
- 社会参加
食事療法
腸内環境を整える食事は、脳の健康維持が期待されます。具体的な食事法は、以下のとおりです。
- 地中海食:野菜や果物、魚、オリーブオイルなどが中心の食事
- MIND(マインド)食:地中海食と高血圧予防の食事法の組合せ
地中海食は、腸内の善玉菌をサポートし、脳の炎症を抑える働きが期待できます。マインド食は、研究によりアルツハイマー型認知症の発症リスク低下との関連が報告されています。以下の食品を、日々の食事に少しずつ加えてみましょう。
- サバやイワシなどの青魚
- ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜
- ベリー類の果物
- ナッツ類、豆類、オリーブオイル、全粒穀物(玄米や全粒粉パンなど)
ご自身で調理することも、日常の活動としておすすめです。献立を考え、段取りを立て、指先を使う一連の作業は、脳の前頭葉を刺激する良いトレーニングになります。
運動療法
運動習慣は、脳の血流改善や神経細胞の保護に寄与し、認知機能の維持に役立つ可能性があります。研究では、運動によって脳由来神経栄養因子(BDNF)という物質が増え、認知と気分の改善に役立つことが報告されています。激しい運動は必要なく、以下の運動を日々に取り入れましょう。
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- 水泳
- サイクリング
少し息が弾むペースを心がけましょう。頻度は週に3回以上、1回あたり30分程度が目安です。運動は一人で行うよりも、家族や友人と一緒に行うのがおすすめです。
会話を楽しみながら体を動かすことで、脳への刺激と社会的な交流にもつながります。
知的活動
脳の健康維持には、知的な活動や社会的刺激も大切です。「楽しい」と感じながら、少しだけ「難しい」ことに挑戦することが大切です。具体的には、以下の活動が挙げられます。
- 手先を使うもの:手工芸、ガーデニング、料理、楽器の演奏
- 戦略を考えるもの:囲碁、将棋、オセロ、ボードゲーム
- 新しい知識や経験を得るもの:読書、旅行の計画、パソコン、語学学習
日常生活でできる工夫は、以下のとおりです。
- 一日の出来事を具体的に思い出す
- 買い物時に合計金額を暗算してみる
- 普段と違う道を通る
- 一駅手前で降りて歩く
- エレベーターの代わりに階段を使う
「興味があったけれど手を出せなかった」ことに、挑戦してみましょう。
社会参加
人との交流は、脳への刺激になります。会話は、脳のさまざまな部分を同時に使う、高度な知的活動になります。具体的には、以下の流れで会話をしています。
- 聴覚・言語理解:相手の話を聞いて理解する
- 思考・記憶:内容について考える
- 思考・計画:自分の意見を組み立てる
- 言語・運動:言葉にして話す
研究では、社会的接触の少なさや孤独が将来の認知症発症との関連が報告されています。社会とつながるポイントは、以下のとおりです。
- 家族や友人とこまめに連絡をとる
- 直接会って話す機会を作る
- 地域のイベントやボランティア活動に顔を出す
- 趣味のサークルや習い事に通い、共通の話題を持つ仲間を見つける
- 可能な範囲で、年齢に関わらず仕事を続ける
無理のない範囲で、人と関わる機会を意識的に作ることが大切です。
アルツハイマー型認知症の発症リスクを高める6つの要因
アルツハイマー型認知症の発症リスクを高める要因について、以下の6つを解説します。
- 生活習慣病との関連
- 遺伝的要因と家族歴
- 腸内環境の乱れ
- 肺炎などの感染症
- 慢性的なストレスや睡眠不足
- 社会的孤立や知的活動の不足
生活習慣病との関連
生活習慣病は、動脈硬化を招き、脳血流を低下させることで、神経細胞の機能障害や認知機能の低下に関与する可能性があります。高血圧は、脳構造や微小血管系に直接影響を及ぼし、動脈硬化を進行させます。血液中の悪玉コレステロールが多い脂質異常症も、動脈硬化を進行させる一つです。
研究では、高血圧の人は認知症のリスクが高いと報告されています。糖尿病においても、認知症のリスクを高める報告があります。肥満は、高血圧や糖尿病などを引き起こしやすく、間接的に認知症のリスクを高めるのです。
生活習慣病は、日々の食事や運動で予防、改善が期待できます。健康診断などで数値を指摘された場合は、放置せず治療に取り組みましょう。
以下の記事では、認知症の進行を緩やかにする方法や最新の治療法、日常生活でできる工夫について医師の監修のもと詳しく解説しています。
>>【医師監修】認知症の進行を止める方法はある?症状悪化を防ぐ治療や対策を解説
遺伝的要因と家族歴
「アポリポ蛋白E(APOE)」遺伝子が発症リスクに関わることがわかっています。ε4(イプシロンフォー)」の型を持つ人は、持たない人と比べ、発症リスクの上昇と早期発症に関連があると報告されています。
遺伝がすべてを決めるわけではなく、APOEのε4を持っていても、必ず発症するわけではありません。ε4を持っていなくても発症する方はいます。遺伝は、リスク因子の一つにすぎません。遺伝子検査でご自身の型を知ることもできます。結果に一喜一憂するのではなく、リスクを知るきっかけと捉えることが大切です。
以下の記事では、認知症の遺伝リスクや関係する要因、日常生活でできる予防策について詳しく解説しています。
>>認知症は遺伝する?考えられる要因や発症リスク、予防法を解説
腸内環境の乱れ
食生活の乱れやストレスなどで、腸内環境が乱れると発症リスクを高めやすいです。研究では、腸と脳は互いに影響し合う(腸脳相関)と報告されています。腸内の細菌バランスが乱れると、腸での軽い炎症や細菌由来の有害物質が増え、血液中を巡ります。
血液脳関門(血液中の有害物質や細菌が脳に入り込むのを防ぐ場所)の働きが乱れ、脳で小さな炎症が起きやすくなります。慢性的な炎症は、アルツハイマー型認知症の原因物質の蓄積を促すリスクが示唆されています。腸内環境を健やかに保つことは、脳の健康を守るために大切です。
肺炎などの感染症
肺炎やインフルエンザなどの感染症も、発症リスクを高める要因の一つです。感染により体で炎症が強まると、脳にも炎症(神経炎症)が起こる可能性があります。研究では、肺炎による入院は認知症リスクの増加と関連していると報告されています。
高齢者にとって、肺炎は体力を奪うだけでなく、脳にも長期的な影響を与える可能性があります。日頃から手洗いやうがいを徹底し、免疫力を保つことが大切です。感染症を予防するために、肺炎球菌ワクチンの接種を検討しましょう。
慢性的なストレスや睡眠不足
長期的なストレスや睡眠不足は、脳に影響を及ぼす要因です。睡眠中は、アミロイドβなど、脳内で老廃物の排出が行われています。睡眠不足や質が悪いと、老廃物の排出が不十分となり、脳に有害物質がたまりやすくなります。
慢性的なストレス下では、ストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されます。コルチゾールは、記憶を司る脳の「海馬(かいば)」部分を傷つけ、縮小させる傾向があります。海馬は、アルツハイマー型認知症で早期にダメージを受ける部位です。慢性的なストレスは、脳の働きに影響します。
認知症予防には、意識的に休息時間をとり、心と体を休ませ、脳をリフレッシュさせる時間の確保が大切です。
社会的孤立や知的活動の不足
社会とのつながりや、頭を使う機会が減ると、脳への刺激が少なくなり、リスク要因となります。誰かと会話をするとき、脳は活発に働いています。会話は、脳のさまざまな部分を同時に使う高度な知的トレーニングです。人との交流が減る「社会的孤立」は、脳の活動を低下させます。
新しいことを学んだり、趣味に没頭したりするなど、脳を使い続ける活動を続けましょう。「認知予備能(にんちよびのう)」は、脳の神経ネットワークの維持に寄与する可能性があります。予備能があるほど、脳に多少の変化が起きても、認知機能を維持しやすくなります。
日々の生活に「楽しい」と感じられる活動を取り入れ、楽しみながら脳を使い続けましょう。
認知機能の低下が気になる際に取るべき3つの行動
認知機能の低下が気になった際に取るべき行動は、以下のとおりです。
- 加齢によるもの忘れとの違いを見分けるセルフチェック
- 専門の医療機関(もの忘れ外来)での認知機能検査
- 軽度認知障害(MCI)の段階で進行を緩やかにするためにできること
加齢によるもの忘れとの違いを見分けるセルフチェック
もの忘れは2種類あり、違いは以下のとおりです。
- 生理的なもの忘れ:食事の内容など、体験したことの「一部」を忘れる
- 認知症によるもの忘れ:食事をしたこと自体など、体験の「全体」を忘れる
もの忘れセルフチェックリストは、以下のとおりです。
- 日付や曜日が、すぐにわからないことがある
- 同じことを何度も話したり、尋ねたりすると家族に言われる
- 料理の味付けが変わり、同じ物をよく買ってくる
- 水道の蛇口やガス栓の閉め忘れが多くなる
- 慣れている道で迷い、車の運転が怖くなる
- 物の名前がすぐに出てこない
- お金の計算や公共料金の支払いが難しくなる
- 服装や身だしなみに気を使わなくなる
- 以前は楽しんでいた趣味や活動に興味がなくなる
- 怒りっぽくなったり、疑い深くなったりするなど性格の変化がある
当てはまる項目があり、ご家族の様子で気になる点があれば、一人で抱え込まず専門の医療機関へ相談しましょう。
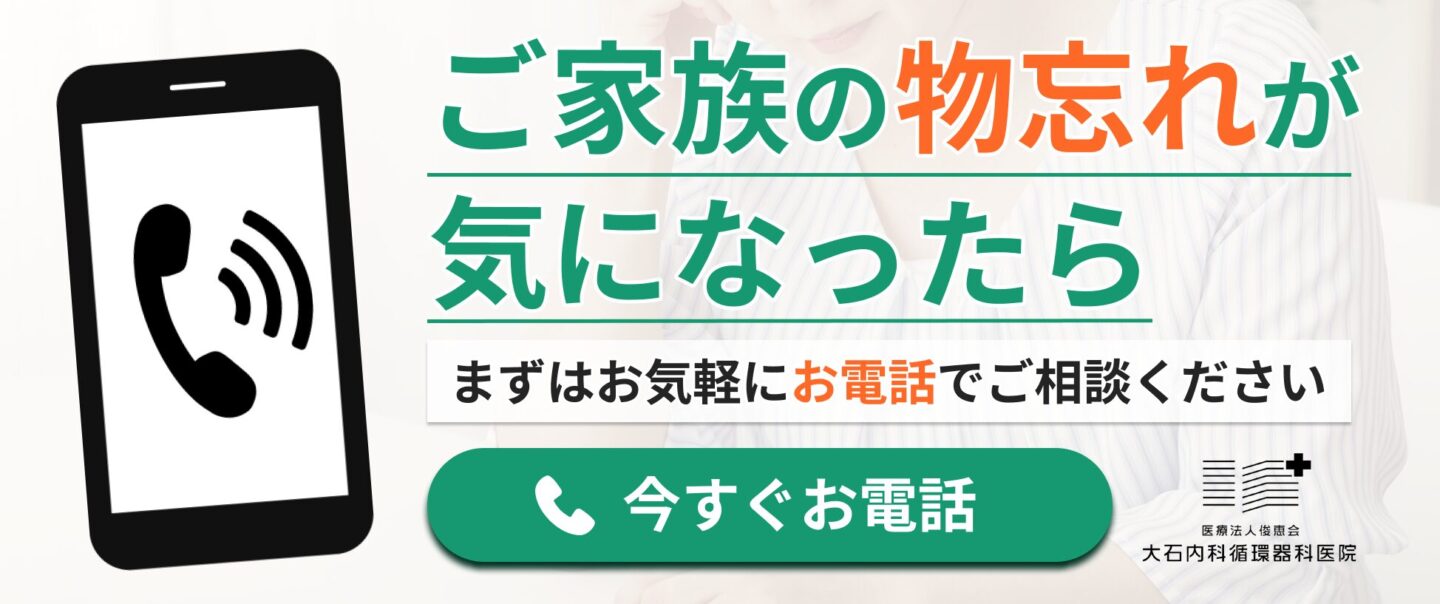
専門の医療機関(もの忘れ外来)での認知機能検査
もの忘れの相談は「もの忘れ外来」や「認知症外来」が専門です。「脳神経内科」や「精神科」でも相談できます。医療機関では、さまざまな検査を通してもの忘れの原因を詳しく調べます。主な検査は、以下のとおりです。
- 問診:ご本人やご家族から症状や生活の様子、困り事などを聞きます
- 認知機能検査:記憶力や判断力などを客観的に評価し、脳の働きを確認します
- 画像検査(CT・MRIなど):脳の形や萎縮の程度、他の病気の有無を調べます
- 血液検査:甲状腺機能の低下やビタミン不足などがないか検査します
研究では、過去のつらい体験による心の傷(PTSD)が、認知機能に影響を与える可能性を示唆しています。問診では過去のストレス体験を聞くこともあり、心の状態も含め、認知機能の状態を定期的に確認していきます。
軽度認知障害(MCI)の段階で進行を緩やかにするためにできること
検査の結果、健康な状態と認知症の中間にあたる「軽度認知障害(MCI)」と呼ばれる段階があります。日常生活に大きな支障はないものの、もの忘れを自覚している状態です。MCIと診断されても、必ず認知症が進行するわけではありません。適切な対策で進行を緩やかにし、認知機能の維持や改善が期待できる場合があります。
対策は、以下のとおりです。
- 食生活の改善:野菜や果物、魚を中心としたバランスの良い食事を心がける
- 運動習慣:ウォーキングなど、少し息が弾むくらいの運動を週3回程度続ける
- 知的活動:読書やパズル、楽器演奏など、脳に良い刺激を与える趣味を持つ
- 社会参加:友人との交流や地域の活動に参加し、人とのつながりを持つ
- 質の良い睡眠:十分な睡眠時間を確保し、脳の疲れをしっかりとる
医師と相談しながら、できることから取り組んでいきましょう。以下の記事では、認知症になりやすい人の特徴や傾向について、最新の知見をもとにわかりやすく解説しています。
>>認知症になりやすい人の特徴とは?
まとめ
アルツハイマー型認知症の発症リスクは、それぞれが影響し合うことが判明しています。食事や運動、人との交流など日々の生活習慣を見直すことで、発症リスクの低下が期待できます。「一駅多く歩いてみる」「趣味の仲間と話す時間を作る」など、日常生活の中で楽しみながら続けられる工夫が大切です。
ご自身やご家族で気になる症状がある場合は、現在の状態を知るためにもチェックリストを活用しましょう。MCIの段階では、適切な対策で進行を遅らせ、認知機能の維持や改善が期待できる場合があります。一人で抱え込まず、もの忘れ外来などの専門家へ相談し、医療面のサポートを受けながら症状に向き合いましょう。
以下の記事では、認知症の検査内容や受診のタイミング、検査の流れについて詳しく解説しています。
>>認知症の検査内容で行うことは?受ける目安や検査の種類・流れも解説
参考文献
- Martha Clare Morris, Christy C Tangney, Yamin Wang, Frank M Sacks, David A Bennett, Neelum T Aggarwal.MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer’s disease.Alzheimers Dement,2015,11,9,p.1007-14
- Szuhany KL, Bugatti M, Otto MW.A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor.J Psychiatr Res,2015,60,p.56-64
- Kuiper JS, Zuidersma M, Oude Voshaar RC, Zuidema SU, van den Heuvel ER, Stolk RP, Smidt N.Social relationships and risk of dementia: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies.Ageing Res Rev,2015,22,p.39-57
- Michelle Canavan, Martin J O’Donnell. Hypertension and Cognitive Impairment: A Review of Mechanisms and Key Concepts. Frontiers in Neurology, 2022, 13, p.821135
- Fang Cao, Fushuang Yang, Jian Li, Wei Guo, Chongheng Zhang, Fa Gao, Xinxin Sun, Yi Zhou, Wenfeng Zhang. The relationship between diabetes and the dementia risk: a meta-analysis. Diabetology & Metabolic Syndrome, 2024, 16, 1, p.101
- E H Corder, A M Saunders, W J Strittmatter, D E Schmechel, P C Gaskell, G W Small, A D Roses, J L Haines, M A Pericak-Vance. Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer’s disease in late onset families. Science, 1993, 261, 5123, p.921-923
- Rawan Tarawneh, Elena Penhos.The gut microbiome and Alzheimer’s disease: Complex and bidirectional interactions.Neurosci Biobehav Rev,2022,141,p.104814
- Tate JA, Snitz BE, Alvarez KA, Nahin RL, Weissfeld LA, Lopez O, Angus DC, Shah F, Ives DG, Fitzpatrick AL, Williamson JD, Arnold AM, DeKosky ST, Yende S; GEM Study Investigators.Infection hospitalization increases risk of dementia in the elderly.Critical Care Medicine,2014,42,5,p.1037-1046
- Aspelund SG, Lorange HL, Halldorsdottir T, Baldursdottir B, Valdimarsdottir H, Valdimarsdottir U, Jónsdóttir HLH.Assessing neurocognitive outcomes in PTSD: a multilevel meta-analytical approach.European Journal of Psychotraumatology,2025,16,1,p.2469978
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







