blog
ブログ
高齢者糖尿病とは、65歳以上で発症する糖尿病です。自覚症状が少なく、気づかないうちに進行する場合があります。この記事では、高齢者が糖尿病になりやすい理由や症状、合併症、血糖コントロールの方法について詳しく解説します。ご自身やご家族の健康を守るため、高齢者糖尿病の正しい知識を身につけて、健やかな毎日を送りましょう。
大石内科循環器科医院では、糖尿病の診察も行っています。オンライン診療も行っており、自宅やオフィスでも診察が可能です。通院のしやすさにも定評がありますので、お悩みの方は気軽にご相談ください。
高齢者糖尿病とは65歳以上で発症する糖尿病
高齢者糖尿病とは、65歳以上で発症する糖尿病のことです。自覚症状が少なく、気づかないうちに進行する場合があります。
加齢に伴い、筋肉量の減少、内臓脂肪が増加しやすくなります。膵臓や心臓の機能が低下し、血糖値のコントロールが難しくなってきます。結果、網膜症や腎症、神経障害といった三大合併症だけでなく、動脈硬化や脳梗塞、心筋梗塞などの合併症のリスクが高まる可能性があります。
高齢者糖尿病の合併症を防ぐには、血糖値の適切な管理が重要です。定期的な健康チェックや、食事・運動の見直しを心がけましょう。高齢者糖尿病は、血管に負担をかけ、動脈硬化を引き起こしやすくなります。動脈硬化が進行すると、脳梗塞や心筋梗塞などの重大な病気につながるため、早めの対策が重要です。
動脈硬化の症状やメカニズム、治療法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
>>動脈硬化を詳しく解説
高齢者糖尿病になりやすい理由
高齢者糖尿病になりやすい理由としては、以下のとおりです。
- 筋肉量の減少
- 内臓脂肪の増加
- 膵臓・心臓機能の低下
- 運動機能の低下
- 呼吸機能の低下
加齢とともに起こる体の変化と糖尿病の関係について、詳しくご紹介します。
筋肉量の減少
年齢を重ねると、筋肉量が徐々に減少していきます。筋肉量の減少は自然な老化現象の一つですが、糖尿病のリスクを高める要因となります。筋肉は、体内で糖をエネルギーに変換する重要な役割を担っています。食事をすると血糖値が上がりますが、筋肉は糖を取り込み、エネルギーとして利用します。
筋肉量が減ると、糖の処理能力が低下し、血糖値が高い状態が続きやすくなります。
内臓脂肪の増加
加齢による内臓脂肪の増加も、糖尿病のリスクを高める要因です。内臓脂肪は、皮下脂肪とは異なり、お腹の奥深くに蓄積される脂肪です。さまざまな生理活性物質を分泌し、体内の炎症を引き起こしたり、インスリンの働きを阻害したりします。インスリンは、血糖値を下げるために不可欠なホルモンです。
インスリンの働きが阻害されると、血糖値がうまくコントロールできなくなり、糖尿病を発症しやすくなります。
膵臓・心臓機能の低下
膵臓・心臓機能の低下も、血糖値のコントロールを難しくし、糖尿病のリスクを高める要因です。加齢により膵臓の機能が低下すると、血糖値をコントロールするインスリンの分泌量が減少したり、分泌のタイミングがずれたりすることがあります。心臓は全身に血液を送るポンプの役割を担っています。
心臓の機能が低下すると、血液循環が悪くなり、全身の細胞への酸素供給や栄養供給が滞ります。
運動機能の低下
加齢に伴い運動機能が低下すると、筋肉量の減少や内臓脂肪の増加の要因になります。糖尿病のリスクを高めるだけでなく、心肺機能の低下にもつながってしまいます。適度な運動を継続することで、血糖値をコントロールしやすくなり、糖尿病の予防・改善につながります。
呼吸機能の低下
呼吸機能の低下も、高齢者糖尿病のリスクを高める要因と密接に関連しています。高齢になると、肺の弾力性が低下したり、呼吸筋力が衰えたりすることで、呼吸機能が低下しやすくなります。
呼吸は、体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するガス交換の役割を担っています。ガス交換がうまくいかないと、体内の細胞が酸素不足に陥り、エネルギー産生が低下します。呼吸機能が低下すると、体内に取り込まれる酸素量が減少します。細胞の活動の低下や糖の代謝がうまくいかなくなり、血糖値が上昇しやすくなります。
高齢者糖尿病の症状と合併症
高齢者糖尿病の症状と合併症について、以下の内容を解説します。
- 高齢者糖尿病の初期症状
- 高齢者糖尿病が進行した場合の症状
- 高血糖による症状(口渇、多飲、多尿など)
- 低血糖の症状(冷や汗、動悸、意識障害など)
- 高齢者糖尿病の三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)
- その他の合併症(動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞など)
何かしらの症状がある場合は、医療機関での検査をご検討ください。
高齢者糖尿病の初期症状
初期に見られる変化として、空腹時の血糖値の上昇が挙げられます。血糖値の上昇は血液検査で確認できます。食後の血糖値も高くなりますが、自覚症状としては現れにくいです。以下のような症状が現れたら、注意しましょう
- のどの渇きが続く
- 急な体重減少がある
- 疲れやすい
- 傷の治りが悪い
- 視界がぼやける
高齢者糖尿病が進行した場合の症状
高齢者糖尿病が進行した場合の症状はさまざまです。高血糖が続くと、体内の水分や栄養が尿と一緒に排出され、脱水症状や栄養不足に陥ることがあります。免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。手足のしびれや痛み、自律神経障害などの神経障害も引き起こします。
高血糖による症状(口渇、多飲、多尿など)
高血糖による代表的な症状は、以下のとおりです。
- 口渇
- 多飲
- 多尿
口渇は、高血糖によって血液中の糖濃度が高くなり、細胞から水分が奪われるために起こります。体は水分を補おうとして、のどが渇くという信号を出します。多飲は、口渇を癒すためです。多尿は、血液中の過剰な糖を尿として排出しようとするために起こります。高血糖の状態が続くと、吐き気や嘔吐、腹痛、倦怠感、意識障害なども現れる可能性があります。
低血糖の症状(冷や汗、動悸、意識障害など)
低血糖は、血糖値が異常に低くなった状態です。加齢とともに自律神経の機能が低下するため、低血糖の自覚症状が現れにくく、重篤な低血糖に陥りやすいため、特に注意が必要です。低血糖による症状は、以下のとおりです。
- 冷や汗
- 動悸
- 手の震え
- 空腹感
- 意識がもうろうとする
低血糖は、糖尿病の治療薬(インスリン製剤やSU薬など)の過剰使用や食事の欠落、激しい運動などによって引き起こされます。めまいやふらつき、頭痛、物忘れ、集中力の低下など、一見低血糖とは関係ないように思える症状が現れる場合があり、発見が遅れる可能性があります。定期的な血糖値の確認が重要です。
低血糖の症状の一つである動悸は、血糖値の急激な変動によって引き起こされることがあります。動悸は低血糖だけでなく、さまざまな原因によって生じるため、適切な検査と対策が必要です。動悸の種類や検査方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
>>動悸の種類や検査方法などについて
高齢者糖尿病の三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)
高齢者糖尿病の三大合併症は以下のとおりです。
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害
高血糖によって、細い血管が損傷することで引き起こされます。網膜症は、網膜の血管が損傷することで、視力低下や失明につながる可能性があります。腎症は、腎臓の血管が損傷することで、腎機能が低下し、最終的には人工透析が必要になることもあります。神経障害は、末梢神経が損傷することで、手足のしびれや痛み、自律神経障害などを引き起こします。
その他の合併症(動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞など)
高齢者糖尿病では、三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)以外にも、以下の心血管疾患リスクを高めます。
- 動脈硬化
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
糖尿病の高血糖危機(高血糖昏睡や糖尿病ケトアシドーシス)は、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。糖尿病は全身の血管や神経に影響を与えるため、合併症を予防するためには、適切な血糖コントロールが不可欠です。免疫力の低下により感染症にかかりやすくなり、足潰瘍や壊疽などの足のトラブルも起こりやすくなります。認知症のリスクを高める可能性も指摘されています。
高齢になるにつれ、認知症のリスクも気になる方が増えてきます。認知症を予防するための具体的な方法については、以下の記事をご覧ください。
>>認知症予防のためにできること
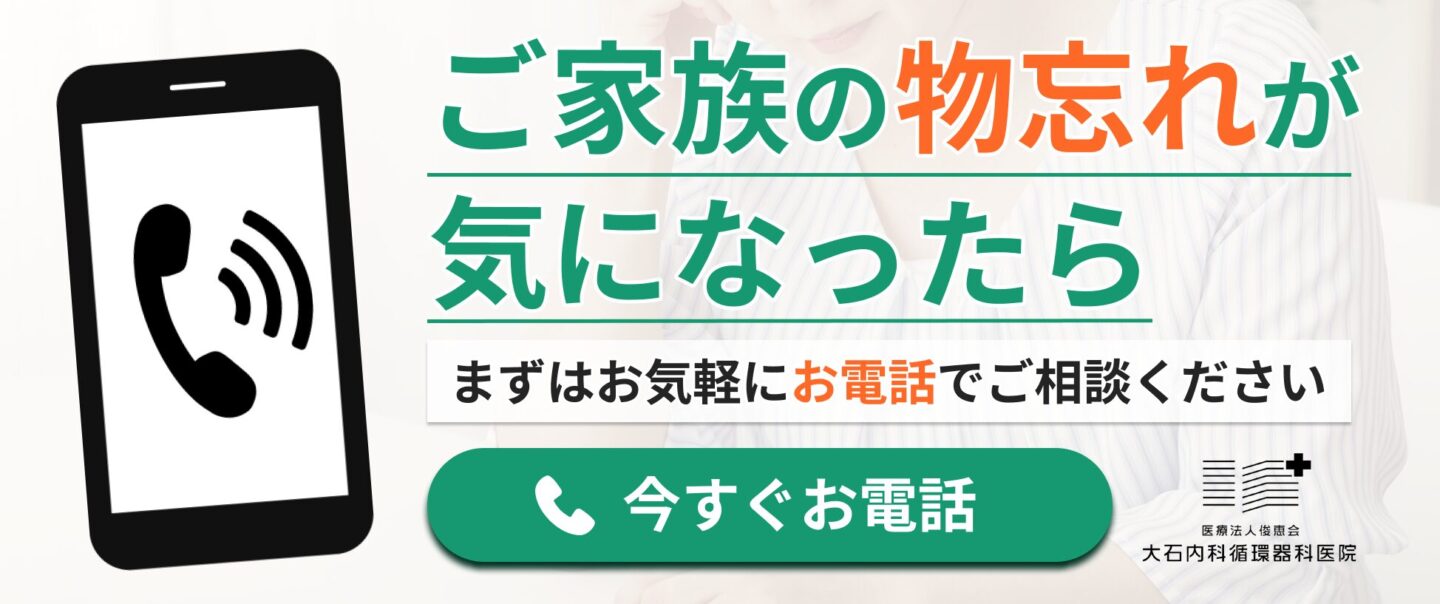
高齢者糖尿病の血糖コントロール方法
高齢者糖尿病の血糖コントロールは、健康寿命を延ばし、豊かな生活を送るために欠かせません。4つの血糖コントロール方法について、高齢者特有の注意点も交えながら詳しく解説します。
- 薬物療法
- インスリン注射
- 食事療法
- 運動療法
薬物療法
高齢者糖尿病の薬物療法では、飲み薬が中心となります。主な薬の種類は以下のとおりです。
- SU薬
- ビグアナイド薬
- SGLT2阻害薬
- DPP4阻害薬
高齢者の場合、腎臓や肝臓の機能が低下していることが多く、薬の代謝や排泄が遅くなるため、副作用が出やすい傾向があります。SU薬は低血糖を起こしやすく、高齢者の場合はふらつきや転倒につながる危険性があります。高齢者糖尿病においては、薬剤性の低血糖が重篤な合併症の引き金となる可能性が示唆されています。
複数の薬を併用すると、副作用のリスクが高まるだけでなく、薬の管理も複雑になり、飲み忘れなどの原因にもなります。少ない種類で効果的に血糖コントロールをすることが重要です。
ご自身の状態に合った薬を選択し、安全に服用するためには、医師との密な連携が不可欠です。定期的な検査で血糖値や合併症の状態をチェックし、薬の効果と副作用を確認しながら、治療方針を調整していく必要があります。
インスリン注射
インスリン注射は、不足しているインスリンを直接体内に補充する治療法です。インスリンは、血糖値を下げるホルモンであり、高齢者糖尿病においても重要な役割を果たします。インスリン注射は、針が細く、痛みも少ないペン型注射器が主流です。注射部位や注射方法を工夫することで、痛みをさらに軽減することも可能です。
インスリン注射は効果的に血糖値をコントロールできますが、低血糖のリスクも伴います。低血糖は、意識障害やけいれん、さらには昏睡状態に陥ることもあるため、適切な対処が必要です。高齢者の場合、低血糖の症状に気づきにくい場合もあるため、より注意が必要です。
インスリン注射を開始する際には、正しい注射方法や低血糖の対処法について、医師や看護師から十分な指導を受けることが重要です。また、血糖自己測定を定期的に行い、血糖値の変化を把握することで、低血糖の予防にもつながります。
食事療法
食事療法は、高齢者糖尿病の血糖コントロールの基盤です。適切なカロリーと栄養バランスを保つことで、血糖値の乱高下を防ぎ、合併症の予防にもつながります。高齢者の場合、食欲が低下し、食事の準備が負担に感じられる場合もあるため、無理なく続けられる方法を見つけることが大切です。1日3食を規則正しく食べる、腹八分目を心がける、よく噛んでゆっくり食べるなど、基本的なことを実践するだけでも効果があります。
食事の内容も重要です。野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維を豊富に含む食品は、血糖値の上昇を緩やかにする可能性があります。良質なタンパク質は、筋肉の維持に効果が期待できます。血糖値を急激に上昇させるため、糖質や脂質の多い食品は摂り過ぎに注意が必要です。
高齢になると、噛む力や飲み込む力が低下することもあります。食材の大きさや調理方法を工夫し、食べやすい食事を心がけましょう。管理栄養士に相談し、個々の状況に合わせた食事プランを作成してもらいましょう。
運動療法
運動療法は、血糖コントロールだけでなく、体力維持や健康増進にも効果的です。高齢者の場合、激しい運動は体に負担がかかります。ウォーキングや軽いジョギング、水中ウォーキング、ヨガや太極拳などの、無理なく続けられる軽い運動を選ぶことが大切です。
筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を上げることで、血糖値のコントロールに役立ちます。運動を行う際は、ご自身の体力に合った強度と時間で行いましょう。最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。ご自身の体調に異変を感じた場合は、無理をせず、すぐに運動を中止してください。
運動療法の効果を高めるためには、継続が大切です。家族や友人と一緒に運動するなど、毎日決まった時間に行える工夫をしましょう。糖尿病の合併症がある場合は、運動の種類や強度について、医師に相談のうえで行うようにしてください。
まとめ
高齢者糖尿病は、加齢による体の変化が大きく関わっており、自覚症状が乏しいまま進行しやすいため、定期的な検査と早期発見が重要です。合併症を防ぐためには、食事療法や運動療法、薬物療法、インスリン注射などを組み合わせた、個々の状態に合わせた血糖コントロールが不可欠です。
高齢者糖尿病は、生活習慣の改善や適切な治療によって、健やかな生活を送ることが可能です。かかりつけ医や専門医に相談し、ご自身の状態に合った治療法を見つけることから始めてみましょう。
高齢者の糖尿病は、自覚症状が少なく気づかないうちに進行し、さまざまな合併症のリスクを高めます。そのため、早期発見と適切な血糖管理が欠かせません。糖尿病の症状や治療法について網羅的に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
>>糖尿病の症状や治療法について
参考文献
- Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care, 2009 Jul;32(7):1335-43.
- Guthrie RA, Guthrie DW. Pathophysiology of diabetes mellitus. Crit Care Nurs Q, 2004 Apr-Jun;27(2):113-25.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







