blog
ブログ
骨粗鬆症は骨がもろくなり骨折しやすくなる病気ですが、実は毎日の食事が大きく関係していることをご存知でしょうか?加齢とともに骨粗鬆症のリスクは高まりますが、若い頃からの食生活が将来の骨の健康に影響を与える可能性があります。
この記事では、骨粗鬆症を悪化させる意外な食べ物はもちろん、骨を強くする食事のポイントについても詳しく解説します。 知らないうちに骨を弱らせている食事を見直し、健康な毎日を送るためのヒントを見つけましょう。
大石内科循環器科医院では、骨密度検査を実施しています。骨粗鬆症は早期発見・早期治療が重要ですので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
骨粗鬆症を悪化させる食事
骨粗鬆症を悪化させる食事として、以下の内容が挙げられます。
- ナトリウム(塩分)の過剰摂取
- リンの過剰摂取
- アルコールの過剰摂取
- カフェインの過剰摂取
- 加工食品やインスタント食品
毎日の食事を見直して骨を丈夫に保ち、健康な毎日を送りましょう。
ナトリウム(塩分)の過剰摂取
塩分の摂りすぎは、骨粗鬆症のリスクを高める可能性があります。塩分の主成分であるナトリウムは、体内でカルシウムの排泄を促進する作用があるためです。カルシウムは骨の主要な構成成分であるため、カルシウムが不足すると骨が弱くなってしまいます。
厚生労働省が推奨する食塩の摂取量の目安は、1日あたり男性7.5g未満、女性6.5g未満です。外食やインスタント食品、加工食品には食塩が多く含まれている場合が多いので、注意が必要です。カップラーメン1杯には約6gの食塩が含まれているものもあり、1食で1日の推奨量に達してしまう可能性もあります。
リンの過剰摂取
リンは、骨の形成に不可欠な栄養素ですが、過剰に摂取すると、体内のカルシウムバランスが崩れ、骨粗鬆症を悪化させる可能性があります。リンは、加工食品やインスタント食品、清涼飲料水、ハム、ソーセージなどに多く含まれています。これらの食品の摂りすぎには注意が必要です。
加工食品に含まれるリン酸塩は、カルシウムの吸収を阻害する作用があるため、注意が必要です。食品のパッケージの裏側には、栄養成分表示が記載されています。リンの含有量をチェックし、摂りすぎに気を付けましょう。1日のリン摂取量の目安は、成人でおよそ1,000mgです。加工食品の多量摂取により、現代人はリンを過剰摂取している傾向があります。
アルコールの過剰摂取
過度のアルコール摂取は、骨粗鬆症のリスクを高めることが知られています。アルコールは、骨を作る細胞である骨芽細胞の働きを阻害し、骨を壊す細胞である破骨細胞の働きを促進する作用があります。アルコールの摂取量は、純アルコール量で1日あたり男性20g、女性10g程度までが適量とされています。
アルコールには利尿作用があり、カルシウムの排泄を促進する作用もあります。特に女性は、男性よりもアルコールの影響を受けやすく、閉経後の女性は骨粗鬆症のリスクがさらに高まるため、より注意が必要です。
カフェインの過剰摂取
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、利尿作用があり、カルシウムの排泄を促進する作用があります。そのため、カフェインの過剰摂取は、骨粗鬆症のリスクを高める可能性があります。カフェイン摂取量の目安は、1日400mgまでとされています。コーヒー1杯には約80~150mgのカフェインが含まれているため、コーヒーを5~6杯以上飲む場合は注意が必要です。
エナジードリンクはカフェイン含有量が多いため、過剰摂取に気を付けましょう。
加工食品やインスタント食品
加工食品やインスタント食品には、リン酸塩などの添加物が含まれていることが多く、カルシウムの吸収を阻害する可能性があります。一般的に塩分や脂肪分も高いため、骨粗鬆症だけでなく、生活習慣病などの健康全般に悪影響を与える可能性があります。さらに、加工食品は、ビタミンやミネラルなどの栄養素が不足している場合が多く、栄養バランスの偏りを招く可能性があります。
新鮮な食材を使った、バランスの良い食事を心がけることが大切です。旬の野菜や果物を積極的に取り入れる、主食・主菜・副菜をそろえた食事を摂る、などを意識してみましょう。
以下の記事では、骨粗鬆症と食べ物の関係をはじめ、食事以外の生活習慣における予防方法も解説しています。併せてご覧ください。
>>骨粗鬆症と食べ物の関係とは?予防・改善に効果的な栄養素を解説
骨粗鬆症予防に効果的な栄養素と食事
骨粗鬆症予防に効果的な栄養素と食事は、以下の内容が挙げられます。
- カルシウム:牛乳・乳製品、小魚、大豆製品など
- ビタミンD:魚介類、きのこ類など
- ビタミンK:納豆、緑黄色野菜など
- マグネシウム:豆類、ナッツ、全粒穀物など
- タンパク質:肉、魚、大豆製品、卵など
カルシウム:牛乳・乳製品、小魚、大豆製品など
カルシウムは、骨の主成分となる大切な栄養素です。丈夫な骨を作るためには、カルシウムを十分に摂取することが不可欠です。骨は常に古い骨が壊され、新しい骨が作られる新陳代謝を繰り返しており、カルシウムはその材料となるためです。カルシウムが不足すると、骨の新陳代謝に影響を与え、骨密度が低下する可能性があります。
カルシウムを多く含む食品には、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、いわしや煮干しなどの小魚、ひじきなどの海藻類、豆腐や納豆などの大豆製品があります。各食品の100gあたりのカルシウム含有量は以下のとおりです。
- 牛乳:110mg
- ヨーグルト:120mg
- チーズ:700mg
- いわし丸干し:380mg
- 煮干し:2,200mg
- ひじき(乾燥):1,400mg
- 木綿豆腐:240mg
- 納豆:60mg
1日に必要なカルシウム量は、成人で700~800mgです。食事内容や栄養摂取について気になる方は、医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。
ビタミンD:魚介類、きのこ類など
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける栄養素です。腸管からのカルシウム吸収を促進し、骨の形成に重要な役割を果たします。ビタミンDが不足すると、せっかくカルシウムを摂取しても、体内に吸収されにくくなってしまいます。
ビタミンDは、鮭やさんまなどの魚介類、きのこ類、卵などに含まれています。各食品の100gあたりのビタミンD含有量は以下のとおりです。
- 鮭:11.0μg
- さんま:29.0μg
- しいたけ(干し):8.5μg
- きくらげ(干し):3.8μg
- 卵:1.1μg
ビタミンDは、1日10~20分ほど、日光浴をすることで生成できます。適度な日光浴をしながらウォーキングなどの軽い運動をすることは、骨の健康維持につながります。ただし、日焼けには注意が必要です。
過度な紫外線は皮膚がんのリスクを高める可能性があるため、日焼け止めを使用したり、帽子をかぶるなどの対策を講じることが重要です。
ビタミンK:納豆、緑黄色野菜など
ビタミンKは、骨の形成に不可欠なオステオカルシンというタンパク質を活性化させる働きがあります。オステオカルシンは骨の基質タンパク質であり、カルシウムを骨に沈着させる役割を担っています。ビタミンKが不足すると、オステオカルシンの活性化が不十分となり、骨の形成が阻害される可能性があります。
ビタミンKは納豆やほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれています。各食品の100gあたりのビタミンK含有量は以下のとおりです。
- 納豆:290mg
- ほうれん草:460mg
- 小松菜:600mg
- ブロッコリー:120mg
ビタミンKは脂溶性ビタミンなので、油と一緒に調理することで吸収率を高めることができます。抗凝固薬を服用している方は、ビタミンKを含む食品の摂取について、事前に医師に相談することをおすすめします。
マグネシウム:豆類、ナッツ、全粒穀物など
マグネシウムは、骨の形成を助け、骨密度を維持するのに役立つ栄養素です。マグネシウムは、カルシウムと同様に骨の構成成分であり、骨の結晶化を促進する作用があります。また、マグネシウムは、ビタミンDの活性化にも関与しています。
マグネシウムが不足すると、骨密度が低下しやすくなるだけでなく、筋肉の痙攣や神経過敏などの症状が現れることもあります。マグネシウムは、大豆やアーモンドなどのナッツ類、玄米などの全粒穀物に多く含まれています。
タンパク質:肉、魚、大豆製品、卵など
タンパク質は、骨の土台となるコラーゲンの材料となる栄養素です。コラーゲンは、骨に弾力性を与え、骨折を防ぐ役割を担っています。タンパク質が不足すると、コラーゲンの生成が不十分となり、骨がもろくなりやすくなります。
タンパク質は、肉や魚、大豆製品、卵などに多く含まれています。十分なタンパク質を摂取することで、骨の強度を維持することができます。
骨粗鬆症の予防には、バランスの良い食事が重要です。さまざまな食品から栄養を摂取し、健康な骨を維持しましょう。
骨粗鬆症の食事療法における注意点
骨粗鬆症の食事療法における注意点として、以下の内容が挙げられます。
- 栄養バランスの取れた食事を心がける
- 特定の栄養素に偏らない
- 適度な運動と組み合わせる
- 定期的な骨密度検査を受ける
- 医師や管理栄養士に相談する
正しい食生活を送り、骨を丈夫に保つための第一歩を踏み出しましょう。
栄養バランスの取れた食事を心がける
骨粗鬆症の予防や改善には、特定の栄養素だけを過剰摂取するのではなく、多様な栄養素をバランス良く摂取することが重要です。カルシウムやビタミンDはもちろん重要ですが、それだけで十分というわけではありません。
骨の健康を維持するためには、タンパク質やビタミンK、マグネシウムなど、さまざまな栄養素が複雑に連携しています。
特定の栄養素に偏らない
特定の栄養素に偏った食事は、骨粗鬆症のリスクを高める可能性があります。加工食品やインスタント食品に多く含まれるリンは、過剰に摂取するとカルシウムの吸収を阻害してしまいます。現代の食生活では、加工食品の摂取頻度が高いため、リンの過剰摂取に陥りやすい傾向があります。
過剰な塩分摂取も骨粗鬆症のリスクを高めます。塩分の主成分であるナトリウムは体内でカルシウムの排泄を促進するため、骨密度が低下する原因となる可能性があります。減塩を心がけ、だしや香辛料、酸味などを活用して薄味に慣れていくことが重要です。
適度な運動と組み合わせる
食事療法に加えて、適度な運動も骨粗鬆症の予防や改善に効果的です。運動は骨に刺激を与え、骨密度を向上させる効果があります。ウォーキングやジョギングなどの軽い運動でも効果がありますが、運動の種類や強度については、個人の状態に応じて医師に相談しましょう。
無理のない範囲で、週に数回、適度な運動を心がけてください。2021年の研究では、抵抗運動と持久運動が、骨粗鬆症とサルコペニアの発症リスクの低減に関連する可能性が報告されています。サルコペニアとは、加齢に伴って筋肉量が減少していくことで、転倒・骨折のリスクを高める要因です。骨粗鬆症とサルコペニアを合併すると、運動機能が低下し、要介護状態に進行するリスクが高まるため注意が必要です。
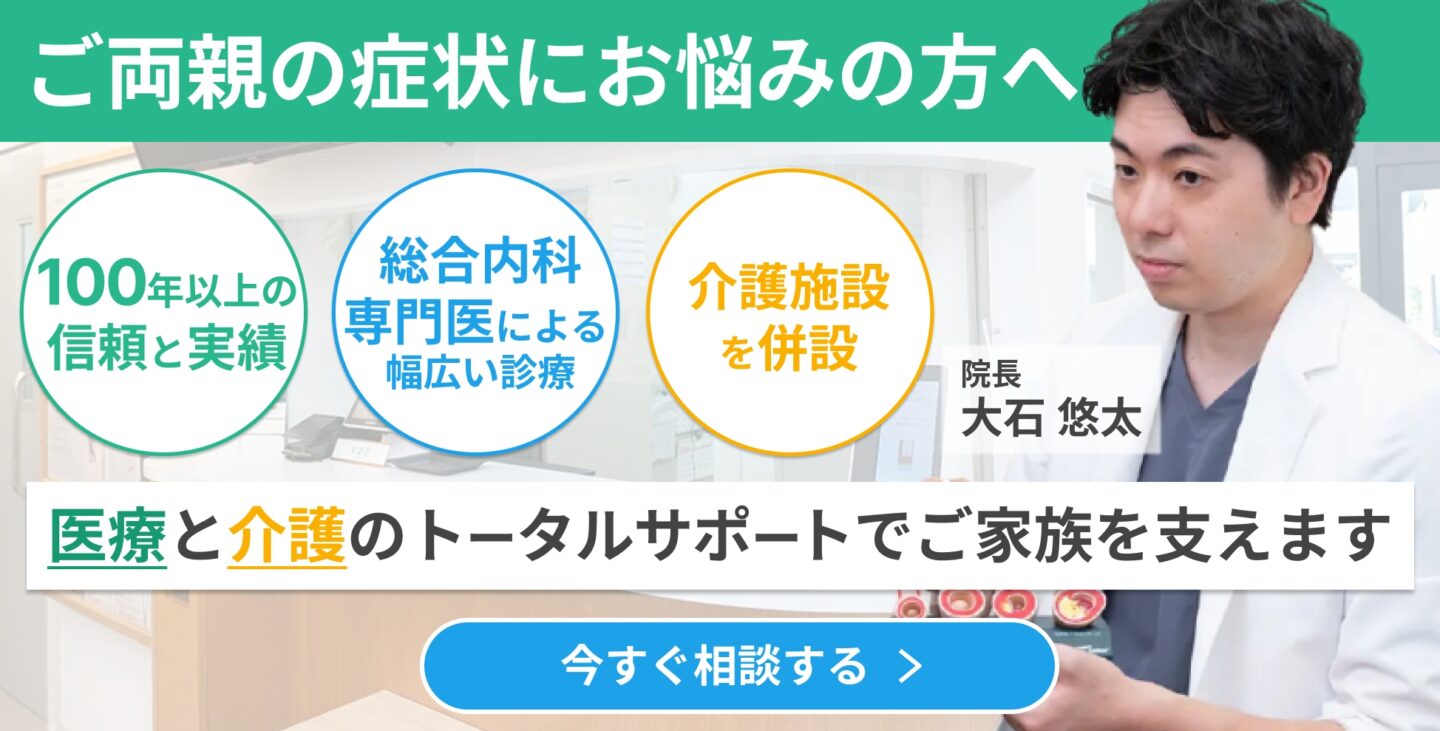
定期的な骨密度検査を受ける
骨粗鬆症は自覚症状が現れにくい場合があります。検査の必要性や頻度については、年齢や状態に応じて医師にご相談ください。
医師や管理栄養士に相談する
骨粗鬆症の食事療法について、不安な点や疑問点があれば、医師や管理栄養士に相談しましょう。個々の状況に合わせて、適切なアドバイスを受けることができます。
食事療法以外にも、薬を服用する薬物療法もあります。以下の記事では、骨粗鬆症の薬の正しい服用方法や種類、特徴などを解説しています。食事以外の対処法を増やしたい方は、併せてご確認ください。
>>骨粗鬆症の薬は危険?副作用と正しい服用方法を詳しく解説
まとめ
骨粗鬆症の予防と改善には、食事の内容がとても大切です。カルシウムやビタミンDだけでなく、さまざまな栄養素をバランス良く摂ることが重要です。塩分やリン、カフェイン、アルコールの摂りすぎには注意が必要で、加工食品やインスタント食品は控えめにしましょう。
カルシウムを多く含む牛乳・乳製品や小魚、ビタミンDが豊富な魚介類ときのこ類を積極的に摂り入れてみてください。栄養バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせて、健康な骨を維持しましょう。
閉経後の女性や高齢者の方は、定期的な骨密度検査を受け、早期発見・治療に努めましょう。毎日の生活習慣を少し見直すことで、将来の健康を守り、いつまでも元気に過ごせるように心がけましょう。
以下の記事では、骨粗鬆症を放置してはいけない理由や初期症状、治療法などを網羅的に解説していますので、併せてご確認ください。
>>骨粗鬆症について
参考文献
- Papadopoulou SK, Papadimitriou K, Voulgaridou G, Georgaki E, Tsotidou E, Zantidou O, Papandreou D. Exercise and Nutrition Impact on Osteoporosis and Sarcopenia-The Incidence of Osteosarcopenia: A Narrative Review. Nutrients, 2021, 13(12), p.4499.
- Lane NE. Epidemiology, etiology, and diagnosis of osteoporosis. Am J Obstet Gynecol, 2006, 194(2 Suppl), p.S3-11.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







