disease
病気から探す
心臓は24時間休むことなく動き続け、全身に血液を送り届けています。心臓の働きを支えているのが、心臓を取り巻く冠動脈という血管です。冠動脈が狭くなると、心臓に必要な血液が十分に届かなくなり、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れる「狭心症」になります。
実は、狭心症は決して他人事ではなく、誰もが罹患する可能性のある身近な病気なのです。この記事では、狭心症の症状や原因、検査方法や治療法を解説します。ご自身の健康状態をチェックするためにも、ぜひ最後までお読みください。
静岡市で胸の痛みや締めつけ感が気になる方は、大石内科循環器科医院にご相談ください。狭心症は動脈硬化などによって心臓への血流が一時的に不足する病気で、放置すると心筋梗塞に進行する危険があります。
当院では循環器専門医が丁寧に症状を伺い、心電図やエコーなどの検査で早期発見をサポートします。気になる胸の症状は軽視せず、安心できる体制のもとで早めにご相談ください。
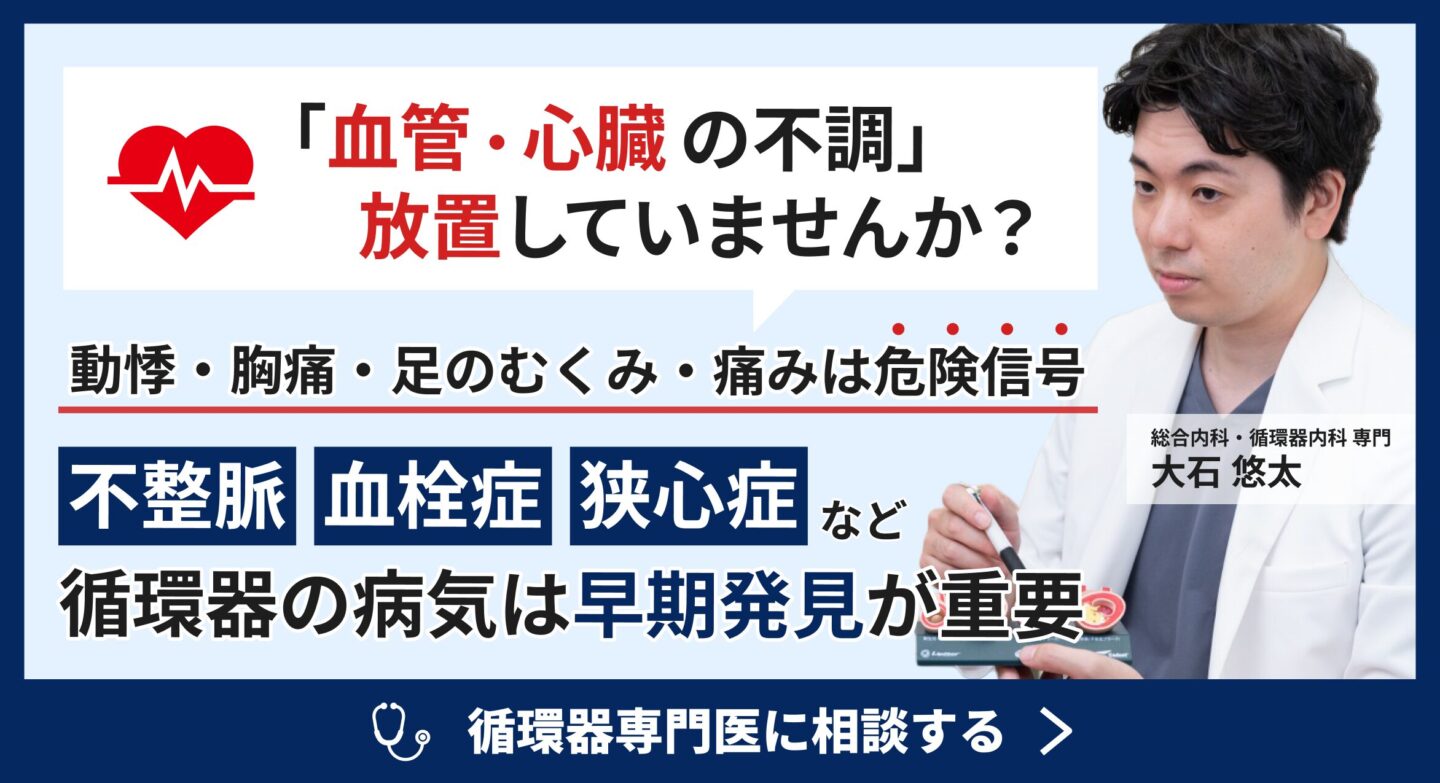
狭心症とは冠動脈が狭まり心臓の筋肉への血流が不足する病気
狭心症とは、心臓を動かす筋肉に酸素が十分届かなくなる病気です。心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を担っており、大量の酸素と栄養を必要とします。その酸素を届ける血管が「冠動脈」ですが、動脈硬化などによってこの冠動脈が狭くなると、血流が不足し、心臓が「酸素不足」の状態に陥ります。
心臓が酸素不足になると、体はサインを出します。その代表的な症状が、胸の痛みや圧迫感、締め付けられるような苦しさです。発作は数分〜10分程度続き、安静にしたり薬を使ったりすると症状が和らぐことがあります。
狭心症は放置すると心筋梗塞に進行する危険性もあるため、早期の診断と治療が大切です。
狭心症の種類
狭心症は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 安定狭心症(労作性狭心症)
- 不安定狭心症
- 異型狭心症(冠攣縮性狭心症)
それぞれの特徴を理解することで、適切な治療につなげることができます。
安定狭心症(労作性狭心症)
安定狭心症は、運動や労作時に起こる予測可能な胸痛が特徴です。階段を上る、重い荷物を持つなど、体を動かしたときに胸の痛みや圧迫感が現れます。これは心臓への負担が増加することで、狭くなった冠動脈では一時的に血液供給が不足するためです。
安静にすると数分で症状が治まります。「坂道を上ると決まって胸が苦しくなる」という症状は、安定狭心症の特徴です。
不安定狭心症
安定狭心症と異なり、安静時にも突然胸の痛みが起こることがあります。以下のような特徴を示す狭心症です。
- 安静時にも突然胸痛が発生
- 痛みがより強く、持続時間も長い
- 従来のパターンと異なる症状の変化
- ニトログリセリンが効きにくい
- 症状の頻度や強さが悪化傾向
この病態では冠動脈がさらに狭くなり、血栓(血液の塊)ができる可能性が高まっています。心筋梗塞へ進展するリスクが極めて高く、緊急の検査と治療が必要な危険な状態です。症状に気づいたら迷わず救急外来を受診する必要があります。
異型狭心症(冠攣縮性狭心症)
異型狭心症は、夜中や早朝など、安静時に胸の痛みや圧迫感が生じる特殊なタイプです。冠動脈が一時的に痙攣(けいれん)を起こし、血管が狭くなることが原因となります。
血管が収縮しやすい冬場に多くみられ「夜中に胸が締め付けられるように痛くなり、目が覚める」という症状が典型的です。ストレス、喫煙、アルコール、寒冷刺激などが誘因となることが多く、カルシウム拮抗薬による治療の効果が期待されています。
狭心症の主な症状
狭心症は心臓の血流が一時的に不足することで生じ、胸の痛みや圧迫感を中心にさまざまな症状を引き起こします。症状の現れ方には個人差があり、軽微な違和感にとどまる方もいれば、強い胸痛を訴える方もいます。主な症状2つを解説します。
胸部症状
典型的な胸の症状は、患者さん自身の表現として以下のように表現されることがよくあります。
- 心臓が締め付けられる感じ
- 胸に重苦しさがある
- 焼けるような痛み
- 胸が押さえつけられる感覚
- 息が詰まるような圧迫感
多くの場合、痛みの中心は胸の真ん中ですが、左肩から腕の内側、背中、顎、歯といった部位に広がる「関連痛」を伴うことがあります。この放散パターンは狭心症を疑ううえで重要な診断の手がかりになります。
随伴する症状
胸部の症状とあわせて、以下のような全身の不調を伴うことがあります。
- 息切れや呼吸困難
- 動悸や不整脈
- 冷や汗や多量の発汗
- 吐き気や嘔吐
- めまい・ふらつき
- 全身の倦怠感
狭心症の発作は通常数分以内に自然におさまることが多いですが、15分以上持続する場合は心筋梗塞へ移行している可能性があります。その際は自己判断で様子を見ず、速やかに救急要請(119番通報)や医療機関での受診が必要です。
狭心症の主な原因
狭心症の最大の原因は、冠動脈が動脈硬化で狭くなり、心臓に十分な酸素が届かなくなることです。動脈硬化は血管の内側にコレステロールや脂肪がたまり、血流が妨げられることで進行します。その背景には生活習慣病や生活習慣そのものが深く関わっています。
狭心症の主な危険因子は以下のとおりです。
- 高血圧:血管に強い負担をかけ、壁を傷つけ動脈硬化を進める
- 脂質異常症:悪玉コレステロール(LDL)が多すぎると血管に蓄積する
- 糖尿病:高血糖が血管を傷め、動脈硬化を促進する
- 肥満:高血圧や糖尿病を引き起こしやすく、リスクを増加させる
- 喫煙:ニコチンが血管を収縮させ、一酸化炭素が酸素供給を妨げる
- 加齢:年齢とともに血管が硬くなり動脈硬化が進む
- 遺伝:家族に狭心症の人がいると発症リスクが高まる
- ストレス:血圧や心拍数を上げ、血管に炎症を起こしやすくする
これらの因子が重なると、動脈硬化が加速し、狭心症のリスクはさらに高まります。生活習慣を整えることは、治療だけでなく予防にもつながります。
動脈硬化は、狭心症だけでなく心筋梗塞や脳卒中など多くの循環器疾患の共通基盤となる重要な病態です。血管の状態を正しく理解し、実際にどの程度進行しているかを知ることは、予防や治療方針を考えるうえで欠かせません。
以下の記事では、動脈硬化について網羅的に解説しているので、ぜひチェックしてみてください
>>動脈硬化
狭心症の検査方法
狭心症かもしれないと思ったら、一人で不安を抱え込まず、まずは医療機関を受診して医師に相談することが大切です。狭心症かどうかを診断するためには、以下の検査を組み合わせて行います。
- 問診と診察
- 心電図検査
- 心臓超音波検査(心エコー検査)
- ホルター心電図検査
- 冠動脈造影検査
- 血液検査
問診と診察
まずは具体的な症状を問診します。
- いつ、どのような時に胸の痛みや圧迫感を感じるか
- 運動をした時や、精神的にストレスを感じた時に症状が出やすいか
- 安静時に症状が現れるか
- 過去の病歴や生活習慣、家族の病歴
狭心症かどうかを見極めるための重要な手がかりになります。家族に心臓病を患った方がいる場合、遺伝的な要因も考慮する必要があるため必ず医師にお伝えください。
心電図検査
心臓の電気的な活動を記録する、基本的な検査です。健康診断などでも広く行われています。安静時の心臓の状態を知るために重要ですが、安静時には異常が見つからない場合でも、運動中に狭心症の症状が現れるケースがあります。自転車こぎやトレッドミル歩行などの運動負荷心電図検査を行い、運動中の心臓の状態を調べます。
以下の記事では心電図検査について、わかることや異常の種類、原因などを解説しているので、合わせてチェックしてみてください。
>>心電図検査で異常はわかる?引っかかる原因や種類、対処法を解説
心臓超音波検査(心エコー検査)
心臓超音波検査(心エコー検査)は、超音波を利用して心臓の動きや構造をリアルタイムで観察する検査です。胸に小さなプローブを当てるだけで行え、痛みはなく体への負担もほとんどありません。
この検査では、心臓の筋肉の厚さや動き、弁の開閉状態、血液の流れなどを詳しく確認できます。検査時間は30分程度で、放射線被ばくもないため、繰り返し安心して受けられる点も特徴です。狭心症や心不全の診断・治療効果の確認に欠かせない検査と言えます。
ホルター心電図検査
ホルター心電図検査は、小型の心電図記録計を体に装着し、24時間にわたって心臓のリズムを記録する検査です。胸に数枚の電極シールを貼り、スマートフォンほどの大きさの記録機を腰や肩に装着して行います。装着したまま普段通りの生活が送れるため、病院での短時間の心電図では捉えきれない不整脈や狭心症発作を検出できるのが大きな特徴です。
この検査により、動悸・胸痛・息切れといった症状が出ている時に心臓がどのような状態になっているかを詳しく確認できます。記録後はデータを解析し、発作の有無や心拍の変化を医師が評価します。
不整脈のサインとしてよく現れる「動悸」については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
>>動悸の詳細はこちら
冠動脈造影検査
冠動脈造影検査は、心臓に酸素や栄養を送る血管(冠動脈)の状態を詳しく調べるための精密検査です。腕や足の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、冠動脈に造影剤を流し込んでX線撮影を行います。これにより、冠動脈がどこで・どの程度狭くなっているか、あるいは詰まっているかを正確に診断できます。
検査は局所麻酔で行われ、痛みはほとんどありませんが、体に管を入れる「侵襲的な検査」であるため、合併症のリスクもわずかに伴います。そのため医師は、症状や他の検査結果を総合的に判断したうえで、この検査が必要かどうかを慎重に決定します。
血液検査
血液検査は、心臓に負担がかかっているかどうかを客観的に評価できる検査です。血液中には心臓の異常があると上昇する物質があり、それを測定することで病気の有無や重症度を判断します。
代表的な項目には、心筋にダメージがあると上昇するトロポニンやCK(クレアチンキナーゼ)、心不全の状態を反映するBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)があります。これらを確認することで、狭心症だけでなく心筋梗塞や心不全といった他の心臓疾患との区別にも役立ちます。
狭心症の治療法
狭心症の治療法は大きく分けて、以下の3つです。
- 薬物療法
- カテーテル治療
- 冠動脈バイパス手術
どの治療法を選択するかは、患者さんの病状や全身状態、患者さんの希望などを考慮して決定します。
薬物療法
薬物療法は、狭心症の症状を抑え、発作を予防するための基本的な治療です。症状が安定していれば通院しながら継続でき、定期的な検査で病状を確認しつつ、必要に応じて薬の種類や量を調整していきます。
主に使われる薬には以下の種類があります。
- ニトログリセリン:血管を広げ心臓への血流を改善する
- β遮断薬:心臓の動きを穏やかにして酸素消費を抑える
- カルシウム拮抗薬:血管を拡張し血流を改善する
- 抗血小板薬:血液をサラサラにして血管の詰まりを予防する
薬の効果は比較的早く現れるものもあり、特にニトログリセリンは発作時に舌の下で使用することで数分以内に症状が和らぎます。こうした薬を組み合わせて使うことで、日常生活の安心感を高めることが可能です。
カテーテル治療
カテーテル治療は、狭くなった冠動脈を内側から広げて血流を改善する治療で、狭心症の代表的な方法の一つです。足の付け根や腕の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、狭窄部位まで進めて治療を行います。治療後は数日間の入院が必要で、退院後も再狭窄を防ぐために薬物療法を続けます。
代表的な方法は次の2つです。
- バルーン治療:風船付きのカテーテルを狭窄部で膨らませ血管を押し広げる
- ステント留置術:金属製の筒(ステント)を留置し血管を広げた状態を維持する
バルーン治療は血管を一時的に拡張させるのに対し、ステント留置術はその効果を長期間維持するために行われます。患者さんの病変の状態や血管の特徴に応じて、医師が最適な方法を選択します。
冠動脈バイパス手術
手術によって心臓の血管のバイパスを作る治療法です。体の他の部分から血管を採取し、狭窄または閉塞した冠動脈の先につなぎ血液の流れを改善する手術です。手術を受けた場合は、1〜2週間程度の入院が必要となります。リハビリテーションを行いながら、社会復帰を目指します。
狭心症は早期発見・早期治療によって、症状の改善や進行を抑制できる可能性のある病気です。気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診し、医師に相談することが大切です。
狭心症の予防・対策につながる生活習慣のポイント
狭心症の予防は、動脈硬化の進行を抑制することに尽きます。血管の老化現象とも言える動脈硬化は、血管壁にコレステロールなどの老廃物が蓄積し、血管内腔が狭くなることで引き起こされます。そのため、予防には日々の生活習慣を見直すことが大切です。具体的には、以下のようなことに気をつけましょう。
- バランスの良い食事
- 適度な運動
- 禁煙
- ストレスをため込まない
- 定期的な健康診断
バランスの良い食事
狭心症の予防や再発防止のためには、野菜や果物を中心にしたバランスの良い食事が欠かせません。特に塩分・脂肪分・糖分の摂りすぎは、血管の負担となるため、注意が必要です。心がけたいポイントは以下のとおりです。
- 野菜や果物を毎日しっかり摂る
- 塩分の多い加工食品やインスタント食品を控える
- 脂っこい揚げ物やスナック菓子を食べすぎない
- ケーキや甘い飲み物など糖分の多いものは適量にする
野菜に含まれる食物繊維は、コレステロールの吸収を抑えたり、血糖値の急上昇を防いだりする働きがあります。ビタミンやミネラルは血管や心臓の健康維持に役立つため、日々の食事で積極的に取り入れることが大切です。
適度な運動
軽い運動を習慣的に行いましょう。激しい運動は逆効果になる場合があるので、ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で行うことが大切です。毎日30分程度、散歩をするだけでも効果があります。
軽い運動を習慣的に行うことで、肥満の解消やストレスの発散、血行促進効果などが期待できます。エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使うようにするのもおすすめです。日常生活の中で、こまめに体を動かすことを意識することで運動不足の解消につながります。
禁煙
喫煙は狭心症のリスクを高めるため、禁煙することが大切です。禁煙は狭心症だけでなく、その他多くの病気の予防にもつながるので健康的な生活を送るためには欠かせません。
禁煙は一人で行うのは難しいので周りの人に協力してもらいながら、禁煙外来などを利用しましょう。禁煙することで血管が拡張し、血流が改善されます。ニコチンによる血管収縮作用もなくなるため、狭心症のリスクを減らすことができます。
ストレスをため込まない
ストレスは血管を収縮させ、血圧を上げるなど心臓に悪影響を与えます。そのため、日常的にストレスを発散し、ため込まない工夫が狭心症予防につながります。実践できる方法の一例は以下のとおりです。
- 趣味やリラックスできる活動を楽しむ
- 家族や友人と過ごす時間を増やす
- 好きな音楽を聴く、ゆっくりお風呂に入る
- 悩みは一人で抱え込まず相談する
ストレスが続くと、ストレスホルモンが分泌され、血管の内側にダメージを与えて動脈硬化を進める恐れがあります。生活の中で無理なく取り入れられる方法を見つけ、心と体のバランスを整えることが大切です。
以下の記事では、ストレスが引き起こす突然の動悸について詳しく解説しています。心当たりのある方はぜひチェックしてみてください。
>>突然の急な動悸、その原因はストレスかも?
定期的な健康診断
狭心症を予防・早期発見するためには、定期的な健康診断が欠かせません。血圧や血糖値、コレステロール値などを定期的に確認することで、動脈硬化や生活習慣病のリスクをいち早く察知できます。チェックすべき主な項目は以下のとおりです。
- 血圧
- 血糖値(空腹時血糖・HbA1c)
- コレステロール値(LDL・HDL・中性脂肪)
健康診断で異常が見つかった場合は、医師の指示に従って治療や生活習慣の改善に取り組みましょう。早期にリスクを把握し、適切に対処することが狭心症だけでなく、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な合併症の予防にもつながります。
当院でも狭心症をはじめとした循環器疾患の診療を行っております。検診で不安がある方や症状に心当たりがある方は、お気軽にご相談ください
まとめ
狭心症は、心臓の血管である冠動脈が狭くなり、心臓への血流が不足することで胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。原因の多くは動脈硬化であり、高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満といった生活習慣病が大きなリスク因子となります。
治療法には以下のような選択肢があります。
- 薬物療法:症状を和らげ発作を予防する
- カテーテル治療:狭くなった血管を広げる
- 外科的治療:重症例での冠動脈バイパス術など
狭心症を放置すると、心筋梗塞や心不全など命に関わる合併症を引き起こす危険があるため、早期発見と治療が欠かせません。あわせて、禁煙、適度な運動、バランスの良い食事など生活習慣の改善が予防に直結します。
当院では、狭心症をはじめとする循環器疾患の診療を行っています。胸の違和感や痛みがある方、健康診断で異常を指摘された方は、お早めにご相談ください。
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







