disease
病気から探す
「健康診断でコレステロールが高いと言われた」「家族に心臓病の人がいる」そんな不安を抱える方も多いのではないでしょうか。動脈硬化は「年齢のせい」とされがちです。実は生活習慣や体質が大きく関わり、放置すれば心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気を引き起こす危険があります。
自覚症状が乏しいため、気づかぬうちに進行してしまうことも少なくありません。この記事では、動脈硬化の原因や症状、検査方法、治療や予防の具体策までわかりやすく解説しています。正しい知識を得ることで、生活習慣を見直し、リスクを減らしながら安心して毎日を過ごせるきっかけとなるはずです。
静岡市で動脈硬化が気になる方は、大石内科循環器科医院へご相談ください。当院では循環器専門医が心電図や超音波検査、血液検査などを組み合わせてリスクを丁寧に評価し、必要に応じた治療や生活習慣の改善をサポートしています。ご自身の状態を正しく知ることで、将来の病気を防ぎ、安心して日々を過ごす一歩につながります。
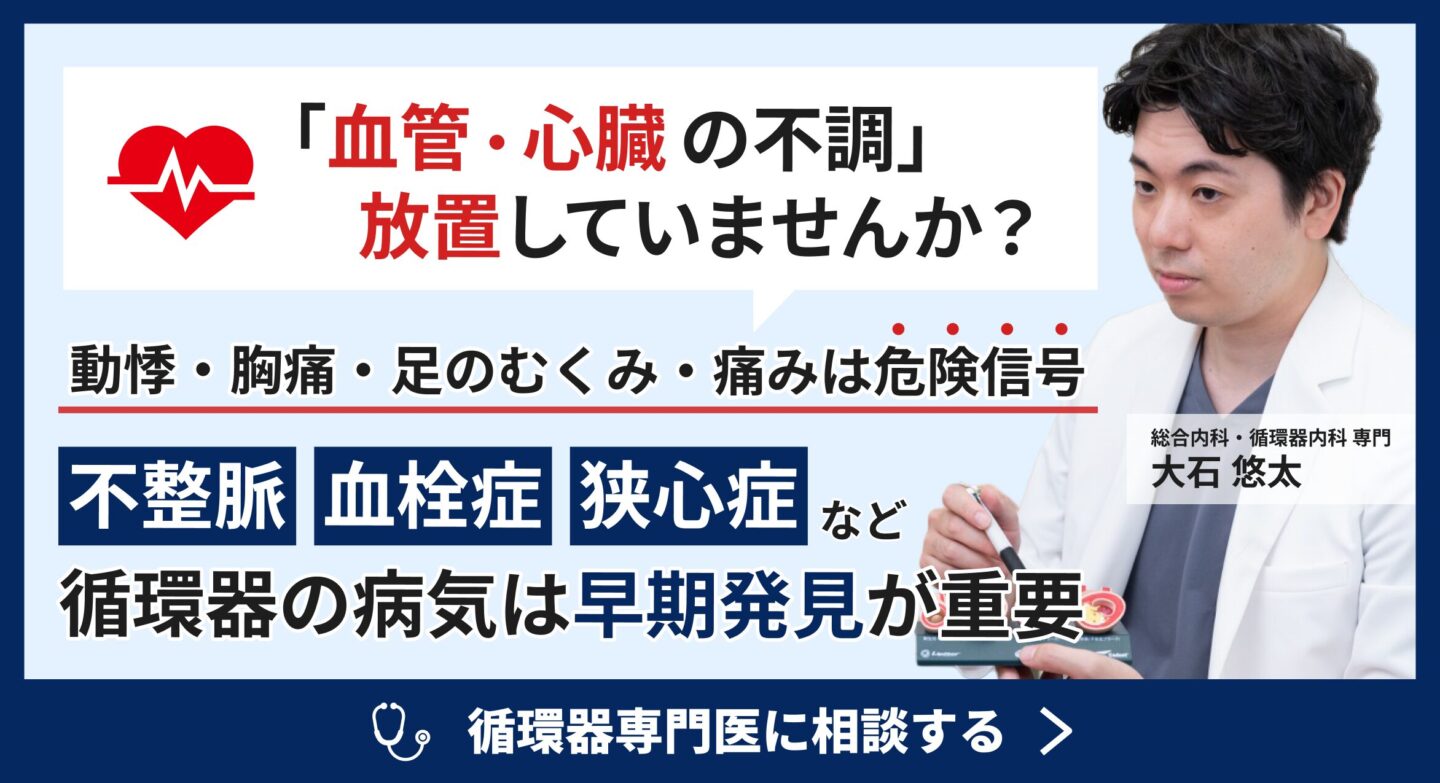
動脈硬化とは血液が流れにくくなる状態
動脈硬化とは、心臓から全身へ血液を送る動脈が硬くなり、血液が流れにくくなる状態を指します。血管の内側にコレステロールや脂肪がたまり、しだいに壁が厚くなることで血管が狭くなっていくのです。
進行すると血流が滞り、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こす危険性があります。ところが、初期には自覚症状がほとんどなく、健康診断などで偶然見つかるケースも少なくありません。
動脈硬化のメカニズム
動脈硬化のメカニズムは、血管の内側で起こる慢性的な炎症と脂質の蓄積によって、血流の通り道が狭くなることです。血管の壁は本来しなやかに血液を流す役割を担っていますが、生活習慣や加齢などの影響で少しずつ傷つきます。
その傷にコレステロールや中性脂肪が入り込み、プラーク(かたまり)を形成すると、血管はさらに厚く硬くなってしまいます。このプラークが大きくなると血流を妨げるだけでなく、破れて血栓(血のかたまり)をつくり、突然血管を詰まらせることもあります。結果として狭心症や脳梗塞といった重大な病気を引き起こすのです。
動脈硬化につながる要因
動脈硬化は血管の「老化現象」とも言えますが、いくつかの要因が重なることでその発症リスクがさらに高まります。ご自身の生活習慣を振り返りながら、予防意識を高めていきましょう。
高血圧や脂質異常(高コレステロール・中性脂肪)
高血圧と脂質異常は、動脈硬化を進める代表的な要因です。血圧が高い状態が続くと、血管の壁に強い圧力がかかり、傷つきやすくなります。その傷に悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が入り込み、血管の内側にこびりついてプラーク(かたまり)をつくります。
プラークが大きくなると血管はさらに狭くなり、血流が悪化してしまいます。結果として、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる重大な病気のリスクが高まります。高血圧や脂質異常を放置しないことが、動脈硬化予防の第一歩です。
糖尿病
血糖値のコントロール不良は、血管を老化させる最大の要因の一つです。高血糖が続くと血管の内側が傷つき、そこに脂質がたまりやすくなります。その結果、動脈硬化が進みやすくなり、血管が詰まったり破れたりするリスクが高まります。糖尿病を放置すると、心筋梗塞や脳梗塞などの合併症を招きやすくなります。
喫煙
喫煙は、動脈硬化を進める最も大きな生活習慣の要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させて血流を悪化させるだけでなく、煙の中の有害物質が血管の内側を傷つけます。その結果、血管がもろくなり、動脈硬化が急速に進みやすくなります。
喫煙を続けると、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクが高まります。「禁煙を始めたい」と思ったら、大石内科循環器科医院の禁煙外来をご活用ください。専門的なサポートで安心して禁煙に取り組めます。
肥満や運動不足
肥満や運動不足も、動脈硬化を進める要因です。特に内臓脂肪が多いと、血圧や血糖、脂質のバランスが崩れやすくなり、血管に炎症を引き起こす物質が分泌されて動脈硬化を加速させます。肥満や運動不足が招くリスクには、次のようなものがあります。
- 高血圧や脂質異常、糖尿病を引き起こしやすくなる
- 血管の炎症が進み、動脈硬化が加速する
- 心筋梗塞や脳梗塞など重大な病気のリスクが高まる
一方で、適度な運動と体重管理は、動脈硬化の予防に直結する改善策です。「健康的に減量したい」「一人では難しい」と感じる方は、大石内科循環器科医院の肥満(ダイエット)外来をご利用ください。
加齢や遺伝の影響
加齢や遺伝も、動脈硬化に大きく影響します。避けられない部分ですが、理解しておくことで予防や早期発見につなげることができます。以下のような影響があることを把握しておきましょう。
- 年齢を重ねると血管が硬くてもろくなる
- 家族に心臓病や脳卒中の方がいるとリスクが高い
- コレステロールが上がりやすい体質を受け継ぐ場合がある
このような背景を持つ方は、生活習慣により一層気を配り、定期的な健診や検査で早めにリスクを把握することが重要です。
加齢や遺伝による影響は自覚しにくいため、血管の状態を客観的に確認することが大切です。血管の硬さや動脈硬化の進行度を調べることで、将来の心血管リスクを把握できます。
以下のページでは、その評価に役立つ検査について解説しています。
動脈硬化の症状
動脈硬化は、起こる場所によって症状が大きく異なります。以下の代表的な症状をわかりやすく説明します。
- 心臓の症状
- 脳の症状
- 首や足の血管の症状
- その他の臓器への影響
心臓の症状
心臓の血管(冠動脈)の動脈硬化は、狭心症や心筋梗塞といった重大な病気を引き起こします。それぞれの症状は以下のとおりです。
- 狭心症:運動時や食後に胸の痛みや圧迫感がある
- 心筋梗塞:突然強い胸の痛みが長時間続き、冷や汗や吐き気を伴うこともある
狭心症は、冠動脈が狭くなり心臓の筋肉に酸素が届きにくくなることで起こります。症状は数分〜十数分で治まるのが一般的です。心筋梗塞は冠動脈が完全に詰まり、心臓に血液が届かなくなる病気です。症状は長く続くのが特徴で、冷や汗や呼吸困難を伴うこともあります。命に直結するため、一刻も早い治療が必要です。
以下の記事では、狭心症の症状や診断・治療法についてさらに詳しく解説しています。胸の痛みが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
>>狭心症の詳細はこちら
脳の症状
脳の血管に動脈硬化が進むと、突然の体の異変として症状が現れます。代表的なものは以下の2つです。
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
一過性脳虚血発作(TIA)は、脳の血流が一時的に滞ることで起こります。片側の手足がしびれる、言葉が出にくいといった症状が出ますが、数分〜数十分で自然に回復するのが特徴です。ただし、脳梗塞の前触れとなる重要なサインであり、軽視はできません。
脳梗塞は脳の血管が完全に詰まる病気で、半身まひや言語障害、強いめまいなどが長く続きます。後遺症が残ることも多く、命に直結する緊急事態です。
首の血管の症状
首を通る頸動脈は、脳に血液を送る大動脈の分岐点です。ここに動脈硬化が起こると血流が不足し、脳梗塞のリスクが特に高まります。代表的なサインは以下のとおりです。
- 一時的な手足のしびれや力が入らない
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
- 視界が二重に見える、視野が狭くなる
- めまいやふらつき
これらは頸動脈の狭窄によって脳への血流が一時的に滞ったサインで、TIAとして現れることもあります。症状が回復しても油断は禁物で、脳梗塞につながる前に早期の対応が必要です。
このような症状がみられる場合、首の血管がどの程度狭くなっているか、血流に異常がないかを確認することが重要です。頸動脈の状態を調べることで、脳梗塞のリスク評価や早期対応につながります。以下のページでは、首の血管を詳しく調べる検査について解説しています。
その他の臓器への影響
動脈硬化は心臓や脳にとどまらず、全身の血管で起こる可能性があります。足の血管で進行すると「閉塞性動脈硬化症」を発症します。歩行や階段の上り下りでふくらはぎや太ももに痛みやしびれが出て、休むと治まるのが初期の特徴です。悪化すると安静時にも痛みが続き、皮膚の色の変化や潰瘍、壊死に至ることもあります。
腎臓の血管が動脈硬化を起こすと腎臓への血流が不足し、老廃物を濾過する機能が低下します。進行すれば腎不全に至り、透析が必要になることもあります。
このように動脈硬化は自覚症状が出にくい一方で、放置すると命に関わる病気を引き起こすため、日頃から生活習慣を見直すことが大切です。
動脈硬化の検査方法・診断方法
動脈硬化は自覚症状が出にくいため、検査によって早期発見することが大切です。症状やリスクに応じて検査内容は変わりますが、動脈硬化を早めに見つけ、合併症を防ぐために欠かせません。
動脈硬化の検査方法と診断方法について、以下の4つを解説します。
- 血液検査でわかること
- 心電図やエコー検査
- CTやMRIによる画像検査
- 冠動脈造影検査
血液検査でわかること
血液検査は、動脈硬化のリスクを把握する基本的な方法です。特に注目されるのがコレステロールの値です。コレステロールは体に必要な成分ですが、血液中に多すぎると血管の内側に溜まり、動脈硬化を進めてしまいます。コレステロールには大きく2種類あります。
- 善玉コレステロール(HDL):血管に溜まった余分なコレステロールを回収する役割
- 悪玉コレステロール(LDL):血管の壁に付着して動脈硬化を進める原因となる
血液検査では、このバランスを調べることで動脈硬化の危険度を評価できます。血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)も重要です。糖尿病は血管を傷つけやすく、動脈硬化を加速させる要因のひとつです。血液検査は、自覚症状のない段階でリスクを早めに知るために欠かせません。
心電図やエコー検査
心電図やエコー検査は、体への負担が少なく心臓や血管の状態を調べられる基本的な検査です。心電図検査では、胸などに電極をつけて心臓の電気的な活動を記録します。狭心症のように冠動脈が狭くなり心臓に血液が十分届かない場合、心臓の動きに異常が表れ、それを心電図で早期に捉えることができます。
エコー検査(超音波検査)は、心臓や血管を画像として確認できる方法です。心臓エコーでは、心臓の動きや弁の状態、筋肉の厚さなどを確認し、動脈硬化による負担を把握できます。さらに頸動脈エコーでは、血管の壁の厚みやプラーク(血管内にたまった脂質のかたまり)の有無を評価します。
プラークが大きくなると血流が悪くなり、脳梗塞のリスクを高めるため、早めのチェックが重要です。
以下の記事では心電図検査について、わかることや異常の種類、原因などを解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
>>心電図検査で異常はわかる?引っかかる原因や種類、対処法を解説
CTやMRIによる画像検査
CTやMRIによる画像検査は、血管の狭さや詰まりを詳しく調べられる検査です。CT(コンピュータ断層撮影)では、造影剤を使って血管を立体的に映し出し、動脈硬化による狭窄やプラークの有無を評価します。特に心臓の冠動脈CTは、心筋梗塞のリスクを詳しく調べるのに役立ちます。
MRI(磁気共鳴画像)では、放射線を使わずに血管や臓器の状態を画像化できます。脳の血管に動脈硬化がある場合、脳梗塞の原因や血流の異常を確認するのに有効です。
これらの画像検査は、血液検査や心電図ではわからない詳細な情報を得られるのが大きな特徴です。症状やリスクに応じて実施され、治療方針を決める重要な手がかりとなります。
冠動脈造影検査
冠動脈造影検査は、心臓の血管(冠動脈)がどの程度狭くなっているかを正確に調べるための検査です。腕や足の血管から「カテーテル」と呼ばれる細い管を通し、冠動脈まで進めて造影剤を流し込みます。その様子をX線で撮影することで、血管の狭窄や閉塞の有無を詳しく確認できます。
この検査は侵襲的ではありますが、心筋梗塞や狭心症の原因を直接明らかにできる最も精度の高い方法です。必要に応じて検査と同時に治療(ステントによる血管の拡張など)を行える場合もあります。
動脈硬化の治療法
動脈硬化の治療は、生活習慣の見直しから始まり、必要に応じて薬や手術へと段階的に進みます。治療の方法は一人ひとりの状態で異なりますが、いずれも目的は血管の健康を守り、心筋梗塞や脳梗塞を防ぐことです。動脈硬化の治療法として、以下の5つを解説します。
食事療法
食事は血管の健康を左右する大切な要素です。動脈硬化を防ぐためには、余分な脂肪や塩分を控え、野菜や魚などをバランス良く取り入れることが重要です。食事のポイントは以下のとおりです。
- 主食・主菜・副菜をそろえてバランス良く
- 揚げ物や脂身の多い肉を控え、魚や大豆製品を活用する
- 塩分を減らし、調味料の使いすぎに注意する
- 野菜は1日350g以上を目標に、色とりどりのものを摂る
- 海藻やきのこ、玄米などで食物繊維をしっかり摂る
- オリーブオイルや青魚に含まれる良質な油を取り入れる
一方で、油っこい食事や塩分の多い食品、甘いものの過剰摂取は血管に負担をかけます。「何を足して、何を減らすか」を意識することが血管を守る第一歩です。
運動療法
運動は血流を良くし、血管の柔軟性を保つ効果があります。無理なく続けられる軽い運動を日常に取り入れることが大切です。おすすめの運動例は以下のとおりです。
- ウォーキング:30分程度を週3回以上
- ジョギング:20分程度を週数回
- 水泳:1回30分程度を目安
- 筋トレ:スクワットや腕立て伏せなど10分程度
日常生活の中でも「エレベーターではなく階段を使う」「一駅分歩く」などの小さな工夫で運動不足を解消できます。ストレッチやヨガも血流改善に役立ち、継続しやすい方法です。
薬物療法
生活習慣の改善だけでは不十分な場合や、動脈硬化が進んでいる場合には薬による治療が行われます。薬の目的は、血管の負担を減らして動脈硬化の進行を抑え、心筋梗塞や脳梗塞といった合併症を防ぐことです。代表的な薬は次のとおりです。
- スタチン系薬:肝臓でのコレステロール合成を抑え、悪玉コレステロール(LDL)を減らす
- RAS阻害薬(ACE阻害薬・ARB):血管の収縮を抑えて血圧を下げ、血管をしなやかに保つ
- カルシウム拮抗薬:血管を広げ、血圧を下げる
- その他:糖尿病や脂質異常症など、動脈硬化のリスク因子に応じた薬
薬はあくまで「補助」ではなく、動脈硬化の進行を抑えるための大切な手段です。医師の指示に従って継続することが、血管を守る近道です。
手術療法
動脈硬化が進み、血管が大きく狭くなったり詰まったりした場合には、カテーテル治療や外科手術が行われます。いずれも血流を改善するために血管を直接治療する方法です。代表的な治療には「冠動脈バイパス手術」と「経皮的冠動脈インターベンション(PCI)」があります。
冠動脈バイパス手術は、体の別の血管を利用して新しい血液の通り道を作り、心臓の筋肉に十分な血流を確保する手術です。PCIはカテーテルを冠動脈まで進め、先端の風船で血管を広げたり、ステントを入れて血流を保つ方法です。
どちらの治療を選ぶかは、血管の状態や全身の健康状態によって異なります。大切なのは、動脈硬化を放置せず、必要に応じて適切な治療を受けることです。
その他の生活習慣改善
動脈硬化を防ぐには、食事や運動に加えて日常の習慣を見直すことも大切です。なかでも次の3つは血管の健康に大きく関わります。
- 禁煙:血管の収縮や内皮細胞の損傷を防ぐ
- ストレス対策:血圧の上昇や生活習慣の乱れを防ぐ
- 良質な睡眠:自律神経を整え、血管の緊張を和らげる
喫煙は特にリスクが高く、タバコに含まれるニコチンは血圧を上げ、一酸化炭素は血液中の酸素運搬を妨げます。禁煙することで動脈硬化だけでなく、がんや呼吸器疾患の予防にもつながります。当院では禁煙外来を設けておりますので、お気軽にご相談ください。
定期的な健康チェックの必要性
動脈硬化は初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行するのが特徴です。そのため、定期的な健康チェックで早期にリスクを見つけることが大切です。健康診断では血圧・血糖値・コレステロール値などを測定し、動脈硬化の危険度を評価します。
結果は自分の体の状態を知るための大切な指標となり、生活習慣の改善や治療の必要性を判断するきっかけになります。健康診断で異常が見つかった場合は、放置せずに医師に相談することが重要です。動脈硬化は、自覚症状のない段階から対策を始めることで重大な病気を防げるため、早期対応が欠かせません。
まとめ
動脈硬化は血管が硬くなり、心筋梗塞や脳梗塞など重大な病気を引き起こす可能性がある病気です。高血圧・高コレステロール・喫煙・肥満・遺伝などが原因となり、初期には自覚症状がほとんどありません。予防には食事・運動・禁煙・ストレス管理が大切で、早期発見と早期治療が何より重要です。
当院では検査から治療まで一人ひとりに合わせて対応いたします。健康診断で異常を指摘された方や症状が気になる方は、お気軽にご相談ください。
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







