disease
病気から探す
- 「最近、ちょっと動いただけで息切れする」
- 「胸の痛みや動悸が気になる」
- 「むくみが続いている」
そんなサインを見過ごしていませんか。もしかすると、それは心臓の筋肉が弱ってしまう「心筋症」の始まりかもしれません。心筋症は放置すると生活の質を大きく下げ、命に関わるリスクを伴うこともあります。しかし、早期に気づき、正しく対処することで進行を抑え、安心して暮らすことは可能です。
心筋症は心臓の筋肉に異常が生じる病気で、進行すると心不全や重い不整脈を引き起こすことがあります。 当院では循環器専門医が丁寧に症状を伺い、心エコーや心電図などの検査で正確に診断し、早期発見と適切な治療につなげます。不安な症状を放置せず、安心できる体制のもとでご相談ください。
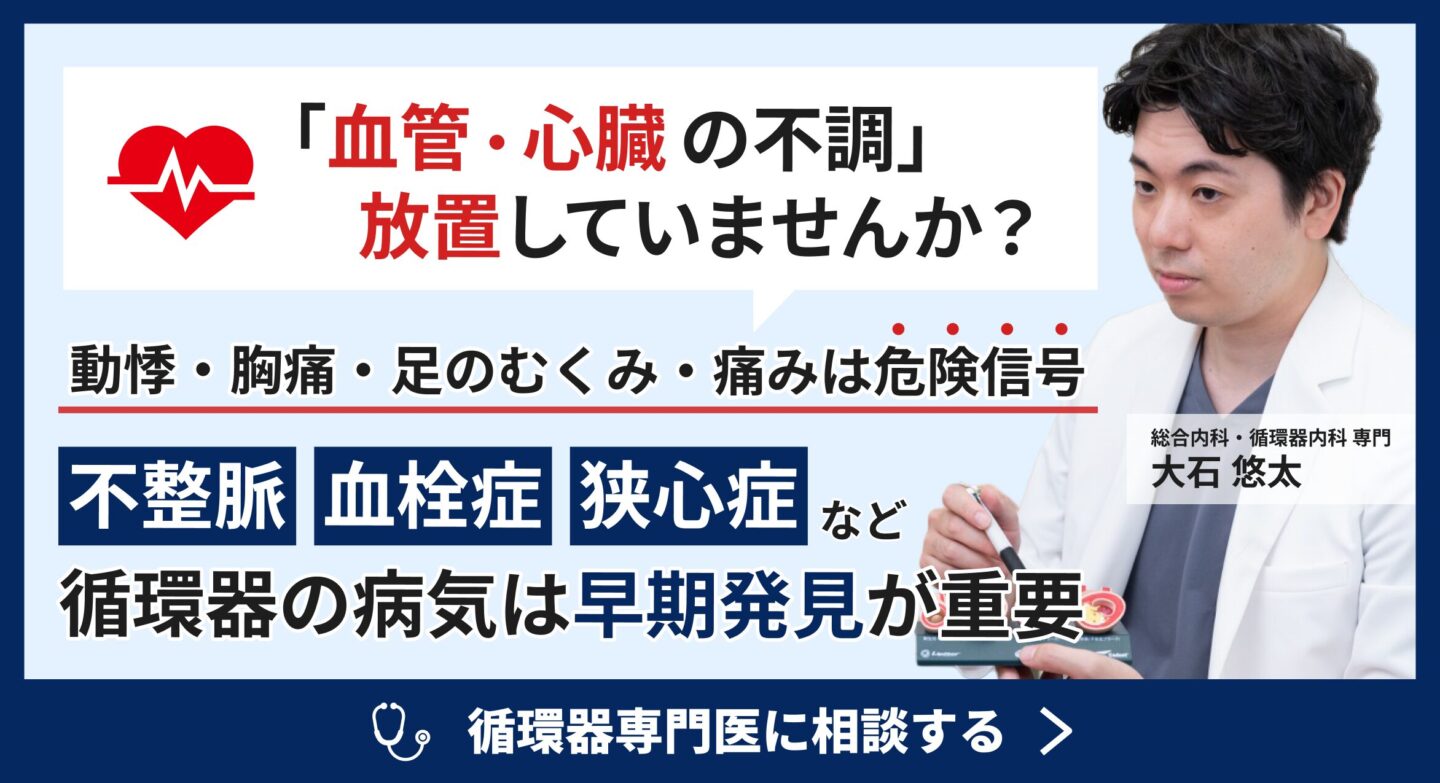
心筋症とは心臓のポンプ機能が低下する病気
心筋症とは、心臓の筋肉そのものに異常が起こり、血液を全身へ送り出す力が弱まってしまう病気です。心臓は休むことなく働き続ける臓器ですが、そのポンプ機能が低下すると、息切れやむくみ、動悸などの症状が現れ、日常生活にも大きな影響を及ぼします。心筋症の特徴を解説します。
心筋症の特徴
心筋症の症状は初期には気づきにくく、進行するにつれて生活に大きな影響を及ぼします。代表的な特徴は以下のとおりです。
- 息切れや動悸が起こりやすい
- むくみや倦怠感が続く
- 胸の痛みや不整脈を伴うことがある
こうした症状は一見「疲れや加齢のせい」と見過ごされやすいですが、放置すれば心不全や突然死のリスクにもつながります。早期発見・早期治療が重要です。
以下の記事では、こうした不整脈の種類ごとの症状や治療の違いについて、より詳しく解説しています。気になる方は参考にしてみてください。
>>不整脈の詳細を見る
心筋症の症状
心筋症は大きく3つのタイプに分類されます。
- 拡張型心筋症:心臓が拡張して収縮力が低下する
- 肥大型心筋症:心筋が分厚くなり血液を送り出しにくくなる
- 拘束型心筋症:心筋が硬くなり心臓の拡張が制限される
それぞれ症状や治療法が異なるため、自分がどのタイプかを正しく理解することが適切な治療の第一歩となります。
拡張型心筋症
拡張型心筋症は、心臓の筋肉が薄く伸びて広がり、収縮力が低下することで血液を全身に十分送り出せなくなる病気です。進行すると心不全に至る可能性が高く、早期発見が非常に重要です。主な症状は次のとおりです。
- 少しの運動でも息切れしやすい
- 疲れやすく全身に倦怠感がある
- 足や手にむくみが出る
- 動悸や不整脈を感じる
これらの症状は「体力の低下」と誤解されやすく、気づかないまま悪化するケースも少なくありません。症状が長引く場合は医師の診察を受けることが、重症化を防ぐ第一歩となります。
不整脈のサインとしてよく現れる「動悸」については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
>>動悸の詳細はこちら
肥大型心筋症
肥大型心筋症は、心臓の筋肉が異常に分厚くなり、心臓内部の血流が妨げられることでポンプ機能に負担がかかる病気です。心臓が厚くなるほど血液を十分に送り出せなくなり、症状が進むと日常生活にも影響が出てきます。主な症状は以下の通りです。
- 運動時の強い息切れや胸の圧迫感
- 不整脈や動悸を感じやすい
- 立ちくらみや失神発作が起こることがある
- 突然死のリスクを伴う場合がある
症状の出方には個人差が大きく、軽度で無症状の人もいれば、若くても重症化するケースもあります。特に失神や強い胸の痛みを感じた場合は、早急な医療機関での検査が必要です。
肥大型心筋症が疑われる場合、心臓の筋肉の厚さや動き、血液の流れを直接確認することが重要です。心臓の構造的な変化を評価することで、症状の原因や重症度を正確に把握できます。以下のページでは、その評価に用いられる検査について解説しています。
拘束型心筋症
拘束型心筋症は、心臓の筋肉が硬くなり心臓が十分に広がらなくなることで血液を取り込む力が低下する病気です。心臓の収縮力は保たれていても、拡張が制限されるため、血液の流れが滞りやすくなります。主な症状は以下の通りです。
- 息切れや呼吸のしづらさが続く
- 全身のむくみや腹部の張り感がある
- 倦怠感が強く体力が落ちやすい
- 不整脈や胸の不快感を伴うことがある
このタイプは他の心筋症に比べて発症頻度は少ないものの、症状が進行すると重度の心不全につながる可能性が高いのが特徴です。早期の段階で正しく診断し、適切な治療を受けることが生活の質を守るために欠かせません。
心筋症の診断基準
心筋症は、問診・身体診察・画像検査を組み合わせて総合的に診断される病気です。まずは自覚症状や生活習慣、家族歴を詳しく確認し、診察では心音や呼吸音、むくみの有無などを調べます。そのうえで心臓の状態を詳しく知るために、次のような検査が行われます。
- 血液検査:心臓の機能や炎症の有無を調べる
- 心電図検査:不整脈や心筋の異常を確認する
- 心臓超音波検査:心筋の厚さや動き、弁の状態を評価する
- 心臓MRI検査:心臓の構造や機能を詳細に画像化する
これらの検査を通じて、心筋症の有無やタイプを診断します。診断のポイントは、心臓の大きさや形の異常、ポンプ機能の低下、他の病気を除外できるかどうかです。特に拡張型心筋症では左心室の拡大が特徴であり、心臓超音波検査が重要な判断材料となります。
以下の記事では心電図検査について、わかることや異常の種類、原因などを解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
>>心電図検査で異常はわかる?引っかかる原因や種類、対処法を解説
心筋症の兆候を見極める3つのサイン
心筋症は、進行するまで自覚症状が乏しいことも多く、「疲れや年齢のせい」と思って見過ごされがちです。しかし、体の小さな変化に早めに気づくことができれば、重症化を防ぎ適切な治療につなげることができます。日常生活の中で気をつけたい、以下の3つのサインを解説します。
- 体力の低下や運動時の息切れ
- 胸の痛みや不規則な心拍
- むくみや倦怠感の増加
体力の低下や運動時の息切れ
運動時の息切れや体力の低下は、心臓のポンプ機能が弱っているサインです。階段を上るだけで息苦しさを覚えたり、以前は平気だった運動が続けられなくなったりすることはありませんか。
心筋症によって全身に十分な血液や酸素が行き渡らなくなると、息切れや動悸が起こりやすくなります。日常生活でも、階段の上り下りや軽い運動、荷物を持つといった動作で息切れや動悸を感じやすくなります。
これらの変化を「年齢のせい」と思い込んで放置すると、症状が進行してしまう危険があります。息切れの頻度が増えていると感じたら、早めに医師へ相談することが大切です。
胸の痛みや不規則な心拍
胸の痛みや心拍の乱れは、心筋症による心臓の異常を知らせる重要なサインです。心臓は本来、規則正しくリズムを刻みながら血液を全身に送り出しています。しかし心筋症で心筋にダメージが加わると、このリズムが乱れ、胸の圧迫感や動悸、不整脈が現れることがあります。症状として注意すべきは、次のような感覚です。
- 胸の締め付け感や圧迫感が続く
- チクチクとした胸の痛みを感じる
- ドキドキと脈打つ感覚や動悸が強まる
- 脈が飛ぶ、脈が速くなるなどリズムが不規則になる
これらの症状は、心臓が正常に働けていないSOSサインです。疲れやストレスのせいと考えて放置すると、重度の不整脈や心不全につながる恐れがあります。異変を感じたら早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けることが大切です。
むくみや倦怠感の増加
結論から言うと、足のむくみや慢性的な疲労感は心筋症による血液循環の低下が原因となるサインです。心臓のポンプ機能が弱まると血液の流れが滞り、体内に水分が溜まりやすくなります。特に心臓から遠い足はむくみやすく、夕方になると症状が強く出ることがあります。全身への酸素や栄養が不足することで、疲れやすさやだるさも感じやすくなります。
これらの症状が続く場合、単なる疲労や加齢ではなく心臓のSOSである可能性があります。放置せずに医療機関を受診し、早めに原因を確認することが安心につながります。
こちらのブログ記事も参考にご覧ください。
>>足のむくみは何科を受診すべき?症状別に病院の選び方を解説!
心筋症の治療法
心筋症の治療は、病気そのものを完全に治すのではなく、症状の進行を抑え、心臓への負担を軽減し、生活の質を保つことを目的としています。治療法として、以下の内容を解説します。
- 薬物療法
- 心臓リハビリテーション
薬物療法
心筋症の治療では、心臓の負担を減らし症状を和らげるために複数の薬を組み合わせて使うのが基本です。薬の種類や量は一人ひとりの症状や進行度に応じて調整され、オーダーメイドの治療が行われます。よく用いられる薬には次のようなものがあります。
- 利尿薬:余分な水分を排出し、むくみを改善して心臓への負担を軽減する(例:ラシックス、アルダクトンA)
- 強心薬:心筋の収縮力を高め、全身への血液循環を助ける(例:ジゴキシン、ドブタミン)
- β遮断薬:心拍数を抑えて心臓を休ませ、負担を減らす(例:カルベジロール、ビソプロロール)
これらの薬は単独で使われることもあれば、組み合わせて処方されることもあります。副作用のリスクもあるため、必ず医師の指示に従い、自己判断で中断や調整をしないことが大切です。
心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションとは、心臓病患者が安全に運動能力を回復し、生活の質を高めるために行う医療プログラムです。心筋症と診断された方にとっては、症状の改善だけでなく再発予防や体力の維持にも効果が期待でき、安心して日常生活を送るための治療の一環と言えます。
その内容は大きく、以下の3つの柱から成り立っています。
- 運動療法:専門スタッフが個々の体力や症状に合わせたプログラムを作成し、ウォーキングや自転車運動、水中運動などを安全に実施
- 食事療法:管理栄養士による栄養指導を受け、減塩を中心とした心臓にやさしい食生活を習得
- 生活習慣の改善:禁煙指導や服薬管理、ストレス対策を行い、再発防止につなげる
これらを組み合わせることで、体力を無理なく回復させながら心臓への負担を軽減し、再び前向きに生活できる状態を目指すことができます。
当院では運動プログラムも実施しています。下記のページで詳細を確認できますので、ぜひご一読ください。
>>大石内科循環器科医院内科の心臓運動プログラム
日常生活で注意すべきこと
心筋症と診断された後も、多くの方が普段通りの生活を送っています。大切なのは、心臓に余計な負担をかけずに、自分らしく安心して過ごすことです。そのためには規則正しい生活習慣を心がけ、医師と連携を取りながら病気と上手に付き合っていく必要があります。日常生活では、以下の点に注意しましょう。
- 定期的な通院と服薬:自己判断で中断せず、医師の指示を守る
- バランスの良い食事:塩分を控え、インスタントや加工食品を避ける
- 適度な運動:ウォーキングなど無理のない範囲で継続する
- 十分な睡眠と休息:疲労や睡眠不足を避ける
- ストレス管理:趣味やリラックス法で心身を整える
- アルコールとタバコを控える:心臓への悪影響を防ぐ
こうした習慣を積み重ねることで、心臓への負担を和らげながら、より安心して充実した日常生活を送ることが可能になります。
まとめ
心筋症は、心臓の筋肉に異常が起こりポンプ機能が低下する病気で、拡張型・肥大型・拘束型の3種類に分けられます。拡張型では心臓が大きく膨らみ疲れやすさや息切れが出やすく、肥大型では心筋が厚くなり胸の痛みや動悸、失神が生じることがあります。
拘束型は心筋が硬くなり、むくみや倦怠感が目立つのが特徴です。こうした初期症状を早く見極めることが重症化を防ぐ第一歩となります。治療には、利尿薬や強心薬、β遮断薬などの薬物療法のほか、心臓リハビリテーションや食事・生活習慣の改善などがあります。診断を受けた場合は、医師の指示を守りながら、定期的な通院と服薬を続けることが大切です。
正しい知識と治療、生活の工夫によって、心筋症と向き合いながらも自分らしい毎日を送ることは可能です。心筋症に限らず動悸や息切れ、胸の痛みなど気になる症状がある方は、循環器専門医の当院へご相談ください。
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







