blog
ブログ
現代社会において、糖尿病は身近な疾患であり、誰でも発症する可能性があります。研究によると、糖尿病が強く疑われる人は約1,000万人、予備群は約1,000万人、合計約2,000万人と推計されています。国民の5人に1人が糖尿病または糖尿病予備群という状況です。
糖尿病は、自覚症状が少ないまま進行し、失明や人工透析といった深刻な合併症を引き起こすこともある病気です。早期発見・早期治療によって合併症リスクを減らし、健康寿命を延ばすことが期待できます。この記事では、糖尿病の診断基準や検査方法、早期発見のポイントを網羅的に解説します。
見逃しがちな体のサインを見つけることで、早期に治療開始できる可能性があります。糖尿病の知識を身につけて、あなたの健康を守りましょう。
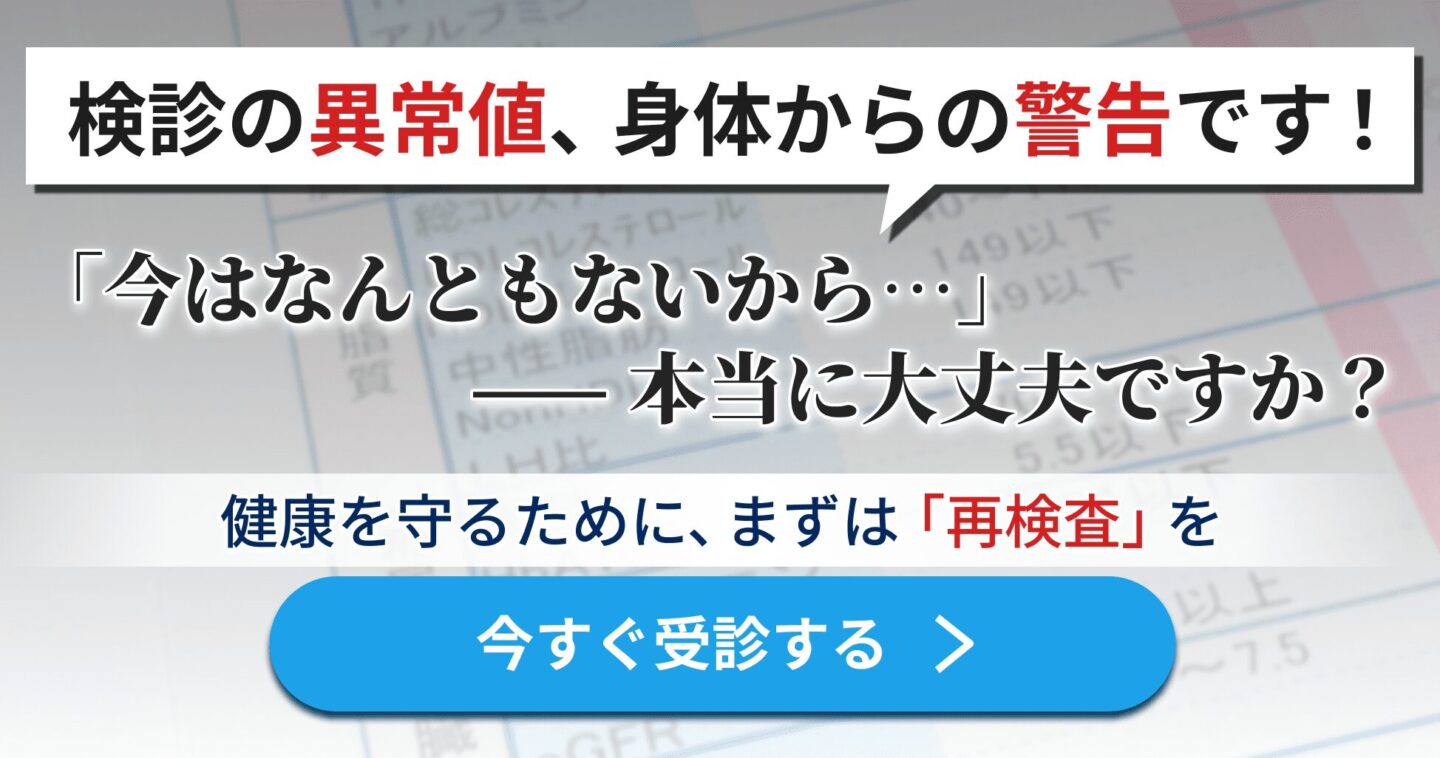
糖尿病とは慢性的に高血糖が続く病気
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が高い状態が続く病気です。血糖値は、食事をすると上昇します。健康な体では、すい臓からインスリンというホルモンが出て、上昇した血糖を細胞の中に取り込み、エネルギーとして利用したり、脂肪やグリコーゲンとして蓄えたりします。
糖尿病では、インスリンの働きが悪くなる、もしくはインスリン自体が十分に作られなくなります。インスリンの働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖が細胞に取り込まれにくくなり、血糖値が高い状態が続きます。高血糖の状態が続くと、血管が傷つき、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。
合併症には、神経障害や網膜症、腎症などがあり、放置すると失明や人工透析が必要になるなど、生活の質を著しく低下させるリスクが高まります。糖尿病は大きく分けて4つのタイプに分類されます。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- その他の特定の機序や疾患によるもの
- 妊娠糖尿病
1型糖尿病は、免疫の異常で自分のすい臓を攻撃してしまい、インスリンがほとんど作られなくなる病気です。2型糖尿病は、遺伝や生活習慣の影響でインスリンの働きが悪くなったり、量が不足したりする病気です。日本人に多いのは、2型糖尿病です。
その他の特定の機序や疾患によるものは、遺伝子の異常や膵臓の病気、特定の薬剤などが原因で発症します。妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて見つかる耐糖能異常(血糖値が正常値よりも高い状態)です。
以下の記事では、糖尿病による心血管系の合併症とその予防策について、より詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
糖尿病の診断基準:種類と具体的な数値
糖尿病の診断基準を、以下の3つの種類について説明します。
- 糖尿病の診断基準値
- 妊娠糖尿病の診断基準値
- 糖尿病予備群の診断基準値
糖尿病の診断基準値
糖尿病は、主に検査値をもとに診断されます。1つの検査項目だけで判断するのではなく、複数の検査結果を組み合わせて総合的に評価することで、より正確な診断が可能です。糖尿病の診断基準値は以下のとおりです。
- 空腹時血糖値:126mg/dL以上
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)2時間値:200mg/dL以上
- 随時血糖値:200mg/dL以上
- HbA1c(NGSP:国際標準化されたHbA1c測定法):6.5%
基準値を超えた場合でも、1回の検査ですぐに糖尿病と診断されるわけではありません。医師は、他の検査結果や症状なども考慮して、総合的に判断します。強い糖尿病の症状(口渇や多飲、多尿、体重減少など)がある場合や、1回の検査で基準値を超えていれば、糖尿病と診断されることがあります。
基準値をわずかに超えた程度であれば、再検査が必要な場合もあります。特に、HbA1c検査だけでなく、他の検査値も含めて総合的に判断する必要があります。
以下の記事では、血糖値の正常値について、年代別の目安や基準をわかりやすく解説し、数値が異常だった場合の対処法や注意点も紹介しています。検査結果を正しく理解したい方におすすめです。
>>血糖値の正常値とは?年代別の基準値と異常時の注意点を解説
妊娠糖尿病の診断基準値
妊娠中は、ホルモンバランスの変化などにより、血糖値が上がりやすくなります。妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて見つかる、あるいは発症した耐糖能異常を指します。妊娠中に高血糖の状態が続くと、お母さんだけでなく赤ちゃんにもさまざまなリスクが生じる可能性があります。巨大児や新生児低血糖、呼吸窮迫症候群などです。
お母さんにとっても、妊娠高血圧症候群や羊水過多症などのリスクが高まる可能性があります。妊娠中は血糖値の管理が特に重要です。最近の研究では、妊娠糖尿病の治療において、個々の妊婦さんの状態に合わせた個別化医療の重要性が指摘されています。
妊娠初期のBMIや血糖値などの臨床データから、薬物療法(スルホニル尿素薬)が必要となるかを早期に予測できる可能性が示唆されています。妊娠糖尿病の診断には、75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)が行われます。空腹時、ブドウ糖摂取1時間後、2時間後の血糖値を測定し、以下の基準値と比較します。
- 空腹時血糖値:92mg/dL以上
- 75gOGTT1時間値:180mg/dL以上
- 75gOGTT2時間値:153mg/dL以上
基準値のいずれか1つでも超えると、妊娠糖尿病と診断される可能性があります。妊娠糖尿病と診断された場合は、食事療法や運動療法を中心とした治療が行われます。場合によっては、インスリン注射などの薬物療法が必要になることもあります。
糖尿病予備群の診断基準値
糖尿病予備群とは、血糖値が正常値よりも高いものの、まだ糖尿病の診断基準には達していない状態のことです。糖尿病予備群の人は、将来的に糖尿病を発症するリスクが高い状態と言えます。糖尿病予備群と診断された場合は、生活習慣の改善に取り組むことが重要です。
糖尿病予備群の診断には、糖尿病と同じ検査値が用いられますが、基準値が異なります。糖尿病予備群の診断基準値は以下のとおりです。
- 空腹時血糖値:100~125mg/dL
- 75gOGTT2時間値:140~199mg/dL
- HbA1c:5.7~6.4%
糖尿病予備群と診断された場合でも、生活習慣を改善することで、糖尿病の発症を予防したり、遅らせたりできます。バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠などを心がけることが重要です。禁煙も効果が期待できます。生活習慣の改善は、医師や栄養士などの専門家の指導のもと行うことが望ましいです。
糖尿病の検査方法
糖尿病の検査方法を以下の5つを解説します。
- 空腹時血糖検査
- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
- HbA1c検査
- 連続血糖測定(CGM)
- 自己血糖測定(SMBG)
空腹時血糖検査
空腹時血糖検査は、朝食前の空腹時に血液中のブドウ糖の量(血糖値)を測定する基本的な検査です。健康診断でも広く実施されています。採血は1回で、費用も比較的安価というメリットがあります。健康な方の空腹時血糖値は、一般的に70~109mg/dLの範囲に収まります。
110mg/dLを超えると、糖尿病予備群の可能性も出てきます。126mg/dL以上になると、糖尿病の可能性が高くなります。検査の具体的な方法ですが、検査前10~14時間程度の絶食が必要です。水は飲んで構いませんが、ジュースやお菓子などは控えます。検査当日は、指定された時間に病院へ行き採血を行います。
結果は通常、当日または後日わかります。もし基準値を超えていれば、再検査や追加の検査が必要になる場合があります。
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)は、ブドウ糖液を飲んで一定時間ごとに血糖値を測定する検査です。空腹時血糖検査だけではわからない、食後の血糖値の上昇具合や血糖を下げる能力を調べることができます。検査時間は2時間ほどで、空腹時血糖検査よりも費用は高くなります。
検査中は安静にしていなければならず、やや負担は大きいですが、より正確に糖尿病かどうかを判断するために重要な検査です。経口ブドウ糖負荷試験は、以下の流れで行われます。
- 前日夜から絶食する(検査前10~14時間は水以外の飲食を控える)
- 空腹時に血糖値を測定する
- 75gのブドウ糖を含んだ検査用飲料を摂取する30分後、1時間後、2時間後の血糖値を測定する
健康な方であれば、ブドウ糖を飲んでも血糖値は一定時間内に正常値に戻ります。しかし、糖尿病の方や予備群の方は、血糖値が下がりにくく高値を維持する傾向があります。
75gOGTTの2時間値が140~199mg/dLの場合は糖尿病予備群、200mg/dL以上であれば糖尿病型と診断されます。空腹時血糖値が92mg/dL以上、1時間値が180mg/dL以上の場合も、妊娠糖尿病の診断基準となります。
HbA1c検査
HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)検査は、過去1~2か月の平均的な血糖値の状態を反映する検査です。赤血球中のヘモグロビンというタンパク質にブドウ糖が結合した割合を測定します。血糖値が高い状態が続いているほど、HbA1cの値も高くなります。
HbA1c検査は、糖尿病の診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。採血は1回で済み、食事の影響を受けないため、いつでも検査可能です。HbA1c値が6.5%以上だと糖尿病型と診断されます。5.7~6.4%の場合は境界型(糖尿病予備群)に該当します。
連続血糖測定(CGM)
連続血糖測定(CGM)は、小さなセンサーを皮膚の下に装着し、皮下組織のブドウ糖値を連続的に測定する検査方法です。血糖値の変化をグラフで確認できるため、食後や夜間などの血糖値の変動を詳細に把握できます。食事や運動が血糖値に与える影響も把握しやすく、よりきめ細やかな血糖コントロールが可能です。
CGMは、糖尿病の診断というよりは、すでに糖尿病と診断されている方の血糖コントロール状態を詳しく把握するために用いられることが多いです。費用は他の検査に比べて高額ですが、より詳細な血糖管理が必要な方に効果が期待できるツールです。
自己血糖測定(SMBG)
自己血糖測定(SMBG)は、自宅で手軽に血糖値を測定できる検査方法です。指先などに針を刺して少量の血液を採取し、専用の機器で血糖値を測定します。血糖値を自分で管理することで、食事や運動療法の効果を日々確認し、生活習慣の改善に役立てられます。医師の指示にもとづき、適切な頻度で測定を行うことが重要です。
それぞれの検査方法にはメリット・デメリットがあり、どの検査を受けるべきかは、症状や病状、検査の目的によって異なります。医師と相談しながら、適切な検査方法を選択することが大切です。
糖尿病を早期発見するポイント
糖尿病を早期発見するポイントは以下のとおりです。
- 喉がよく渇く
- 尿の回数が増える
- 疲れやすくなる
- 急激に体重が減少する
喉がよく渇く
喉の渇きは、糖尿病の代表的な初期症状の一つです。健康な方でも、運動後や暑い日には喉が渇きます。糖尿病の場合は、大量の水分を摂取しても喉の渇きがなかなか治まらないことがあります。高血糖によって体内の水分が尿として過剰に排出されるためです。
糖尿病以外にも、脱水症状や他の病気が原因で喉が渇くことがあります。夏場に水分補給を怠ったり、下痢や嘔吐が続いたりする場合などです。腎臓の病気や特定の薬の副作用でも喉の渇きが現れることがあります。喉の渇きが続くようであれば、一度医療機関を受診し、糖尿病の検査を受けることをおすすめします。
尿の回数が増える
尿の回数が増える、いわゆる頻尿も、糖尿病の初期症状として見られます。高血糖の状態では、腎臓が血液中の過剰な糖分を尿として排出しようと働くため、尿量が増加し、トイレに行く回数も増えます。夜中に何度もトイレに起きる場合(夜間頻尿)は、糖尿病の可能性を疑う必要があります。
頻尿の原因は糖尿病以外にも、以下が影響することがあります。
- 前立腺肥大症や膀胱炎などの泌尿器系の疾患
- 利尿作用のあるカフェイン摂取
- アルコールの過剰摂取
糖尿病が原因の頻尿の場合、血糖コントロールが改善されると症状も軽減します。生活習慣の改善や薬物療法などさまざまな治療法がありますので、医師と相談しながら適切な治療を受けることが大切です。
以下の記事では、尿に泡が立つ原因や、泡立ちが病気のサインである可能性、どのようなときに受診すべきかの目安を詳しく解説しています。日々の排尿に気になる変化がある方は参考にしてください。
>>尿の泡立ちは病気のサイン?原因と受診の目安を解説
疲れやすくなる
疲れやすくなる、倦怠感を頻繁に感じることも、糖尿病の初期症状の一つです。高血糖の状態では、体内のブドウ糖がエネルギー源として効率的に利用されないため、慢性的なエネルギー不足に陥り、疲れやすさやだるさを感じやすくなります。疲れやすいからといって必ずしも糖尿病であるとは限りません。
過労や睡眠不足、精神的なストレス、貧血、甲状腺機能低下症など、さまざまな原因で疲れやすくなることがあります。十分な休息を取っても慢性的な疲労感や倦怠感が続く場合は、一度医療機関を受診し、糖尿病の検査を受けることをおすすめします。
他の初期症状(喉の渇きや頻尿など)も同時に現れている場合は注意が必要です。
急激に体重が減少する
急激な体重減少も、糖尿病の初期症状として現れることがあります。高血糖の状態では、ブドウ糖がエネルギーとして利用されにくいため、体はエネルギーを確保するために脂肪や筋肉を分解し始めます。その結果、意図しない体重減少が起こることがあります。
体重減少の原因は、糖尿病以外にも、甲状腺機能亢進症や悪性腫瘍、うつ病、摂食障害など、多岐にわたります。過度なダイエットや食事制限によっても体重が減少します。思い当たる原因がなく、急激に体重が減った場合は、糖尿病の可能性も考慮し、医療機関を受診することが重要です。
糖尿病の早期発見・早期治療は、合併症の予防や健康寿命の延伸につながります。ご自身の体の変化に気を配り、少しでも気になる症状があれば、医療機関に相談しましょう。
糖尿病の予防方法
糖尿病の予防方法を以下の4つ説明します。
- 食生活を見直す
- 適度に運動する
- 十分な睡眠を確保する
- 定期的に検査を受ける
食生活を見直す
食生活の改善は、糖尿病予防の基盤になります。栄養バランスの良い食事を心がけ、血糖値の急激な上昇を抑えることが重要です。具体的には、以下の7つのポイントに注意しましょう。
- 野菜をたっぷり摂る
- 果物は適量に
- 主食は控えめに
- 良質なタンパク質を摂る
- 脂質の摂りすぎに注意
- 間食は控えめに
- ゆっくりよく噛んで食べる
野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は、糖質の吸収を穏やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑制する働きがあると考えられています。1日の目標摂取量は350g以上です。生の野菜サラダだけでなく、温野菜や煮物、炒め物など、さまざまな調理法で野菜を摂取しましょう。
果物はビタミンやミネラルが豊富ですが、果糖という糖分が含まれています。果糖は、他の糖質に比べて血糖値を上げにくいと言われていますが、摂りすぎると血糖値が上昇する可能性があります。1日に片手の手のひらに乗るくらいの量が目安です。果物ジュースは糖分が濃縮されているため、控えるようにしましょう。
ご飯やパン、麺類などの炭水化物は、体内でブドウ糖に分解され、エネルギー源となります。摂りすぎると血糖値が上昇しやすいため、適切な量を心がけましょう。ご飯であれば茶碗軽く1杯程度を目安にしてください。白米だけでなく、玄米や雑穀米など、食物繊維が豊富なものを選ぶのもおすすめです。
肉や魚、卵、大豆製品などは、体を作るために必要な栄養素です。適度に摂取することで、筋肉量の維持にも役立ちます。植物性タンパク質は大豆製品に多く含まれ、コレステロール値を下げる効果も期待できます。魚に多く含まれるEPAやDHA、オリーブオイルやアマニ油などの植物性の油を選ぶようにしましょう。
適度に運動する
運動不足は、肥満やインスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを高めます。適度な運動は、血糖値を下げ、インスリンの働きを改善する効果があります。2型糖尿病の患者さんにおける脂肪量と筋肉量、特に腕の脂肪量と筋肉量は、心血管疾患と非心血管死亡率に異なる関連があると報告されています。以下におすすめの運動を紹介します。
- ウォーキング
- ジョギング
- 水泳
- 筋力トレーニング
- ストレッチ
気軽に始められる運動として、ウォーキングがおすすめです。毎日30分程度、やや速足で歩くことを習慣づけましょう。強度を高めたい場合は、坂道や階段を歩くのも効果が期待できます。体力に自信のある方は、ジョギングもおすすめです。週に2~3回、30分程度を目安に行いましょう。
水泳は、全身の筋肉を使うため、効率よくカロリーを消費できます。膝や腰への負担が少ないため、高齢の方や関節に痛みのある方にもおすすめです。筋トレは、筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させる効果があります。筋肉はブドウ糖を消費するため、血糖値のコントロールにも役立ちます。週に2~3回程度行いましょう。
柔軟性を高めることで、ケガの予防や血行促進につながります。運動前後のストレッチだけでなく、毎日の習慣として10分程度行うことをおすすめします。
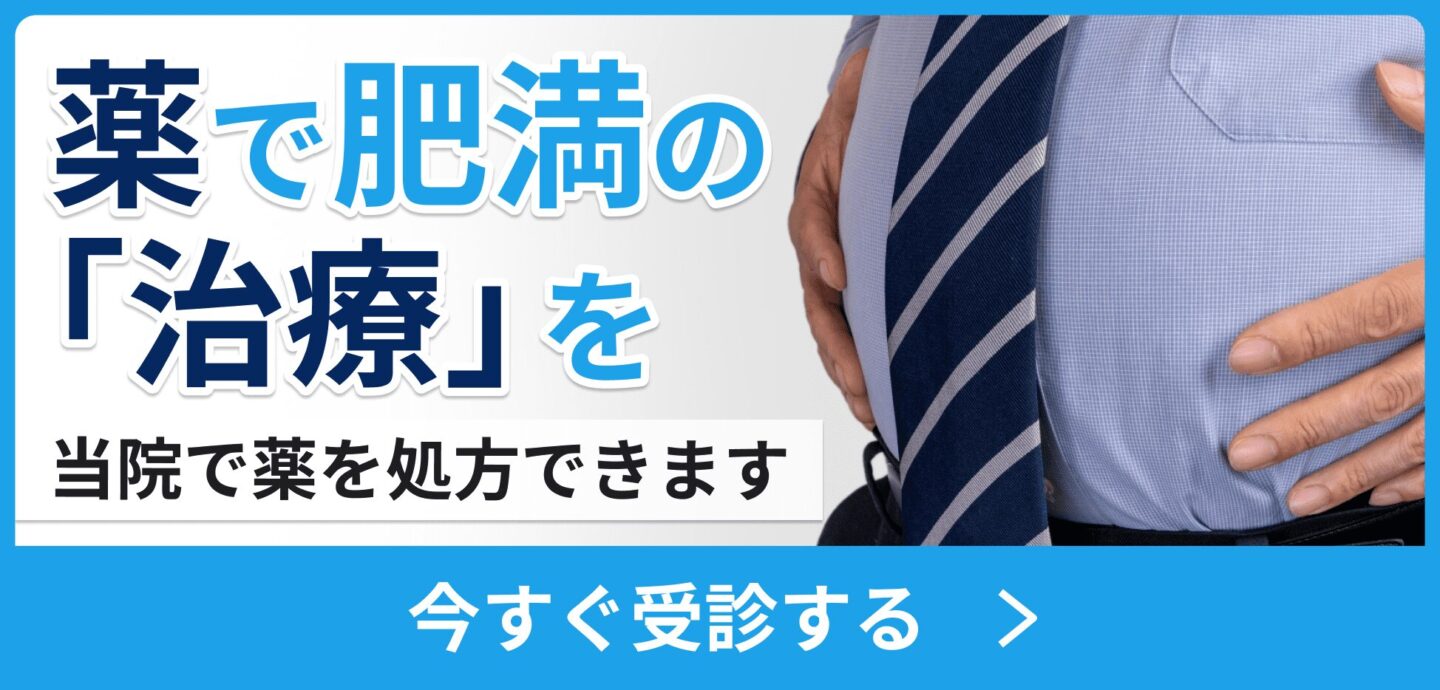
十分な睡眠を確保する
質の高い睡眠を十分にとることは、糖尿病予防につながります。睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、血糖値のコントロールを悪くする可能性があります。以下に十分な睡眠を確保するためのポイントを紹介します。
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 寝る前にカフェインを摂らない
- 寝る前にリラックスする
- 適度な明るさで眠る
- 睡眠時間は7時間程度を目安にする
体内時計を整えるために、毎日同じ時間に寝起きする習慣を身につけましょう。コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、覚醒作用があり、睡眠の質を低下させる可能性があります。寝る前の摂取は避けましょう。ハーブティーやノンカフェインの飲み物を選びましょう。
ぬるめのお湯に浸かったり、好きな音楽を聴いたり、読書をするなど、リラックス時間を作ることで、スムーズに入眠しやすくなります。明るい部屋では、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されます。寝る前は部屋を暗くし、スマホやパソコンの画面の明るさも落とすようにしましょう。
睡眠時間が短すぎても長すぎても、健康に悪影響を与える可能性があります。個人差はありますが、7時間程度の睡眠時間を確保するように心がけましょう。
定期的に検査を受ける
糖尿病は初期段階では自覚症状がない場合が多く、気づかないうちに病気が進行していることもあります。定期的な健康診断で血糖値やHbA1cをチェックすることで、早期発見・早期治療につながります。定期的に検査を受けるためのポイントは以下のとおりです。
- 健康診断を毎年受ける
- 血糖値が気になる場合は医療機関を受診する
- 糖尿病と診断された場合は医師の指示に従って治療を受ける
健康診断では、血糖値やHbA1c、血圧、コレステロール値など、さまざまな項目がチェックされます。健康診断で血糖値が高いと指摘された場合や、喉の渇き、尿の回数が増える、体重減少などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。内科や糖尿病内科の受診をおすすめします。
糖尿病と診断された場合は、医師の指示に従って、食事療法や運動療法、薬物療法などを適切に行うことが大切です。自己判断で治療を中断したり、変更したりすることは危険です。糖尿病は、生活習慣の改善によって予防可能な病気です。紹介したポイントを参考に、日々の生活を見直し、健康的な生活習慣を心がけましょう。
まとめ
糖尿病は初期症状に乏しいため、定期的な検査と日々の生活習慣の見直しが重要です。喉の渇きや頻尿、疲れやすさ、急な体重減少といった症状が現れたら、早めに医療機関を受診しましょう。食生活では、野菜をたっぷり摂り、果物や主食、脂質は控えめに、良質なタンパク質をバランス良く摂取することが大切です。
よく噛んで食べることも重要です。適度な運動は、ウォーキングやジョギング、水泳など、無理なく続けられるものを選びましょう。十分な睡眠、ストレスを溜めない生活も、血糖値のコントロールにつながります。糖尿病は身近な疾患であり、誰でも発症する可能性があります。
本記事を参考に、ご自身の生活習慣を見直し、糖尿病予防に役立てていただければ幸いです。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Benham JL, Gingras V, McLennan NM, Most J, Yamamoto JM, Aiken CE, Ozanne SE, Reynolds RM and ADA/EASD PMDI.Precision gestational diabetes treatment: a systematic review and meta-analyses.Communications medicine,2023,3,1,p.135
- Guo J, Wei Y, Heiland EG and Marseglia A.Differential impacts of fat and muscle mass on cardiovascular and non-cardiovascular mortality in individuals with type 2 diabetes.Journal of cachexia, sarcopenia and muscle,2024,15,5,p.1930-1941
- 厚生労働省:糖尿病診療の現状(令和4年)
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







