blog
ブログ
糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどなく、血液検査で初めて異常に気づく場合が多くあります。厚生労働省によると、糖尿病予備軍を含めると約2,000万人が糖尿病のリスクを抱えていると言われています。自覚症状が出にくいため、血液検査の結果を正しく理解し、適切な対応をすることが大切です。
本記事では、糖尿病の血液検査で調べる項目(HbA1cや血糖値、グリコアルブミン)の見方や治療開始の目安、検査結果からわかることを解説します。検査項目と基準値を参考に、ご自身の健康状態を確認しましょう。
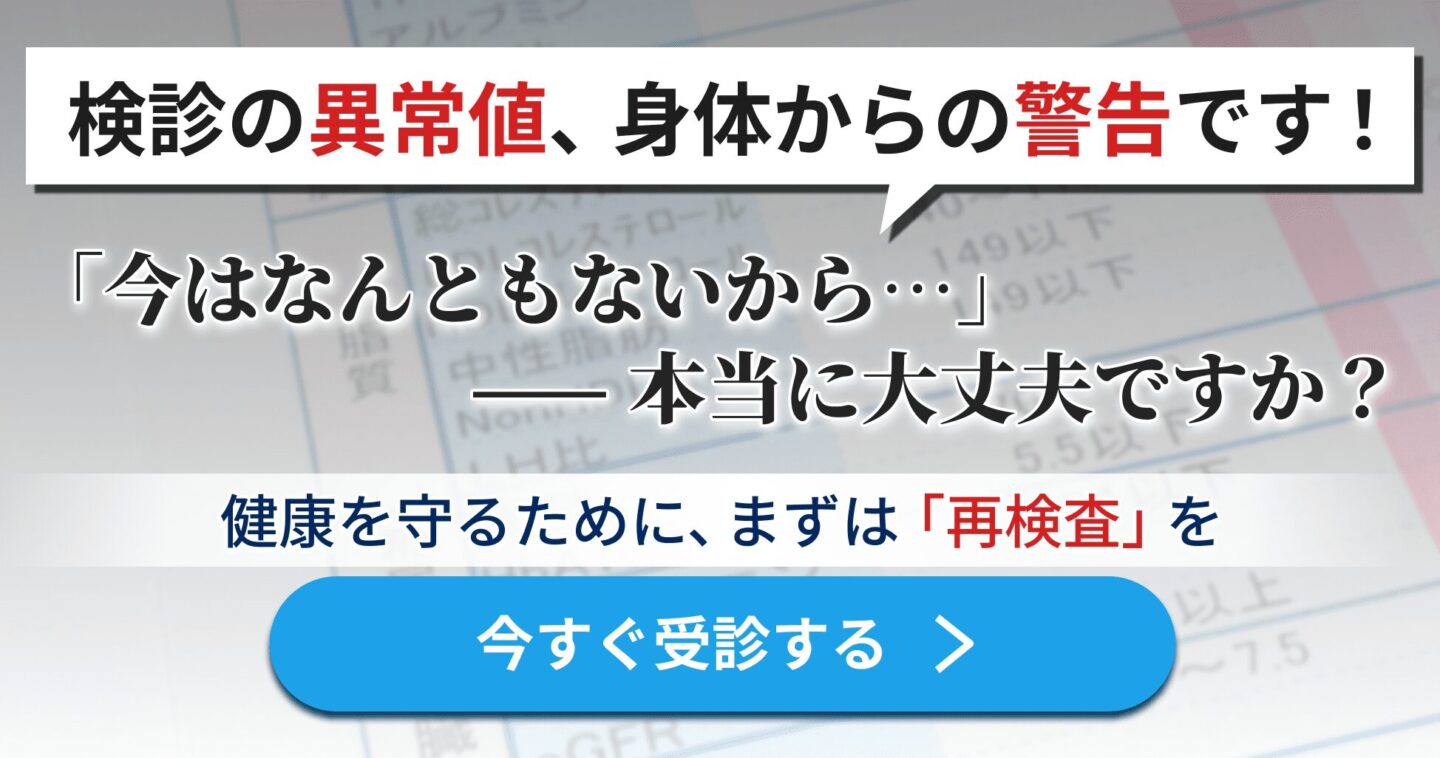
糖尿病の血液検査で調べる項目
糖尿病の血液検査で調べる項目は、以下のとおりです。
- HbA1c
- 血糖値
- グリコアルブミン
HbA1c
HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)は、過去1~2か月間の平均的な血糖値の状態を反映する検査項目です。赤血球の中にあるヘモグロビンに、ブドウ糖が結合した割合を測定します。ヘモグロビンは、約120日の寿命をもち、血液中に存在する間、ブドウ糖と結合や分離を繰り返します。血糖値が高い状態が続くと、HbA1cの値も高くなります。
HbA1cは、食事の影響を受けにくく、糖尿病の診断や治療効果の判定に適した指標です。ただし、貧血などの影響で、HbA1cの値が実際よりも高く出たり、低く出たりする場合があります。赤血球の寿命が変化したり、ヘモグロビンの種類が変わったりすることが原因です。
血糖値
血糖値は、血液中のブドウ糖の濃度を示す検査項目です。血糖値の検査には、空腹時血糖や随時血糖、75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験)などがあります。空腹時血糖は、10時間以上の絶食後の血糖値を測定する検査です。
随時血糖値は、食事のタイミングに関係なく測定する血糖値です。食後など血糖値が高くなりやすいタイミングで測定すると高値が出やすいため、複数回測定します。
75gOGTTは、75gのブドウ糖液を飲んで、血糖値の変化を調べる検査です。ブドウ糖を摂取した後の血糖値がどのように変化するかをみることで、膵臓がインスリンを分泌できているか、体がインスリンを適切に利用できているかを評価できます。
血糖値は、食事や運動、ストレスなどの影響を受けやすいため、1回の検査結果だけで判断せず、複数回の検査結果を総合的に判断します。
以下の記事では、血糖値を下げるために効果が期待できる生活習慣の改善ポイントを7つに分けて詳しく紹介していますので、実践の参考にしてください。
>>血糖値を下げる7つの効果が期待できる方法!生活習慣改善のポイント
グリコアルブミン
グリコアルブミンは、過去2~3週間の平均血糖値を反映する検査項目です。血液中のアルブミンにブドウ糖が結合した割合を測定します。アルブミンの寿命は約20日であるため、HbA1cよりも短い期間の血糖値の状態を把握できます。
HbA1cと同様に、食事の影響を受けにくい点がメリットです。HbA1cでは正確な値が得られない貧血などの場合も、グリコアルブミンは影響を受けにくいという利点があります。
糖尿病の検査結果の見方
糖尿病の検査結果の見方について、以下の2点を解説します。
- 正常値
- 糖尿病の診断基準
正常値
各検査結果の正常値は以下のとおりです。
- HbA1c:4.6~6.2%
- 空腹時血糖:70~99mg/dL
- 随時血糖値:140mg/dL未満
- 75gOGTT2時間値:140mg/dL未満
- グリコアルブミン:11~16%
1つの検査結果が正常値に収まっていない場合でも、すぐに糖尿病と診断されるわけではありません。複数の検査結果や症状の有無などから、医師が総合的に判断します。
糖尿病の診断基準
糖尿病の診断基準は、以下のとおりです。
- HbA1c:6.5%以上
- 空腹時血糖:126mg/dL以上
- 随時血糖値:200mg/dL以上
- 75gOGTT2時間値:200mg/dL以上
- グリコアルブミン:20%以上
HbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病の可能性が高いと考えられますが、貧血などがあると値が変動することがあります。一度の検査で判断するのではなく、後日改めて検査を行い、同じ結果が出た場合に、糖尿病と診断される場合が多いです。
空腹時血糖値が100~125mg/dL、HbA1cが5.6~6.4%、グリコアルブミンが16.1~19.9%の場合は、境界型糖尿病(糖尿病予備軍)と呼ばれ、将来的に糖尿病になるリスクが高い状態です。
糖尿病の検査には、他にもインスリン分泌能を調べるCペプチドや自己免疫の指標となる抗GAD抗体などの項目を調べることもあります。糖尿病の種類を特定したり、治療方針を決定したりする際に役立ちます。
糖尿病の治療開始の目安
糖尿病の治療開始の目安について、以下をそれぞれ解説します。
- HbA1c 6.5%以上:医療機関を受診
- HbA1c 7.0%以上:薬物療法を開始
- HbA1c 8.0%超:インスリン導入検討
HbA1c 6.5%以上:医療機関を受診
HbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病の可能性があります。この段階では、自覚症状がない場合も多いので、検査結果を見て初めて異常に気づく人も少なくありません。糖尿病は放置すると、神経障害や網膜症、腎症などの合併症を引き起こし、生活の質を低下させるだけでなく、生命に関わる場合があります。
HbA1cが6.5%以上の場合、別の日に再検査を行い、6.5%以上の数値が確認されれば、糖尿病と診断されます。境界型糖尿病(糖尿病予備軍)と診断された場合も、医療機関での定期的な検査が必要です。
以下の記事では、糖尿病による心血管系の合併症とその予防策について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
糖尿病が進行すると、血管への影響が現れやすくなり、動脈硬化の進行が問題になることがあります。血管の硬さや血流の状態を客観的に把握する検査も、合併症リスクを評価するうえで参考になります。以下のページでは、血管の状態を調べる検査について詳しく解説しています。
HbA1c 7.0%以上:薬物療法を開始
HbA1cが7.0%を超えると、生活習慣の改善だけでは血糖コントロールが難しくなり、薬物療法が必要になる場合があります。糖尿病の薬には、飲み薬と注射薬があり、医師が患者さんの状態に応じて適切な薬剤を選択し、血糖値のコントロールを目指します。
食事療法や運動療法を継続することも大切です。効果には個人差がありますが、治療法を組み合わせることで、血糖コントロールの改善が期待されます。
HbA1c 8.0%超:インスリン導入検討
HbA1cが8.0%を超えると、高血糖の状態が長く続いており、膵臓から分泌されるインスリンの量がかなり少なくなっている可能性があります。放置すると、意識障害や昏睡に陥る可能性もあるため注意が必要です。飲み薬だけでは血糖コントロールが難しく、インスリン注射の導入を検討します。
適切なインスリン療法は、個人差はありますが、良好な血糖コントロールが期待され、合併症の進行を抑制する可能性があります。インスリン注射は、医師の指導のもとで行われる治療法の一つです。適切な指導を受ければ、自宅でも安全に注射を行うことができます。
定期的な通院でHbA1cや血糖値の推移を確認し、治療方針を調整していくことが重要です。医療機関を受診する際は、糖尿病専門医や内分泌内科を受診するのがおすすめです。
糖尿病の自覚症状
糖尿病の自覚症状について、以下の4つを解説します。
- 頻尿・多尿
- 喉の渇き
- 疲労感
- 体重減少
頻尿・多尿
健康な状態では、腎臓で血液が濾過され、老廃物だけが尿として排出される仕組みです。しかし、糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、腎臓は糖を濾過しきれなくなり、尿の中に糖が排出されます。糖には水分を引き寄せる性質があるため、尿量が増え、トイレに行く回数が増える頻尿や1回あたりの尿量が増える多尿の症状が現れます。
夜間頻尿は、糖尿病のサインとして注目すべき症状です。夜中に何度もトイレに起きるため、睡眠不足になり、日中の集中力低下や倦怠感につながる場合があります。
喉の渇き
多尿によって体内の水分が失われると、体は脱水状態になり、喉の渇きを感じます。喉が渇き水分を多く摂っているにもかかわらず、すぐに喉が渇く悪循環に陥ります。喉の渇きは、乾燥によるものではなく、体が水分を必要としています。スポーツドリンクやジュースではなく、水やお茶で水分補給をするように心がけてください。
脱水症状が進むと、めまいやふらつき、意識障害などの症状が現れることもあります。高齢者や乳幼児は脱水症状を起こしやすいため、注意が必要です。
疲労感
私たちの体は、糖をエネルギー源として活動していますが、糖尿病になると、糖をエネルギーとして効率的に利用できなくなります。体は常にエネルギー不足の状態になり、慢性的な疲労感や倦怠感に悩まされるようになります。
十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中常に眠気や倦怠感があり、体の重だるさが続く場合は、糖尿病の可能性がある状態です。疲労感は、精神的なストレスや過労、他の病気によっても引き起こされるため、正しい原因の把握が重要です。原因を特定するためには、医療機関を受診し、血液検査などを受けましょう。
体重減少
糖尿病になると、体はエネルギー源である糖をうまく利用できないため、脂肪や筋肉を分解してエネルギーを作り出します。結果、体重が減少する場合があります。食事制限や運動をしていないのに体重が減る場合は、糖尿病の可能性があるため、注意が必要です。体重減少は、他の病気である可能性もあるため、医療機関を受診しましょう。
今日からできる糖尿病のセルフケア
今日からできる糖尿病のセルフケアは、以下のとおりです。
- 食生活の見直し
- 適度な運動
- 禁酒・禁煙
- ストレス管理
- 十分な睡眠
- 定期的な受診
食生活の見直し
食事療法は、糖尿病治療の基本です。具体的には、以下を意識しましょう。
- 適切なカロリーを摂る
- 栄養バランスの良い食事をする
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 食物繊維を積極的に摂る
- 低糖質の食品を選ぶ
適切なカロリーは、年齢や性別、身体活動量によって異なります。自身に合ったカロリーを計算し、過剰摂取にならないようにしましょう。栄養バランスの良い食事のために、主食(ご飯やパン、麺類)や主菜(肉や魚、卵)、副菜(野菜やきのこ、海藻)をそろえてください。炭水化物やたんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂ることが大切です。
よく噛んで食べると、血糖値の上昇が緩やかになるため、満腹感を得やすく食べすぎ防止にもつながります。食物繊維は、食後の血糖値の上昇を抑える働きがあるため、食物繊維を多く含む食品を最初に食べることがおすすめです。野菜や海藻、きのこなどを積極的に摂りましょう。野菜は、毎食、小鉢1皿を目安にしましょう。
糖質は、血糖値を上昇させる主な栄養素です。白米やパン、麺類などの糖質の多い食品は、摂りすぎに注意し、精製度の低い食品(玄米や全粒粉パンなど)を選びましょう。GI値(グリセミック・インデックス)を参考に、血糖値の上昇が比較的穏やかな食品を選ぶことも一つの方法です。
適度な運動
運動は、血糖値を下げ、インスリンの働きを良くする効果が期待されます。おすすめの適度な運動は、以下のとおりです。
- 有酸素運動
- 筋力トレーニング
- 日常生活でのこまめな運動
有酸素運動として、ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなど、息が少しはずむ程度の運動を、週に合計150分以上行うことがおすすめです。毎日30分のウォーキングを5日間行なったり、15分のウォーキングを10日間行なったり、自分のペースで継続することが大切です。
筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を上げる効果があります。基礎代謝が上がると、エネルギー消費量が増え、血糖値のコントロールに役立ちます。スクワットや腕立て伏せ、腹筋運動など自宅で簡単にできる筋力トレーニングを週2回程度取り入れるのがおすすめです。
日常生活の中では、エレベーターではなく階段を使う、一駅前で降りて歩く、電車やバスでは座らずに立つなど、こまめに体を動かす習慣を身につけましょう。日常生活でのこまめな運動はNEAT(Non-Exercise Activity Thermogenesis:非運動性活動熱産生)と呼ばれ、1日の総エネルギー消費量に大きく影響します。
禁酒・禁煙
喫煙は、動脈硬化を促進し、糖尿病の合併症(神経障害や網膜症、腎症など)のリスクを高めます。禁煙することで、合併症のリスクを減らすことができる場合があります。過度の飲酒は、肝臓への負担を増やし、血糖コントロールを悪化させる可能性があるので控えましょう。
ストレス管理
ストレスは、血糖値を上昇させるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促し、血糖コントロールを悪化させる原因の一つです。ストレスをため込まないように注意しましょう。読書や音楽鑑賞、映画鑑賞、ガーデニングなど、自分が楽しめる趣味の時間を持つことは、ストレス解消になります。
呼吸法やヨガ、瞑想、アロマテラピーなど、リラックスできる時間を作ることも大切です。家族や友人、職場の同僚、医療従事者など、信頼できる人に相談することで、ストレスを軽減できる場合があります。自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身のリラックスを心がけましょう。
十分な睡眠
睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、血糖値を上昇させるホルモンの分泌を増加させるため、血糖コントロールの悪化につながります。毎日、同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。睡眠時間は、個人差がありますが、7〜8時間が目安です。
質の良い睡眠をとるために、寝る前のカフェイン摂取やスマホの使用は控え、寝室の環境を整えましょう。
定期的な受診
糖尿病は、自覚症状がないまま進行することがあります。定期的に医療機関を受診し、血糖値やHbA1c、その他の検査を受け、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。治療方針は、患者さんの病状や年齢、生活習慣、治療に対する希望などを考慮して決定されます。疑問や不安があれば、医師に相談するようにしましょう。
まとめ
糖尿病の疑いがある、または健康診断で血糖値が高いと指摘された方は、紹介した検査項目や基準値を参考に、ご自身の状態を把握しましょう。自覚症状がなくても、検査結果に異常があれば、放置せずに医療機関を受診し、専門医の指導を受けましょう。糖尿病は早期発見と早期治療が大切です。
糖尿病は、日々の生活習慣の見直しも重要です。食事療法や適度な運動、禁酒・禁煙、ストレス管理、十分な睡眠などのセルフケアを積極的に実践し、合併症の予防に努めましょう。正しい知識を身につけ、適切な治療と毎日のセルフケアを行えば、健やかな生活を送ることができます。
健診で異常があった際の再検査について、詳しい情報は下記ページをご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
厚生労働省:糖尿病診療の現状(令和4年)
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







