blog
ブログ
健康診断の結果、BMIの数値が気になっていませんか。BMIはただの数字ではなく、健康状態を知る目安となる指標の一つです。世界保健機関(WHO)も採用するBMIは、肥満度を測る国際的な指標で、簡単な計算であなたの健康リスクが明らかになります。
しかし、BMIは万能ではありません。筋肉質の人はBMIが高めに出るなど、注意が必要な点もあります。この記事では、BMIでわかる肥満度やリスク、合併症などについて解説します。理想のBMIを目指し、健康維持のための一歩を踏み出しましょう。
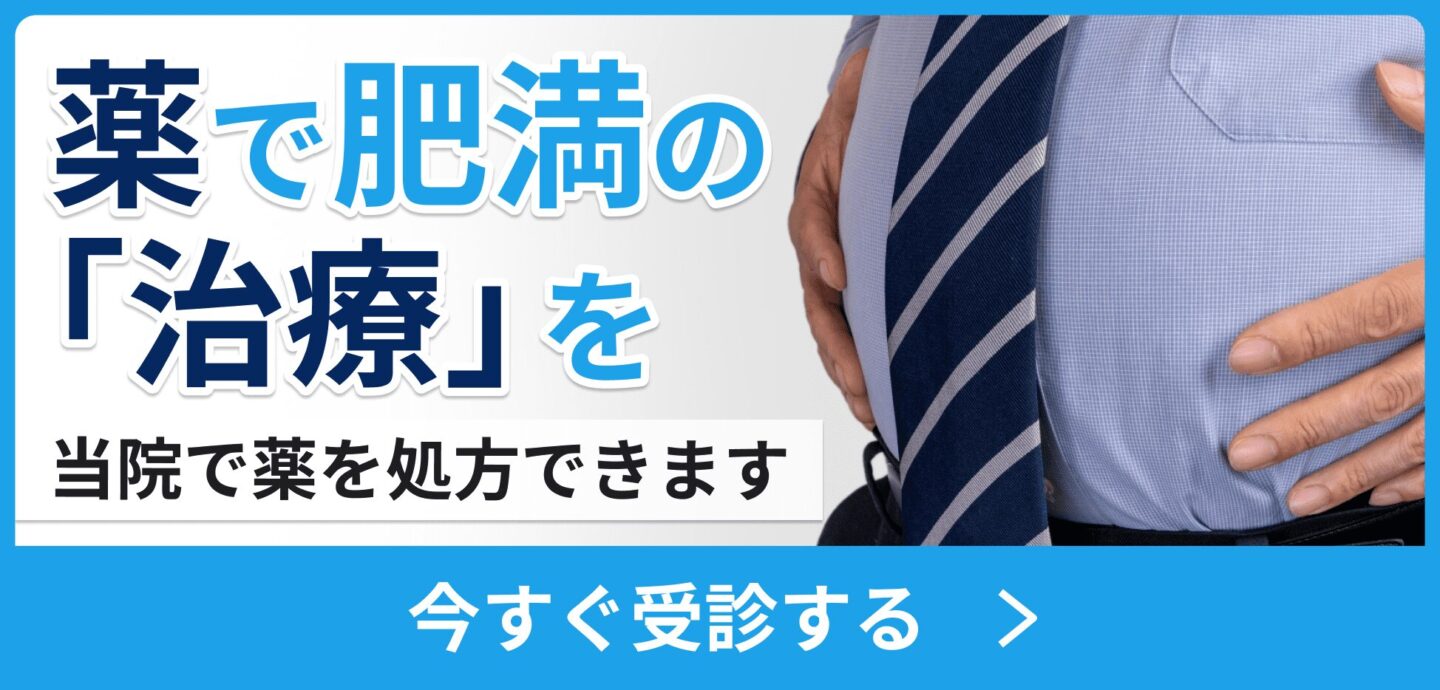
BMIでわかる肥満度チェック:計算方法と基準値
健康診断でBMIの数値を見てダイエットを始める方は多いです。BMIは、自分の体型が健康的な範囲内にあるかを手軽にチェックできるツールです。BMIの計算方法や基準値について解説します。
BMIとは身長と体重から計算される体格指数のこと
BMI(Body Mass Index)とは、身長と体重から計算される「体格指数」のことで、世界保健機関(WHO)も採用している国際的な指標です。BMIを計算することで、自分は肥満なのか、痩せ気味なのか、あるいは適正な体重なのかを知ることができます。BMIを知ることは、健康リスクの目安を知るための第一歩です。BMIは体の状態を知るためのバロメーターの一つと言えます。
しかし、BMIだけですべてがわかるわけではありません。筋肉質の人は筋肉の重さでBMIが高めに出る傾向があります。高齢の方は筋肉量が少なく脂肪が多いため、BMIが低くても体脂肪が高い場合があり、注意が必要です。
BMIはあくまでも目安の一つとして捉え、腹囲や体脂肪率なども合わせてチェックすることが、より正確な健康状態の把握につながります。
BMIの計算方法と基準値
BMIの計算方法はとても簡単で、以下の式で表せます。
BMI = 体重(kg) ÷ (身長(m)²)
体重が50kg、身長が1.6mの人は、以下のように計算できます。
BMI = 50 ÷ 1.6 ÷ 1.6 = 19.5
計算したBMIの値がどの範囲に当てはまるのか、以下の日本肥満学会が定めた基準値をまとめた表で確認してみましょう。
| BMI値の範囲 | 判定 |
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5~24.9 | 普通体重 |
| 25~29.9 | 肥満(1度) |
| 30~34.9 | 肥満(2度) |
| 35~39.9 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
BMIが22のときが最も病気になりにくい「適正体重」と言われています。健康状態を総合的に判断するためには、他の検査結果や医師の診察も重要です。BMIの結果を参考に、今後の健康管理に役立ててみてください。
BMIが高いとどうなるの?肥満のリスクと合併症
BMIが高い状態が続くと、体に負担がかかり、さまざまな病気を引き起こしやすくなります。肥満は体に少しずつダメージを蓄積し、健康を損なうリスクを高めます。以下の病気のリスクがあります。
- 生活習慣病:糖尿病・高血圧・脂質異常症
- 心血管疾患:心筋梗塞、脳卒中
- がん:大腸がん・乳がん・子宮体がん
- 睡眠時無呼吸症候群
- 変形性関節症
- 脂肪肝
- 精神的な影響:自己肯定感の低下など
生活習慣病:糖尿病・高血圧・脂質異常症
BMIが高いと、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まる可能性があります。
- 糖尿病
肥満の状態ではインスリンの働きが鈍くなり(インスリン抵抗性)、血糖値がうまくコントロールできなくなります。血糖コントロールが上手くできない状態が続くと糖尿病を発症し、網膜症や腎症、神経障害といった合併症を引き起こす可能性があります。 - 高血圧
肥満は、血液量を増加させ、血管に負担をかけ、血圧を上昇させます。高血圧自体は自覚症状が少ないため、定期的な血圧測定が重要です。 - 脂質異常症
肥満になると、血液中のコレステロールや中性脂肪といった脂質が増加し、血管壁に付着しやすくなります。脂質異常症も自覚症状はほとんどないため、血液検査でコレステロールや中性脂肪の値を定期的にチェックする必要があります。
生活習慣病は、複数の病気を合併することもあります。糖尿病の人は高血圧や脂質異常症も併発しやすく、心血管疾患のリスクがさらに高まります。生活習慣病が複数合併した状態はメタボリックシンドロームと呼ばれ、放置すると命に関わる危険性も高まります。
以下の記事では、内臓脂肪を減らすための方法や効果などを解説していますので、ぜひご確認ください。
>>内臓脂肪を減らすための方法やその効果と注意点を解説
心血管疾患:心筋梗塞、脳卒中
肥満は、心臓や血管に大きな負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高くします。心血管疾患は、動脈硬化と密接に関連しています。動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失ってしまう状態です。肥満に加えて、生活習慣病が重なると、動脈硬化はさらに進行し心血管疾患のリスクは加速度的に上昇します。
心筋梗塞は、心臓の血管(冠動脈)が動脈硬化によって狭くなったり、詰まったりすることで、心臓の筋肉に血液が供給されなくなり、心臓の筋肉が壊死してしまう病気です。激しい胸の痛みや呼吸困難などの症状が現れ、突然死につながることもあります。
脳卒中は、脳の血管が動脈硬化によって狭くなったり、詰まったり、あるいは破れたりすることで、脳の機能が損なわれる病気です。
- 意識障害
- 半身まひ
- 言語障害
上記のような症状が現れ、後遺症が残ることもあります。
がん:大腸がん・乳がん・子宮体がん
肥満は、大腸がんや乳がん、子宮体がんといったさまざまながんのリスクも高めると言われています。肥満によって体内のホルモンバランスが乱れたり、慢性的な炎症が起こったりすることが原因の一つと考えられています。
脂肪細胞から分泌される女性ホルモン(エストロゲン)は、乳がんや子宮体がんのリスクを高める因子となることが知られています。また、肥満に伴う慢性炎症は、細胞のDNAに損傷を与え、がん化を促進する可能性が指摘されています。
睡眠時無呼吸症候群
肥満の人は、首周りの脂肪が気道を圧迫しやすいため、睡眠中に呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群のリスクを高める要因の一つと考えられています。睡眠時無呼吸症候群は、大きないびきや日中の強い眠気といった症状を引き起こすだけでなく、高血圧や心血管疾患のリスクを高めるため、注意が必要です。
変形性関節症
肥満は、体重増加によって関節、特に膝や股関節といった体重を支える関節に大きな負担をかけ、変形性関節症を引き起こしやすくなります。変形性関節症は、関節軟骨がすり減り、関節の変形や痛み、動きの制限が生じる病気です。肥満により進行が早まるだけでなく、痛みも増強する傾向があります。
脂肪肝
BMIが高いと、肝臓に脂肪が蓄積し、脂肪肝になりやすくなります。脂肪肝自体は自覚症状が少ないですが、進行すると肝硬変や肝臓がんに発展する可能性もあるため、注意が必要です。脂肪肝は、過剰な飲酒だけでなく、肥満によっても引き起こされるため、食生活や運動習慣の見直しが必要です。
精神的な影響:自己肯定感の低下など
肥満は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。自分の体型に自信が持てなくなり、自己肯定感が低下したり、人とのコミュニケーションを避けるようになったりする人もいます。また、肥満はうつ病などの精神疾患のリスクを高めることも知られています。
肥満はさまざまな健康問題のリスクを高めるため、BMIが高い場合は、生活習慣の改善に取り組むことが重要です。
肥満の対処法
肥満の対処法は以下のとおりです。
- 食事療法:カロリー制限、バランスの良い食事
- 運動療法:有酸素運動・筋力トレーニング
- 行動療法・認知行動療法
- 薬物療法・外科的治療
- リバウンドを防ぐためのポイント
食事療法:カロリー制限、バランスの良い食事
食事療法は、肥満改善において重要です。食事療法の基本は、摂取カロリーを消費カロリーよりも少なくすることです。目標とする1日の摂取カロリーの目安は、目標体重(kg)×25kcalです。高度肥満(BMI40以上)の場合には、1日20~25kcal×目標体重(kg)を目安にしてください。
目標体重が60kgの場合は、1日の摂取カロリーを1500kcal以下に抑える必要があります。カロリーを制限するだけでなく、バランスの良い食事を心がけることも大切です。主食や主菜、副菜をバランスよく摂りましょう。
野菜はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富でカロリーも低いので、積極的に摂るようにしてください。揚げ物や脂肪分の多い食品、甘いお菓子やジュースなどはカロリーが高いため、なるべく控えめにしましょう。よく噛んでゆっくりと食事をすることも満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果があります。
当院では、食事栄養指導も行っています。気になる方は以下の記事をご確認ください。
>>大石内科循環器科医院の食事・栄養指導はこちら
運動療法:有酸素運動・筋力トレーニング
運動療法は、消費カロリーを増やし、体脂肪を減らす効果があります。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで、より効果的に肥満を改善できます。有酸素運動としては、以下の運動が該当します。
- ウォーキング
- ジョギング
- 水泳
- サイクリング
週に3~5回、1回あたり20~30分程度行うのがおすすめです。筋力トレーニングは、以下のような筋肉に負荷をかける運動です。
- スクワット
- 腕立て伏せ
- ダンベル体操
筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、痩せやすい体質になります。週に2~3回行うのがおすすめです。
行動療法・認知行動療法
行動療法は、肥満につながる行動パターンを変えていく治療法です。間食の習慣をやめたり、食事の量を減らしたりといった行動の改善を目指します。
認知行動療法は、肥満につながる考え方や感情のパターンを変えていく治療法です。「ストレスがたまるとつい食べ過ぎてしまう」というような自分の思考パターンを分析し、より健康的な行動につながるように改善していきます。
薬物療法・外科的治療
肥満の治療には、食事療法や運動療法が基本となりますが、十分な効果が得られない場合には、薬物療法や外科的治療が選択肢となる場合があります。
薬物療法は、食欲を抑制する薬や脂肪の吸収を抑える薬などを使用します。外科的治療としては、胃を小さくする手術などがあります。薬物療法や外科的治療は、医師の指示のもとで慎重に検討する必要があります。
リバウンドを防ぐためのポイント
リバウンドを防ぐためには、急激なダイエットを避け、ゆっくりと減量していくことが大切です。肥満症の患者さんは、3〜6か月で現体重の3%程度の減量を目安にしましょう。減量後も、健康的な食生活と適度な運動を続けることが重要です。
肥満の予防策
肥満を予防するためには、以下の生活習慣を心がけることが重要です。
- バランスの取れた食事
- 適度な運動
- 十分な睡眠
- ストレスをため込まない
毎日の食事では、野菜を多く摂り、脂肪分の多い食事は控えめにしましょう。適度な運動は、ウォーキングなどの軽い運動でも効果があります。毎日30分程度の運動を目標に、無理なく続けられる運動を見つけましょう。
質の高い睡眠を十分に取ることも大切です。睡眠不足は、食欲を増加させるホルモンの分泌を促すため、肥満につながりやすくなります。最後に、ストレスをため込まないことも大切です。ストレスは、過食の原因となることがあります。趣味やリラックスできる活動を通して、ストレスを発散する方法を見つけるようにしましょう。
肥満になりやすい食事をはじめ、肥満解消のための食事療法について、以下の記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。
>>肥満になる食事は?解消するためにやるべき食事療法やおすすめメニューについて
まとめ
BMIは、肥満度をチェックする便利な指標ですが、あくまで目安の一つです。 計算結果だけで一喜一憂するのではなく、ご自身の体型や生活習慣も考慮しましょう。
BMIが高いと、以下の健康問題につながる可能性があります。
- 生活習慣病
- 心血管疾患
- がんのリスク向上
健康的な食生活や適度な運動を取り入れることで、BMIを改善し、健康リスクを減らすことができます。焦らず、少しずつ、生活習慣を改善していくことで、より健康的な体を目指すことができます。
当院の肥満外来では、専門の医師が栄養指導や運動プログラム、必要に応じて治療薬の処方を通じて、個別のケアプランを提供します。肥満治療薬のみの処方も可能のため、お気軽にご相談ください。
当院では、肥満や生活習慣病のリスク評価に有用な検査も実施しています。以下のページで詳細をご確認いただけます。
参考文献
Atilla Engin. The Definition and Prevalence of Obesity and Metabolic Syndrome. Adv Exp Med Biol, 2017
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







