blog
ブログ
遺伝や食生活、運動不足やストレスなどの要因が複雑に絡み合い、肥満という健康リスクを生み出しています。この記事では、肥満の原因から、糖尿病や高血圧といった合併症のリスク、そして具体的な改善策までを網羅的に解説します。
遺伝的な体質に不安を抱えている方、生活習慣の改善に悩んでいる方、そして健康診断の結果が気になっている方は要チェックです。ぜひ、ご自身の健康状態を見つめ直す機会にしてください。
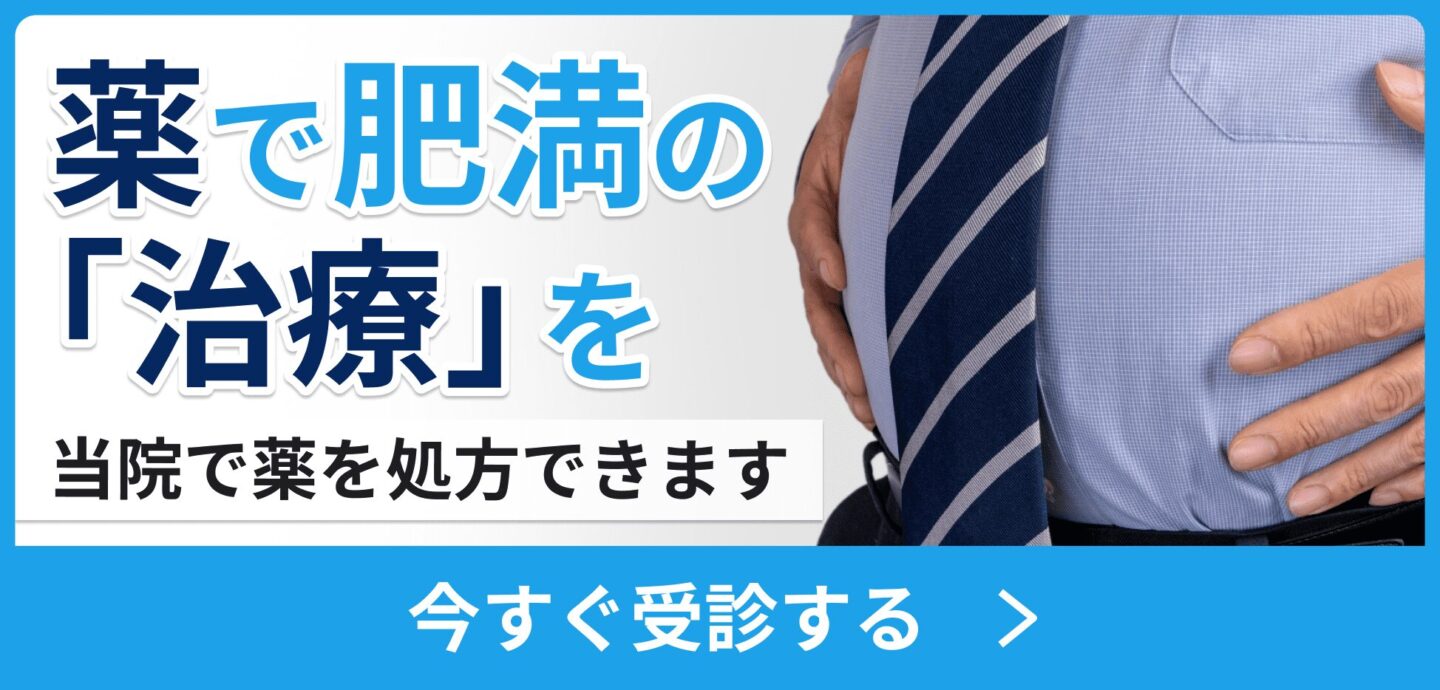
肥満の原因4選
肥満の主な原因は以下の4つです。
- 遺伝の影響
- 食生活の乱れとカロリー過多
- 運動不足とエネルギー消費の低下
- 睡眠不足やストレスなどの生活習慣
遺伝の影響
肥満は遺伝子が基礎代謝や脂肪の蓄積に影響を与えるため、親が肥満だと子も肥満になりやすい傾向があります。基礎代謝の個人差は肥満のリスクに影響を与える可能性がありますが、食生活や運動習慣の影響がより大きいとされています。
遺伝により内臓脂肪がつきやすい体質の人は生活習慣病のリスクが高まります。ただし、遺伝だけで肥満が決まるわけではなく、食生活や運動の改善で予防や対策が可能です。
食生活の乱れとカロリー過多
食生活の乱れは肥満の主な原因で、高カロリーな食事や偏った栄養バランス、ドカ食いや早食い、夜遅い食事などが影響します。摂取エネルギーが消費エネルギーを超えると、体脂肪が増えて肥満につながります。特に脂肪分や糖質の多い食品、ファストフードやスナック菓子は要注意です。
バランスの良い食事と摂取カロリーの管理が肥満予防の基本であり、健康に大きく影響するため、早めの対策が重要です。
運動不足とエネルギー消費の低下
現代社会では運動不足が進み、エネルギー消費の低下が肥満の原因となっています。運動は基礎代謝を高め、太りにくい体質を作るほか、ストレス解消にも効果的です。
日常生活で階段を使う、一駅分歩くなど、こまめに体を動かす工夫をしましょう。有酸素運動は脂肪燃焼に効果的で、週に数回30分を目安に取り組むと肥満予防・改善に役立ちます。
睡眠不足やストレスなどの生活習慣
睡眠不足やストレスは、食欲をコントロールするホルモンの乱れや代謝低下を引き起こし、肥満の原因になります。また、ストレスは甘いものや脂っこいものを欲しやすくするため注意が必要です。質の良い睡眠やストレス解消を心がけましょう。
寝る前のカフェインやデジタル機器を控え、リラックスする習慣を取り入れることが効果的です。肥満予防だけでなく心身の健康維持にも役立ちます。
肥満が引き起こす病気と合併症5選
肥満が原因で発症する主な病気と合併症のリスクは以下の5つです。
- 糖尿病と高血糖のリスク
- 高血圧と脳卒中・心筋梗塞のリスク
- 脂質異常症と動脈硬化・心血管疾患のリスク
- 脂肪肝と肝機能障害・肝硬変・肝がんのリスク
- 睡眠時無呼吸症候群のリスク
糖尿病と高血糖のリスク
肥満は主に2型糖尿病のリスク因子とされており、特に内臓脂肪が増えるとインスリンの働きが低下し、血糖値が上がりやすくなります。糖尿病が進行すると、網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化などの合併症を引き起こし、生活の質を低下させる恐れがあります。早期発見と予防が重要です。
高血圧と脳卒中・心筋梗塞のリスク
肥満は血管を圧迫し、脂肪細胞が血管を収縮させる物質を分泌するため、高血圧のリスクを高めます。高血圧は自覚症状が少なく進行しやすい病気で、動脈硬化を促進します。動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞など生命に関わる病気の原因となるため、予防と早期対策が重要です。
脂質異常症と動脈硬化・心血管疾患のリスク
脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪といった脂質の値が異常な状態です。肥満になると、脂質のバランスが崩れ、悪玉コレステロールが増加し、善玉コレステロールが減少する傾向があります。
血管の壁にコレステロールが蓄積しやすくなり、動脈硬化を進行させます。動脈硬化が進むと、血管が狭くなり、血液の流れが悪くなります。最終的には、血管が詰まる、または破れることで、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患を発症するリスクが高まります。
脂肪肝と肝機能障害・肝硬変・肝がんのリスク
脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。肥満の人は、肝臓に脂肪がたまりやすく、脂肪肝になりやすい傾向があります。
脂肪肝は初期段階では自覚症状がほとんどありません。しかし、脂肪肝が進行すると、肝臓の炎症が慢性化し、肝機能が低下する可能性があります。脂肪肝の一部は非アルコール性脂肪肝炎(NASH)が進行しており、肝硬変や肝がんのリスクが高まることが心配されています。
睡眠時無呼吸症候群のリスク
肥満は首周りの脂肪が気道を圧迫し、睡眠時無呼吸症候群を引き起こすリスクを高めます。睡眠の質を低下させ、日中の眠気や集中力低下を招き、高血圧や心臓病、脳卒中のリスクも上昇させます。
日中の眠気は交通事故などの原因にもなるため注意が必要です。健康維持には、適切な食事や運動、十分な睡眠が重要で、気になる症状があれば早期に医療機関を受診しましょう。
肥満の改善法4選
肥満は、見た目の問題だけでなく、さまざまな病気のリスクを高めるため、健康改善が大切です。無理なく続けられる肥満の改善法を4つご紹介します。
- 食生活の改善
- 運動療法
- 行動療法
- 薬物療法
自分に合った方法を見つけて、少しずつ改善していきましょう。
食生活の改善
肥満改善には、バランスの良い食事と適切なカロリー摂取が基本です。バランスの良い食事をするには、以下の栄養素をバランス良く摂る必要があります。
- 炭水化物(ご飯やパン)
- たんぱく質(肉、魚、卵、大豆製品)
- ビタミン・ミネラル(野菜、果物、海藻)
- 脂質
厚生労働省の「食事バランスガイド」を参考にすると、1日に必要な食品量をわかりやすく確認でき、健康維持にも役立ちます。摂取カロリーを把握し、消費カロリーを上回らないよう注意することも重要です。
世界保健機関(WHO)も肥満を主要な死因の一つとして警告しており、生活習慣病による死亡率が増加する予測もあります。ご飯の量を減らす、焼き魚を選ぶ、間食を控えるなど、無理なく続けられる方法で肥満改善を目指しましょう。
当院では、食事栄養指導も行っています。気になる方は以下の記事をご確認ください。
>>大石内科循環器科医院の食事・栄養指導はこちら
運動療法
運動は、消費カロリーを増やし体脂肪を減らす効果があり、肥満改善に有効です。有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)は脂肪燃焼に優れ、筋力トレーニング(スクワット、腕立て伏せなど)は筋肉量を増やし基礎代謝を上げる効果があります。
基礎代謝が上がると、安静時でも消費カロリーが増え、太りにくい体質を作ります。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで、相乗効果が期待できます。週に3回のウォーキングと2回の筋力トレーニングが推奨されることが多いですが、個人の健康状態に応じた運動計画が重要です。
運動には、ストレス軽減、血圧・血糖値の改善、睡眠の質の向上といった健康効果もあります。日常生活では、階段を使う、一駅分歩くなど、こまめに体を動かす習慣を取り入れることが大切です。
行動療法
肥満は食生活や運動習慣だけでなく、生活習慣全体に関連した問題です。夜遅い食事は、体内時計に影響を与えるBMAL1というたんぱく質の働きを阻害し、脂肪の蓄積を促進します。
睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩し、過食を招くほか、成長ホルモンの分泌を抑制して脂肪分解を妨げます。さらに、ストレスが増えるとコルチゾールが分泌され、食欲が増進や脂肪蓄積が促進されることもあります。
肥満改善には、生活習慣全体を見直すことが重要です。規則正しい生活を送り、十分な睡眠を確保し、ストレスを管理することが大切です。自分に合ったストレス解消法を見つけるために、アロマテラピーやヨガ、瞑想や読書、音楽鑑賞など、さまざまな方法を試してみましょう。
薬物療法
肥満症は、BMIが30以上、またはBMIが25以上で高血圧や糖尿病などの生活習慣病を伴う状態です。薬物療法は、食事療法や運動療法で効果が得られない場合に医師の判断で行われます。
日本で承認されている肥満症治療薬には、食欲を重視するものや脂肪の吸収を主体とするものがあります。糖尿病治療薬の中には体重減少効果があるものもあり、肥満症の治療に使用されます。
薬物療法は補助的な治療法であり、食事療法や運動療法と併用することが大切です。肥満を放置するとさまざまな合併症が生じる可能性があるため、健康的な生活を目指し、生活習慣の改善に取り組みましょう。
肥満の予防と健康管理のポイント3選
肥満予防を意識して行動することで健康を管理することは可能です。具体的な方法を3つのポイントに絞って、わかりやすく解説します。
- 定期的な健康診断とBMIのチェック
- 適切な食生活と運動習慣の維持
- 専門家への相談:医師や栄養士による個別指導
定期的な健康診断とBMIのチェック
健康診断は、自分の体の状態を客観的に知るための貴重な機会です。肥満の指標となるBMI(ボディマス指数)は、定期的にチェックするようにしましょう。BMIは、体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)で計算できます。例えば、体重が70kgで身長が1.7mの人は、70 ÷ 1.7 ÷ 1.7 = 約24.2となります。
BMIは、国際的な基準では25以上で過体重、30以上で肥満とされています。日本肥満学会の基準では、BMI25以上を肥満と判定しています。BMIはあくまでも目安の一つですが、肥満の傾向や健康リスクを評価するうえで重要な数値です。
健康診断では、BMIだけでなく、血圧や血糖値、コレステロール値なども測定されます。複数の数値を総合的に見ることで、生活習慣病のリスクを早期に発見し、適切な対策を立てることができます。
適切な食生活と運動習慣の維持
肥満の予防と改善には、適切な食生活と運動習慣が欠かせません。両者は車の両輪のように相互に関係しており、どちらか一方だけでは健康を手に入れることは難しいです。食生活では、主食・主菜・副菜をそろえた栄養バランスの良い食事を心がけ、過食を避けることが重要です。
具体的には、炭水化物、タンパク質、ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取し、食物繊維が豊富な食品を意識的に選ぶことが推奨されます。脂っこいものや甘いものは控えめにし、よく噛んでゆっくり食べることも大切です。
運動については、有酸素運動(ウォーキングやジョギング)と筋力トレーニング(スクワットや腕立て伏せ)を組み合わせることで、より効果的に肥満を予防・改善できます。
有酸素運動は脂肪を燃焼させ、筋力トレーニングは基礎代謝を高めます。1日30分の運動を目指し、小さな行動から始めることがおすすめです。無理な食事制限や過度な運動は、かえって健康を損なう可能性があります。大切なのは、自分の体と心に耳を傾けながら、無理なく続けられる食生活と運動習慣を身につけることです。
以下の記事では、内臓脂肪を減らすための方法や効果などを解説していますので、ぜひご確認ください。
>>内臓脂肪を減らすための方法やその効果と注意点を解説
専門家への相談:医師や栄養士による個別指導
肥満の予防や改善に悩んでいる場合、医師や栄養士などの専門家に相談することが効果的です。医師は肥満関連の病気や健康状態を判断し、必要に応じて薬物療法を検討します。栄養士は食生活や生活習慣を分析し、具体的な食事指導を行います。
自己流のダイエットよりも専門家のサポートを受けることで、安全で効果的な対策が可能です。肥満は一人で抱え込むには重すぎる問題であり、専門家とともに健康への道を歩むことが重要です。
当院では、肥満や生活習慣病のリスクを評価するために、以下のような検査を行っています。医師による正確な評価のもと、効果的な改善プランを立てることができます。
まとめ
肥満は見た目だけでなく、糖尿病や高血圧、脂質異常症や睡眠時無呼吸症候群などの病気リスクを高める深刻な問題です。遺伝や体質に加え、食生活の乱れや運動不足、睡眠不足、ストレスが肥満の原因となります。
WHOも肥満を主要な死因の一つとして警鐘を鳴らしています。健康的な生活を送るためには、バランスの取れた食事や適度な運動、規則正しい生活習慣が重要です。少しずつ生活習慣を改善し、専門家のサポートを受けることも有効です。自分に合った方法を見つけることが健康への第一歩です。
当院の肥満外来では、専門の医師が栄養指導や運動プログラム、必要に応じて治療薬の処方を通じて、個別のケアプランを提供します。肥満治療薬のみの処方も可能のため、お気軽にご相談ください。
参考文献
Safaei M, Sundararajan EA, Driss M, Boulila W, Shapi’i A. “A systematic literature review on obesity:Understanding the causes & consequences of obesity and reviewing various machine learning approaches used to predict obesity.” Computers in biology and medicine 136, no. (2021):104754.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







