blog
ブログ
脈拍は、健康状態を把握するうえで重要な指標の一つです。高齢になると、心臓や血管の状態も変化していく可能性があります。最近の研究では、9万人以上の成人を対象とした調査で、安静時の脈拍が長期的に大きく変動する人が2割もいることが明らかになりました。
毎日自分の脈を測ることで、心臓の状態を把握し、異変を早期に発見できる可能性が高まります。この記事では、高齢者の脈拍の正常値は一体どれくらいなのか、年齢による変化、そして脈拍の測り方まで、わかりやすく解説します。
脈拍の異常がサインする病気についても触れているので、ご自身の健康管理にぜひお役立てください。大石内科循環器科医院では、脈拍異常についても診療をしております。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
高齢者の正常な脈拍|年齢による変化と測り方
脈拍とは、心臓の収縮と拡張により血液が血管を通過する際に生じる律動的な波動のことです。脈拍を測ることで、心臓がどのように働いているかを知ることができます。高齢者の場合、加齢とともに心臓や血管に変化が起こりやすいため、脈拍を定期的に測ることは健康管理において重要です。
日々の健康管理の一環として、脈拍を意識することは有用といえます。気になる症状がある場合は、医療機関へ相談するきっかけにもなります。以下の内容を解説します。
- 加齢による脈拍への影響
- 正常脈拍の範囲(年齢別)
- 脈拍の正確な測り方
- 家庭でできる脈拍測定のコツ
加齢による脈拍への影響
年齢を重ねると、心臓の筋肉も徐々に衰えてきます。血管も弾力を失い硬くなってしまい、柔軟性が失われていき、心臓は以前より強い力で血液を送り出さなければならなくなります。心臓が血液を送り出す際により多くの力を必要とする分、高齢者の心臓への負担は大きくなるのです。
加齢による変化は、脈拍数や脈のリズムにも影響を及ぼします。安静時の脈拍数は、加齢によって少なくなる場合もあれば、逆に速くなる場合もあります。脈が飛ぶ、脈のリズムが乱れるといった不整脈も起こりやすくなります。
最近の研究で、ウェアラブルセンサーを用いて9万人以上の成人の安静時心拍数を2年間追跡調査した研究結果があります。結果によると、個人の安静時心拍数は短期的に見ると比較的安定しているものの、長期的に見ると10bpm以上の変動が見られる人が2割もいることがわかりました。
一人ひとりの平常値が異なり、年齢や生活習慣、健康状態によって大きく変わる可能性があることを示唆しています。自分の脈拍を把握し、少しでも異変を感じたら、医療機関に相談することが大切です。
正常脈拍の範囲(年齢別)
脈拍の基準値は個人差があり、一般的な目安として、成人では1分間に60~100回程度とされています。高齢者の場合も個人差があり、50~70回程度の方も多く見られます。加齢による心臓機能の低下を反映している可能性があります。
各年齢層における1分間の正常脈拍数は以下のとおりです。
- 20~30代:60~90回程度
- 40~50代:60~90回程度
- 60~70代:50~80回程度
- 80代以上:50~70回程度
ただし、数値はあくまでも目安です。個人差がありますので、普段から自分の脈拍を測り、ご自身の平常値を把握しておくことが大切です。毎日の脈拍チェックを習慣化し、自分の体からのメッセージを受け取れるようになりましょう。
脈拍の正確な測り方
脈拍を測る最も一般的な方法は、橈骨動脈(手首の親指側)に触れる方法です。人差し指、中指、薬指の3本を橈骨動脈に軽く当て、脈拍を1分間数えます。脈拍を測る際は、以下の点に注意しましょう。
- 安静時に測る:運動後や入浴後など、脈拍が速くなっているときは正確な値を測ることができません。
- 楽な姿勢で測る:緊張すると脈拍が速くなることがあるので、リラックスした状態で測りましょう。
- 同じ場所で測る:毎回同じ場所で測ることで、より正確な変化を把握することができます。
家庭でできる脈拍測定のコツ
脈拍を測るときは、ストップウォッチや時計を用意しておくと便利です。脈拍を数え間違えないように、数を声に出したり、メモしたりしながら測るのも良いです。
スマートウォッチやスマートフォンアプリで簡単に脈拍を測ることもできます。機器を利用する場合は、医師に相談の上、機器の使用方法をよく確認し、正しく使いましょう。毎日の脈拍の変化を記録することで、自分の健康状態を把握するのに役立ちます。何か異変を感じた場合は、早めに当院へご相談ください。
脈拍100以上は危険?脈拍異常の種類
脈拍は、心臓が全身に血液を送るたびに血管壁が拡張収縮する様子を指します。健康な人であれば、規則正しく一定のリズムで脈打ちます。しかし、さまざまな要因で脈拍が乱れることがあります。脈拍異常の種類は以下のとおりです。
- 脈拍が速くなる(頻脈)
- 脈拍が遅くなる(徐脈)
- 脈拍のリズムが乱れる(不整脈)
頻脈:脈拍が速すぎる状態
頻脈とは、安静時の脈拍数が異常に速い状態を指します。一般的には、安静時に1分間に100回以上の脈拍がある場合を頻脈と定義します。
92,457人のアメリカ人成人を対象とした研究では、安静時心拍数の個人差は大きく、40〜109 bpmに及ぶことが示されました。研究からもわかるように、100bpmという値は必ずしも危険な状態を表すわけではありません。年齢や持病、他の症状の有無、普段の脈拍数などを総合的に判断する必要があります。
頻脈は、心臓自身の異常だけでなく、他の病気や体の状態が原因で引き起こされることもあります。以下のような状態では、心臓に負担をかけて脈拍が早くなることがあります。
- 発熱
- 脱水症状
- 貧血
- 甲状腺機能亢進症
- 過度なストレスや不安
- 興奮状態
- 一部の薬の副作用
めまいや動悸、息切れ、胸の痛みといった症状を伴う頻脈は、速やかに医療機関を受診することが重要です。放置すると、症状が悪化したり、他の病気を引き起こしたりする可能性もあるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
特に動悸には注意が必要です。以下のページでは、動悸について網羅的に解説していますので併せて確認してみてください。
>>動悸について
徐脈:脈拍が遅すぎる状態
徐脈とは、安静時の脈拍数が異常に遅い状態です。一般的には、安静時に1分間に50回未満の脈拍がある場合を徐脈と定義します。
高齢者では、加齢に伴う心臓機能の低下によって徐脈となるケースが多く見られます。持久力のあるアスリートも、心臓が効率的に血液を送り出せるため、安静時の脈拍が遅い傾向があります。上記の場合は、特に心配する必要はありません。
しかし、徐脈によって以下のような症状が現れる場合は注意が必要です。
- めまい
- 失神
- 息切れ
- 倦怠感
急に脈拍が遅くなった場合は、早急に医療機関を受診しましょう。徐脈の原因としては、心臓の病気(洞不全症候群、房室ブロックなど)や甲状腺機能低下症、一部の薬の副作用などが考えられます。
不整脈:脈拍のリズムが乱れる状態
不整脈とは、脈拍のリズムが乱れる状態です。脈が飛ぶ、脈が速くなったり遅くなったりするなど、さまざまな症状があります。健康な人でも、一時的に不整脈が起こることはありますが、心臓の病気のサインである場合もあります。不整脈には、以下のようなさまざまな種類があります。
- 期外収縮:脈が飛ぶように感じることが多く、比較的よく見られる不整脈
- 心房細動:心房が細かく震えることで、脈がバラバラになる不整脈
自覚症状がない場合もありますが、動悸やめまい、息切れなどの症状を伴うことがあります。症状が現れた場合は、医療機関を受診し、適切な検査を受けることが重要です。
脈拍異常時の症状
脈拍の異常は、自覚症状がない場合もありますが、さまざまな症状が現れることもあります。代表的な症状としては、以下があります。
- 動悸
- 息切れ
- めまい
- ふらつき
- 胸の痛み
- 失神
上記の症状は、脈拍異常だけでなく、他の病気の可能性もあります。症状が続く場合や、急に症状が悪化した場合は、放置せずに速やかに医療機関を受診しましょう。自己判断は危険ですので、専門医の診断を受けることが大切です。
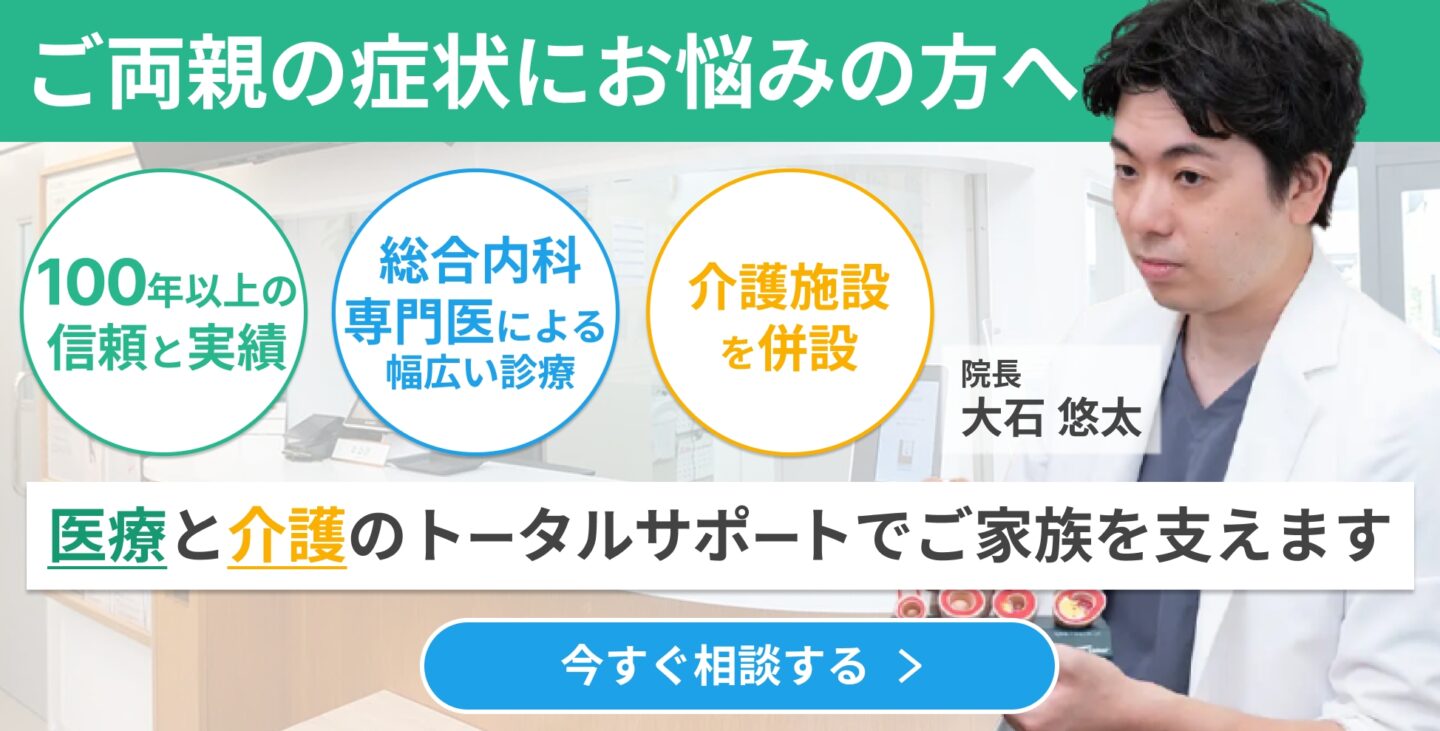
脈拍が異常になる原因
普段と異なる脈拍を感じると、誰しも不安を覚えるものです。加齢に伴い、安静時でも心臓がドキドキしたり、脈が飛んだりする経験が増えてくることがあります。自然な体の変化によるもので、心臓や血管の加齢変化が主な要因となります。
心臓病や甲状腺の病気など、さまざまな病気が原因で起こることもあります。健康な毎日を送るためにも、脈拍が異常になる原因を知り、適切な対処法を理解しておきましょう。
加齢による心臓と血管の変化
加齢による心臓と血管の変化は自然な現象ですが、脈拍の異常につながることがあります。例えば、安静時の脈拍数が異常に高くなったり、脈のリズムが不規則になったりすることがあります。具体的には、以下のような変化が挙げられます。
- 心臓の変化: 心臓の筋肉の弾力低下、収縮力の低下、弁の機能低下
- 血管の変化: 血管の弾力低下、血管の硬化、動脈硬化の進行
加齢による変化は、個人差が大きく、生活習慣や持病によっても影響を受けます。日頃から、バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけ、心臓と血管の健康を維持することが大切です。
病気の影響(心臓病、甲状腺の病気など)
脈拍の異常は、加齢以外にも、さまざまな病気が原因で起こることがあります。心臓病や甲状腺の病気など、多くの病気が脈拍に影響を与える可能性があり、緊急性を要するものもあります。心臓病の中には、脈拍が速くなる病気(頻脈)、遅くなる病気(徐脈)、リズムが乱れる病気(不整脈)など、さまざまな種類があります。
心房細動は脈がバラバラになる不整脈の一種で、心臓の中で血液が固まりやすくなり、脳梗塞などのリスクを高める危険な病気です。心臓の壁の一部が小刻みに震えることで、心臓が規則正しく収縮できなくなります。
収縮できない状態では、心臓から全身へ十分な血液を送り出すことができなくなり、動悸やめまい、息切れなどの症状を引き起こします。血液が心臓内で滞留しやすくなるため、血栓(血液の塊)が生じやすくなり、血栓が脳の血管に詰まると脳梗塞を引き起こす危険性があります。
甲状腺ホルモンは、心臓の働きを調節する役割をもっています。甲状腺機能亢進症では、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、代謝が亢進し、脈拍が速くなります。甲状腺ホルモンが心臓を刺激し、拍動数を増加させるためです。動悸や息切れ、発汗、体重減少などの症状が現れます。
逆に、甲状腺機能低下症では、甲状腺ホルモンが不足し、代謝が低下し、脈拍が遅くなることがあります。倦怠感や寒がり、便秘、体重増加などの症状が現れます。主な症状と脈拍への影響は以下のとおりです。
- 心房細動: 脈がバラバラになる、動悸、息切れ、めまい
- 洞不整脈:脈のリズムが乱れる、脈が飛ぶ、脈が不規則
- 心不全:脈拍が速くなる、息切れ、むくみ、倦怠感
- 甲状腺機能亢進症:脈拍が速くなる、動悸、息切れ、発汗、体重減少
- 甲状腺機能低下症:脈拍が遅くなる、倦怠感、寒がり、便秘、体重増加
上記の病気以外にも、貧血や脱水症状、発熱、薬の副作用などでも脈拍が異常になることがあります。脈拍の異常を感じた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。
心不全は、脈拍の異常と深く関わる病気の一つです。原因や症状、治療法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
>>心不全について
脈拍異常への対処法
日常生活の中で脈の乱れを感じることは、年齢を重ねるにつれて珍しくありません。以下のさまざまな要因が関係しています。
- 生活リズムの乱れ
- 運動不足
- ストレス
- 睡眠不足
多くの場合、生活習慣を見直すことで改善できる可能性があります。早めに対処することで、大きな病気の予防にもつながりますので、具体的な対処法をまとめます。
運動習慣を見直す
適度な運動は心臓の健康を保ち、脈拍を安定させるために大切です。心臓は筋肉でできており、他の筋肉と同じように、使わなければ衰えてしまいます。
運動によって心臓を鍛えることで、全身に血液を送り出すポンプ機能が強化されます。心臓が効率よく血液を送り出せるようになり、脈拍が安定するのです。以下のような、無理なく続けられる有酸素運動がおすすめです。
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- サイクリング
- 水泳
Tsengらの研究では、中強度の運動トレーニングが睡眠の質の改善に効果があり、心拍変動にも良い影響を与えることが示唆されています。1回30分程度、週に3~5回を目安に行うのがおすすめです。
運動を始める前には、必ず医師に相談し、自分の体に合った運動量や種類を選び、安全に運動を続けましょう。例えば、高血圧や心臓病などの持病がある場合は、運動の種類や強度を調整する必要があります。
適度な運動は心臓の健康を維持するだけでなく、血圧のコントロールにも役立ちます。特に高血圧の方は、適切な運動習慣を取り入れることで、血圧を安定させる効果が期待できます。血圧について詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
>>大石内科循環器科医院|高血圧の基礎知識・症状・治療について
食生活を見直す
バランスの良い食事は、健康な体づくりの基本であり、脈拍の安定にも大きく関わります。塩分や糖分、脂肪分の摂りすぎに注意することが大切です。野菜や果物を含む、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
カフェインやアルコールの過剰摂取も脈拍に影響を与えることがあるため、適量を心がけましょう。カフェインは交感神経を刺激し、心拍数を増加させる作用があります。
アルコールは血管を拡張させ、一時的に血圧を下げる作用がありますが、過剰摂取は心臓に負担をかけ、不整脈のリスクを高める可能性があります。
ストレス管理を行う
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、脈拍数を上昇させる大きな原因の一つです。日常生活でストレスをため込まないように、自分なりのストレス解消法を見つけ、心身のリラックスを心がけましょう。以下のような、自分に合う方法でストレスを解消するのがおすすめです。
- 趣味を楽しむ
- 軽い運動をする
- 自然の中で過ごす
- アロマテラピーを試す
- 好きな音楽を聴く
- 温かいお風呂にゆっくり浸かる
睡眠をしっかりとることも重要です。睡眠不足はストレスを悪化させるだけでなく、自律神経のバランスをさらに崩し、脈拍の異常を招く可能性があります。
睡眠の質を高める
睡眠は、心身を休ませ、日中の活動で疲れた体を回復させるために不可欠です。睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、脈拍の異常につながる可能性があります。Querらの研究では、安静時心拍数には個人差があり、睡眠時間の長さと関連があることが示唆されています。睡眠の質を高めるためには、以下のような工夫がおすすめです。
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 寝る前にカフェインを摂らない
- 寝室を暗く静かに保つ、
- 寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見ない
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
睡眠時間は、個人差がありますが7~8時間が目安です。質の良い睡眠をとることで、心身ともにリラックスし、脈拍も安定しやすくなります。
薬で脈拍をコントロールする
生活習慣の改善で脈拍異常が改善しない場合は、薬物療法が必要となることもあります。脈拍の異常に対しては、症状や原因に応じて適切な治療法が選択されます。薬物療法が必要な場合は、医師に相談の上、適切な治療を受けることが重要です。
薬の種類や服用方法は、患者さんの状態によって異なりますので、必ず医師の指示に従って服用してください。自己判断で薬の服用を中止したり、量を増やしたりすることは危険です。薬の副作用や他の薬との飲み合わせについても、医師や薬剤師に相談しましょう。
まとめ
加齢とともに心臓や血管は変化し、脈拍にも影響が出ます。脈拍数が常に100以上だったり、急に速くなったり遅くなったりする場合は、医療機関への相談がおすすめです。
日頃から脈拍を測り、自身の平常値を把握しておきましょう。規則正しい生活習慣と適切なストレス管理は、脈拍の安定につながります。何か気になる症状があれば、自己判断せずに当院までご相談ください。安心して毎日を過ごせるようにしましょう。
参考文献
- Tseng TH, Chen HC, Wang LY, Chien MY. Effects of exercise training on sleep quality and heart rate variability in middle-aged and older adults with poor sleep quality: a randomized controlled trial. Journal of clinical sleep medicine 16, no. 9 (2020): 1483-1492.
- Quer G, Gouda P, Galarnyk M, Topol EJ, Steinhubl SR. Inter- and intraindividual variability in daily resting heart rate and its associations with age, sex, sleep, BMI, and time of year: Retrospective, longitudinal cohort study of 92,457 adults. PloS one 15, no. 2 (2020): e0227709.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







