blog
ブログ
健康診断で中性脂肪の数値が高く不安という方、実は少なくありません。放置すると動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気を引き起こすリスクが高まる可能性があります。
この記事では、中性脂肪が高いことによるリスクや具体的な改善策、再検査の必要性などをわかりやすく解説します。一緒に健康を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。
健康診断で異常を指摘された場合は、早めに再検査を受け、適切な治療を受けることが大切です。健康診断で異常があった場合の対処法を詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
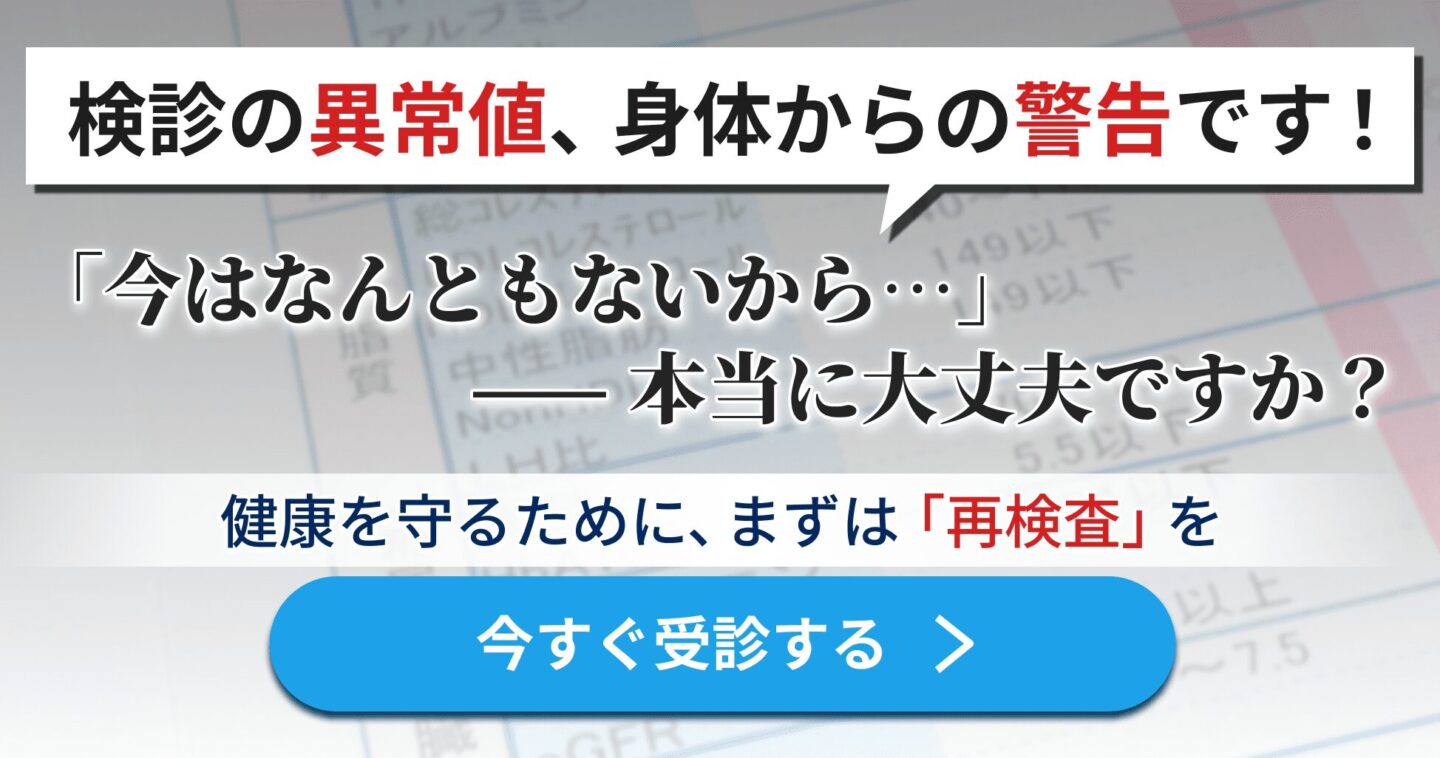
中性脂肪が高いことによるリスク
中性脂肪が高いことによるリスクは、血管や臓器にさまざまな影響を与える可能性があることです。具体的には、以下のリスクがあります。
- 動脈硬化
- 心筋梗塞
- 脳卒中
動脈硬化
動脈硬化とは、血管が硬くなって、柔軟性が失われている状態です。中性脂肪が高い状態が続くと、血管の壁にコレステロールなどの脂肪が溜まり、血管が狭くなってしまいます。すると、心臓や脳、腎臓など、体のあらゆる臓器に栄養や酸素が十分に届きにくくなってしまいます。
動脈硬化は自覚症状がないまま進行することが多いので、注意が必要です。血漿トリグリセリド(中性脂肪)値は、心血管疾患リスクの増加と関連があることが複数の研究で示されています。中性脂肪が高い状態を放置すると、血管の病気のリスクを高めてしまう可能性があります。
心筋梗塞
心筋梗塞とは、心臓の筋肉が壊死してしまう病気です。冠動脈(心臓に栄養や酸素を届けるための血管)の動脈硬化が進行すると、血管が狭くなり、心筋への酸素供給が不足し、胸の痛みや呼吸困難、冷や汗、吐き気といった症状が現れることがあります。
心筋梗塞は突然発症するケースが多いですが、発作の前兆として「胸の圧迫感」や「左腕や首の違和感」、「息切れ」などの症状が出ることがあります。 こうしたサインを見逃さず、早めに医療機関を受診することが大切です。
心筋梗塞の前兆や予防法について、循環器専門医が詳しく解説している記事を参考にし、リスクを早期に察知できるようにしましょう。
>>循環器専門医が心筋梗塞の前兆を解説
脳卒中
脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に障害が起こる病気です。脳の血管で動脈硬化が進むと、血管が詰まりやすくなったり、もろくなって破れやすくなったりします。血管が詰まるタイプの脳卒中を脳梗塞、血管が破れるタイプの脳卒中を脳出血といいます。
脳卒中の症状は、以下のとおりです。
- 失神
- 手足の麻痺
- 構音障害
中性脂肪が高い状態を放置すると、動脈硬化のリスクが高まり、脳卒中のリスクも高まります。中性脂肪を適切な値に保つことは、病気を予防するために大切です。
中性脂肪を下げるための5つの具体的な対策
中性脂肪を下げるための具体的な方法について、以下の5つの内容を解説します。
- 食生活の改善
- 適度な運動
- アルコール摂取の制限
- ストレス管理
食生活の改善
食生活の改善は、中性脂肪を下げるうえで重要なポイントです。人間の体は、食べ物から摂取したエネルギーをすぐに使わない場合、中性脂肪に変換して蓄えておきます。糖質や脂質の摂りすぎは、中性脂肪の蓄積を加速させてしまうのです。
バランスの良い食事を心がけましょう。主食・主菜・副菜をそろえ、野菜や海藻、きのこ、果物などを積極的に摂り入れることが大切です。中性脂肪を改善する食事のポイントは、以下のとおりです
- 青魚を摂取する
サバやイワシ、サンマ、ブリなどを週2〜3回摂取し、EPAやDHAを補給しましょう。EPAとDHAは体内で合成できない必須脂肪酸で、血液の流れを改善し、中性脂肪の合成を抑制する効果が報告されています。 - 食物繊維が豊富な食品を摂取する
野菜や海藻、きのこ類を毎食摂るようにしましょう。食後の血糖値上昇を抑え、中性脂肪の合成を抑制する効果が期待できます。 - 糖質の過剰摂取に注意する
白米やパン、麺類などの精製された穀物は、血糖値を急上昇させ、中性脂肪の合成を促進します。代わりに、玄米や全粒粉パンなど、精製度の低い穀物を選択することで、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。 - 大豆製品を取り入れる
納豆や豆腐、味噌などを摂るようにしましょう。大豆タンパク質がコレステロールを下げる効果が期待できます。
中性脂肪やコレステロールの異常は「脂質異常症」として知られ、放置すると動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める可能性があります。 もし健康診断などで「脂質異常」を指摘された場合は、早めに医療機関で相談し、適切な管理を行うことが大切です。
以下の記事では、脂質異常症の詳しい原因や症状、どの診療科に相談すべきかについて解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
>>脂質異常症とは?何科に相談すれば良いのか原因や症状についても解説
適度な運動
運動は、体内の脂肪を燃焼させ、中性脂肪を減らす効果があります。以下の有酸素運動は、脂肪をエネルギー源として利用するため、中性脂肪を下げるのに効果的です。
- ウォーキング
- ジョギング
- サイクリング
- 水泳
週に3回以上、30分程度の有酸素運動を目標に取り組んでみましょう。筋力トレーニングも重要です。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、日常生活で消費されるエネルギー量が増加します。脂肪が燃焼しやすくなり、中性脂肪の低下につながります。
スクワットや腕立て伏せ、腹筋運動など、自宅で手軽にできる筋トレも効果的です。有酸素運動と筋トレを組み合わせることで、より効果的に中性脂肪を下げることが期待できます。
アルコール摂取の制限
アルコールは、高カロリーであることに加え、アルコールを分解する過程で中性脂肪が合成されやすくなります。過剰な飲酒は、中性脂肪値を上昇させる要因となるため、注意が必要です。お酒を好む方は、現在の飲酒量を把握し、徐々に減らしていくことを意識しましょう。
ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、焼酎なら0.5合程度を目安に、適量を守るようにしてください。週に2日は休肝日を設けるなど、飲酒頻度にも気を配りましょう。
ストレス管理
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、中性脂肪を増やす原因となることがあります。ストレスをため込まないよう、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするのも良い方法です。ウォーキングやヨガなどの軽い運動も、ストレス軽減の効果が期待できます。
質の良い睡眠も、ストレス軽減につながります。心を落ち着かせ、リラックス効果を高める瞑想もおすすめします。
中性脂肪の再検査の必要性と流れ
中性脂肪の再検査の必要性と流れについて、以下の内容を解説します。
- 再検査が必要な理由
- 再検査の流れ・費用・期間
- 検査結果の見方
再検査が必要な理由
再検査が必要な理由は、継続的に中性脂肪が高い状態かを正確に判断するためです。一度の検査で中性脂肪の数値が高くても、前日の食事内容や一時的なストレスなど、さまざまな要因が影響している可能性があります。
脂っこい食事をした翌日に検査を受けると、中性脂肪の数値が高くなることがあります。食事で摂取した脂肪が、一時的に血液中に増加するためです。数日後に再検査を受けると、数値が正常に戻っていることもあります。
再検査でも中性脂肪が高い状態が続いている場合は、食生活や運動習慣を見直す必要があります。中性脂肪の管理には、日常的な食事の改善や適度な運動が不可欠です。具体的な対策については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
>>【医師監修】中性脂肪が高いと体に悪い?おすすめの食事や運動方法も解説
再検査の流れ・費用・期間
再検査は、最初の検査から2週間~3か月程度の期間をあけて行うことが一般的です。生活習慣の改善による効果が表れるのに時間がかかるためです。具体的な流れは、多くの場合、最初の検査と同様です。医療機関を受診し、採血を行います
費用は健康保険が適用されるため、数百円〜数千円程度で済むことがほとんどです。検査結果は通常、数日~1週間程度でわかります。結果が出たら医師の診察を受け、今後の対策について相談しましょう。
検査結果の見方
日本人間ドック学会によると、中性脂肪の正常値は、30~149mg/dLです。150mg/dLを超えると、脂質異常症(高トリグリセライド血症)と診断される可能性があります。
高トリグリセライド血症は、中性脂肪値が高い状態が続くことで、動脈硬化のリスクを高めるだけでなく、急性膵炎(きゅうせいすいえん)などのリスクも高めます。再検査の結果が正常値であれば、ひとまず安心ですが、油断せずに健康的な生活習慣を維持していくことが大切です。
基準値を超えている場合は、医師の指示に従い、食生活の改善や運動療法、場合によっては薬物療法などの治療に取り組む必要が考えられます。医師との相談を通じて、あなたに合った治療法を見つけ、一緒に健康を目指していきましょう。
医師に相談する際のポイント
医師に相談する際は、自分の状況を具体的に伝えることが大切です。以下の具体的な情報を整理しておきましょう。
- 過去の健康診断の結果
- 現在の食生活
- 運動習慣
- 喫煙習慣
- 飲酒習慣
- 服用中の薬
- 睡眠時間
- ストレスの状況
- 家族の病歴
食生活については、何をどのくらい食べているかを具体的に伝えることが重要です。「朝食はパンとコーヒー、昼食はコンビニ弁当、夕食は揚げ物が多い」と具体的に説明することで、医師はあなたの食生活の問題点を把握しやすくなります。
運動習慣についても、頻度や種類、時間などを具体的に伝えましょう。「週に2回、30分程度のウォーキングをしています」と伝えることで、運動不足の程度を医師が判断しやすくなります。
薬物療法が必要な場合
生活習慣の改善だけでは中性脂肪値が十分に下がらない場合、医師の判断で薬物療法が開始されることがあります。薬物療法には、主にフィブラート系薬剤やスタチン系薬剤などが用いられます。薬物療法で期待される効果は、以下のとおりです。
- 中性脂肪値の低下
- HDLコレステロール(善玉コレステロール)値の上昇
- LDLコレステロール(悪玉コレステロール)値の低下
期待できる効果もありますが、副作用が起こる可能性もあります。吐き気や下痢、便秘、筋肉痛、肝機能障害などの症状です。
薬物療法は、医師の指示に従って正しく服用することが重要です。自己判断で服用を中止したり、量を変更したりすることはやめましょう。薬を服用しているからといって、生活習慣の改善を怠ってはいけません。食事や運動の見直しを並行して行うことで、より効果的に中性脂肪値やコレステロール値をコントロールできる可能性が高まります。
コレステロール値を適切に管理するために、どのような食事法や生活習慣の改善が有効なのか、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
>>コレステロール値が高い方が実践すべき食事法や生活習慣の改善法を解説
まとめ
健康診断で中性脂肪の数値が高くて、不安な気持ちを抱えている方も少なくありません。しかし生活習慣の改善で、中性脂肪値はコントロールできる可能性があります。食生活ではバランスの良い食事を心がけ、適度な運動を習慣に取り入れてみましょう。ストレスをためすぎないように工夫することも大切です。
再検査が必要な場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より具体的な対策を立てることができます。自分自身の体と向き合い、健康的な毎日を送るための第一歩を踏み出しましょう。
当院では、健康診断で異常があった方や体の不調があった方に対して、専門医がサポートしております。健康診断で異常を指摘された方は、お気軽にご相談ください。健康診断で異常を指摘された場合の再検査内容について、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
>>健康診断で異常があったらどうする?|静岡市にお住まいの方へ
参考文献
- Klaus G Parhofer, Ulrich Laufs. Lipid Profile and Lipoprotein(a) Testing. Dtsch Arztebl Int, 2023, 120(35-36), p.582-588.
- Maaike Kockx, Leonard Kritharides. Triglyceride-Rich Lipoproteins. Cardiol Clin, 2018, 36(2), p.265-275.
- W S Harris. n-3 fatty acids and serum lipoproteins: human studies. Am J Clin Nutr, 1997, 65(5 Suppl), p.1645S-1654S.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







