blog
ブログ
健康診断の結果に不安を感じたことはありませんか?糖尿病は初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうこともあるため、健康診断での早期発見が重要です。厚生労働省の調査では、日本には約1,000万人の糖尿病患者や予備軍がいるとされ、国民的な健康課題となっています。
この記事では、健康診断でチェックすべき糖尿病の数値や、早期発見のメリット、糖尿病になりやすい人の特徴、予防策までを解説します。健康診断を有効に活用し、将来の合併症を防ぎながら、健康な毎日を目指しましょう。
大石内科循環器科医院では、健康診断も実施しています。糖尿病をはじめ、どの病気に関しても早期発見・早期治療が重要ですので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
糖尿病の健康診断で重要な3つの項目
健康診断は、自分自身の健康状態を把握し、病気の予防や早期発見につなげるための大切な機会です。重症化を防ぐためには、健康診断で糖尿病に関わる数値を確認することが重要です。糖尿病の早期発見に役立つ重要な検査項目3つは以下のとおりです。
- 空腹時血糖値
- HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)
- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
空腹時血糖値
空腹時血糖値は、10時間以上絶食した状態で採血し、血液中のブドウ糖濃度を測定する検査です。健康診断では糖尿病の早期発見に欠かせない基本的な検査項目の一つです。
日本糖尿病学会の診断基準では、正常値は100mg/dL未満とされています。100~109mg/dLは「正常高値」と呼ばれ、将来的に糖尿病になるリスクが高い状態とされています。食後の血糖値上昇が緩やかであれば問題ありませんが、急激に上昇する場合は注意が必要です。
110~125mg/dLは「境界型」と呼ばれ、糖尿病予備軍の状態です。「境界型」の段階で生活習慣を見直すことで、糖尿病の発症リスクを低減できる可能性があります。126mg/dL以上になると「糖尿病型」と診断される可能性が高くなります。最終的な診断は医師による総合的な判断によります。
空腹時血糖値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、さまざまな合併症のリスクが高まる可能性があります。目では網膜症、腎臓では腎症、神経では神経障害などを引き起こし、放置すると失明や人工透析が必要になるケースもあります。健康診断で早期に異常を見つけることが、合併症を防ぐための第一歩となります。
糖尿病の予防や治療を進めるうえでは、血糖値が血管に与えている影響を把握し、状態を客観的に評価することも重要です。血管の硬さや詰まり具合を確認する検査については、以下のページで解説しています。
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は、過去1~2か月の平均的な血糖値の状態を反映する検査です。赤血球中のヘモグロビンというタンパク質にブドウ糖が結合したものをHbA1cと呼びます。血糖値が高い状態が続けば続くほど、HbA1cの値も高くなる傾向があります。
検査の大きなメリットは、食事のタイミングに左右されずに測定できる点です。空腹時でなくても検査可能なため、より柔軟に糖尿病リスクを評価できます。
HbA1cの値が6.5%以上の場合は「糖尿病型」と診断される可能性があります。5.6~6.4%の場合は「境界型」とされ、糖尿病予備軍の状態です。5.0~5.5%の場合は、将来的な糖尿病リスクが高いとされ注意が必要です。理想的なHbA1cの値は4.6~5.2%とされています。
健康診断の結果をもとに生活習慣を見直し、安定した血糖値の維持を目指しましょう。
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)は、一定量のブドウ糖液を飲み、血糖値の変化を時間ごとに測定する検査です。空腹時の血糖値に加え、30分・1時間・2時間後の血糖の推移を確認することで、体の糖代謝の状態を調べることができます。空腹時血糖値やHbA1cの値が正常範囲内でも、糖尿病の疑いがある場合に実施されます。
2時間後の血糖値が200mg/dL以上であれば「糖尿病型」と診断される可能性が高くなります。140~199mg/dLの場合は「境界型」、140mg/dL未満の場合は「正常型」とされます。検査前後は喫煙や激しい運動を避けることで、より正確な結果を得ることができます。
経口ブドウ糖負荷試験は、インスリン分泌能やインスリン抵抗性なども評価できるため、糖尿病の診断精度を高める検査として有効です。「インスリン抵抗性」とは、インスリンが十分に分泌されているにもかかわらず、血糖値が下がりにくくなる状態を指します。
検査結果を理解するうえで「血糖値の正常範囲」を知っておくことはとても大切です。以下の記事では、血糖値の基準値や、異常が見つかった場合に考えられるリスク、そして対策についてわかりやすく解説しています。
>>血糖値の正常範囲とは?異常値が引き起こすリスクと対策を解説
糖尿病の早期発見で得られる3つのメリット
糖尿病の早期発見で得られる3つのメリットは以下のとおりです。
- 合併症リスクの軽減(網膜症、腎症、神経障害など)
- 健康寿命の延伸
- 生活の質(QOL)の向上
合併症リスクの軽減(網膜症、腎症、神経障害など)
糖尿病の合併症は、大きく分けて「細小血管障害」と「大血管障害」の2つに分類されます。細小血管障害は、毛細血管のように細い血管に障害が起こる合併症です。代表的なものは以下のとおりです。
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害
網膜症は、目の網膜にある血管が損傷し、視力低下や失明に至ることもあります。腎症は、腎機能が低下し、最終的には人工透析が必要になるケースもあります。神経障害は、手足のしびれや痛み、自律神経の障害による排尿・排便障害などを引き起こします。
大血管障害は、心臓の血管や脳の血管、足の血管など、太い血管に障害が起こる合併症です。代表的なものは以下のとおりです。
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
- 足の壊疽
合併症は、命に関わる重篤な状態を引き起こす可能性もあるため、早期発見と適切な治療が不可欠です。糖尿病を早期に発見し、血糖値やHbA1cの値を適切に管理することで、合併症のリスクを下げることが可能です。
健康寿命の延伸
健康寿命とは、健康上の問題がなく、自立した生活を送ることができる期間のことです。糖尿病は、合併症によって健康寿命を縮めてしまう可能性があります。
糖尿病性神経障害によって足に潰瘍や壊疽が生じ、足を切断しなければならなくなるケースもあります。糖尿病性腎症が進行すると、人工透析が必要になる場合もあります。人工透析は週に数回、病院に通わなければならないため、日常生活に大きな制約が生じます。
糖尿病を早期に発見し、食事療法や運動療法、薬物療法などを組み合わせた治療を行うことで、合併症の進行を防ぎ、健康寿命を延ばすことが期待できます。
生活の質(QOL)の向上
QOL(Quality of Life)とは「生活の質」を意味し、身体的・精神的・社会的な健康状態を含めた、人生における満足度を表す概念です。糖尿病は、合併症によって日常生活にさまざまな支障をきたし、QOLを低下させる可能性があります。糖尿病網膜症によって視力が低下すると、車の運転や読書、趣味の活動などが制限されてしまいます。
糖尿病性神経障害による手足のしびれや痛みは、睡眠を妨げ、日常生活動作を困難にする可能性があります。糖尿病を早期に発見し、適切な治療と生活習慣の改善に取り組むことが重要です。合併症の発症や進行を抑制し、生活の質(QOL)の低下を防ぐことができます。
血糖コントロールの目標値を達成して合併症を予防することで、日常生活の活動性を維持し、QOLを向上させることが期待できます。
糖尿病になりやすい人の特徴
糖尿病になりやすい人の特徴は以下の5つです。
- 肥満である
- 親族に糖尿病患者がいる
- 40歳を超えている
- 運動不足が続いている
- ストレスが多い
肥満である
肥満は糖尿病のリスクを大きく高める要因の一つです。内臓脂肪が多いタイプの肥満は特に注意が必要です。脂肪組織から分泌される物質がインスリンの働きを妨げ「インスリン抵抗性」の状態を引き起こすからです。
インスリン抵抗性が続くと、膵臓が過剰にインスリンを分泌しますが、やがて疲弊してインスリン分泌が低下します。最終的には血糖値がコントロールできなくなり、糖尿病を発症します。内臓脂肪は、皮下脂肪よりもインスリン抵抗性を高める作用が強いことが知られています。BMIだけでなく腹囲もチェックし、内臓脂肪を減らすことが予防の第一歩です。
肥満は単なる体重の増加だけでなく、生活習慣病や食習慣とも深く関係しています。以下の記事では、肥満の主な原因や、糖尿病をはじめとする健康リスク、そして予防・改善のための具体的な方法について詳しく解説しています。
>>肥満の原因とは?生活習慣病や食事との関係、リスクを減らす改善方法を解説
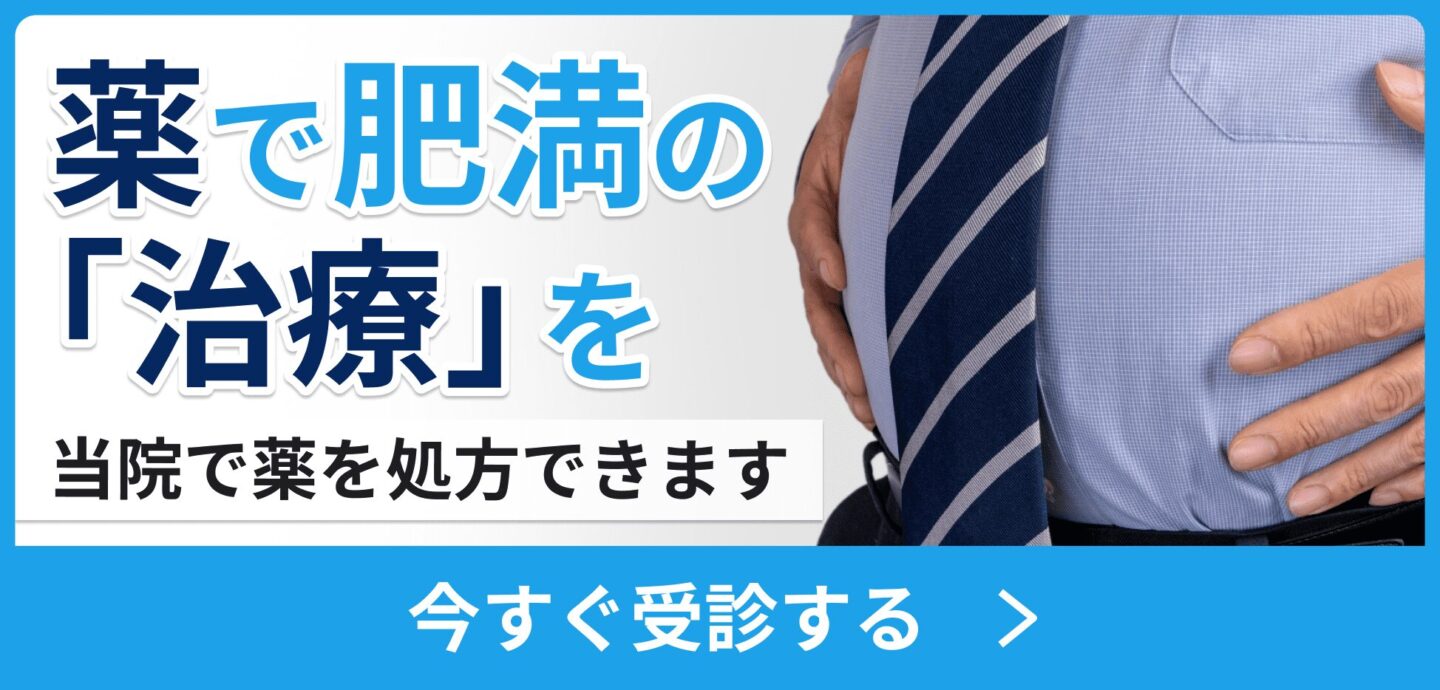
親族に糖尿病患者がいる
糖尿病の発症には遺伝的な要因も関わっているため、両親や兄弟姉妹などの親族に糖尿病患者がいる場合、発症リスクが高くなります。親族に糖尿病患者がいる方は、そうでない方と比べて、インスリン分泌能力が低い、またはインスリン抵抗性が高いなどの体質的な特徴を持つ可能性があります。
遺伝的要因は関連しますが、生活習慣を改善することで、糖尿病の発症リスクを下げることは可能です。
40歳を超えている
加齢に伴って、血糖値をコントロールする機能は徐々に低下します。インスリンの分泌能力が低下し、インスリン抵抗性も高まる傾向があるため、40歳以上は糖尿病のリスクが高まります。加齢による細胞の老化や膵臓の機能低下、筋肉量の減少などが原因と考えられています。
更年期を迎える女性は、女性ホルモンの減少により、内臓脂肪が蓄積しやすく、インスリン抵抗性が高まりやすくなるため注意が必要です。40歳を過ぎたら、定期的な健康診断を受け、血糖値やHbA1c、血圧、脂質などの数値を確認しましょう。
運動不足が続いている
運動は筋肉がブドウ糖を取り込むのを助け、血糖値を下げる効果があります。インスリンの働きを良くし、肥満やストレスの予防にもつながります。1日30分程度のウォーキングなど、軽い運動でも効果があります。日常生活の中で、こまめに体を動かす習慣を身につけましょう。
エスカレーターではなく階段を使ったり、一駅分歩いたり、電車では座らずに立つなど、できることから始めてみましょう。
ストレスが多い
ストレスは、交感神経を刺激し、血糖値を上昇させるホルモン(アドレナリンやコルチゾールなど)の分泌を促します。慢性的なストレスは、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病のリスクを高めます。ストレスによって暴飲暴食や睡眠不足になったり、運動量が減ったりすることも、糖尿病リスクを高める一因です。
ストレス解消には、自分自身に合った方法を見つけることが大切です。具体的な方法は以下のとおりです。
- リラックスできる時間を作る
- 趣味に没頭する
- アロマを焚く
- 好きな音楽を聴く
- 散歩をする
- ヨガや瞑想をする
- 家族や友人と過ごす
- ペットと触れ合う
- 自然の中で過ごす
- 好きな映画やドラマを観る
- 読書をする
日本で行われた地域ベースのプログラムの研究では、高リスク群への標準化された健康カウンセリングは、クリニック受診を促し、血圧、HbA1c、LDLコレステロールの低下につながったと報告されています。専門家による適切な指導とサポートが、生活習慣病の予防に効果的であることを示唆しています。
自分一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることも検討してみましょう。
糖尿病の進行や日々のストレスによって心臓に負担がかかる場合、不整脈などの異常が隠れていることもあります。以下のページでは、心臓の状態を確認する基本的な検査について解説しています。
糖尿病の4つの予防策
糖尿病の予防策について以下の4つを解説します。
- 食生活の改善
- 適度な運動習慣の導入
- 適正体重の維持
- 定期的な健康診断の受診
食生活の改善
バランスの良い食事を摂ることは、血糖値のコントロールだけでなく、健康全般を維持するために不可欠です。野菜を豊富に摂取し、主食であるご飯やパン、麺類などの炭水化物の量を調整し、脂っこい食事は控えめにしましょう。
厚生労働省は、1日350g以上の野菜摂取を推奨しています。野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、血糖値の上昇を緩やかにする効果も期待できます。炭水化物の過剰摂取は血糖値を急上昇させる原因となります。白米やパン、麺類などの炭水化物は、適量を摂取するように心がけましょう。ご飯であれば150g前後が目安です。
揚げ物や脂身の多い肉などの高脂肪食は、肥満やインスリン抵抗性を促進する可能性があります。摂取頻度を減らし、代わりに魚や鶏肉のささ身、豆腐などの良質なタンパク質を摂取するように心がけましょう。
適度な運動習慣の導入
運動はインスリン感受性を高めるため、インスリンの働きが改善され、血糖コントロールが良好に保たれます。肥満予防にも効果的です。内臓脂肪が蓄積すると、インスリンの働きが阻害され、糖尿病のリスクが高まることが知られています。
週に数回、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などを継続的に行うようにしましょう。運動が苦手な方は、日常生活の中で体を動かす機会を増やすだけでも効果があります。意識的に体を動かす習慣を身につけることが大切です。
適正体重の維持
適正体重を維持するためには、バランスの良い食事と適度な運動が不可欠です。自分の身長に合った適正体重を把握し、体重管理を行いましょう。BMI(体格指数)は、肥満度を評価する指標として広く用いられています。BMIは、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算できます。
日本肥満学会では、BMIが25以上を肥満と定義しています。健康的なBMIの範囲は18.5~24.9です。
定期的な健康診断の受診
糖尿病は、初期段階ではほとんど自覚症状が現れないことが多く、気づかないうちに進行してしまうケースもあります。健康診断で血糖値やHbA1cの数値を定期的にチェックすることは、自覚症状が出る前に異常を見つけ、早期の対策につなげるために重要です。
健康診断の結果で異常値が見つかった場合は、放置せずにできるだけ早く医療機関を受診し、医師の指導に従うことが大切です。糖尿病予備群と診断された場合は、生活習慣の改善を積極的に行うことで、糖尿病の発症を予防できる可能性が高まります。
健康診断では、空腹時血糖値やHbA1c、随時血糖値などの検査項目をしっかり確認しましょう。検査結果を通じて自分の体の状態を客観的に把握し、医師からの具体的なアドバイスをもとに、効果的な予防対策を実践することが重要です。
まとめ
糖尿病は早期発見・早期治療が大切な病気です。血糖コントロールの状態や糖尿病のリスクを把握するため、健康診断では、以下の数値を確認しましょう。
- 空腹時血糖値
- HbA1c
- 経口ブドウ糖負荷試験
糖尿病の主なリスク要因は以下のとおりです。
- 肥満
- 家族歴
- 年齢
- 運動不足
- ストレス
生活習慣の改善方法として、以下のことに気をつけることで、糖尿病の予防につながります。
- 食生活の改善
- 適度な運動
- 適正体重の維持
- 定期的な健康診断
健康診断は、糖尿病のリスクに気づくための大切な機会です。未来の健康を守るために、できることから始めてみましょう。
血糖値を下げるためには、まずは日常生活の見直しが欠かせません。以下の記事では、血糖値改善に役立つ7つの具体的な方法について紹介していますので、生活習慣の見直しにぜひ役立ててください。
>>血糖値を下げる7つの効果が期待できる方法!生活習慣改善のポイント
参考文献
- HiroyasufIso, Midori Noguchi, Tetsuji Yokoyama, Toshiko Yoshida, Isao Saito, Ayumi Shintani, Toshimi Sairenchi, Hitoshi Nishizawa, Hironori Imano, Akihiko Kitamura, Iichiro Shimomura. Effect of a Community-Based Program to Accelerate Referral to Physicians for Individuals at High-Risk of Lifestyle-Related Diseases: A Cluster Randomized Trial. J Atheroscler Thromb, 2023, 30, 10, p.1389-1406
- 平成28年「国民健康・栄養調査」の結果,厚生労働省
- 栄養・食生活,厚生労働省
- 参考:食後のひどい眠気は糖尿病のサイン?眠気以外に注意すべき症状を解説
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







