blog
ブログ
健康診断で血糖値を指摘された場合、糖尿病である可能性があります。糖尿病は初期症状に気づきにくく、知らないうちに病気が進行しているケースが多い生活習慣病です。糖尿病には1型と2型があり、それぞれ原因や症状、治療法が大きく異なります。
この記事では、1型糖尿病と2型糖尿病の違いを解説し、特有の症状や治療法、そして共通の症状と治療法も紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、糖尿病の正しい知識を身につけて、健康管理に役立ててください。
大石内科循環器科医院では、糖尿病に関する検査と丁寧な診療を行っています。症状が気になる方はもちろん「ちょっと不安かも…」という段階でも、早めのチェックが何より大切です。地域のかかりつけ医として、あなたの健康を全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
1型糖尿病と2型糖尿病の違い
1型糖尿病と2型糖尿病の決定的な違いを以下の項目に沿って解説します。
- メカニズムの違い
- 原因の違い
メカニズムの違い
1型糖尿病と2型糖尿病の最も大きな違いは、体内でインスリンがどのように働いているかという点です。インスリンは、血液中のブドウ糖をエネルギー源として細胞に取り込む役割を果たすホルモンです。
1型糖尿病は、インスリンを生成する膵臓のβ細胞が、自身の免疫システムによって誤って攻撃され破壊されてしまいます。1型糖尿病は、自己免疫疾患の一つです。インスリンがほとんど、または全く作られなくなります。インスリンがないと、ブドウ糖は細胞の中に入れず、血液中に溢れてしまうため、高血糖を引き起こします。
2型糖尿病では、インスリン自体は作られていますが、働きが不十分な状態です。インスリンの分泌量が少なくなっている、あるいは細胞がインスリンのシグナルを受け取りにくくなっている(インスリン抵抗性)ことが原因です。どちらの場合も、ブドウ糖が細胞に取り込まれにくくなり、血液中に蓄積してしまいます。
原因の違い
1型糖尿病の主な原因は、自己免疫反応です。遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられていますが、詳細なメカニズムは現在も研究が進められています。ウイルス感染などが発症の引き金となる可能性も示唆されていますが、まだ解明されていない部分が多く残されています。
2型糖尿病の原因には、遺伝的要因と生活習慣の両方が関与していると考えられます。両親や兄弟姉妹に2型糖尿病の方がいる場合、遺伝的に発症リスクが高いと言えます。肥満や運動不足、偏った食事、過度の飲酒、喫煙などの生活習慣もリスクを高める要因です。加齢も大きなリスクの一つです。
治療を進めるうえでは、こうした生活習慣や加齢などの要因が血管に与えている影響を把握し、治療効果を評価することも重要です。血圧や血管の状態を確認する検査については、以下のページで解説しています。
肥満は単なる体重の増加だけでなく、生活習慣病や食習慣とも深く関係しています。以下の記事では、肥満の主な原因や、糖尿病をはじめとする健康リスク、そして予防・改善のための具体的な方法について詳しく解説しています。
>>肥満の原因とは?生活習慣病や食事との関係、リスクを減らす改善方法を解説
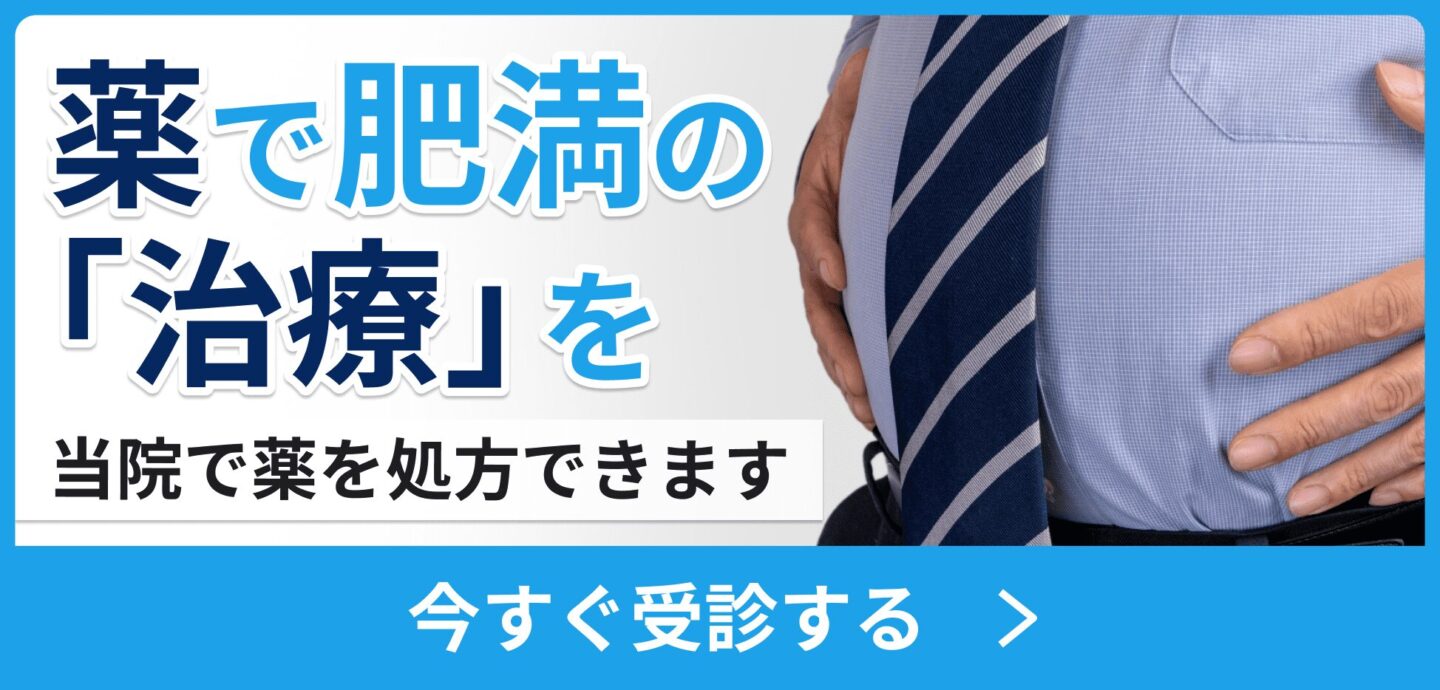
1型・2型に共通する糖尿病の症状
1型・2型に共通する糖尿病の症状は以下のとおりです。
- のどの渇き
- 頻尿
のどの渇き
のどの渇きは、糖尿病の典型的な症状の一つです。健康な状態では、血液中のブドウ糖は細胞に取り込まれ、エネルギー源として利用されます。しかし、糖尿病になると、インスリンの作用不足により、ブドウ糖が細胞に取り込めなくなります。結果、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が上昇します。
血糖値が上昇すると、高い血糖値を下げようとして、腎臓を通して血液中の過剰なブドウ糖を尿中に排出します。ブドウ糖を尿に排出する過程で、体内の水分も一緒に排出されてしまうため、脱水状態になり、強いのどの渇きを感じることが多いです。糖尿病によるのどの渇きは、水をたくさん飲んでも改善しづらい点が特徴です。
口の渇きや皮膚の乾燥を伴うこともあります。持続血糖モニタリング(CGM)と生態学的瞬間的評価を用いた研究では、高血糖時にはのどの渇きや頻尿を感じることが報告されています。
血糖値を下げるためには、まずは日常生活の見直しが欠かせません。以下の記事では、血糖値改善に役立つ7つの具体的な方法について紹介していますので、生活習慣の見直しにぜひ役立ててください。
>>血糖値を下げる7つの効果が期待できる方法!生活習慣改善のポイント
頻尿
頻尿も、糖尿病でよく見られる症状の一つです。糖尿病になると、余分な糖を尿として排出しようとするため、尿の量が増え、排尿の回数が増えます。特に、夜間に何度もトイレに起きる夜間頻尿は、糖尿病の初期症状としてよくみられます。
夜間頻尿は睡眠の質を低下させ、日中の倦怠感につながることもあるため、適切な処置が必要です。糖尿病による頻尿は、尿の量が多いことに加えて、尿に糖が含まれているため、独特の甘い臭いがすることがあります。尿から甘い臭いがする場合は、糖尿病の可能性も考慮し、医療機関に相談することが重要です。
1型糖尿病に特有の症状
1型糖尿病に特有の症状は以下のとおりです。
- 急激な体重減少
- ケトアシドーシス
急激な体重減少
1型糖尿病の患者さんは、発症後、数週間〜数か月の間に急激な体重減少を経験することがあります。インスリン不足によってブドウ糖がエネルギー源として利用できず、体が脂肪を分解してエネルギーを産生しようとするためです。
急激な体重減少は、1型糖尿病の初期症状として現れることが多いです。5〜10kgといった短期間での大きな体重減少は、体に何らかの異常が起きているサインの可能性があります。体重減少以外にも、空腹感の増加や倦怠感、脱力感などの症状が現れることもあります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
ケトアシドーシス
ケトアシドーシスは、1型糖尿病でみられる重篤な合併症です。インスリンが不足すると、体はエネルギー源として脂肪を分解し始め、ケトン体と呼ばれる物質が生成されます。ケトン体は酸性であるため、血液中に過剰に蓄積されると血液が酸性に傾き、ケトアシドーシスと呼ばれる状態を引き起こします。
ケトアシドーシスの症状は、吐き気や嘔吐、腹痛、倦怠感などです。呼吸が速くなったり、意識がもうろうとしたりするなど、重篤な症状が現れる場合もあります。ケトアシドーシスは、放置すると昏睡状態に陥り、命に関わる危険な状態となる可能性があります。症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。
ケトアシドーシスは、適切なインスリン治療を行うことで予防できます。1型糖尿病と診断された患者さんは、医師の指示に従ってインスリン療法を継続し、血糖コントロールを良好に保つことが重要です。定期的な血液検査でケトン体の量を測定することで、ケトアシドーシスの早期発見にもつながります。
糖尿病が引き起こす影響は感染症だけでなく、心臓や血管のトラブルにも及びます。以下の記事では、糖尿病による心臓・血管へのリスクや、その予防法について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
2型糖尿病に特有の症状
2型糖尿病に特有の症状は以下のとおりです。
- 疲労感
- 皮膚のかゆみ
疲労感
疲労感は2型糖尿病の代表的な症状です。健康な状態では、食事から摂取した糖分がエネルギーに変換され、活動するための力となります。2型糖尿病の場合、糖分をエネルギーとして効率的に利用できないため、エネルギー不足の状態に陥り、疲労感を感じやすくなります。
疲労感の具体例として、以下の症状が挙げられます。
- 朝起きても疲れが取れない
- 日中も体がだるい
- 集中力が続かない
Hermannsらの研究では、持続血糖モニタリングと生態学的瞬間的評価を用いて糖尿病患者の症状を分析しました。結果、高血糖時に疲労感の症状スコアが高いことが報告されており、高血糖と疲労感の関連性が示唆されています。
皮膚のかゆみ
2型糖尿病では、高血糖によって血液の粘度が上昇し、血流が悪化することで、皮膚への酸素や栄養の供給が不足し、乾燥しやすくなります。乾燥した皮膚はバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなるため、かゆみの原因です。高血糖は、皮膚の常在菌のバランスを崩し、炎症を引き起こす原因にもなります。
かゆみは全身に現れることもありますが、特に下肢や肛門周囲など、汗・分泌物が溜まりやすい部位に症状が現れやすいです。我慢できずに掻きむしってしまうと、皮膚が傷つき、細菌感染を引き起こすリスクが高まるため、適切な対処が必要です。かゆみが続く場合は、自己判断で市販薬を使用せず、医療機関を受診してください。
1型・2型に共通する糖尿病の治療法
1型・2型に共通する糖尿病の治療法は以下のとおりです。
- 食事療法
- 運動療法
- ストレス管理
食事療法
食事療法は、糖尿病治療の基盤となる重要な要素です。1型、2型どちらの糖尿病においても、血糖値の急激な上昇を抑える食事を心がけることが重要です。炭水化物(ご飯、パン、麺類、イモ類、砂糖など)は血糖値を上昇させやすい栄養素であるため、摂取量に注意しましょう。
1日に必要なエネルギー量は、年齢や性別、身体活動量などによって異なります。医師や栄養士と相談し、ご自身に適したエネルギー量を把握したうえで、栄養バランスの良い食事を摂ることが大切です。主食・主菜・副菜をそろえ、野菜やきのこ、海藻などを積極的に摂りましょう。食物繊維は、糖の吸収を穏やかにする効果が期待できます。
外食や旅行の際にも、血糖値コントロールを意識したメニュー選びを心がけましょう。丼ものや麺類よりも、定食を選ぶと、栄養バランスが整いやすくなります。ご飯の量を少なめにする、野菜を先に食べるなど、工夫次第で血糖値の上昇を抑えられます。
果物はビタミンやミネラルが豊富ですが、果糖が含まれているため、一度にたくさん食べるのではなく、量を調整しましょう。
運動療法
適度な運動は、血糖値の低下に役立ちます。1型、2型どちらの糖尿病でも、無理のない範囲で運動を継続することが大切です。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪を燃焼し、インスリンの働きを良くする効果が期待できます。週に150分を目標に、1回30分程度の運動を、週5日程度行うのが理想的です。
スクワットや腕立て伏せなどの筋力トレーニングもおすすめです。筋肉量が増えると、基礎代謝が上がり、血糖値が安定しやすくなります。筋トレは週2〜3回行いましょう。運動を始める前には、必ず医師に相談し、ご自身の体調に合わせた適切な運動の種類や強度、時間などを決めましょう。
低血糖を起こしやすい方は、運動前に血糖値を測定し、必要に応じて補食を摂ってください。
ストレス管理
ストレスは、血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促すため、糖尿病の悪化要因の一つと考えられています。ストレスをうまく管理することは、1型、2型どちらの糖尿病にとっても重要です。ストレスを軽減するためには、リラックスできる時間を作る、趣味を楽しむなど、自分なりの方法を見つけることが大切です。
悩みや不安を抱えている場合は、一人で抱え込まずに、家族や友人、医療従事者に相談することも有効です。交流会に参加する、地域の相談窓口を利用するなど、他の患者さんとつながることで、精神的なサポートを得られることもあります。
ご自身の生活リズムや性格に合ったストレス解消法を見つけて、心身ともに健康な状態を保ちましょう。
糖尿病の進行や日々のストレスによって心臓に負担がかかる場合、不整脈などの異常が隠れていることもあります。以下のページでは、心臓の状態を確認する基本的な検査について解説しています。
1型糖尿病の治療法:インスリン療法
インスリン療法は、1型糖尿病とともに生きるうえで欠かせません。適切なインスリン療法を行うことで、血糖値をコントロールし、合併症を予防することが期待できます。インスリン療法は、不足しているインスリンを外部から補うことで、血糖値を正常な範囲に保つ治療法です。
インスリン製剤には、効果の発現時間や持続時間によっていくつかの種類があります。大きく分けると、食事の前に注射する「超速効型」インスリンと、1日に1回または2回注射する「持続型インスリン」があります。
超速効型インスリンは、食後に血糖値が急上昇するのを抑えるために使用します。一方、持続型インスリンは、1日を通して基礎となるインスリンを補給し、血糖値を安定させる役割を果たします。
インスリンの注射方法は、インスリンペンや注射器を用いて皮下に注射する方法が一般的です。注射部位は、お腹や太もも、上腕など、皮下脂肪の厚い場所を選びます。一定の速度で持続的にインスリンを注入するインスリンポンプを使用する方法もあります。
血糖値の正常範囲を正しく知っておくことも重要です。以下の記事では、血糖値の基準値や、異常値が引き起こす健康リスク、そして日常生活でできる対策について詳しく解説していますので、参考にしてください。
>>血糖値の正常範囲とは?異常値が引き起こすリスクと対策を解説
2型糖尿病の治療法:GLP-1受容体作動薬
2型糖尿病の治療では、食事療法と運動療法だけで十分な血糖コントロールができない場合、薬物療法を検討します。薬物療法にもさまざまな選択肢があり、代表的なものがGLP-1受容体作動薬です。GLP-1受容体作動薬は、体内で自然に分泌されるホルモンであるGLP-1と似た働きをする薬です。
GLP-1は、食事を摂ると腸から分泌され、膵臓からのインスリン分泌を促進する働きがあります。食事をしたときに適切な量のインスリンが分泌されるようにサポートすることで、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。GLP-1受容体作動薬は注射薬ですが、注射針は細く、痛みはほとんど感じません。
製剤の種類も豊富で、毎日注射するもの、週に1回注射するものなど、患者さんのライフスタイルや治療状況に合わせて選択できます。食欲抑制効果もGLP-1受容体作動薬の特徴です。GLP-1受容体作動薬の副作用は、吐き気や嘔吐、下痢、便秘などです。症状が強い場合や長引く場合は、医師に相談しましょう。
GLP-1受容体作動薬は、医師の指示のもとで使用することが大切です。自己判断で服用を中止したり、量を変えたりすることは避けてください。
まとめ
1型糖尿病・2型糖尿病はどちらも血糖値が高い状態ですが、原因や治療法が異なります。1型は自己免疫疾患でインスリンを産生できないため、インスリン注射が必須です。急激な体重減少がある場合は、1型糖尿病が疑われます。2型は生活習慣が大きく影響し、食事療法、運動療法に加え、進行した場合は薬物療法が必要です。
疲労感や皮膚のかゆみが現れた場合は、2型糖尿病の可能性があるため、日ごろの生活習慣を見直しましょう。糖尿病は早期発見・早期治療が大切です。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
当院でも糖尿病の診療を行っており、お悩みの方のご相談を受け付けております。以下の記事では糖尿病の症状や合併症、インスリンや血糖値の関係などについて詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
>>糖尿病について
参考文献
Norbert Hermanns, Dominic Ehrmann, Bernhard Kulzer, Laura Klinker, Thomas Haak, Andreas Schmitt. Somatic and mental symptoms associated with dysglycaemia, diabetes-related complications and mental conditions in people with diabetes: Assessments in daily life using continuous glucose monitoring and ecological momentary assessment. Diabetes Obesity and Metabolism, 2025, 27(1), p.61-70.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







