blog
ブログ
若年性糖尿病は増加傾向にあり、決して他人事ではありません。免疫の異常や遺伝、生活習慣の乱れなどさまざまな要因が複雑に絡み合っています。のどの渇きや頻尿、体重減少などの症状は、放置すれば合併症を引き起こす可能性もあります。糖尿病は早期発見、早期治療が重要とされています。
この記事では、20代で糖尿病になる原因や症状、予防、治療法について解説します。糖尿病に対する正しい知識を身につけ、発症リスクを減らしましょう。
大石内科循環器科医院では、糖尿病に関する検査と丁寧な診療を行っています。症状が気になる方はもちろん「ちょっと不安かも…」という段階でも、早めのチェックが何より大切です。地域のかかりつけ医として、あなたの健康を全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
20代で糖尿病になる原因
20代で糖尿病になる原因については以下のとおりです。
- 自己免疫疾患(1型糖尿病の場合)
- 遺伝的要因
- 肥満
- エナジードリンクなどの摂りすぎ
- 過度なストレス
- MODY(若年発症成人型糖尿病)
自己免疫疾患(1型糖尿病の場合)
1型糖尿病は、免疫システムが誤って膵臓のβ細胞を攻撃し破壊することが原因で起こります。通常、免疫システムは、細菌やウイルスなど外敵だけを攻撃しますが、1型糖尿病は自分の体の一部であるβ細胞を攻撃します。インスリンは、血糖値を下げる大切なホルモンで、食事から得た糖分を体に取り込む手助けをします。
β細胞が破壊されるとインスリンが作られず、高血糖の状態が続きます。なぜ免疫システムがβ細胞を攻撃するのか、メカニズムは完全には解明されていません。
遺伝的要因
家族に糖尿病の方がいる場合、糖尿病になりやすい体質を持っている可能性があります。糖尿病の発症に関わる遺伝子を引き継いでいることが、理由の一つと考えられています。遺伝の影響の現れ方は、糖尿病の種類によって異なります。
MODY(若年発症成人型糖尿病)では、特定の遺伝子異常が原因で起こり、10〜20代など若い世代に発症することがあります。2型糖尿病はいくつかの遺伝子の組み合わせに加え、食生活の乱れや運動不足など生活習慣が重なることで発症することがわかっています。
遺伝的な要因があったとしても、健康的な生活習慣を続けることで、糖尿病の発症時期を遅らせたり、症状を軽くしたりすることは可能です。家族に糖尿病の方がいる場合は、早い段階から生活習慣を見直し、予防に取り組むことが大切です。
肥満
肥満は、2型糖尿病の大きなリスク要因の一つです。食べすぎや運動不足によって内臓脂肪が蓄積されると、インスリンの働きが悪くなります。インスリン抵抗性と呼ばれ、細胞がインスリンに反応しにくくなる状態です。インスリン抵抗性が起こると、血糖値を下げるために通常よりも多くのインスリンが必要になります。
初期段階では、膵臓はより多くのインスリンを分泌し、血糖値を正常範囲に維持しようとします。膵臓が過剰なインスリン分泌を長期間続けることができなくなると、高血糖状態が続き、糖尿病へと進行します。
若い世代であっても、高血糖の状態が続くことで血管への負担が蓄積されている場合があります。治療を進めるうえでは、現在の血管の状態を客観的に把握し、評価することも重要です。血圧や血管の状態を確認する検査については、以下のページで解説しています。
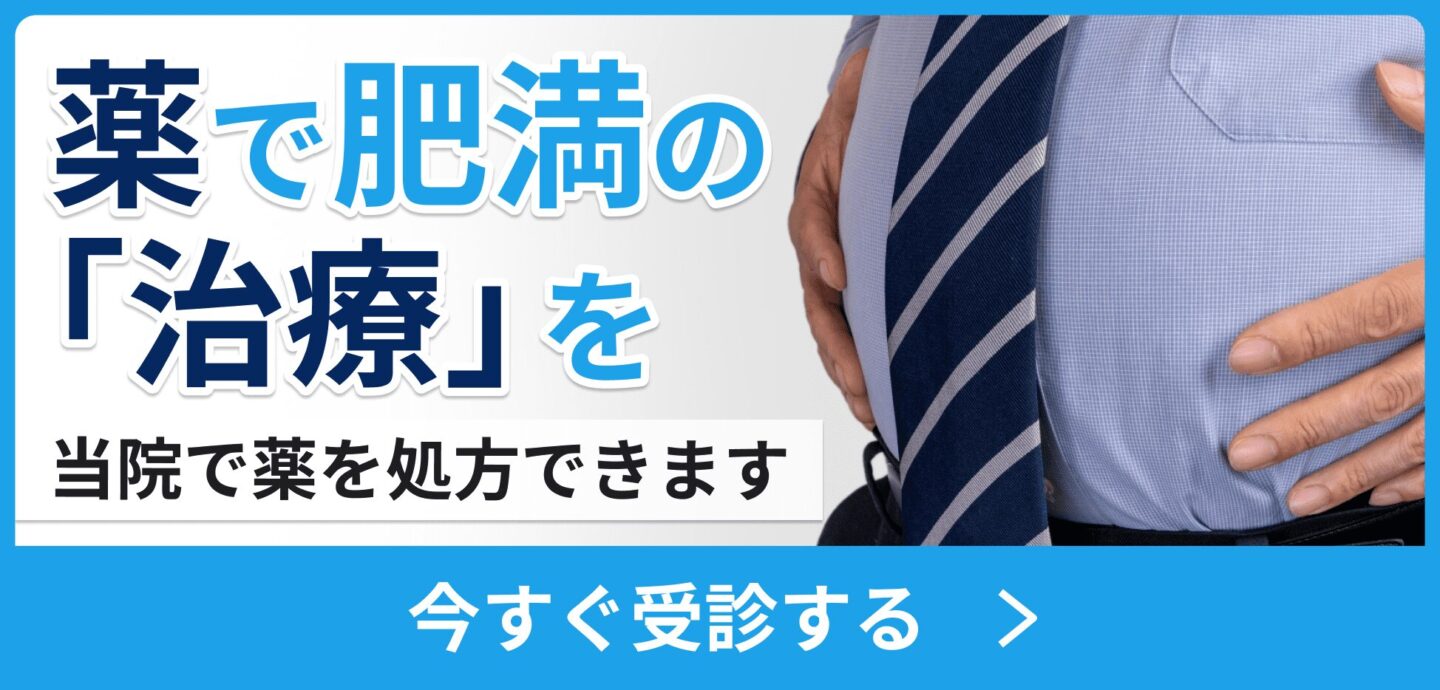
エナジードリンクなどの摂りすぎ
エナジードリンクや清涼飲料水には、大量の糖分が含まれます。エナジードリンクなどを日常的に摂りすぎると、血糖値が急激に上昇し、膵臓に大きな負担がかかります。膵臓に大きな負担がかかると、インスリンを分泌する能力が低下し、糖尿病のリスクを高める可能性があります。
糖分の過剰摂取は肥満にもつながり、インスリン抵抗性を引き起こす悪循環に陥ることがあります。清涼飲料水には100mlあたり約10gの糖分が含まれ、500mlでは角砂糖約12個分に相当します。血糖値を良好に保つには、飲み物の選び方にも注意が必要です。
過度なストレス
強いストレスを感じ続けると、コルチゾールなどの血糖値を上げるホルモンが分泌されやすくなります。慢性的なストレスに長期間さらされると、血糖値が高い状態が続き、糖尿病の発症リスクを高める可能性があります。ストレスは自律神経のバランスを崩し、交感神経を優位にさせます。
交感神経が優位になると、肝臓から糖が放出されやすくなり、血糖値が上昇しやすくなります。ストレスは食欲を増進させるホルモンの分泌も促進するため、過食につながりやすく、間接的に糖尿病のリスクを高める可能性もあります。
MODY(若年発症成人型糖尿病)
MODY(若年発症成人型糖尿病:Maturity-Onset Diabetes of the Young)は、遺伝子変異が原因で起こる糖尿病の一種です。遺伝子の種類によって症状や重症度は異なりますが、多くの場合、25歳以下で発症します。MODYは、他の糖尿病と症状が似ているため誤診されることもあり、2型糖尿病と診断されるケースが多くみられます。
MODYはインスリン分泌機能低下が主な原因であるため、薬物療法が必要になる場合があります。正確な診断のためには、遺伝子検査が必要です。
若年性糖尿病の症状
若年性糖尿病の症状は以下のとおりです。
- のどの渇き
- 頻尿
- 体重減少
- 倦怠感
- 皮膚のかゆみ
のどの渇き
のどの渇きは、糖尿病の代表的な初期症状の一つです。血糖値が高くなると、体は水分で薄めようとします。細胞内の水分が血管内に移動し、浸透圧を調整しようと働くため、のどが渇き、水分を多く摂るようになります。体内の水分が不足すると現れる症状は、以下のとおりです。
- いつもより多くの水分を摂取する
- 夜中に何度もトイレに起きる
- 口の中が乾く
- 肌が乾燥する
頻尿
糖尿病になると、血液中の過剰な糖分を体外に排出するために、腎臓がより多くの尿を作ります。尿の量が増加するとトイレに行く回数が増え、夜間のトイレの回数が増加します。夜間多尿と呼ばれ、睡眠不足を引き起こし、日中の倦怠感や集中力の低下につながることもあります。
健康な腎臓は、血液中の老廃物を濾過(ろか)し尿として排出します。体内に必要なブドウ糖は再吸収され血液中に戻ります。糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、腎臓の再吸収能力を超え、ブドウ糖が尿中に排出されます。ブドウ糖と一緒に水分も排出されるため、尿量が増加し頻尿となります。
体重減少
糖尿病の症状の一つに体重減少があります。インスリンが正常に働かず、ブドウ糖がエネルギーとして利用されにくくなり、エネルギー不足となります。エネルギー不足を補うため、体は脂肪や筋肉を分解し始め、体重減少につながります。急激な体重減少は糖尿病のサインである可能性があります。
倦怠感
糖尿病はブドウ糖をうまく利用できないため、細胞がエネルギー不足に陥り、倦怠感や疲労感を引き起こします。十分な睡眠をとっていても、常に疲れていたり、体がだるかったりなどの状態が続く場合は、糖尿病の可能性があります。慢性的な疲労感や倦怠感を覚える場合は、医療機関に相談しましょう。
若年性糖尿病の進行によって心臓に負担がかかっている場合、動悸などの症状が現れることもあります。現在の心臓の状態を詳しく確認し、評価することは健康を守るうえで大切です。以下のページでは、心臓の状態を確認する基本的な検査について解説しています。
皮膚のかゆみ
高血糖の状態が続くと、皮膚が乾燥し、かゆみを感じやすくなります。血液の浸透圧が高くなり、皮膚の水分が血管内に移動するからです。乾燥した皮膚はバリア機能が低下するため、外部からの刺激を受けやすく、かゆみが増悪する悪循環に陥ることもあります。
高血糖は末梢神経を損傷し、神経障害を引き起こす可能性があります。神経障害は、皮膚の感覚異常や痛み、かゆみを引き起こします。糖尿病によって血行が悪くなると、皮膚への栄養供給が不足し、皮膚の抵抗力が低下します。皮膚のかゆみは、糖尿病の合併症の一つである可能性があるため、医療機関を受診することが大切です。
糖尿病は、心臓や血管にも深刻なリスクを及ぼすことがあります。以下の記事では、糖尿病による心血管系の合併症とその予防策について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
若年性糖尿病を防ぐ対策
若年性糖尿病を防ぐための対策は、以下のとおりです。
- 糖分を含む飲み物を減らす
- 低GI食品を多く摂取する
- 適度に運動する
- アルコールを控える
糖分を含む飲み物を減らす
糖分を含む飲み物を避け、水やお茶、無糖のコーヒーなどを飲む習慣を身につけましょう。喉の渇きを潤すだけでなく、体への負担を軽減し、健康維持にもつながります。野菜ジュースやフルーツジュースには、多くの糖分が含まれる場合があります。ジュースを選ぶ際は、糖質の量を確認しましょう。
低GI食品を多く摂取する
GI値とは、血糖値を上昇させるスピードを示す指標です。白米やパン、うどん、じゃがいもなどはGI値が高い食品です。GI値が高い食品を摂取すると、血糖値が急上昇し、膵臓が過剰にインスリンを分泌する必要があります。GI値が低い食品の例は以下のとおりです。
- 玄米
- 全粒粉パン
- そば
- さつまいも
低GI食品は、食物繊維が豊富に含まれていることが多く、腸内環境を整える効果も期待できます。腹持ちが良いというメリットもあり、食べすぎを防ぐことにもつながります。白米を玄米に、食パンを全粒粉パンに置き換えるなど、食事を工夫することで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待されます。
1型糖尿病の若年者を対象とした研究では、低炭水化物食と地中海式食事は、低血糖などのリスク因子を増やすことなく、血糖値の改善を示しました。
食生活の見直しをはじめ、日常的に取り入れられる工夫を知っておくことが血糖値管理の鍵となります。以下の記事では、血糖値を下げるために効果が期待できる7つの生活習慣改善法について、具体的に解説していますので、ぜひ参考にしてください。
>>血糖値を下げる7つの効果が期待できる方法!生活習慣改善のポイント
適度に運動する
適度な運動は、インスリンの働きを改善し、血糖値のコントロールに役立ちます。激しい運動の必要はなく、ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳など、無理なく続けられる運動を取り入れましょう。1日30分程度の有酸素運動や週に2回程度の筋力トレーニングを行うと、基礎代謝を高める効果も期待できます。
アルコールを控える
糖尿病予防のためには、アルコールの摂取量を控えることが重要です。アルコールにはカロリーが多く含まれるため、肥満のリスクも高まります。過度の飲酒は、血糖コントロールを乱し、糖尿病の悪化につながる可能性があります。アルコールは、肝臓での糖新生(とうしんせい)を阻害し、低血糖を引き起こす可能性もあります。
糖新生とは、肝臓がブドウ糖を作り出す働きのことです。飲酒する場合は、少量にとどめ、空腹時は避けましょう。お酒の種類によっても血糖値への影響が異なるため、医師や栄養士に相談し、適切な飲酒量を守ることが大切です。
低血糖と似たような注意が必要な状態として「血糖値スパイク」があります。血糖値スパイクは食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する現象で、放置すると動脈硬化や心血管疾患のリスクを高めるとされています。以下の記事では、血糖値スパイクの詳しい症状や健康リスク、予防するための具体的な対策について解説していますので、あわせてご覧ください。
>>血糖値スパイクの症状と健康リスク!知っておくべき対策法
若年性糖尿病の治療法
若年性糖尿病の治療法については以下のとおりです。
- インスリン療法
- 経口血糖降下薬
インスリン療法
1型糖尿病の場合、体内でインスリンが作られないため、インスリン注射によって補う必要があります。インスリン注射は、血糖をコントロールし、合併症を防ぐ大切な治療です。適切なインスリン療法を行うことで、健康な人に近い生活を目指すことが可能です。
2型糖尿病でも、食事療法や運動療法、経口血糖降下薬で血糖コントロールが不良の場合、インスリン療法を行うことがあります。インスリン療法には、ペン型の注射器やインスリンポンプ(インスリンを継続的に体内に供給する小型のポンプ)などがあります。医師は患者さんの生活スタイルや病状に合わせて適切な投与方法を決定します。
経口血糖降下薬
2型糖尿病の初期治療では、経口血糖降下薬が用いられる場合があります。経口血糖降下薬は、膵臓からのインスリン分泌を促進したり、肝臓での糖新生を抑制したり、インスリンの働きを高める作用があります。経口血糖降下薬には、スルホニルウレア薬(SU薬)やビグアナイド薬、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬などの種類があります。
医師は、患者さんの病状や他の病気の有無、服用している薬などを考慮し、副作用に配慮しながら適切な薬を選択します。経口血糖降下薬の副作用は以下のとおりです。
- 低血糖
- 胃腸障害
- 体重減少
副作用が強い場合や効果が不十分な場合は、医師に相談して薬の種類や量を変更する必要があります。
まとめ
20代で糖尿病になる原因には、1型糖尿病や遺伝、肥満、糖分の過剰摂取、ストレス、MODYなど、さまざまな要因が関係しています。予防や対策として、糖分を含む飲み物を控えることや低GI食品を積極的に取り入れること、適度な運動を続けることなどが大切です。治療法には、インスリン療法や経口血糖降下薬などがあり、病状や生活習慣に合わせた治療が必要です。
糖尿病は適切な治療と生活習慣の見直しにより、コントロールすることが期待できる疾患です。一人で悩まず、医師や医療スタッフに相談しながら、健康的な生活を目指しましょう。
以下の記事では、糖尿病による心血管系の合併症とその予防策について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
>>糖尿病による合併症リスク|心臓と血管に与える影響と対策方法
参考文献
- Neriya Levran, Noah Levek, Noah Gruber, Arnon Afek, Efrat Monsonego-Ornan, Orit Pinhas-Hamiel. Low-carbohydrate diet proved effective and safe for youths with type 1 diabetes: A randomised trial. Acta Paediatrica, 2025, 114, 2, p.417-427
- Laura S Hoffman, Tamaryn J Fox, Catherine Anastasopoulou, Ishwarlal Jialal. Maturity Onset Diabetes in the Young. StatPearls [Internet], 2025
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







