blog
ブログ
「少し歩いただけで息切れする」「年齢のせいだと思って我慢している」。そんな症状の裏に、実は心不全や肺の病気など命に関わる疾患が隠れていることがあります。加齢による体力低下やストレスなども原因になりますが、息切れは体からのSOSである可能性を見逃せません。
この記事では、高齢者に多い息切れの原因や受けるべき検査・治療法、毎日の生活でできる工夫まで解説します。息切れの正体を理解することで、不安を和らげて、安心して過ごすためのヒントを見つけることができます。
静岡市で息切れにお悩みの方は、大石内科循環器科医院へご相談ください。当院では循環器専門医が心電図や超音波検査、血液検査などを用いて原因を丁寧に調べ、必要に応じた治療や生活改善をサポートします。
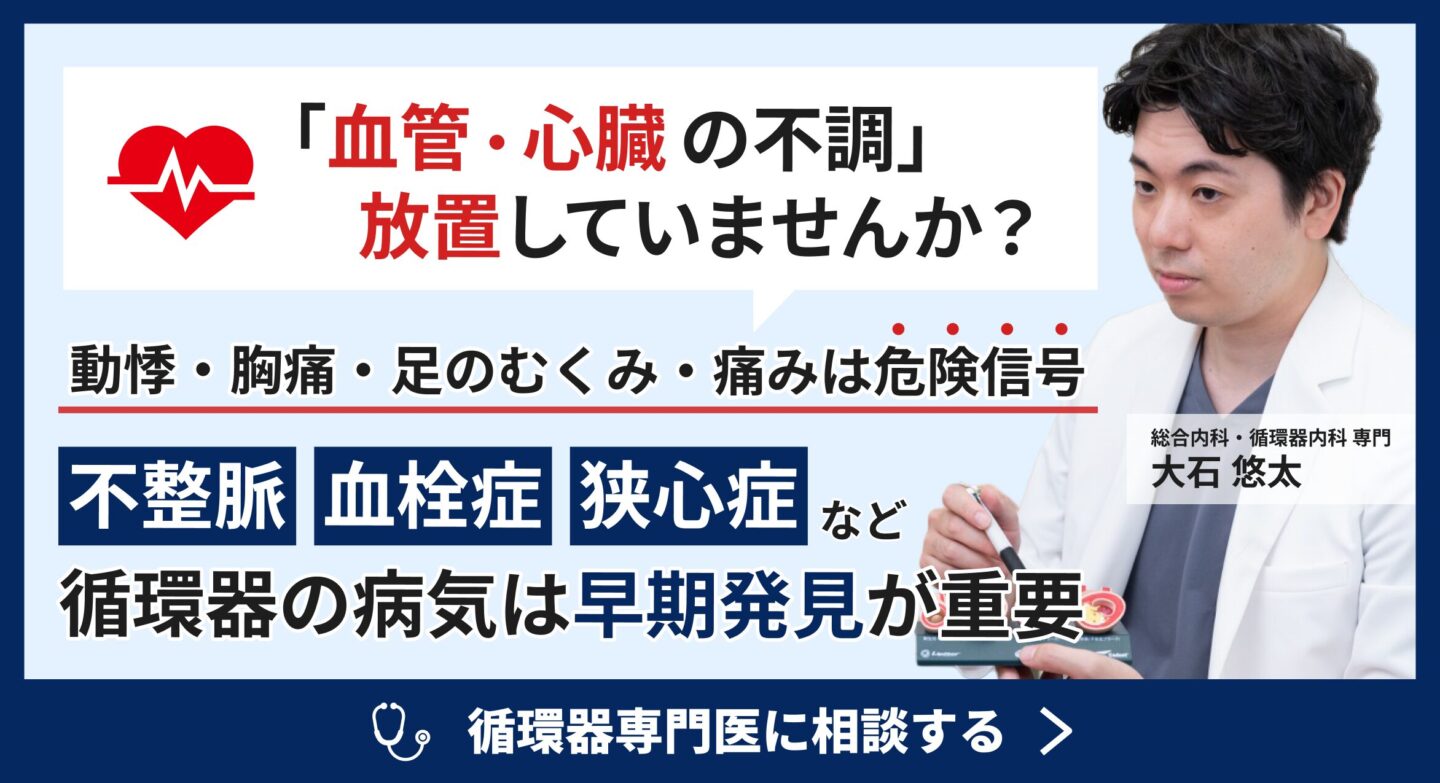
高齢者の息切れを引き起こす主な原因
息切れは、体が「酸素が足りないよ」と教えてくれるサインです。その裏には、治療が必要な病気が隠れている可能性もあります。高齢者の息切れの主な原因は以下の5つです。
- 心臓の病気:心不全・狭心症・不整脈など
- 肺の病気:COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺炎・間質性肺炎など
- 心臓・肺以外の病気:貧血・腎臓病・甲状腺疾患など
- 加齢による筋力低下やフレイル
- ストレスや不安による心因性の息切れ
心臓の病気:心不全・狭心症・不整脈など
心臓の病気は高齢者の息切れの代表的な原因であり、放置すれば命に関わることがあります。心臓は全身に血液を送るポンプの役割を担っており、その機能が低下すると酸素が足りなくなり、息切れとして現れます。特に、運動や坂道・階段で強く感じやすいのが特徴です。
主な病気と症状の特徴は次のとおりです。
- 心不全:動くと息苦しい、夜間横になると咳や苦しさが出る、足のむくみ
- 狭心症・心筋梗塞:胸の圧迫感や痛みを伴う息切れ、冷や汗や肩の痛み
- 不整脈:脈が速くなる・飛ぶとともに息苦しい、めまいや意識が遠のく感覚
なかでも不整脈の一種である発作性上室性頻拍(PSVT)は、持病のない方でも突然脈が速くなり、動悸・息切れ・胸の痛みを伴います。一般人口の約1000人あたり2〜3人が経験するとの報告もあり、珍しい病気ではありません。
心臓の病気が疑われる場合、原因や重症度を正確に把握するためには、いくつかの検査が重要になります。特に、心臓の動きや血液の流れを直接確認できる検査は、心不全や不整脈、狭心症の評価に欠かせません。以下の記事では、心臓の状態を詳しく調べる代表的な検査について、目的やわかることを解説しています。
肺の病気:COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺炎・間質性肺炎など
肺の働きが損なわれると、酸素を十分に取り込めなくなり、強い息切れが生じます。特に慢性疾患から感染症、急性の重症病まで幅広く関係するため、早めの対応が重要です。代表的な病気と特徴は、以下のとおりです。
- COPD(慢性閉塞性肺疾患):咳や痰・動作時の息切れ、進行がゆっくり
- 肺炎:発熱・咳・色つき痰・胸痛を伴う強い息苦しさ
- 間質性肺炎:肺が硬くなり膨らみにくくなる、空咳や息切れ
- 肺塞栓症:肺の血管が詰まる、急に激しい息切れを起こす危険な病気
これらは症状や経過が異なるものの、いずれも放置すると重症化します。息切れが日常的に続いたり急に悪化したりした場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
以下の記事では、胸の痛みを部位ごとに分けて原因や考えられる病気について解説しています。
>>胸が痛い!痛む場所(左・右・真ん中)による原因や病気の可能性を解説
心臓・肺以外の病気:貧血・腎臓病・甲状腺疾患など
息切れの原因は心臓や肺だけでなく、全身のさまざまな臓器に隠れていることがあります。貧血では酸素を運ぶヘモグロビンが不足し、全身が酸素不足に陥って息切れや動悸が起こります。腎臓病では余分な水分が体にたまり、肺に水がしみ出して肺水腫を起こし、呼吸が苦しくなるほか、貧血を悪化させることもあります。
さらに甲状腺機能亢進症では代謝が異常に高まり、心臓に負担がかかって息切れが生じます。顔色の悪さ、むくみ、動悸などの症状も合わせて現れるため、軽視せず受診することが大切です。
これらの病気が疑われる場合、原因となる臓器の状態を正確に確認する検査が重要になります。特に甲状腺は、ホルモンの分泌異常が全身症状として現れやすく、息切れや動悸の原因を見極めるうえで評価が欠かせません。
以下のページでは、甲状腺の形や腫れ、しこりの有無などを調べる検査について詳しく解説しています。
加齢による筋力低下やフレイル
大きな病気がなくても、加齢に伴う筋力の低下は息切れの大きな原因になります。年齢を重ねると、手足だけでなく横隔膜や肋間筋などの呼吸筋も衰え、呼吸が浅く速くなります。そのため、少し動いただけでも息が上がりやすくなるのです。
特に次のような状態が重なると「フレイル(虚弱)」のサインであり注意が必要です。
- 食が細く栄養状態が良くない
- 外出の機会が減り体を動かさなくなった
- 半年で2〜3kg体重が減った
フレイルは単なる体力低下ではなく、転倒や病気のリスクを高めます。息切れが「年のせい」と思える場合でも、生活習慣や体調を振り返り、早めの対策をとることが大切です。
以下の記事では、動悸で病院を受診する目安や検査・治療の流れを詳しく解説しています。
>>動悸で病院に行くタイミングはいつ?受診の目安や検査、治療の流れ
ストレスや不安による心因性の息切れ
体に異常がなくても、強いストレスや不安が息切れを引き起こすことがあります。自律神経のバランスが乱れると、呼吸が浅く速くなり「息が苦しい」と感じるのです。心因性の息切れには、次のような特徴があります。
- 安静時でも突然息苦しくなる
- 息が吸えない、空気が足りないと感じる
- めまい、動悸、手足のしびれを伴うことがある
- 検査で体に異常が見つからない
まずは心臓や肺の病気がないか確認することが大切です。そのうえで不安が強い場合は心療内科など専門的なケアを受けることで、安心して日常生活を送れるようになります。
以下の記事では、動悸の症状に応じた具体的な対処法や、普段から気をつけたいポイントを解説しています。
>>動悸の対処法を症状別に解説!自宅でできる応急処置と普段から気をつけたいポイント
息切れを診断する主な検査
息切れを診断する主な検査として、以下の4つを解説します。
- 胸部X線(レントゲン)
- 心電図
- 血液検査
- 呼吸機能検査
胸部X線(レントゲン)
胸部X線は、心臓や肺の状態を一目で確認できる基本的な検査です。胸にX線をあてて影を写し出すことで、心臓・肺・血管の異常を幅広くチェックできます。胸部X線では、主に次の点を確認します。
- 心臓が大きくなっていないか(心拡大)
- 肺に水がたまっていないか(肺水腫)
- 肺炎や肺気腫などの有無
シンプルで短時間に行えるため、胸の症状があるときに実施される基本検査の一つです。
心電図
心電図は、心臓の電気的な動きを記録し、不整脈や狭心症・心筋梗塞の兆候を調べる基本的な検査です。手足や胸に電極を貼り、拍動に伴って発生する微弱な電気信号を波形として記録します。これにより、脈が速すぎたり乱れたりする「不整脈」の有無や種類を詳しく確認できます。
動悸を伴う息切れの場合、突然脈が速くなる発作性上室性頻拍などを見つけるために重要です。検査は安静時に行うのが一般的ですが、体を動かしながら記録する「運動負荷心電図」を用いることもあります。短時間で痛みもなく、心臓病の早期発見に欠かせない検査です。
心電図検査や運動負荷心電図については、それぞれの検査の目的や流れ、どのような異常がわかるのかを以下のページで詳しくご案内しています。
血液検査
血液検査は、息切れの原因を幅広く調べるために欠かせない検査です。腕から少量の血液を採り、体の状態を数値で確認できます。特にBNPという値は、心臓にかかる負担を示す重要な指標で、心不全の診断や重症度の判定に用いられます。ほかにも次のような情報が得られます。
- 貧血の有無:酸素を運ぶ力が足りているか
- 腎臓や甲状腺の機能:代謝や水分調整の異常を確認
- 体内の炎症反応:感染症や炎症性疾患を把握
一度の採血で多くの情報が得られるため、原因不明の息切れの精査に効果が期待できます。
呼吸機能検査
呼吸機能検査は、息切れの原因が肺にあるかどうかを確かめる基本的な検査です。鼻をクリップで止め、筒をくわえて息を吸ったり吐いたりすることで、肺の働きを数値化します。特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断には欠かせず、肺年齢を知ることもできます。測定するのは、主に以下の3点です。
- 肺活量:空気をどれだけ吸い込めるか
- 呼出力:しっかり息を吐き出せるか
- ガス交換能力:酸素を取り込み二酸化炭素を排出できているか
十分な情報が得られない場合は、心臓超音波(エコー)検査やCT検査など、より詳しい検査を追加して診断を深めていきます。
息切れの治療法
病院で行われる主な治療法は以下のとおりです。
- 薬物療法
- 在宅酸素療法
- 呼吸リハビリテーション
一つひとつの意味を理解することで、安心して治療に臨みましょう。
薬物療法
息切れの治療は、原因に応じた薬物療法が基本です。薬は症状を和らげるだけでなく、病気の進行を抑える役割を担います。効果が出ても自己判断で中止すると、再発や悪化につながるため、必ず医師の指示通りに継続することが重要です。
原因別に使われる主なお薬には以下のものがあります。
- 心臓の病気が原因の場合:利尿薬・血管拡張薬・β遮断薬やカルシウム拮抗薬
- 肺の病気が原因の場合:気管支拡張薬・ステロイド薬
- 貧血が原因の場合:鉄剤
心臓疾患では心臓への負担を減らす薬が中心です。肺疾患では、気道を広げたり炎症を抑えたりする薬が有効とされています。貧血では鉄剤を補うことで酸素を運ぶ力を改善します。薬物療法は病気に合わせたオーダーメイドの治療であり、継続こそが回復への第一歩です。
在宅酸素療法
在宅酸素療法(HOT)は、病気の進行によって体の中の酸素が慢性的に不足している場合に行う治療です。自宅に酸素濃縮器を設置し、鼻につけたチューブから酸素を吸入します。治療の目的は、全身に十分な酸素を届けて心臓や臓器への負担を減らし、生活の質を保ちながら長く健康に過ごせるようにすることです。
酸素は燃焼を助ける性質があるため、タバコやストーブ、ガスコンロなど火気の使用には十分な注意が必要です。医療保険の対象となり、高額療養費制度などの支援も利用できるため、費用面が心配な方は医師やソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。
呼吸リハビリテーション
息切れを改善するには、体を動かすことをやめないことが大切です。息苦しさを理由に安静を続けると筋力が低下し、息切れが悪化する悪循環に陥ります。この流れを断ち切るのが呼吸リハビリテーションです。専門家が一人ひとりの状態に合わせてプログラムを組み、安全に体を動かす方法を指導します。
主な内容は次のとおりです。
- 運動療法:ウォーキングや自転車こぎ、筋力トレーニング
- 呼吸訓練:口すぼめ呼吸や腹式呼吸で呼吸を楽にする練習
- 栄養・生活指導:食事や日常動作の工夫を学ぶ
続けることで息切れが軽くなり、動作も楽になります。さらに自信がつき、外出や趣味を楽しむ意欲が戻ることで、生活の質を高めることができます。
息切れを和らげる日常生活の工夫
病院での治療に加え、毎日の生活で少し工夫するだけでも、息切れは和らげられる可能性があります。ご自宅で今日から始められる、呼吸を楽にする具体的な方法は以下のとおりです。
- 塩分制限
- 無理のない有酸素運動
- 呼吸を楽にする方法
- 口すぼめ呼吸法
塩分制限
心不全による息切れを和らげるためには、塩分を控えることが重要です。塩分を摂りすぎると体は水分をため込み、血液量が増えて心臓に大きな負担がかかります。その結果、余分な水分が肺に染み出し「肺うっ血」と呼ばれる状態となり、まるで水中で溺れるような苦しさにつながります。
1日の塩分摂取目標は6g未満です。ラーメンの汁を飲み干すだけで簡単に超えてしまうため、注意が必要です。減塩でもおいしく食べる工夫があります。だしや香辛料、香味野菜、レモンや酢の酸味を活用すれば、薄味でも満足感を得られます。
また、加工食品や漬物、干物を控え、麺類の汁は残すことが大切です。しょうゆやソースは直接かけず「つけて」食べることで使用量を減らせます。まずは食品の栄養成分表示を確認する習慣から始めましょう。
無理のない有酸素運動
息切れの改善には、無理のない範囲での有酸素運動が欠かせません。安静にしすぎると筋力が衰え、少し動いただけで心臓や肺に大きな負担がかかります。適度な運動を生活に取り入れることで、心肺機能を維持し、息切れの悪循環を断ち切ることができます。
大切なのは「苦しくなるまで頑張ること」ではなく「楽に続けられること」です。安全に取り入れるためのポイントは以下のとおりです。
- 運動の種類:ウォーキング、ゆったりした自転車こぎ、水中歩行など
- 強さの目安:少し息が弾むが会話できる程度
- 進め方:1日10分から始め、慣れたら少しずつ延ばす(週3〜5日が理想)
- 注意点:開始前に必ず主治医に相談し、体調が悪い日は無理せず休む
これらを守れば、安心して続けられる運動習慣を作れます。
呼吸を楽にする方法
息切れを和らげるためには、呼吸法の工夫によって、呼吸に使う筋肉を鍛えることができます。呼吸法を毎日少しずつ取り入れることで、呼吸のしやすさを実感しやすくなります。自宅でできる代表的な方法は次の2つです。
- 腹式呼吸:お腹に手を当て、鼻から息を吸って膨らませ、口をすぼめてゆっくり吐く
- 呼吸筋ストレッチ:息を吸いながら腕を大きく上げ、胸を広げ、吐きながら下ろす動作を繰り返す
これらの方法は道具を使わずに手軽に始められ、続けることで呼吸が楽になり、日常生活の質も高まっていきます。
口すぼめ呼吸法
口すぼめ呼吸法は、息苦しさを感じたときに実践できるシンプルな方法です。特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)など、息を吐き出しにくい方に効果が期待できます。吐くときに口をすぼめて抵抗をかけることで気管支が内側から支えられ、肺の奥に残った空気をスムーズに吐き出せます。
口すぼめ呼吸法のやり方は以下の流れです。
- 姿勢を整える:背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックス
- 鼻から息を吸う:「1、2」と数えながらゆっくり吸う
- 口をすぼめて吐く:口笛を吹く形にして「1、2、3、4」と倍の時間をかけて吐く
階段を上るときや入浴中など、息苦しくなりやすい場面で行うと効果が期待できます。息切れの予防にもなり、パニックを防ぎ落ち着いて呼吸できるようになります。
まとめ
息切れは単なる「年のせい」ではなく、心臓や肺の病気が隠れている可能性があります。ご紹介したように、原因は多岐にわたり、適切な検査と治療で症状を和らげることができます。
「最近、息切れが気になる」と感じたら、自己判断せずに、まずはかかりつけ医や循環器内科へ相談しましょう。専門家と一緒に原因を見つけ、ご自身に合った治療やリハビリ、生活習慣の工夫を取り入れることをおすすめします。
息切れを正しく理解し対処することで、これからも安心して活動的な毎日を送ることができます。「いつものことだから」と自己判断せず、少しでも不安に感じたら、医療機関を受診しましょう。当院では循環器専門医が丁寧にお話を伺い、必要に応じた検査や治療で早期発見をサポートします。
参考文献
Yamama Hafeez, Bryan S. Quintanilla Rodriguez, Intisar Ahmed, Shamai A. Grossman. Paroxysmal Supraventricular Tachycardia. StatPearls, 2025.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







