blog
ブログ
足の血管が浮き出てボコボコと見える、夕方になるとずっしりと重く感じる足のだるさ。そんな症状を「年齢のせい」や「疲れ」と思っていませんか?それは下肢静脈瘤の可能性もあります。命に直結する病気ではないものの、放置すると皮膚の変色や炎症、さらには潰瘍に進行するリスクもあります。
この記事では、何科を受診すべきかをはじめ、原因や発症リスク、放置した場合の危険性、治療法まで解説します。正しい知識を持つことで、不快な症状を和らげ、健やかな足で毎日を過ごす一歩につながります。
静岡市で足の血管の浮きやだるさが気になる方は、大石内科循環器科医院へご相談ください。当院では循環器専門医が超音波検査で静脈の状態を詳しく確認し、症状に合わせた治療や生活改善をご提案しています。
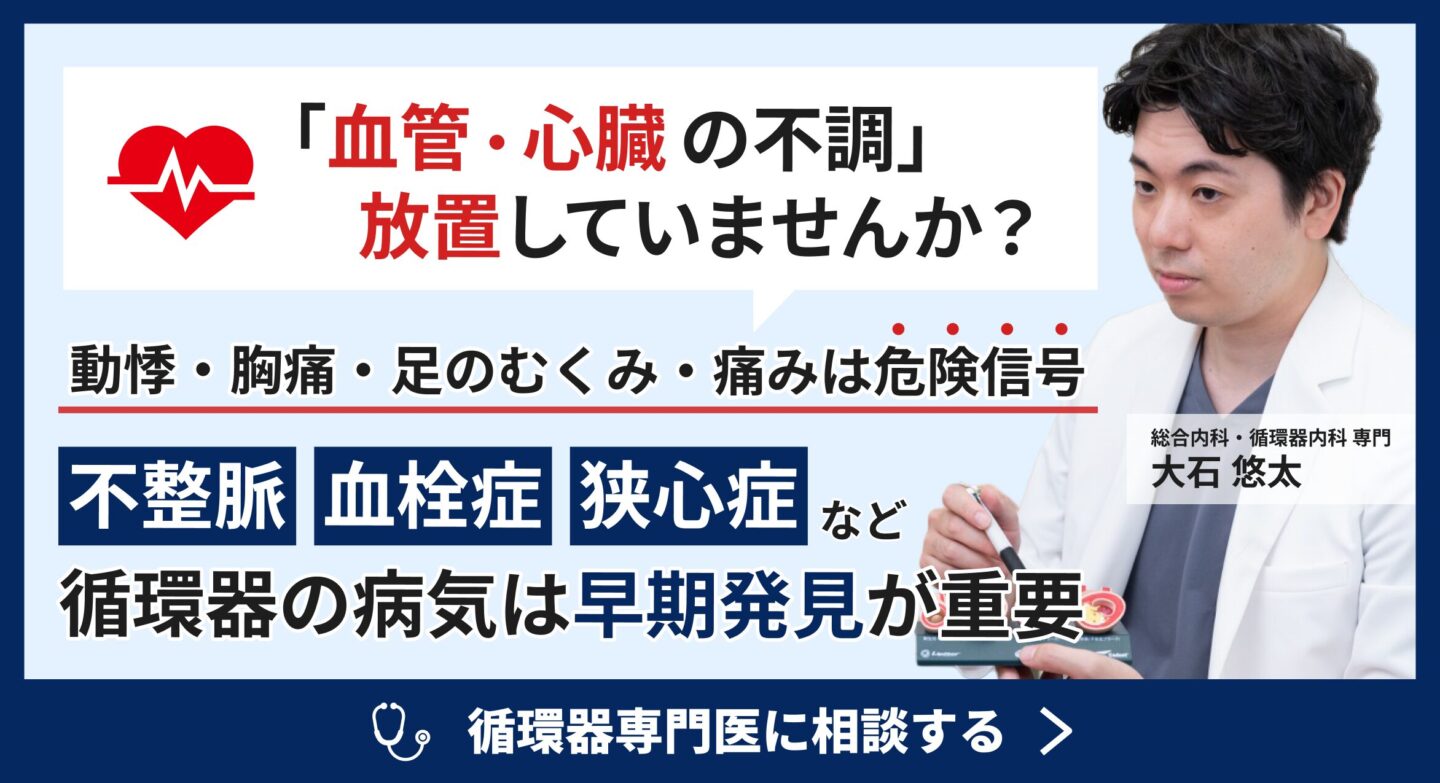
下肢静脈瘤の受診すべき診療科
下肢静脈瘤は症状に応じて受診先が変わる病気です。基本的に血管の専門科で診てもらうのが安心です。
基本は血管外科・心臓血管外科・循環器内科
下肢静脈瘤を専門的に診断・治療できるのは、血管外科が基本の受診先です。超音波検査で静脈の状態を詳しく調べ、症状に合わせて圧迫療法からレーザー治療、手術まで幅広く対応します。血管外科が近くにない場合は、心臓血管外科や循環器内科でも相談できます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 血管外科:診断から手術まで一貫対応しており、専門性が高い
- 心臓血管外科:全身の血管手術を扱い、下肢静脈瘤にも対応可能
- 循環器内科:薬による治療や検査をする
受診の際には、心臓や血管全体に負担がかかっていないかを確認することも大切です。特に循環器内科では、心臓の動きや機能を把握する検査が行われ、全身状態を踏まえた判断につながります。以下のページでは、心臓の状態を詳しく調べる検査について解説しています。
下肢静脈瘤の主な症状:足の血管が浮き出る
足の血管がボコボコと浮き出るのは、下肢静脈瘤の代表的なサインです。症状は見た目の変化だけでなく、血液が逆流してうっ血することで、さまざまな不快な症状を伴います。単なる疲れやむくみと勘違いしやすいため、以下のような症状がないか確認してみましょう。
- 見た目の変化:血管が青く浮き出る、コブ状に膨らむ、細い血管がクモの巣のように広がる
- 足の異常感:夕方になると重くだるい、靴下の跡が深く残る、熱っぽさやピリピリした痛み
- 夜間の症状:夜中や明け方にふくらはぎがつる(こむら返り)
- 皮膚トラブル:すねのかゆみ、治りにくい湿疹、茶色っぽい色素沈着
軽い症状でも放置すると悪化して生活の質に影響するため、早めの受診が安心につながります。以下の記事では、足のむくみが痛いときに考えられる原因や受診の目安、解消のためのストレッチ方法について解説しています。
>>足のむくみが痛い原因は?受診の目安や解消するためのストレッチ
下肢静脈瘤の原因
下肢静脈瘤は、一つの原因だけで発症することは少なく、複数の要因が複雑に絡み合って起こる病気です。下肢静脈瘤の主な原因として以下の3つを解説します。
- 静脈弁の機能不全
- 遺伝的要因
- 発症リスクを高める要因(立ち仕事・妊娠・出産・加齢など)
静脈弁の機能不全
下肢静脈瘤の直接的な原因は、静脈弁が壊れて血液の逆流を防げなくなることです。静脈弁は血液の流れを一方通行にする「逆流防止の扉」の役割を担っています。足の血液は、重力に逆らって心臓に戻る必要があります。「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たし、静脈弁と協力して血液を押し上げています。
弁が壊れて閉じなくなると血液が下に逆流し、足の静脈にたまってしまいます。この状態が続くと、静脈は風船のように膨らみ、皮膚の表面にコブのような形で浮き出てくるのです。これが下肢静脈瘤の正体であり、一度壊れた静脈弁は自然に元に戻ることはありません。
そのため、症状が見られた場合には、早めの受診と治療が重要になります。静脈弁の機能や血液の逆流の有無を確認するには、超音波検査が有効です。静脈だけでなく動脈の状態もあわせて評価することで、足の症状の原因をより正確に把握できます。
以下のページでは、足の血管を調べる検査について解説しています。
遺伝的要因
下肢静脈瘤は「なりやすい体質」が関係しており、遺伝的な要因が大きいと考えられています。ご両親や兄弟姉妹に下肢静脈瘤の方がいる場合、ご自身も発症するリスクが高まります。特に両親ともに下肢静脈瘤を持つ場合、その子どもの発症率は約90%にのぼるという調査報告もあります。
遺伝するのは病気そのものではなく、血管や静脈弁に関する体質です。血管の壁が弱い・静脈弁が弱いなどの状態を受け継ぐことで、静脈に負担がかかりやすくなり、下肢静脈瘤を発症しやすくなります。ただし、遺伝的要因があるからといって必ず発症するわけではありません。
生活習慣や環境も大きく影響します。ご家族に下肢静脈瘤がある場合は、自身のリスクを理解し、足の状態をこまめにチェックして早めの受診につなげることが大切です。
発症リスクを高める要因(立ち仕事・妊娠・出産・加齢など)
下肢静脈瘤は体質だけでなく、生活習慣や環境によってリスクが高まる病気です。日常の中に思い当たる要因がないか、以下を確認してみましょう。
- 長時間の同じ姿勢:美容師や調理師などの立ち仕事、デスクワークで座りっぱなし
- 妊娠・出産:ホルモンの影響で血管が柔らかくなり、子宮が静脈を圧迫する
- 加齢:血管の弾力や静脈弁の働きが弱まり、逆流を防げなくなる
- 肥満:足への負担増に加え、内臓脂肪が腹部の血管を圧迫し血流を妨げる
- その他の要因:便秘による強いいきみ、重い荷物の持ち運びなど腹圧がかかる習慣
こうした小さな負担の積み重ねが、少しずつ静脈弁を傷つけ、症状の発症へとつながります。
下肢静脈瘤を放置するリスク
下肢静脈瘤は、放置すると症状はゆっくり確実に進行していきます。下肢静脈瘤を放置するリスクとして、以下を解説します。
- 皮膚の色素沈着
- 皮膚炎
- 潰瘍
皮膚の色素沈着
足首まわりに茶色いシミが出てきたら、下肢静脈瘤が進行しているサインです。これは「うっ滞性色素沈着」と呼ばれ、血管内の圧力が高まり、赤血球が血管の外に漏れ出すことで起こります。分解された赤血球から鉄分(ヘモジデリン)が沈着し、皮膚が茶色く変色するのです。
色素沈着が起こるまでの流れは以下のとおりです。
- 静脈のうっ滞:血液がたまり、静脈内の圧力が上昇する
- 赤血球の漏出:圧力に耐えきれず血管外に赤血球が漏れる
- ヘモジデリン沈着:赤血球が分解され鉄分が皮膚に沈着する
- 皮膚の変色:茶色いシミとして現れ、広がっていく
一度できた色素沈着は完全に消えることが難しく、治療をしても薄くなるまで時間がかかります。皮膚の変化に早めに気づき、専門医に相談することが重要です。
皮膚炎
下肢静脈瘤が進行すると「うっ滞性皮膚炎」を起こしやすくなります。血液の流れが滞ることで皮膚に酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物がたまってバリア機能が低下します。その結果、わずかな刺激でも炎症を起こし、つらい皮膚トラブルにつながります。以下のような症状が現れます。
- 強いかゆみ:夜眠れないほど激しいこともある
- 赤み・湿疹:すねのあたりに赤いブツブツが出る
- じゅくじゅく:炎症が悪化すると黄色い液体が染み出す
- 皮膚の硬化:慢性化すると乾燥してゴワゴワになる
かゆみ止めの薬で一時的に楽になりますが、血液のうっ滞を改善しなければ再発を繰り返すのが特徴です。湿疹がなかなか治らないと感じたら、早めに専門医に相談しましょう。
潰瘍
下肢静脈瘤を放置して血液のうっ滞が進行すると、皮膚の組織が壊死し、えぐれたような深い傷「潰瘍」ができることがあります。潰瘍は下肢静脈瘤の合併症の中でも重い症状の一つで、皮膚が栄養不足で弱っているため、軽い刺激でも深い傷に進展しやすいです。
一度できると治りにくく、数か月〜数年にわたり治療が必要になることもあります。強い痛みで歩行や睡眠に支障をきたし、さらに感染や再発を繰り返すリスクも高いため、生活の質を損ないます。潰瘍に至る前に、足のかゆみや色の変化などの初期サインを見逃さず、早めに専門医を受診することが重要です。
下肢静脈瘤の治療法
下肢静脈瘤の治療は、症状の重さやお体の状態、ご自身の生活スタイルに合わせて、最適な方法を選びます。下肢静脈瘤の治療法として、以下の4つを解説します。
- 保存的治療(圧迫療法)
- 血管内治療(レーザー・高周波焼灼術)
- 硬化療法
- ストリッピング手術
保存的治療(圧迫療法)
保存的治療は下肢静脈瘤の基本となる治療法であり、症状を和らげ、進行を抑えることを目的とします。その中心が、医療用の弾性ストッキングを使った圧迫療法です。段階的に圧力をかける設計により、血液の逆流を防ぎ、心臓への戻りを助けます。これにより、足のだるさやむくみが軽減されます。
特に次のような方に適しています。
- 症状が軽く、だるさやむくみを改善したい方
- 妊娠中で積極的治療ができない方
- ご高齢や持病のため手術が難しい方
- 血管内治療や手術後の再発予防をしたい方
市販の着圧ソックスとは異なり、医療用ストッキングは適切な圧迫力が保証された医療機器です。最大限の効果を得るためには、医師や看護師に足のサイズを測ってもらい、自分に合った製品を選ぶことが大切です。
以下の記事では、むくみの主な原因や注意すべき病気、生活の中でできる改善法を解説しています。
>>むくみの原因は?危険なむくみや考えられる病気、日常でできる対処法を解説
血管内治療(レーザー・高周波焼灼術)
下肢静脈瘤の治療で一般的なのが血管内治療です。原因となっている静脈にカテーテルを入れ、内側から熱を加えて塞ぐことで逆流を止めます。局所麻酔で行うため体への負担が少なく、日帰りで受けられるのも特徴です。以下の流れで治療は行われます。
- 超音波で血管を確認し、膝付近からカテーテルを挿入
- 麻酔薬を注入し、痛みや周囲への影響を防ぐ
- カテーテル先端からレーザーまたは高周波を照射し、静脈を収縮・閉塞
血管内治療のメリットは以下のとおりです。
- 傷跡が目立たない(針穴程度)
- 痛みが少なく体への負担が軽い
- 入院不要で日帰り治療ができる
レーザーと高周波にはそれぞれ特徴があります。複数の研究結果をまとめた報告によると、高周波治療はレーザー治療に比べて、治療後の痛みやしびれなどの感覚異常が起こるリスクが低い傾向にあります。
レーザーは治療後に痛みや感覚の異常がやや出やすいものの、皮膚のシミが起こりにくい傾向があります。高周波は痛みや感覚異常が少ない反面、皮膚のシミが出やすいとされています。どちらの方法が適しているかは、静脈瘤の状態や患者さんの希望に応じて、医師と相談しながら決めていくことが大切です。
硬化療法
硬化療法は、皮膚表面に見える細い血管の静脈瘤に行われる治療法です。クモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤など、見た目が気になる血管に「硬化剤」という薬を注射します。血管の壁をくっつけて塞ぐことで、時間とともに吸収され目立たなくなります。
短時間(5~10分程度)で済み、麻酔を必要としないことが多いため、体への負担が少ないのがメリットです。一方で、治療後に茶色いシミやしこりができることがあり、多くは自然に改善しますが注意が必要です。まれにアレルギー反応が起こることもあります。
治療後は弾性ストッキングで一定期間の圧迫が欠かせません。硬化療法だけでは逆流の原因となる太い静脈瘤を治せないため、血管内治療や手術と併用されることもあります。
ストリッピング手術
ストリッピング手術は、100年以上の歴史を持つ下肢静脈瘤の根治的治療法です。逆流の原因となる大伏在静脈や小伏在静脈を体の中から取り除く方法です。現在は血管内治療が主流になったため頻度は減りましたが、今も選択肢の一つとされます。ストリッピング手術が選ばれるケースは、次のような場合です。
- 静脈瘤が太く、血管内治療では対応が難しい場合
- 血管のうねりが強く、カテーテル治療が困難な場合
- 血栓性静脈炎を繰り返している場合
この方法では足の付け根や膝の裏に数センチの傷ができ、皮下出血や痛みが出やすく、入院が必要になることもあります。一方で、再発率が低いというメリットがあり、重症例では今も重要な治療法の一つです。
まとめ
足の血管が浮き出る、だるさやむくみが続くなどの症状は、単なる疲れや歳のせいだと見過ごされがちです。しかし、下肢静脈瘤は放置すると、皮膚の変色や治りにくい潰瘍などの深刻なトラブルにつながる可能性があります。
「何科に行けばいいの?」と迷ったら、まずは「血管外科」「循環器内科」や専門のクリニックへ相談してみましょう。
気になる症状は抱え込まず、専門医に相談することが、健やかな足を取り戻すための第一歩になります。
参考文献
Liang Y, Hu M, Yang H, Long Z, Jiang W, Qin X. Endovenous radiofrequency ablation vs laser ablation in patients with lower extremity varicose veins: A meta-analysis.
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







