blog
ブログ
健康診断や検査で「心電図に異常があります」と言われると、多くの方が「心臓の病気では?」と不安を抱きます。実際、心電図の異常は必ずしも重大な心臓病を意味するわけではなく、一時的な変化や生活習慣に関連するケースも少なくありません。
しかし、放置すると危険につながる病気が隠れていることもあります。この記事では、心電図検査でわかること、異常の種類や原因、考えられる病気、受けるべき治療や日常生活での注意点までを解説します。正しい知識を持つことで、不安を減らし、これからの健康管理に前向きに取り組むきっかけになるでしょう。
当院では心電図を用いて不整脈や狭心症などの心臓の異常を早期に発見し、必要に応じた治療へつなげています。 循環器専門医が丁寧に症状を伺い、安心して検査・診察を受けられる体制を整えています。気になる症状を放置せず、健康を守る第一歩として心電図検査をおすすめします。
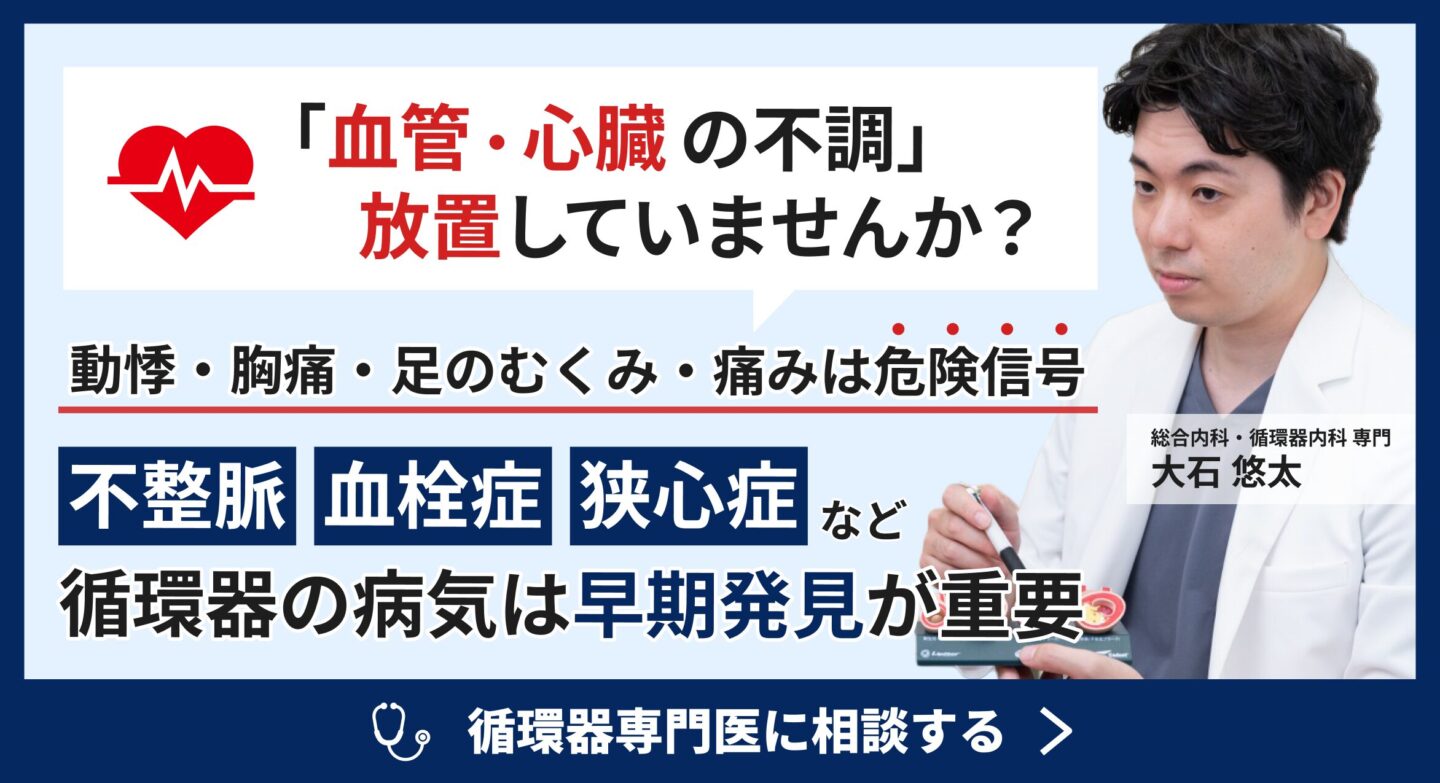
正常な心電図の波形の種類
心電図は心臓の電気的な動きを記録する検査であり、正常な波形はP波・QRS波・T波の3種類で構成されています。それぞれが心臓の異なる働きを反映し、異常があれば病気のサインとなることもあります。基本的な波形の特徴は以下のとおりです。
- P波(心房の収縮を示す):なだらかな山型 幅0.08〜0.1秒 高さ0.1〜0.2mV程度
- QRS波(心室の収縮を示す):鋭い波形で幅0.10秒以下 心室が適切に働いている指標
- T波(心室の回復を示す):小さな丘のような形 四肢誘導で0.5mV以下が目安
これらの波形が正常範囲内にあることで、心房と心室がリズムよく活動していると判断できます。逆に、幅や形状に異常がみられる場合は、心房肥大・心筋虚血・伝導障害などの可能性を示唆します。心電図の判読は専門的な知識が不可欠ですが、基礎を知ることで結果を理解しやすくなり、定期的な検査が健康管理に役立ちます。
心電図の波形を理解することで、検査結果にどのような意味があるのかを把握しやすくなります。実際の検査では、これらの波形をもとに心臓のリズムや異常の有無を総合的に評価します。以下のページでは、心電図検査そのものについて詳しく解説しています。
心電図検査でわかる4つのこと
心電図検査でわかることは以下のとおりです。
- 心臓のリズムや脈拍数の異常
- 心筋の酸素不足
- 心臓肥大
- 心筋梗塞や狭心症などの心臓病
心臓のリズムや脈拍数の異常
心電図検査では心臓のリズムや脈拍数の異常を発見でき、不整脈の種類を特定することが可能です。 不整脈は自覚症状がなくても進行し、放置すると脳梗塞や心不全などにつながる場合があります。代表的な不整脈には次のようなものがあります。
- 頻脈:脈が速くなる状態
- 徐脈:脈が遅くなる状態
- 期外収縮:通常のリズムに余分な拍動が入る状態
- 心房細動:心房が細かく震える状態
心電図検査は不整脈の有無だけでなく、その種類や重症度を判断し、治療方針を決めるうえで欠かせない検査と言えます。
心筋の酸素不足
心電図検査では心筋に酸素が十分に届いていない「心筋虚血」を確認できます。 心筋虚血は放置すると、狭心症や心筋梗塞を引き起こす要因であり、早期に把握することが重要です。検査では次のような点を評価できます。
- 冠動脈の狭窄による酸素不足の有無
- 波形変化から虚血の範囲や程度を推測
狭心症では、一時的に血流が不足することで心電図のST部分が下がる、T波が逆向きになるなどの変化が見られます。心筋梗塞ではさらに深刻で、心筋の一部が壊死してしまうため、異常Q波やSTの上昇などの特徴的なサインが現れます。
こうした変化を心電図で捉えることで、虚血の重症度や進行を早期に判断し、適切な治療につながります。
心臓肥大
心電図検査では、心臓が通常より大きくなっている「心臓肥大」を確認できます。 これは心臓の筋肉が厚くなりすぎた状態を指し、特に高血圧や心臓の弁の病気が原因になることが多いです。高血圧などが原因の場合は、放置すると心臓に大きな負担をかけます。
心電図では、心臓の大きさの程度や波形の変化(QRS波の振れ幅が大きくなるなど)を通して肥大の有無を推測します。心臓が肥大すると、収縮する効率が落ちたり、不整脈が起こりやすくなったりします。そのまま進行すれば心不全へとつながる危険もあります。早期に発見して生活習慣や治療で対応することが、心臓を守るために大切です。
心筋梗塞や狭心症などの心臓病
心電図検査では、狭心症や心筋梗塞などの重大な心臓病を早期に見つけることができます。 どちらも冠動脈という血管に異常が起きる病気ですが、進行の度合いに違いがあります。狭心症は血管が一時的に狭くなって心筋に酸素が足りなくなる状態です。心筋梗塞は血管が完全に詰まり、心筋の一部が壊死してしまう深刻な状態です。
心電図では次のような特徴的な波形の変化が現れます。
- STセグメントの上昇:急性期のサイン
- 異常Q波の出現:壊死した心筋を示す
狭心症は発作が繰り返されることが多く、心筋梗塞は突然発症して命に直結することがあります。急性期には一刻も早い治療が必要であり、心電図はその早期発見と治療方針の決定に欠かせない検査です。
定期的に検査を受けることでリスクをいち早く察知し、重症化を防ぐことにつながります。特以下の記事では、狭心症の症状や原因、検査・治療法について詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。
>>狭心症について
心電図異常の種類
心電図異常にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が違います。代表的な4つの心電図異常について、解説します。
心房細動の兆候
心房細動は心臓のリズムが乱れる代表的な不整脈で、心電図で早期に発見することが重要です。 心臓の上部である心房が規則正しく動けず細かく震えます。そのため、血液が滞って血栓ができやすくなり、脳梗塞など重い合併症の原因になります。心電図ではP波が消え、細かい波(f波)が連続して見えるのが特徴です。
主な症状には次のようなものがあります。
- 動悸:脈が速くなる 遅くなる 不規則になる
- 息切れ:肺への血流不足で呼吸が苦しくなる 安静時や運動時に出やすい
- めまい:脳への血流不足でふらつきや意識が遠のく感覚
ただし、自覚症状が全くない場合も多く、健康診断で初めて指摘されることもあります。 特に高齢者や高血圧、心不全を持つ人ではリスクが高いです。近年はMASLD(代謝機能不全関連脂肪肝疾患)の患者で心房細動が増えることも報告されています。放置すると合併症につながるため、早期発見と治療が欠かせません。
心房細動が疑われる場合、安静時の心電図だけでなく、体を動かしたときに心拍やリズムがどのように変化するかを確認することも重要です。運動によって症状や不整脈が現れやすくなるケースもあり、診断や治療方針の判断に役立ちます。
以下のページでは、運動負荷をかけて心臓の反応を調べる検査について解説しています。
心室性期外収縮
心室性期外収縮は、心臓の下の部分(心室)から通常より早く収縮の刺激が出る不整脈で、多くの場合は心配のない現象です。 心電図ではQRS波が広くなったり形が変わったりするのが特徴で、健康な人でも見られることがあります。
自覚症状として多いのは次のようなものです。
- 脈が飛ぶ感じ:一瞬止まったように感じる
- 胸のドキッとした動き:不意に強い拍動を感じる
- 胸部の不快感:違和感や重さを覚えることがある
自覚症状が全くないケースも多く、健康診断の心電図で初めて見つかる人もいます。 大部分は治療を必要とせず、経過観察で十分です。頻度が多い場合や心筋梗塞・心筋症などの基礎疾患を持つ人では、重い不整脈(心室頻拍や心室細動)につながる恐れがあります。
動悸や不快感が続くときは、早めに医療機関で相談することが大切です。
以下の記事では、不整脈の代表的な種類や症状、治療法などを網羅的に解説しています。
>>不整脈について
冠動脈疾患
冠動脈疾患は、心臓に血液を送る血管(冠動脈)が細くなったり詰まったりする病気です。 主として、狭心症と心筋梗塞があります。狭心症は血流が一時的に不足する状態で、胸の痛みや息苦しさを繰り返します。心筋梗塞は血管が完全に詰まり、心臓の筋肉が壊死してしまう危険な病気です。
心電図では、ST部分の上昇や下降、T波の異常、異常Q波などの変化が現れ、診断の手がかりになります。症状は胸痛・冷や汗・息切れなどで、発作時には一刻を争う治療が必要です。安静時には異常が出ない場合もあるため、運動をしながら行う心電図検査で見つかることもあります。
冠動脈疾患では、症状が出たり消えたりすることがあり、安静時の検査だけでは異常を捉えにくい場合があります。日常生活中の心拍や心電図の変化を連続して記録することで、発作時の異常や虚血の兆候が見つかることがあります。
以下のページでは、長時間の心電図記録によって心臓の状態を調べる検査について解説しています。
QT延長症候群
QT延長症候群は、心電図で「QT間隔」が異常に長くなる病気で、重い不整脈や突然死を引き起こす危険があるため注意が必要です。 QT間隔とは心臓の下部(心室)が収縮して再び拡張するまでの時間を示します。原因としては次のようなものがあります。
- 先天性:遺伝子の異常によるもの
- 後天性:薬の副作用や電解質の乱れによるもの
症状には、失神やけいれん、動悸などがみられます。重症では「トルサード・ド・ポワント(TdP)」と呼ばれる不整脈が起こり、突然死につながることもあります。QT延長症候群はまれですが、心電図で早期に見つけて原因を調べ、適切な治療を受けることが何より大切です。
異常を指摘された場合は、必ず専門医に相談しましょう。
心電図異常の主な原因
心電図の異常は必ずしも重い心臓病を意味するわけではなく、生活習慣や体質などが影響している場合もあります。 適切な対策を取ることで健康を維持できるケースは少なくありません。心電図異常の背景にはさまざまな要因がありますが、特に関わりの大きいのは次の3つです。
- 高血圧症
- 糖尿病
- 遺伝的要因
高血圧症
高血圧は、自覚症状がほとんどないまま心臓に負担をかけ続け、心電図異常の背景として多い原因の一つです。 血圧が高い状態が長く続くと、心臓は強い力で血液を送り出そうとするため筋肉が厚くなり、心室肥大と呼ばれる状態を起こします。
こうした変化は心電図の波形にも反映され、将来的に不整脈・心不全・虚血性心疾患などのリスクを高めます。初期段階では症状がなく、長年放置してしまうケースが多いのが特徴です。高血圧が慢性化すると、心臓を養う冠動脈にも大きな負担がかかり、狭心症や心筋梗塞といった重い病気の誘因となる可能性があります。
そのため、日常的な血圧測定と心電図検査で早めに異常を見つけ、生活習慣の改善や治療につなげることが何より大切です。
高血圧について網羅的に知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
>>高血圧の基礎知識・症状・治療について
糖尿病
糖尿病は血糖値が高い状態が続くことで血管を傷つけ、心電図異常の背景となる代表的な生活習慣病です。 高血糖が慢性的に続くと動脈硬化が進み、心臓に大きな負担を与えます。主な影響は次のとおりです。
- 動脈硬化:冠動脈が狭くなり狭心症や心筋梗塞のリスクが上がる
- 不整脈:心房細動などが起こりやすく心電図に異常が出やすい
- 全身の合併症:腎臓・神経・目などにも障害が進む
特に心筋梗塞は、糖尿病がある人では発症リスクが2〜4倍高いとされ、突然死につながる危険な病気です。自覚症状が少ないまま進行することも多く、足のしびれや倦怠感などの小さな変化を見逃すと重症化する恐れがあります。
そのため糖尿病のある人は、定期的に心電図検査を受けて異常を早期に見つけ、適切な治療につなげることが大切です。
遺伝的要因
心電図の異常は、生まれつきの体質や遺伝子の影響によって起こることがあります。 親から子へ受け継がれる遺伝子の変化によって、心臓の電気的な働きに乱れが生じるのです。代表的なものは次のとおりです。
- QT延長症候群:QT間隔が異常に長くなり、失神や突然死のリスクがある
- ブルガダ症候群:心室の電気伝導に異常が起き、重い不整脈を起こす可能性がある
- 遺伝性心房細動:心房のリズムが乱れやすく、脳梗塞のリスクを高める
若い人にも現れることがあり、症状がなくても心電図で初めて見つかるケースもあります。特に「家族に突然死や心臓病の既往がある人」は要注意です。遺伝的な要因による心電図異常はまれですが、早期発見すれば、薬や生活管理でリスクを減らすことが可能です。
家族歴がある方は、一度心電図検査を受けておくと安心です。
心電図異常を指摘された場合の対処法
心電図は心臓の一側面を示すにすぎないため、結果だけで不安になる必要はありません。ここでは、心電図異常を指摘されたときに取るべき4つの主要な対処法を解説します。
循環器専門医の受診
心電図で異常を指摘されたら、まず循環器専門医に相談することが大切です。 心臓の病気は放置すると重い合併症につながることがあり、専門医による詳しい検査や診断でリスクを早めに把握できます。
循環器専門医は心電図の結果だけでなく、次のような情報を総合的に評価します。
- 症状:動悸・胸痛・息切れなどの有無
- 既往歴:高血圧や糖尿病など心臓病の危険因子
- 生活習慣:喫煙・飲酒・運動不足など
- 家族歴:突然死や心疾患の家族歴
- 検査結果:血液検査や心エコーなどの追加情報
期外収縮(脈が飛ぶ・強く打つ感じ)が見つかった場合も、頻度や他の兆候をもとに精密検査の必要性を判断します。早めに専門医を受診することは、不安を解消し、合併症の予防につながる最善の一歩です。
循環器専門医を受診した際には、心電図だけでなく心臓の動きや構造を詳しく確認する検査が行われることがあります。心臓のポンプ機能や弁の状態を評価することで、心電図異常の原因をより正確に判断できます。以下のページでは、その評価に用いられる検査について解説しています。
基礎疾患の治療
心電図の異常は、高血圧や糖尿病といった生活習慣病が原因になっていることが多いため、基礎疾患を治療・管理することが欠かせません。 適切に対応することで、心電図の改善だけでなく将来の心臓病予防にもつながります。
基礎疾患の管理には次のような方法があります。
- 薬物療法:血圧や血糖を安定させる薬を継続して服用
- 生活習慣の改善:減塩やバランスの良い食事、適度な運動を続ける
- 定期的な検査:心電図や血液検査で経過を確認し合併症を防ぐ
糖尿病の人で心電図に異常Q波が見つかった場合、気づかないうちに心筋梗塞を起こしていた可能性があります。この場合は血糖管理を徹底するとともに、再発予防のための治療が重要です。
基礎疾患の治療は地道ですが、心臓を守り長く健康でいるための効果が期待できる方法といえます。
薬物療法
心電図の異常によっては、薬を使った治療(薬物療法)が必要になることがあります。 たとえば不整脈や心筋症では、心拍数やリズムを整える抗不整脈薬や、心臓の負担を減らす薬が処方されます。また、心房細動など血栓ができやすい状態では、脳梗塞を防ぐために抗凝固薬が使われることもあります。
これらの薬は心電図異常の改善だけでなく、合併症の予防にも効果が期待されます。ただし、薬には副作用があるため、必ず医師の指示に従い、継続的に通院しながら効果や安全性を確認することが大切です。
治療は個々の病状や体質に合わせて選ばれるため、自己判断で中断や変更をせず、医師と相談しながら続けることが重要です。
カテーテルアブレーションなどの外科的治療
薬で十分に効果が得られない場合や、特定の不整脈では外科的治療が検討されます。 代表的なのが、カテーテルアブレーションで、心臓に細い管(カテーテル)を通して入り込み、異常な電気信号を発している部分を熱で焼き切る治療法です。原因となる電気経路を直接処置するため、根本的な改善が期待できます。
外科的治療が考慮されるのは次のような場合です。
- 薬物療法で効果が不十分なとき
- 特定の不整脈があるとき:例 発作性上室性頻拍など
- 重い弁膜症や冠動脈疾患を合併しているとき
近年は体への負担が少ない低侵襲の手技が進歩しており、回復も早くなっています。どの治療を選ぶかは、患者さんの状態や希望を踏まえ、医師と十分に相談して決めることが大切です。
心電図異常がある方の日常生活の注意点
心電図に異常があっても、日常生活の工夫によって心臓への負担を減らし、症状の悪化や合併症を防ぐことができます。 大切なのは、無理をせず続けられる習慣を取り入れることです。特に意識したいのは次の3つのポイントです。
- 食生活を改善する
- 適度に運動を続ける
- 十分に休息を取る
食生活を改善する
心電図に異常がある方は、食生活を見直すことが心臓の健康を守る第一歩です。 特に高血圧や糖尿病などの基礎疾患を持つ人では、食事内容が直接心臓の負担につながります。塩分のとりすぎは血圧を上げて心臓に過剰な負担をかけるため、減塩を心がけることが大切です。
揚げ物や脂肪分の多い食事は動脈硬化を進めやすいため、野菜・魚・大豆製品などを中心としたバランスの良い食事を意識しましょう。甘い飲み物やお菓子のとりすぎも血糖値を上昇させ、糖尿病や心筋梗塞のリスクを高める要因です。
日々の食生活は小さな積み重ねですが、減塩・低脂肪・適正カロリーを意識するだけで、心臓への負担を減らすことができます。
適度に運動を続ける
心電図に異常がある場合でも、無理のない範囲で運動を続けることは心臓の健康維持に役立ちます。 適度な運動は血圧や血糖値を整え、血流を改善することで心臓の負担を軽減します。ただし、激しい運動や突然の負荷は逆効果になるため注意が必要です。
おすすめの運動例は次のとおりです。
- ウォーキング:会話できる程度の速さで1日20〜30分
- ストレッチ:体をほぐし血流を促す
- 軽い筋トレ:スクワットや腕立てなど無理のない範囲で
体調が優れないときや胸の痛み・強い息切れがある場合は運動を控え、医師に相談することが大切です。「継続できる軽めの運動」を習慣化することが、心臓を守る鍵となります。
十分に休息を取る
心電図に異常がある方にとって、十分な休息と睡眠を確保することは心臓を守るうえで欠かせません。 睡眠不足や過度なストレスは交感神経を刺激し、脈が乱れたり血圧が上がったりして心臓に負担をかけます。十分な休養によって心臓は回復し、リズムを安定させることができます。心がけたいポイントは次のとおりです。
- 睡眠:1日7時間前後を目安に規則正しく眠る
- 休養:疲れを感じたら無理をせず休む
- ストレス対策:深呼吸や趣味で気持ちを切り替える
仕事や家事に追われて休むことを後回しにすると、心電図異常が悪化する可能性もあります。休息を「治療の一部」と考え、生活の中で優先することが大切です。
心電図の異常に関するよくある質問
心電図に異常があると告げられると、多くの方が「この先どうなるのだろう」と不安を抱きます。 ただし、異常があるからといって必ずしも重い病気というわけではありません。正しい知識を持ち、必要な検査や生活管理を続けることで、多くの場合は安心して日常生活を送ることができます。
読者から特に多い以下の3つの質問に答えます。
- 心電図異常は治る?
- 定期検査の頻度はどのくらい?
- 心電図異常でも自覚症状がなければ問題ない?
心電図異常は治る?
心電図の異常は原因によって「治るもの」と「付き合っていくもの」があります。 例えば、睡眠不足やストレス、体調不良など一時的な理由で出た異常は、休養や生活習慣を整えることで元に戻ることが少なくありません。
逆に、高血圧や糖尿病、心臓の病気が背景にある場合は、薬や治療で病気をコントロールしながら心電図の変化を安定させていく必要があります。つまり、異常そのものを直接「治す」というよりも、原因を正しく見つけて対応することが大切です。心電図はあくまで心臓の状態を映し出す鏡のようなものです。
早めに医師に相談し、必要な治療や生活改善を行えば、多くの場合は安心して日常生活を続けることができます。
心電図異常の原因が「不整脈」である場合は、放置せず適切な対処が必要です。以下のページでは、不整脈の種類や治療法、日常生活で注意すべきポイントについて詳しく解説しています。
>>不整脈は治るのか?循環器専門医が治療法と生活改善のポイントを解説
定期検査の頻度はどのくらい?
心電図検査の頻度は、健康状態や持病の有無によって変わります。 健康な人であれば年1回の健康診断で十分ですが、基礎疾患がある方や心電図に異常を指摘された方は、より短い間隔での検査が推奨されます。目安は次のとおりです。
- 健康な方:年1回の健康診断で実施する
- 高血圧や糖尿病がある方:半年〜1年に1回は受ける
- すでに心電図異常を指摘された方:医師の指示に従い、数か月ごとにチェック
心電図はその日の体調や状況でも変化するため、1回の結果だけで判断せず、定期的に記録を積み重ねることが大切です。 特に持病がある方は、検査を続けることで異常の進行や合併症を早めに発見できます。
心電図異常でも自覚症状がなければ問題ない?
自覚症状がなくても、心電図に異常がある場合は放置せず確認することが大切です。 心電図は体調や一時的な要因で変化することもありますが、背景に高血圧・糖尿病・冠動脈疾患などの病気が隠れている可能性もあります。
実際、心房細動や心筋梗塞の痕跡などは症状が出ないまま進行することがあり、異常がきっかけで初めて見つかるケースもあります。自覚症状がないから安心、という判断は危険です。重要なのは、異常が出た原因を調べ、必要に応じて治療や生活改善を行うことです。
「症状がなくても検査でわかることがある」と理解し、医師の指示に従って経過を見守ることが安心につながります。
まとめ
心電図異常とは、心臓の電気的な活動に乱れが見られる状態を指します。 異常の種類によって症状や危険性はさまざまで、なかには生活習慣の影響や一時的な変化で起こることもあります。健康診断で指摘されて不安を感じる方も多いですが、必ずしも重い心臓病を意味するわけではありません。
背景には高血圧・糖尿病・遺伝的な体質などが関わることが多く、早めに原因を調べることが安心につながります。大切なのは、自己判断で放置せず専門医に相談することです。心電図の異常は早期発見と適切な治療で改善や予防が可能であり、健康を守るチャンスにもなります。
健康診断などで心電図異常と指摘された方や動悸や胸の違和感など心配な方は、循環器専門医の当院までご相談ください。
参考文献
Dimala CA, Nso N, Wasserlauf J, Njei B. Electrocardiographic abnormalities in patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: A systematic review and meta‑analysis Current Problems in Cardiology, 2024, 49(7), p. 102580
大石内科循環器科医院
420-0839
静岡市葵区鷹匠2-6-1
TEL:054-252-0585







